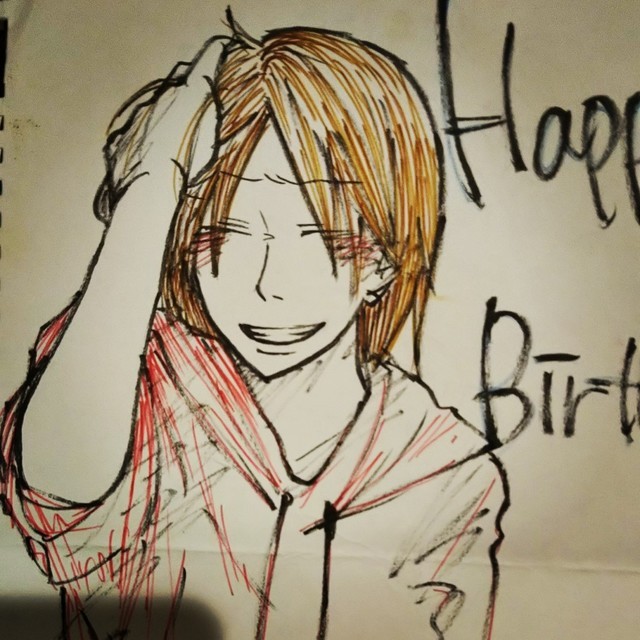第1話
文字数 4,994文字
離れるほどに整う様。痘痕なクレーター。光が飛ばすは影と不都合。今宵は満月。目を突く明度、その背後にまだ遊び足りない太陽が見える。まだ遊びたいと言っている。月はその影響をモロに受ける。月は本当はどう思っているんだろう。
「やあめた」
そう言い放つと同時に髪の根元を止めていたゴムを取る。ギュッと息を詰めていたものが深呼吸するように膨らんでその背中に流れ落ちる。橙と黄色でピカピカの長い爪が白い光をチカリと反射する。
最短で記録した猛暑日から早二ヶ月、気づけば暦の上では秋に差し掛かっていた。電力、水というライフラインの窮乏から突如ハードモードに切り替わった今年の夏、未だエアコンなしではいられないものの、ふとした時にやさしい風を感じられるようになった。
満月の強い光に照らされた千夏さんは、たった今解放されたばかりの髪をぐるぐるとつかむと「あのさあ」と言った。
「経験者なんでしょ? 本気で来なさいよ」
そのもう片方の手と腰に挟まれてじっとしているのはバスケットボール。ここから見れば純粋な球体だが、実際触ればボコボコだ。バスケをやってたとは言ったものの、それは学生時代の昼休みの話だ。
「それでも中、高三年間毎日でしょう? 部活よそれ」
部活動を舐めているとしか思えないが、言った所でヤブヘビなのは目に見えていた。女性という生き物が勢いで喋るのはいつものこと。こういう場合とにかく口を挟んではいけない。
これ見よがしにつかれる大きなため息。その、髪をつかんでいた方の手を放す。まっすぐ見つめる目。女性と形容した事を今目の前にいる人に照らし合わせる。痘痕なクレーター。この人もまた女性だろうけど、こんな時誰に聞いたらいいのだろう。「女子」と「女性」と「おばさん」の境はどこにある。
千夏さんに初めて会ったのは自宅の玄関だった。駅から徒歩二十分、いくら表だけリノベーションした所で、耐震に不安を残すアパートの壁は薄く、隣人の生活音は丸聞こえだった。去年までいた西側の隣人は夜中に何度もトイレに起きるタイプで、当時卒論に追われてた自分にはひどく堪えた。そいつが出て行った翌週末、呼び鈴とともに三十センチ四方の段ボールを抱えて現れた東側の隣人、それがすなわち当時酩酊状態だった千夏さんだ。彼女はドアを片足で固定した状態で「うるせえんだよ」と巻き舌ぎみに言った。据わった目。マスクの白とどす黒い肌のコントラスト。額と目尻に刻まれた細かなシワ。
「毎日毎日べンベンベンベン。え? 三味線か? おぬし三味線でもなろうておるのか?」
ヤバい。瞬時に絶対絡んじゃいけない相手だと分かったが、その抱えている荷物の宛先が自分名義だと気づいてしまう。誤配達だろう。クレームの間を縫うようにして荷物のことを尋ねると、たった今思い出したように「おおう」と言った。かろうじて飲み込んだゲップにその身体が荷物ごと大きく揺れる。頼むからここで吐かないでくれと思う。
「これオタクの?」
「そうです」
「君、オオサワチヒロっていうの?」
「ハイ」
間違って届いたんですねすいません、と配達員を恨みながらチヒロは謝った。女性が前後に揺らめきながらふうん、と言う。
「さっきも言ったけど毎日毎日ベンベンベンベンうるさいのよ。何? 何なのアレ? 二日酔いに響くのよ。知ってる? 二日酔い。この世の終わりを覚悟する闇を」
自らこの世の終わりに飛び込むなんて夏の虫と変わらない。つまりチヒロのかき鳴らしている楽器は壁の薄さに関係ない。
「あるでしょ! 騒音よ! 寝られやしない。こちとら平日朝五時起きなの。それを夜中までベンベンやられたら」
夜中と言っても節度をわきまえている。せいぜい二十二時までだ。それとなく言い訳するが、ここぞとばかりに大きなため息がかぶせられた。
「あのねえ、小さい頃言われなかった? 二十時過ぎたら夜中なの。お隣さん家に電話かけてもいけないの。どうしてもな時は『夜分遅くにすいません』って言わなきゃいけないの」
何時代の人だろう、とチヒロはぼんやり思った。厄介なのは「くだを巻く酔っ払いは大抵自分の動向を記憶していない」こと。つまりここで消費されていく時間丸々湯水になる可能性があった。冗談じゃない。
「分かりましたから今日はお引き取りください」
言って押し返そうとするが、突っ張り棒の役割をしている片足が絶妙に女を成り立たせていて外せない。女は数分にしてドアの一部と化していた。仕方なく一歩前に出ると再びその口が開いた。
「分かってないでしょう。なら明日から練習やめんの? 毎日毎日よくもまあ飽きずにずうっとやってること」
バチバチ、と頭上の蛍光灯で虫が弾けた。
「やめないでしょ? こんなこと言われた位で。だったら言えばいいじゃない。うるせえって」
うるせえって。
言えたらどんなに楽か。覚えずチヒロは手のひらに爪を立てた。女が目だけでその手を見やる。
「……満月の夜、顔貸して」
「は?」
「それでカンベンするって言ってんの」
女はようやく足を下ろした。
「いい? 私もヒマじゃないから週末。大体見てれば分かるでしょ、アレ。ああ丸いなあって思ったらその週末私に付き合うこと。月イチよ。安いモンでしょ」
チヒロはかすめる事案にとっさに身を引いた。
「ウリとかやってないんで」
「クソガキ。甲斐性なしなんてこっちから願い下げよ」
約束ね、そう言うと女は帰って行った。すぐさま隣の玄関の開閉の音がする。何ら変わらぬ翌日、あれは夢かと思ったが、週明け六時きっかりに階下の駐車場からエンジン音がすることに気づく。そうして例の約束が初めて決行されたのは八月半ば、二度目はこの日、九月上旬だった。
「何、チヒロボーイはバンドマンになるの?」
前回に比べて口調以上の何かが砕ける。ドアにはきっと足をついたまま。この人にはプライバシーとかパーソナルスペースとかいう概念はないのだろう。二十三にもなってボーイと呼ばれるのも変な感じだったが、話しぶりから三十代後半と推測される彼女からすれば学生上がりのひよっこボーイなのかもしれない。チヒロは頷かなかった。
なる、と言うのは簡単だった。だからこそ簡単に表に出してはいけない気がした。それこそ何かの賞もらったとか選ばれたとかそういうものなしに安易に口にしてしまったが最後、一緒にされたくない連中と一括りにされる気がした。
「上手いの?」
評価。一定の基準以上。それ以下。
才能ナシ。凡才。才能アリ。
自分が人に聴かせるだけの価値あるものを生み出しているかなんて分からなかった。それでも世間体より同期の出世より年収よりそんなことよりただ好きでここを離れられなかった。
「チヒロの楽器、同じことの繰り返し」
そんな事は無い。そう聞こえるだけで。
「ずっと低い音。ずっと重低音」
ベンベンベンベン。
「……三味線じゃなくてベース」
「知ってるわよ。どっちも似たようなものよ。ずっと同じことの繰り返し。一体何が楽しいんだかって思ってた」
満月が照らす本当は黒いすっぴん。
「でも今なら分かる気がする」
千夏さんはそう言うと、ボールをついてその上に座った。
「……バスケやってたんでしょ? いいのかよ」
「いいの。蹴ると死ぬほど怒られたけど、こうして座るのは何も言われなかった」
あくまで監督基準だけど、と言いながら天を仰ぐ。
「チヒロボーイ、 一つだけとある少女の物語を語ろう」
「いいよ」
「まぁ聞け」
格好に似合わないゴツゴツのシューズ。千夏さんは膝に肘をつくと、遠いどこかに焦点を合わせた。
「あるところにそれはそれは愛らしい女の子がいました。少女は小学二年生になったある日母親に促されるままにバスケットを始めました。世間で言うミニバスケットです。少女は母親の喜ぶ顔を見るために頑張って体育館に通いました」
その後ろに見えるフリースローライン。アクリル板から垂れ下がったゴールネット。
「すると近所に住む二つ年上の男の子がいっしょにバスケをしようと言い始めました。少女は男の子のことが大嫌いでした。何しろ身長が頭一つ分高い上、走るのも早く、学校のマラソン大会でいつもメダルを取るような子でしたから。だから勝負をしても向こうから『今日はもうおわり』と言われない限り終われないのです。それまでずっとずっと負け続けるのです。少女のガッデムは募り募って、ついには殺意にさしかかろうとしていました」
いつかのごとく目が据わる。千夏さんの口にする殺意はやけにリアルだった。
「そんなある日のこと、いつも通り一対一をしている時、接触から滑って少女はゴール下のレンガに頬を打ちつけました。皮ふの薄い所です。血が出ました。しかし痛みは全くありません。少女は待ちに待ったその瞬間が来たのだと思いました。ここぞとばかりに全力で泣き、男の子を追い払いました。当時小学五年生、空には満月が浮かんでいました。それから二度と男の子は現れませんでした。めでたしめでたし」
髪が流れて女性の顔を覆う。それを振りやると足を組む。チヒロがかろうじて「めでたいの?」と聞くとフ、と口元だけで笑った。
「ちょっと前にさあ、実家帰った時に偶然再開したんだわ。お互いいい大人だよ」
その手が右の頬に触れた。タバコが欲しいね、と言う。そんなものを持っていない。でしょうね、と言われた。
「バツイチなんだって。たまにでいいから帰って来い。久しぶりに遊ぼう、って」
千夏にとってのチヒロもとい、チヒロにとっての千夏もまたただの隣人。だから「それ」は無責任、ただ首を突っ込む行為に他ならない。それでも口にせずにはいられなかった。
「行くの?」
「さあ」
「やめといた方がよくない?」
「まあなるようになるでしょ」
「やめときなって」
千夏は肘をついたまま嘲るように言った。
「デリケートな妙齢のじょっすィーと夢追いバンドマン、社会的にどっちの方が価値あるんだろうね」
口を開こうとしてもふさわしい言葉が続かなかった。
千夏が容赦ない訳じゃない。千夏の方が少しだけ多く歳を重ねている。ただそれだけのことだった。
「ねえ、じゃあ君はいつまでこの生活続けんの? 十年後の自分想像した事ある? 周りみんな結婚して子供いて、そんな中それでもその楽器の方が大事って胸張って言える?」
ベンベンベンベン。
腹に響く重低音。手元になくても指が動く。
「……逃げんのかよ」
「利口に生きるだけ」
「つまんねえな」
千夏の目元が緩む。初めて見る笑顔だった。
「十年後同じこと言えたら夢追いバンドマンの方が価値あるって認めてあげる」
約束、そう言って別れると、数日後千夏は何も言わずアパートを出た。
〈大澤真尋っていうの。その男の子〉
あの日帰りの車の中でそう口にした。
〈だから声かけたの。一字違いだったから〉
そういう本人、結局名乗りはしなかった。後日、まだ転送手続きがされていない郵便物が間違って届いて初めて彼女が〈小澤千夏〉であることを知った。
「……っていう話。その後一通だけ手紙が届いたんだけど、苗字がシオドメになってた。負けず嫌いも度を越すと一般とか運命とかいろんなもの越えていくんだろうな」
「手紙! で、結局デリケートな妙齢のじょっすィーの方が上だったってこと?」
「どうだか」
ハンドルを切る。ここを曲がれば野外バスケットのできる公共施設だ。
「ここで問題。頭空っぽのじょっすィーと夢追いバンドマン、社会的にどっちの方が価値があるでしょう」
「若いじょっすィーでしょ」
「ぎゃふん」
いつかの自分のように助手席で肘をついている女性がフ、と口元を緩めた。
「楽しみだね。気に入ってもらえるといいね」
そうして十年前、同じように空を見上げた。痘痕なクレーター。それでもチヒロは気に入ってくれる誰かを探し続けた。自分にできることを続けてきた。
〈チヒロの楽器、同じことの繰り返し〉
〈ずっと低い音。ずっと重低音〉
薄い壁越し、ずっと聞いている人がいた。うるせえと言いながら、それでも自分のどこかに置き換えながら。
〈でも今は分かる気がする〉
「うん」
車から降りる。見上げた空にまぶしい満月。その背後に太陽のニヤニヤしている様子が浮かぶ。その影響をモロに受ける月は、
「見とけよ」
そう思っているに違いない。遊びはもう終わりだ。
長かった休日がもうすぐ終わる。