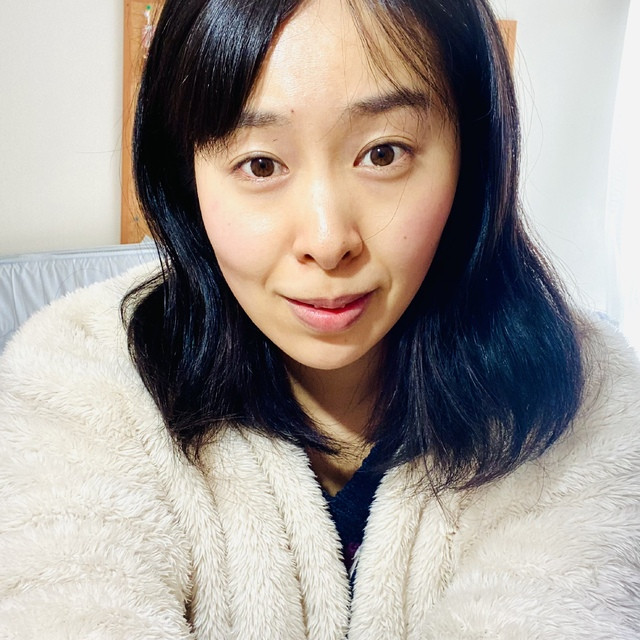第1話
文字数 15,644文字
少年ポールのディズニーの夢
ポールは、黒人で、高校に通っている。
将来の夢はまだない。
「いいよ、私達がやっとくから。」
ロックスターのような格好の女の子、チェルが言った。
女の子達は、ニヤニヤと笑って言った。
「あいつ、変わってる。」
ポールはチェルの気持ちに気づいていた。
チェルは、ポールが好きなのだ。
「僕は君のような人とは、恋愛はできない。」
「はあ?」
女の子達は、ポールをせせら笑った。
「いいよ。私だって、今は、あんたとは付き合いたくないから。」
チェルは答えた。
ポール一家は、長い間、団地に住んでいたが、ついこの間、おじいちゃんの家に引っ越して来た。
転校する必要はなかった。
家は古いが、暖炉がある。
気づいたら、暖炉のそばで寝てしまっていた。
起きると、おじいちゃんの家に似ているが、別の家に来ていた。
暖炉の前の、ユリ椅子で老人が寝ている。
ポールは、椅子から立ち上がり、部屋を出ようとした。
「ヒール?」
「えっ。」
「ジョイ?」
「すみません、僕、間違って、家に入ってしまったみたいで。」
老人は、ポールを見た。
「おや、新しいお手伝いか。」
「え‥。」
「よし、いい。今日は、庭の草むしりをしてもらおうか。」
老人はニヤリと笑った。
「え‥。」
「時給は15ドルだよ。何を立ってる。こっちだ。」
「15ドル‥。」
「このカマを使っていいから。」
「はい‥。」
ポールは、老人に言われるがままに、草むしりをした。
草むしりを終え、部屋に戻ると、老人は酒を飲みながら、ブツブツとつぶやいていた。
「俺が生まれたのは、1901年12月5日だった。イリノイ州シカゴのとても貧しい家だ。母親はドイツ人とイギリス人のハーフ。戦争中は、自分も捕まるのではないかと思ったよ。」
「あの、どうしたんですか。」
老人は、遠くを見ながら話し続けた。
「父親は厳格だった。仕事に失敗してばかりだったが、いつも冒険の話をしてくれたので、俺は、父が好きだった。」
「あの、僕、そろそろ帰らないと。」
「おやぁ‥。8時までではないのかい、スミス君。」
「僕の名前は、ポール・リアスです。」
「アハハ。変な名前。あ。」
老人は口をおさえた。
「人の名前を笑ったら怒られる。どこで、ジュディスが聞いているか分からないから。」
「ジュディス?」
「俺の面倒を見ている女でね、とても怖いんだ。」
「面倒を?では、その方が奥さんですか。」
「違うってぇ。」
老人は手を目の前で振った。
「従姉だよ。旦那と子供と、近くに住んでいる。」
「そうですか。」
外を見ると、知らない景色が広がっている。
ポールは顔をしかめて、窓に近づいた。
「何をやっている。物語の中に迷い込んだつもりか?」
「すみません、あなたの名前を教えてください。」
「アハハ、何、言ってんの。」
老人は笑った。
「じゃあ当ててみてよ。こっちに来て。」
ポールは、老人について行った。
「君は黒人。真っ黒で、目しか分からない。」
老人は階段の上の段から、言った。
ポールはもしや、老人から、性的なことを迫られるのではないかと、一瞬、身を引いた。
老人は、ポールを怪訝な目で見た。
「黒人は書けない。だって、イライアスがイケナイと言った。」
老人はぶつぶつとつぶやいていたが、「ああ!」といい、突然こっちに来た。
「大丈夫ですか!」
老人はハッとした顔をし、言った。
「すまん。つい、ガキの頃のことを思い出してしまう。」
「ここが、俺の秘密の部屋だ。」
そこには、ミッキーやアリスのデッサンが、沢山貼ってあった。
「俺が誰かわかるか?」
「分かりません。」
「まだ分からんか。」
老人は背をむけた。
ポールは、この老人は、ディズニーの画を盗んでいる人ではないかと疑い始めてしまった。
「お前は精神病患者なのか。」
老人は振り向いて言った。
「ちがいます。」
「ちがう?大体、俺の所に来るのは、死の病の者か、精神病患者だというのに。」
「あの、僕、もう帰ります。」
「帰る?帰り方はどうするのだ。」
「帰り方‥。」
ポールはうつむいた。
「君はバスケが好きなのか。」
ポールは小柄で、バスケは苦手だったが、いつもバスケプレイヤー風の服を着ている。
「別に‥。ただ、この服は好きで、よく着ています。」
老人が近づいてきたので、ポールは後退りした。
「何を。俺は、ウォルト・ディズニーだぞ。」
「ウォルトディズニー?」
「そうだ。」
「えっ、だってその人は、60年前に亡くなっているはずだ。」
「今は1964年。君の目の前にいる男は、62才のウォルトディズニーだ。」
ポールはうつむいた。
「どうした、信じないのか。」
「写真で見ていたのと、あまりにも違いますから。」
「写真は、よく撮れたものしか掲載しておらん。」
気づくと、自宅の暖炉の前で目を覚ました。
次の日、学校へは、ミッキーの絵の服を着て行った。
「おはよー、ポール。今日はミッキーなんだ。」
ウェアスルが話しかけた。
「ディズニーさんの夢を見ちゃって。」
「夢を?俺もこの前、夢見たぜ。」
ウェアスルが夢の話を始めた。
「あいつ、マジうける。」
女子達が爆笑している。
ポールは、親から掃除を頼まれていたが、学校から帰ると、ベッドでまた寝てしまった。
「死ぬ前に、ひとつ教えておく。ミッキーマウスを考えたのは、俺じゃない。父親のイライアス・ディズニーだ。」
ウォルトさんが覗き込んでいた。
「ウォルトさん?」
「ああ。そうだ。‥ちがう。ミッキーマウスを最初に書いたのは、俺じゃなく、父親のイライアスだ。」
「僕、まだ死にません。」
「‥ったく。わかっとらん。」
ウォルトの子供の頃は、ネズミが床を走るなんてことは、どこの家庭でもあった。
綺麗好きで、お金持ちに憧れていた兄のロイを励ますために、イライアスが書いたネズミが、ミッキーマウスの始まりだった。
「ロイ。ちょっと来い。父さんがいい物を描いたから。」
「何。」
「ほら。ネズミ君だよ。」
「うえー。」
ロイは舌を出した。
「お父さん、これ、何。ライチか何か。」
「ぶぶー。これはネズミです。」
「かわいい!これ、もらっていい?」
「いいよ。お前の物だ。」
イライアスは、ウォルトの頭をなでた。
ディズニー家の子供は、ロイとウォルトの2人だけだった。
イライアスは、冒険の話をしてくれた。
ジャングルで大トラを退治する話だ。
「‥それでな、父さん達は、道に豚の死体を置くことにした。おびき寄せ作戦だ。」
「おびき寄せ作戦?」
「そうだ。敵を騙して呼び寄せる時は、そう呼ぶ。」
小学校では、クラスの病弱なクリス君のことを、ウォルトは心配していた。
「あのさ。クリスと友達になりたいなら、私が放課後、おびき寄せてあげようか?」
「おびき寄せる?いいよ。クリス君とはもう友達だし、それに、おびき寄せるは、敵に使う言葉だ。」
「ホント?」
「うん、ホント‥。」
しかし、放課後も、クリス君は教室で椅子に座っていた。
「どうしよう。」
ウォルトは、校門で考えた。
クリス君のことは心配していたが、少し苦手だった。
「ウォル、まだいたのか。」
ロイが友人たちと来た。
「マイコちゃんが、クリス君をおびき寄せたんです。」
「おびき寄せる?どこに?」
「教室です。」
ロイとウォルトが見に行くと、クリスはもういなかった。
玄関に向かう途中で、クリスは泣きながら先生と歩いていた。
「どうしよう。」
「だけど、お前がやったんじゃないんだろ。」
そのことでウォルトが少し泣き、公園に寄ったので、帰るのが夕方6時になってしまった。
「お父さんに‥言う?」
「当たり前でしょう。どうしてこんなに遅くなったの!」
母親のフローラは怒った。
イライアスは、2人を正座させた。
「なぜ、そんなに遅くなったのか言いなさい。」
「マイコちゃんが、クリス君をおびき寄せたんです。」
「おびき寄せる?そんなことしちゃダメじゃないか。」
「だけど、イライアスだって‥。」
父がこんなに怒っている時に、ウォルトが、父をイライアスと呼んだので、ロイはウォルトをこづいた。
「なあ、ロイ。おびき寄せは、敵に使う言葉だ、分かるだろう。」
「分かるけど、この話に、俺は関係ないよ。」
「関係なくない。なぜ弟を連れ、すぐに家に戻らなかったんだ。」
「‥ごめんなさい。」
「さぁさ、ロイはもういいから。」
フローラが、ロイの肩を持った。
「お父さん、僕‥。」
父は何も言わずに、どこかを見て、無視をしている。
ウォルトは立ち上がり、台所でパンを食べた。
寝る時になって、父に、
「今日はごめんなさいね、ダーリン。」
と言うと、父は笑って、ウォルトの頭をなでた。
ウォルトが15才になった時に、ずっと憧れで眺めていた、父のネズミ君について、父にたずねた。
「父さん、これ、売れるかな?」
「売れないよ、そんなもの。くだらない。‥例え売れたとしても、せいぜい5ドルくらいにしかならん。」
ウォルトは、ネズミの絵を眺めた。
「じゃあ、僕が売っていい?」
「そんなもので金儲けするつもりなら、返してもらう。よこせ。」
父は、ネズミ君の絵を破ってしまった。でも、ウォルトは、ネズミ君をマスターしていた。
見ていたフローラが、イライアスにこそこそ話した。
次の日、イライアスは笑顔で、言った。
「父さんが間違っていた。絵が描きたいなら、そうしなさい。」
アートスクールにウォルトを入れてくれた。
「父さん、僕、漫画家になる。」
「好きにしろ。ただ、一つ言っておく。くだらん話は書くな。書くなら、意味のある話にしろ。」
イライアスは、ウォルトを指さし、言った。
「あの‥。」
「ネズミはお前にやる。」
「ミッキーという名前だ。」
イライアスは、ニヤリと笑った。
フローラとイライアスは、クスクスと笑った。
それは、2人の間での、イライアスのあだ名だったのだ。
ポールが庭仕事を終えて、部屋に戻ると、ウォルトさんが泣きながら1人でしゃべっていた。
「ごめんなさい、お父さん。でも、お父さんとお母さんをモデルにした、映画を作ったんだよ!!オーロラ姫。見てくれた?‥なーに。お父さん、いつもお母さんにキスしてたでしょう。」
ウォルトさんは、ワーワー泣いている。
ガチャ。
家に、誰かが入ってきた。
「うるさいわよ!!何事なの!!」
「ジュディス。」
「ウォール、またなの?いい加減にして。」
「勝手に来るなと言っているだろう!!」
「だけどね、ご近所さんにも、あんまり迷惑かけられないから。」
ジュディスは疲れたように言った。
「あら、新しいお手伝いの子なの?」
「そう。新人の、セント‥。」
「ポール・リアスです。」
「はじめまして、ポール。」
「私は夕食の準備をするわ。その間、あなたは‥。」
「俺は、君の本を読んでいるよ。」
「じゃあ、とっておきの曲をかけてあげる。」
パメラは音楽をかけた。
「この曲は聴いているとね、物語に入り込めるの。」
パメラは言い、キッチンに行ってしまった。
「いいね、オーロラはドイツ人だ。シンデレラもドイツ人。アリス?アリスはフランス人。でも、ドイツ人とのハーフっていう設定だよ。」
ウォルトは、パメラの本を読まずに、1人でぶつぶつと語りかけていた。
「じゃあ、そう言ってあげればいいでしょう。」
パメラが言い、ウォルトは黙った。
「ドイツ人ばかり、悪者にされて。可哀想に。」
パメラは、お洒落な肉料理を置いた。
「これは仔羊の煮込み料理よ。」
「わぁぁ。美味しそうだ。」
2人は横並びの机で、料理を食べた。
「じゃあ、白雪姫は何人なの?」
「白雪は‥日本人だ。」
「日本人?!やだ、ウォルト。知らないの?日本人のお姫様は、そんな城には住んでいないのよ。」
パメラは立ち上がり、本を持ってきた。
「ほら、これが、日本のお城。綺麗でしょう。」
「古いんだねぇ。」
「古い?当たり前でしょう。何百年も前に建てられたんだから。」
ウォルトは子供の頃のことを思い出した。
父親と、兵隊になりきり、遊んでいる。
漫画家になり、家を出た後も、辛い時は実家に帰り、父親に抱きついた。
ウォルトは、広報をお願いしている、アブに言った。
「とにかく。ウォルトディズニーは父親とは仲が悪い、ということでな。」
「え‥でも。この前も、お父さんが会社に来ていたでしょう。仲が悪いと?」
「そう。仲が良いなんて、家族に迷惑をかけるだろう!」
「父さん!」
「あ‥俺達のネズミ君は、こんなにでかくなったか。」
父は、ミッキーのポスターを見て行った。
「ちがう、これは、ポスター用だよぉ!原寸大はこのくらい。」
ウォルトは指で示した。
「父さん、これ見てよ。」
「なんだこれ。真っ黒じゃないか。」
「当たり前だ、黒人だよぉ。」
「‥いいか。黒人ってものは、こんなんじゃない。もっと恐ろしくて怖い人間なんだ。」
父は、物語を言う時の口調になった。
「お前は黒人なんて書かない方がいい。黒人はな、黒人だけのものだ。」
「いい?あなたと私の会話は聞かれているの。」
「ええっ。誰にだい?」
「その人は妖精よ。」
「妖精‥?ピノキオのブルーフェアリーのような人ですか?それともシンデレラのフェアリーゴッドマザー?」
パメラは首をふった。
「では、白雪姫の悪い魔女かい?あれは、君がモデルになってる。」
パメラは笑った。
「私がモデルですって?」
「ああ、そうさ。」
「そんなわけないでしょ。」
パメラは大笑いした。
2人は恋人‥だと思う関係だった。
しかし、ウォルトにとって、最大の試練が訪れる。
「ああ、もう信じられない!私のメアリを、映画化するだなんて!」
「そんなに怒らなくてもいいだろう。僕が一番好きな話だ。」
「言っておくけど、メアリは私だけの人なのよ!」
ウォルトはため息をついた。
「私だけの人なんて。では、なぜ、本を出版したんだ。」
「それにはいろいろな事情があるの。あなたには分からない、大人の事情ってものが!!」
ウォルトは黙って家を出た。
ウォルトは、1人で話す所が自分と似ていたし、食べる時も音をたてて食べる。そこがパメラを安心させた。
パメラにとってウォルトは、気軽なボーイフレンドだったのだ。
パメラは、ウォルトが自分よりもずっと大物で、ずっと仕事ができるということを考えないようにしていたせいで、一緒の仕事はうまく進まなかった。
「早く決めなよ。そうじゃなきゃ、僕は死んじゃうよ。」
「死ぬですって?あなたが?」
「ああ、そうなれば、君は誰とデートをするんだい?」
「あのね、私にはそういう人が他にもたくさんいるんです!」
ウォルトはまた、黙って家を出た。
ウォルトは、パメラの人柄だけでなく、才能にも惚れていた。
もちろん独身だし、そこも好きだった。
パメラには、自分のように、有名になってほしかったのだ。
ウォルトの時代の女性は、偉い人の奥さんになるしか、偉くなる方法がなかった。
「アブ。僕は結婚する。」
「えっ、結婚?もしかして、トラバースさんとですか?」
「違うよ。結婚したことにする。」
ウォルトは結婚したことにした。そして、子供が2匹いることにした。
「‥なんで、ネズミ君の名前がミッキーなのぉ?」
「それは秘密です。お父さんとお母さんのな。」
「ふーん。でもさ、いつか教えてくれるよね?」
「さあ、どうかな。でも、秘密を解くカギは、いつも君の胸の中だ。」
父はキラキラして答えた。
「困るなぁ。だってキャラ設定が出来ないんだもの。」
「設定?漫画を描く上でか。」
「うん‥彼女がいるとか、子供がいるとか。」
「子供?ミッキーには子供いるよ。」
「えっ。それ、何人?」
「2人。あっ、2匹か。」
「それだけぇ?変だなぁ。ネズミなら、もっと沢山生まれるはずだもん。」
「まあ、父さんのネズミには、子供はそんなに生まれなかったんだな。よし、今日は、このへんにしておくか。」
「ちょっと待って。ミッキーの奥さんの名前だけ教えて。」
「ミニー・マウス。世界で一番カワイイ、ネズミちゃんだ。」
「ミニー?名前が、似てるんだねぇ。」
「ミッキーとミニー。いいだろう?」
「ふーん、へ・ん・な・の!」
ウォルトは大きな声で言った。
「えーと、パメラ。いいね、ここは会社だ。」
「ええ、そうでしょうよ。そして、私は‥あなたの、上司。」
「いや、上司ってわけじゃない。」
「じゃあ、取引先の役員ってわけだ。」
「とにかくさ、仲間には優しくしてくれよ。色目を使え、ってわけじゃない。」
「承知、しました。」
パメラはシャキッとした。
しかし、パメラは怒り狂ってしまう。
「ところでディズニーさん、この会社はどうしてこう、ハゲが多いの?」
「さあ、どういうわけだろうねぇ。」
音楽の話し合いでは、ついにパメラは泣きだしてしまった。
「ミッキーさん、なんなの?これ。」
「パメラ、ミッキーは父のあだ名だ。父がミッキーで、母がミニー。多分、兄が生まれる前に2人でつけた。」
「そんなことどうでもいいわよ!!」
パメラは出て行ってしまった。
仕事は順調に進まなくなった。
そんな中、ウォルトは、ディズニーランドで働く、黒人青年と仲良くなる。
名前は、ルイという。
ウォルトがメリーゴーランドの馬に横座りしていたので、ルイが注意したのだ。
「お客様、すみませんが、横座りは危険ですので。」
「どうしてそんなこと言う?書いてなかったぞ。」
「すみません、でも決まりなんです。」
「決まり?ウォルトディズニーが決めた決まりか?」
ウォルトが引き下がらないので、2人は事務所で話すことになった。
「あの、僕、あなたがディズニーさんとは知らなくて。」
「いや、知らなくて当然だとも。写真の男とは全く違う。」
ポールは、今日は学校で、調理実習の日だった。
みんなでハンバーグを作るのだ。
「ポール。何、そのぐちゃぐちゃ。こう。こうやるの。」
チェルが、ポールにハンバーグの丸め方を教えた。
「マジでお前ら、付き合ってんのか?」
トイがニヤニヤと笑った。
「ばーか、違うっつーの。」
チェルが言った。
「ポール?」
「あの‥失礼かも、しれませんけど。お酒‥飲みすぎると、よくないって。」
「酒か?いや俺は、映画のストーリーを考えているんだ。あ~、次回作は、どんなストーリーにしよう。それで、どんなお姫様にしよう。」
「‥酒を飲むと、くるくる世界が回って面白いんだよ。でも、昔‥。」
ウォルトさんは笑いだした。
「どんな感じなのかなぁ‥?ドラッグをやるって。」
「さあ、分かりません。‥うちの母親が、昔、やったことがあって、酷い目にあったと言っていました。」
「へええ。なら、なんで、みんな、そんなものをやるんだろう。」
「さあ‥僕には、分かりません。」
ルイは本当にドラッグをやったことがなかったが、地元で人気のDJコングは、ドラッグをやっていると知っていた。
コングは、ルイの兄貴分である。
ルイは、コングのクラブに行った。
「よぉ、兄弟。久しぶりだぜ。」
「このクラブには、昔は、白人は入れなかったが、俺がやめさせたんだ。
見ろ。今では、黒人より、白人の方が多い。」
ルイはうつむき、顔をあげ、言った。
「兄さん、差別をしているのは、白人より黒人の方じゃないのかと、僕は思うんだ。」
「兄弟。白人は、俺達を船に乗せて運び、奴隷にした奴らだぜ。」
ルイは鼻をかき、首をかしげた。
コングは大笑いした。
「兄弟。そりゃ無茶な話だぜ。黒人差別については、教科書にも書いてある。」
黒人の仲間が酒を持ってきた。
イエーとか、ヒューヒューとか、歓声をあげている。
「ほらな。黒人はこうして、仲間うちだけで理解し合い、生きてきた。兄弟。」
次の日。明るくなって、ルイが散歩をしていると、コングが来た。
「ところでお前。どうしてこっちに来た。ディズニーで働いてるって聞いたぜ。」
ルイは、黙った。
「まさか、クビになったか?」
「いや‥兄さん、まだ、ドラッグ持ってるかな?」
ルイはコングの家の車庫に来ていた。
「ほら。昔の残りがまだここにある。」
ルイは、ドラッグを持った。
「ディズニーさんが、こんなものをやってみたいと?」
ルイはうつむいた。
2人は外に出た。
「いや~俺には、夢のような世界だぜ。」
「兄さん、今度、来てみないか?」
「いや、俺はいい。ラップとブルース。そして仲間。少しのレディー。俺には、それだけの世界で十分だ。」
コングは、余裕の表情で、ニヤリと笑った。
3日後の夕方5時。
夕日が差し込む窓際に、2人はいた。
「いいか。今から俺は、ドラッグをやる。2人でせーので飲もう。」
「僕も‥なんですか?」
「そうさ。当たり前だ。‥この会社にいたければね。」
ウォルトはニヤリと笑った。
気づいたら夜で、2人は、ゲイバーに来てしまっていた。
2人とも、ゲラゲラ笑っている。裸のオカマに、ウォルトはお札を渡した。
次の朝。
我に帰ったウォルトは、ドラッグをしても、なんの意味もないと実感した。
なんの夢も、見ることはできないし、危うく、犯罪に巻き込まれるところであった。
ルイは、疲れた顔でいつも通り出勤していた。
「ルイ。昨日のことは、これな。」
ウォルトは、人差し指を口に当てた。
ルイは無表情で、うなずいた。
ウォルトは、絵を描くことと、お茶とコーヒーをいれることと、スクランブルエッグを作ること以外は、まともにできるとは言えなかった。
掃除の仕方も、普通の人とは違い、窓を箒がけしてから、拭いたりしていた。
「俺は66才で死ぬことにした。亡くなるのには、理由がある。
親しい仲間はみんな孤独だったが、本制作が始まると、若いのが入ってきて、
みんな、恋をして、楽しんでいた。
ある日のことだ。
俺は、現場で泣いてしまった。
俺が、感動以外で泣いたことは、22才の時以来であった。
でも、それでようやく、楽しんでいた者達も気づいてくれた。
制作に集中し、恋もやめた。
もう、自分は、いない方がいい。
自分がいなくても、やっていける、それが、俺が死ぬ理由だった。
俺は、いつものように、ブランデーにドーナツを浸して食べた。
今日ならいけると思った。
そして、睡眠薬を服薬した。いつもの30倍の量だった。
俺はベッドに横たわり、眠るように死んだ。
第一発見者は、兄のロイだった。
俺が自殺したことに気づき、俺にすがりついて泣いた。
しかし、世界の子供達の夢を壊さないために、立ち上がり、自殺の証拠を隠滅した。
捨てた物は、睡眠薬だけでない。
俺の遺書まで捨てたのだ。
でも、絵だけは、のこしてくれた。
いつものように、ジュディスと旦那、息子のハル、ハルのガールフレンドのミカリが来た。
ジュディスは、「嘘でしょぉ!!」と叫び、俺にすがりついて大泣きした。
ジュディスの旦那のケイトは、俺の手を握って悲しんだ。
ハルのガールフレンドのミカリは、家を飛び出し、近所の女の子達を呼びに行ってしまった。
葬儀には、1000人以上の子供達が来た。
トイレが足りないと思ったが、みんなちゃんと我慢できた。
パメラは、悲しむファンの後ろの方で、腕を組み、俺の亡骸を見つめていた。
ロイが、外に出て風にあたっていると、
どこからともなく、声が聞こえた。
『ほら兄さん。俺の家の前に、遊園地を作った方がよかっただろう?』
ロイは涙をこぼした。
俺は貧しい方が好きだった。
なので、金持ちになってからも、小さな家に住んだ。
ディズニーランドも、こんなに大きなものではなく、
俺の家の庭にある、小さな遊園地でよかった。
ディズニーワールドリゾートの完成を見ることなく、俺はこの世を去る。
映画を作る時にいつも悩んでいたことは、ラッキーエンドにするか、ハッピーエンドにするかということだ。
俺は、どちらかというと、ラッキーエンドの方が好きだった。
ありがとう諸君。俺に生きる希望を与えてくれたのは、諸君なのだ。」
「いい話ね、ウォルト。」
パメラが、珍しいフレーバーティーを持って、後ろに立っていた。
「だけど、どうしてそんなに、未来のことが分かるの?あまりにも、リアルすぎるわ。」
「それは‥。」
「ねえ、どうして?もしかしてあなた、未来を見てきたということ?そうなの?」
「いや、未来を見てきたわけじゃない。今のは、俺が考えた作り話だ。」
パメラは高らかに笑った。
「あなたって面白いのね。‥従姉と仲が良いなんて羨ましいわ。私の従兄なんて、変な女と結婚して、10年前に交通事故で亡くなってしまったのよ。」
「今でも親しくしているのは、ジュディスだけだ。というか、そっちが親しくしてくる。俺の従弟も、変な人と結婚し、戦死した。いたたまれないよ。」
「自分の思い通りにいく人なんていない。自分が思い通りにできる人間は、自分だけだ。」
「ええ、ホント、そうよね。」
「なあポム。俺がメリーポピンズをどうして、実写にしたか分かるかい?」
パメラはウォルトを見た。
「それは、君に主役を務めてほしかったのさ。だって君は昔、女優だったんだろう?」
パメラは少し笑った。
「でもそれはずっと昔の話よ。いろいろしてしまったけど、本当にお気に入りの映画になったわ。」
パメラが泣いてから1カ月後、メリーポピンズの打ち合わせが再開した。
パメラは神妙な面持ちだったが、前よりも落ち着いて、打ち合わせに臨んでいた。
「パメラ‥今日はレストランに行かないか?」
普段は、外食が苦手なパメラだったが、渋々OKした。
2人は、いつもよりもお洒落な服で、少しだけ高級なディナーを食べた。
パメラが外食が苦手な理由は、ウォルトの隣だと、みんながジロジロ見るからだ。
でも本当は、みんな、美しいパメラを見ているのだった。
「美味いね。パメラの料理の方がもっとうまいけど。」
パメラは食べ終わると立ち上がって、スケッチブックを出した。
「私ね、あなたのように絵がうまくなりたくて、最近、お姫様の絵を描いているのよ。」
「へえ、見せてよ。」
「ほら。」
そこには、いろいろな国のお姫様の絵が、リアルに書かれていた。
「上手いじゃないか。」
パメラは満面の笑みで笑った。
「これはフィリピンのお姫様。こっちがベトナムのお姫様よ。私、アジアに興味があるの。いつか、アジアに行ってみたいわ。」
パメラは夢見心地で言った。
女子達は、落ち込んでいるチェルのまわりに集まって座っていた。
男子達はニヤニヤと見ている。
ルゥは、チェルの取り巻きの1人で、インド人と白人のハーフ、リランカのことが好きだった。
「あんなやつ、止めた方がいいよ。まじで。」
「絶対、チェルのこと、裏切るって。」
ポールが来た。
女子は無言で、ポールを見た。
チェルもちらりと見たが、またうつむいた。
最近のポールは、ディズニーキャラクターのキーホルダーを、カバンに10個以上つけている。服は毎日のようにキャラクターだ。
「おはよー。ポール。」
男子達が少し引き気味で話しかけた。
「どうした、これ。」
「いやぁ、ちょっと最近、ハマっちゃって。」
ポールはニヤニヤと笑った。
男子達も心配そうな表情でポールを見つめた。
ポールは、進路調査の紙に、『ディズニーカンパニー』と書いた。
担任の、アレクサンドラ先生が呼びだした。
「ポール。ディズニーに入るためには、何の勉強が必要?」
「必要なものは、両親の愛です。先生。」
「ポール。あなたがご両親から愛されているのは、よく分かってる。でも、なんの勉強をすればいいと思う?」
「それは‥絵‥です。」
「そう。本当に入りたいなら、アートスクールに通わせてもらうとか、今の推理研究会から、美術部に変えるとか、そういうことが必要でしょう。」
「はい‥。」
「1901年12月5日。俺は、イライアス・ディズニーとフローラ・ディズニーの2人目の息子として、産声をあげた。元気だったかどうかは分からない。なんせ2500グラムの未熟児だったと聞いている。その日は、晴れの曇りで、紫色の猫が家の前に来ていた。その猫がチシャ猫のモデルとなっている。ちなみにそれを教えてくれたのは、父のイライアス・ディズニーだ。父はいつも、私に生きるために必要なヒントをくれた‥。」
ウォルトさんは、窓の外を見ながら、1人でしゃべっている。
「あの‥ウォルトさん?」
「ん?‥おや。ポールか。」
「はい。また、来てしまって。」
「いや、いいよいいよ、客人は歓迎だ。今、お茶をいれよう。」
「チシャ猫を描いてくれたのは、父だ。俺が描いたチシャ猫は、どこにでもいる猫だった。」
ウォルトさんは、ハーブティーをいれてくれた。
「ハーブティーはいい。孤独を癒してくれる。」
ポールもハーブティーを飲んだ。
「アリスのうさぎを描いたのは、俺だけどね。」
ウォルトさんは満足そうに笑った。
「イライアス!!」
「ああ?なんだ。」
「じゃーん!!ミッキーの家族です。」
イライアスはメガネをつけ、ウォルトが描いたミッキーの家族を見た。
「沢山いるんだねぇ。」
「当たり前じゃん。ミッキーは二十日ネズミだもん。」
「この子がねぇ、ミッキーの妹のチッキー。」
うなずきながら、イライアスが言った。
「チミーじゃなくて、チッキーなのか?」
「そう!ミッキーのお父さんとお母さんは、子供達にキをつけたかったんだぁ!それはね、家に、キツツキが巣を作っていて、その音が、幸せの音だったからなんです!」
「それでね、この人がミッキーのおじいちゃん。この人がおばあちゃん。ミニーのおじいちゃんはね、もう亡くなってしまっていないんです。」
「ああ、そうなんだ。」
「ミッキーとミニーには、子供が沢山いる。ほら。」
「この子だけ、白いんだねぇ。」
「この子はホワイト君。黄色のワンピースの子はレイちゃんで、とても小さい。」
「ミッキーと家族は、いつも猫に怯えて暮らしているんです。」
「ああ、猫にね。」
イライアスはしげしげと絵を眺めた。
しかし、ウォルトが大人になって、登場人物が多すぎると、アニメ制作が大変という理由から、ミッキーとミニー以外、カットされてしまった。
「わああああ!!またクリス君に、遊ぼうって言っちゃったよおおお!!」
中学生のウォルトは、大泣きしていた。
『クリス君、今度また、遊ばない?みんなでさ。家に集まって。』
『いや?それならデートはぁ?僕と2人で。』
「おい。クリス君は、病弱すぎるから、誘っちゃダメだって、父さんが言ってただろう。」
「ウォル。父さんが言っているだろう。社会で生きていくためには、余計なことに口をだすなって。」
ウォルトはロイを見た。
「お前は絵しか描けない。だからそのことをしっかり覚えるんだ。」
イライアスとフローラは、なぜか、よく、ハプスブルク家の話をしていた。
「ねえそれ、なんの話?」
「それはそれは、怖い、人食い鬼の話です。」
イライアスは言った。
「じゃあそれを教えてよ。」
「いいけど‥今度、出かけた時にな。」
イライアスは、ウォルトが変な不良に引っ掛からないよう、昼間の黒人パブに連れて行った。ちなみにこの店にはすでに、ロイを何度か連れてきていた。
店員もお客も、黒人ばかりだ。
みんな、ウォルトとイライアスをジロジロと見た。
「ああ~めんどくせぇ。」
イライアスは、黒人を睨み、舌打ちをした。
「お父さん、やめなよ!」
「いいんだ。」
イライアスは、横柄な態度をとった。
「お前の友達の、黒人のボリ君の家は、貧乏すぎるからな。関わっちゃだめだぞ。」
「お父さん!しーっ!」
「ごめんなさい、僕のお父さんが。」
ウォルトは黒人に謝りに行くと、黒人はニンマリ笑った。
イライアスがやっていることの意味を分かっていたのだ。
「なんだ。お前、あの人に何言いやがった。」
イライアスが聞いた。
「何も。お父さんが馬鹿だから、謝っただけ。」
「余計なことを言うな。」
イライアスがウォルトをゴツンとしたので、ウォルトはそのパブで、大変、肩身の狭い思いをして過ごした。
家でウォルトは父に聞いた。
「それでさ、お父さん!聞き忘れちゃった、人食い鬼の話。」
「ああ、そうだった。ハプスブルク家はな、フランスの王族だったんだけど、実は、人を食って生活してたんだ。」
「人を食べて?!」
ウォルトは手で口をおおった。
「それでな‥。」
父はハプスブルク家について話した。
途中、話がそれ、「アハハ!面白い!!」ウォルトは無邪気に笑った。
ウォルトは発達障害だったので、いつまでも子供のようだった。
ディズニー一家は貧しく、ウォルトも新聞配達や郵便配達を手伝ったりした。
「これでも、少しは金になるかな。」
イライアスが言うと、フローラはうなずいた。
ウォルトは物語のように、仲の悪い家の郵便を交換したりしなかった。
「えらいな。」
イライアスはニッコリ笑った。
「フローラ、ウォルトは本当にいい子だな。‥それに絵も上手だ。天才かもしれん。」
イライアスは、ウォルトに聞こえるように、こそこそ話した。
時々、イライアスの友人が、牛肉をくれたので、ステーキを食べた。
父は毎回、「あ~今日もくたびれた。」と言って、椅子に座った。
「あの‥ご両親と仲がよかったなら、亡くなった時とか、すごく、辛かったですよね‥。」
「ああ、辛かったとも。」
「お父さん、ミニーが亡くなるシーンを描いてみた。ほら。ミッキーが泣いてるんだよ。」
「おや。どうしてそんなもの描くの。ミッキーとミニーは、永遠だよ。」
「ダメ。これはイライアスとフローラの未来の姿なんだよ。お父さん。お母さんを残して、先にいったら、絶対にダメだから。」
「母は俺が雇った修理工のせいで死んだんだ。」
「‥とても、悲しいですね。」
「ああ。俺はその時、フロリダにいたがね。すぐに駆け付けたよ。」
クラスの女子はまた、落ち込んでいるチェルのまわりに集まって話していた。
「チェル。本当にポールが好きなら、うちらも応援するよ。」
「でもさ。なんかあったら、スマホですぐに電話して。ポールに突然襲われたとか、そういう時は。」
ガラガラッ。
ポールが教室に入ってきたので、クラスのみんなは一斉にポールを見た。
「おはよーポール。」
ルーが声をかけると、他の男子達も、「おう。」などと声をかけた。
「おはよう。」
ポールは、ディズニーキーホルダーをじゃらじゃらつけ、夢見心地だ。
男子達はこそこそ話した。
ポールの学業態度にはなんの問題はなかった。
「ポール。」
チェルがポールの机に来た。
「えっ。」
「あの‥ポールがディズニーが好きみたいだから、私、ディズニーについて調べてみたんだ。」
「えっ。ホント?」
「うん。」
チェルはディズニーのイラストの切り抜きなどを貼った、ノートをみせた。
「これが、ウォルトディズニーさんの最初のキャラクター。オズワルド。」
「オズワルド??」
「うん。私達が生まれるずっと前に流行ったものだから。」
「へええ‥。」
放課後、チェルが言った。
「掃除、やっとくよ。今日こそ。」
「え。ホント?」
女子達がニヤニヤと笑っている。
ポールが玄関から出た時、教頭のヒーマス先生が声をかけた。
「ポール君。どこへ行くんだい?」
「えっ‥あの‥帰ります。」
「ダメだ。掃除をやってないじゃないか。」
ポールは校長室の掃除をやることになってしまった。
ポールは疲れ果て、今日も家に帰ると寝てしまった。
ウォルトさんは、コーヒーを飲みながら、ぷりぷりと怒っていた。
「‥俺が描いた女の中では、アリエルが一番好きだ。
アリエルが結婚するのは本当は許せない。」
「あの、ウォルトさん。」
「ん。」
「ポールです。」
「おお、ポール君か。久しぶりだね。」
「そう、ですか。」
「ああ。君に最後に会ったのは、もう19年前だ。」
「19年も前?」
「今、君がいるのは2025年だ。」
「‥じゃ、みんなもう、亡くなってる?」
「いや、そんなことない。」
ウォルトさんは、満足そうに言った。
「そう、ですか。」
ポールはうつむいた。
「パメラのことか?」
「はい。」
「パメラは死んだというか、小さくなった。」
「え‥。」
「100才の誕生日の朝、パメラは、赤ん坊に戻っていたんだ。パメラは、子供を持たなかったことに罪を感じていた。それで、自分自身が赤ん坊に戻ってしまったという訳だ。」
「‥本当にそんなことが?」
「ああ、本当だとも。」
「カフェインは好きか?うまいカフェラテの淹れ方を知ってる。」
「はい。」
ポールは少し顔をあげ、答えた。
ウォルトさんはぶつぶつ言いながら、カフェラテをいれてくれた。
「どうだ。」
「美味しい、です。」
「そうだろう。疲れた時は、いつもこれを飲む。」
ウォルトさんは満足そうに言った。
「何か、俺に、聞きたいことはあるかい。‥夢の中で紛れ込んで来た者に、この質問をすると、大体、ミッキーはどう考えたのかとたずねてくる。‥ポール。君にはもう教えただろう?」
「はい。」
「他人は、他人のモノだ。自分は自分だけのモノ。それは家族や両親でも同じだよ。ポール、それは分かるな?」
「はい、分かってます。それで、ウォルトさんに聞きたいことは、オズワルドについてなんです。オズワルドは‥どうやって生み出されたのですか?」
「いい質問だ。」
「やっぱり、キャラクターはお前が考えなきゃダメだ。」
ウォルトがもうすぐ有名になりそうな時、イライアスが言った。
「え‥僕だけじゃ無理だよ。父さんもいてくれなきゃ。」
「ダメだ。集中して、考えろ。」
ウォルトはしぶしぶ、新キャラクターを考えた。でも浮かばなかったので、父のネズミをウサギにしただけのキャラクターにした。
「これ‥。」
「いいよ、これ。それで、名前は。」
「名前‥。」
「おい。お前、友達の名前にするなんて言わないよな。その子にもお金をあげなきゃいけなくなるんだから。」
「じゃ、オズワルド。」
もともと、オズワルドはグーフィーにつけていた名前だった。
「よし。」
父はニヤリと笑った。
しかし、オズワルドは自分が先に書いていたという、ウォルトの中学時代の友人が現れたり、配給会社に権利を取られたりしてしまった。
そのせいで、ウォルトの最初の会社はつぶれてしまう。
ちなみに、5年後に、その中学時代の友人は自殺してしまい、そのことで、2年ほど、ウォルトは落ち込んでしまった。
「やっぱりミッキーにするよぉ。」
「じゃ、そうしろ。その前に、母さんに聞いてな。」
「どうして‥母さんに?」
「どんな時でも、大事なことは、女親に聞いて決めるもんだから。」
ウォルトはしぶしぶ、フローラに聞き、ミッキーを主要キャラクターに戻した。
王子のモデルは、大体、兄だった。
アブは昔からの友達で、生涯仲良くした。
「今までの話、嘘か誠か。決めるのは君次第だ。」
ウォルトさんは言った。
「信じてます。でもウォルトさんは今‥何歳ですか?」
「俺か?俺は130歳だ。」
「そんな‥。」
「ああ、本当だ。」
ウォルトさんは満足そうに言った。
「君とはまた会えるといいな。」
ウォルトさんの笑顔はだんだん遠くなる。
ポールは、自宅のベッドで起きた。
「これまでの話、信じるか信じないかは、君次第だ。」
ウォルトさんは画面に向かって言い、ニヤリと笑った。
「それにしても、人生は素晴らしい。」
そう言って、窓を開けた。
「アハハ!今日はいい日だ!」
窓を開けたまま、家のドアを開け、歩いて行ってしまった。
ウォルトさんは、途中、宙がえりを一回した。
まるでミッキーのように。
ディズニーランドで、ミッキーマウスは貧しいウォルト少年の手をとった。
偉大なアーティストとなったウォルトディズニーの手も、同じように。
The end
ポールは、黒人で、高校に通っている。
将来の夢はまだない。
「いいよ、私達がやっとくから。」
ロックスターのような格好の女の子、チェルが言った。
女の子達は、ニヤニヤと笑って言った。
「あいつ、変わってる。」
ポールはチェルの気持ちに気づいていた。
チェルは、ポールが好きなのだ。
「僕は君のような人とは、恋愛はできない。」
「はあ?」
女の子達は、ポールをせせら笑った。
「いいよ。私だって、今は、あんたとは付き合いたくないから。」
チェルは答えた。
ポール一家は、長い間、団地に住んでいたが、ついこの間、おじいちゃんの家に引っ越して来た。
転校する必要はなかった。
家は古いが、暖炉がある。
気づいたら、暖炉のそばで寝てしまっていた。
起きると、おじいちゃんの家に似ているが、別の家に来ていた。
暖炉の前の、ユリ椅子で老人が寝ている。
ポールは、椅子から立ち上がり、部屋を出ようとした。
「ヒール?」
「えっ。」
「ジョイ?」
「すみません、僕、間違って、家に入ってしまったみたいで。」
老人は、ポールを見た。
「おや、新しいお手伝いか。」
「え‥。」
「よし、いい。今日は、庭の草むしりをしてもらおうか。」
老人はニヤリと笑った。
「え‥。」
「時給は15ドルだよ。何を立ってる。こっちだ。」
「15ドル‥。」
「このカマを使っていいから。」
「はい‥。」
ポールは、老人に言われるがままに、草むしりをした。
草むしりを終え、部屋に戻ると、老人は酒を飲みながら、ブツブツとつぶやいていた。
「俺が生まれたのは、1901年12月5日だった。イリノイ州シカゴのとても貧しい家だ。母親はドイツ人とイギリス人のハーフ。戦争中は、自分も捕まるのではないかと思ったよ。」
「あの、どうしたんですか。」
老人は、遠くを見ながら話し続けた。
「父親は厳格だった。仕事に失敗してばかりだったが、いつも冒険の話をしてくれたので、俺は、父が好きだった。」
「あの、僕、そろそろ帰らないと。」
「おやぁ‥。8時までではないのかい、スミス君。」
「僕の名前は、ポール・リアスです。」
「アハハ。変な名前。あ。」
老人は口をおさえた。
「人の名前を笑ったら怒られる。どこで、ジュディスが聞いているか分からないから。」
「ジュディス?」
「俺の面倒を見ている女でね、とても怖いんだ。」
「面倒を?では、その方が奥さんですか。」
「違うってぇ。」
老人は手を目の前で振った。
「従姉だよ。旦那と子供と、近くに住んでいる。」
「そうですか。」
外を見ると、知らない景色が広がっている。
ポールは顔をしかめて、窓に近づいた。
「何をやっている。物語の中に迷い込んだつもりか?」
「すみません、あなたの名前を教えてください。」
「アハハ、何、言ってんの。」
老人は笑った。
「じゃあ当ててみてよ。こっちに来て。」
ポールは、老人について行った。
「君は黒人。真っ黒で、目しか分からない。」
老人は階段の上の段から、言った。
ポールはもしや、老人から、性的なことを迫られるのではないかと、一瞬、身を引いた。
老人は、ポールを怪訝な目で見た。
「黒人は書けない。だって、イライアスがイケナイと言った。」
老人はぶつぶつとつぶやいていたが、「ああ!」といい、突然こっちに来た。
「大丈夫ですか!」
老人はハッとした顔をし、言った。
「すまん。つい、ガキの頃のことを思い出してしまう。」
「ここが、俺の秘密の部屋だ。」
そこには、ミッキーやアリスのデッサンが、沢山貼ってあった。
「俺が誰かわかるか?」
「分かりません。」
「まだ分からんか。」
老人は背をむけた。
ポールは、この老人は、ディズニーの画を盗んでいる人ではないかと疑い始めてしまった。
「お前は精神病患者なのか。」
老人は振り向いて言った。
「ちがいます。」
「ちがう?大体、俺の所に来るのは、死の病の者か、精神病患者だというのに。」
「あの、僕、もう帰ります。」
「帰る?帰り方はどうするのだ。」
「帰り方‥。」
ポールはうつむいた。
「君はバスケが好きなのか。」
ポールは小柄で、バスケは苦手だったが、いつもバスケプレイヤー風の服を着ている。
「別に‥。ただ、この服は好きで、よく着ています。」
老人が近づいてきたので、ポールは後退りした。
「何を。俺は、ウォルト・ディズニーだぞ。」
「ウォルトディズニー?」
「そうだ。」
「えっ、だってその人は、60年前に亡くなっているはずだ。」
「今は1964年。君の目の前にいる男は、62才のウォルトディズニーだ。」
ポールはうつむいた。
「どうした、信じないのか。」
「写真で見ていたのと、あまりにも違いますから。」
「写真は、よく撮れたものしか掲載しておらん。」
気づくと、自宅の暖炉の前で目を覚ました。
次の日、学校へは、ミッキーの絵の服を着て行った。
「おはよー、ポール。今日はミッキーなんだ。」
ウェアスルが話しかけた。
「ディズニーさんの夢を見ちゃって。」
「夢を?俺もこの前、夢見たぜ。」
ウェアスルが夢の話を始めた。
「あいつ、マジうける。」
女子達が爆笑している。
ポールは、親から掃除を頼まれていたが、学校から帰ると、ベッドでまた寝てしまった。
「死ぬ前に、ひとつ教えておく。ミッキーマウスを考えたのは、俺じゃない。父親のイライアス・ディズニーだ。」
ウォルトさんが覗き込んでいた。
「ウォルトさん?」
「ああ。そうだ。‥ちがう。ミッキーマウスを最初に書いたのは、俺じゃなく、父親のイライアスだ。」
「僕、まだ死にません。」
「‥ったく。わかっとらん。」
ウォルトの子供の頃は、ネズミが床を走るなんてことは、どこの家庭でもあった。
綺麗好きで、お金持ちに憧れていた兄のロイを励ますために、イライアスが書いたネズミが、ミッキーマウスの始まりだった。
「ロイ。ちょっと来い。父さんがいい物を描いたから。」
「何。」
「ほら。ネズミ君だよ。」
「うえー。」
ロイは舌を出した。
「お父さん、これ、何。ライチか何か。」
「ぶぶー。これはネズミです。」
「かわいい!これ、もらっていい?」
「いいよ。お前の物だ。」
イライアスは、ウォルトの頭をなでた。
ディズニー家の子供は、ロイとウォルトの2人だけだった。
イライアスは、冒険の話をしてくれた。
ジャングルで大トラを退治する話だ。
「‥それでな、父さん達は、道に豚の死体を置くことにした。おびき寄せ作戦だ。」
「おびき寄せ作戦?」
「そうだ。敵を騙して呼び寄せる時は、そう呼ぶ。」
小学校では、クラスの病弱なクリス君のことを、ウォルトは心配していた。
「あのさ。クリスと友達になりたいなら、私が放課後、おびき寄せてあげようか?」
「おびき寄せる?いいよ。クリス君とはもう友達だし、それに、おびき寄せるは、敵に使う言葉だ。」
「ホント?」
「うん、ホント‥。」
しかし、放課後も、クリス君は教室で椅子に座っていた。
「どうしよう。」
ウォルトは、校門で考えた。
クリス君のことは心配していたが、少し苦手だった。
「ウォル、まだいたのか。」
ロイが友人たちと来た。
「マイコちゃんが、クリス君をおびき寄せたんです。」
「おびき寄せる?どこに?」
「教室です。」
ロイとウォルトが見に行くと、クリスはもういなかった。
玄関に向かう途中で、クリスは泣きながら先生と歩いていた。
「どうしよう。」
「だけど、お前がやったんじゃないんだろ。」
そのことでウォルトが少し泣き、公園に寄ったので、帰るのが夕方6時になってしまった。
「お父さんに‥言う?」
「当たり前でしょう。どうしてこんなに遅くなったの!」
母親のフローラは怒った。
イライアスは、2人を正座させた。
「なぜ、そんなに遅くなったのか言いなさい。」
「マイコちゃんが、クリス君をおびき寄せたんです。」
「おびき寄せる?そんなことしちゃダメじゃないか。」
「だけど、イライアスだって‥。」
父がこんなに怒っている時に、ウォルトが、父をイライアスと呼んだので、ロイはウォルトをこづいた。
「なあ、ロイ。おびき寄せは、敵に使う言葉だ、分かるだろう。」
「分かるけど、この話に、俺は関係ないよ。」
「関係なくない。なぜ弟を連れ、すぐに家に戻らなかったんだ。」
「‥ごめんなさい。」
「さぁさ、ロイはもういいから。」
フローラが、ロイの肩を持った。
「お父さん、僕‥。」
父は何も言わずに、どこかを見て、無視をしている。
ウォルトは立ち上がり、台所でパンを食べた。
寝る時になって、父に、
「今日はごめんなさいね、ダーリン。」
と言うと、父は笑って、ウォルトの頭をなでた。
ウォルトが15才になった時に、ずっと憧れで眺めていた、父のネズミ君について、父にたずねた。
「父さん、これ、売れるかな?」
「売れないよ、そんなもの。くだらない。‥例え売れたとしても、せいぜい5ドルくらいにしかならん。」
ウォルトは、ネズミの絵を眺めた。
「じゃあ、僕が売っていい?」
「そんなもので金儲けするつもりなら、返してもらう。よこせ。」
父は、ネズミ君の絵を破ってしまった。でも、ウォルトは、ネズミ君をマスターしていた。
見ていたフローラが、イライアスにこそこそ話した。
次の日、イライアスは笑顔で、言った。
「父さんが間違っていた。絵が描きたいなら、そうしなさい。」
アートスクールにウォルトを入れてくれた。
「父さん、僕、漫画家になる。」
「好きにしろ。ただ、一つ言っておく。くだらん話は書くな。書くなら、意味のある話にしろ。」
イライアスは、ウォルトを指さし、言った。
「あの‥。」
「ネズミはお前にやる。」
「ミッキーという名前だ。」
イライアスは、ニヤリと笑った。
フローラとイライアスは、クスクスと笑った。
それは、2人の間での、イライアスのあだ名だったのだ。
ポールが庭仕事を終えて、部屋に戻ると、ウォルトさんが泣きながら1人でしゃべっていた。
「ごめんなさい、お父さん。でも、お父さんとお母さんをモデルにした、映画を作ったんだよ!!オーロラ姫。見てくれた?‥なーに。お父さん、いつもお母さんにキスしてたでしょう。」
ウォルトさんは、ワーワー泣いている。
ガチャ。
家に、誰かが入ってきた。
「うるさいわよ!!何事なの!!」
「ジュディス。」
「ウォール、またなの?いい加減にして。」
「勝手に来るなと言っているだろう!!」
「だけどね、ご近所さんにも、あんまり迷惑かけられないから。」
ジュディスは疲れたように言った。
「あら、新しいお手伝いの子なの?」
「そう。新人の、セント‥。」
「ポール・リアスです。」
「はじめまして、ポール。」
「私は夕食の準備をするわ。その間、あなたは‥。」
「俺は、君の本を読んでいるよ。」
「じゃあ、とっておきの曲をかけてあげる。」
パメラは音楽をかけた。
「この曲は聴いているとね、物語に入り込めるの。」
パメラは言い、キッチンに行ってしまった。
「いいね、オーロラはドイツ人だ。シンデレラもドイツ人。アリス?アリスはフランス人。でも、ドイツ人とのハーフっていう設定だよ。」
ウォルトは、パメラの本を読まずに、1人でぶつぶつと語りかけていた。
「じゃあ、そう言ってあげればいいでしょう。」
パメラが言い、ウォルトは黙った。
「ドイツ人ばかり、悪者にされて。可哀想に。」
パメラは、お洒落な肉料理を置いた。
「これは仔羊の煮込み料理よ。」
「わぁぁ。美味しそうだ。」
2人は横並びの机で、料理を食べた。
「じゃあ、白雪姫は何人なの?」
「白雪は‥日本人だ。」
「日本人?!やだ、ウォルト。知らないの?日本人のお姫様は、そんな城には住んでいないのよ。」
パメラは立ち上がり、本を持ってきた。
「ほら、これが、日本のお城。綺麗でしょう。」
「古いんだねぇ。」
「古い?当たり前でしょう。何百年も前に建てられたんだから。」
ウォルトは子供の頃のことを思い出した。
父親と、兵隊になりきり、遊んでいる。
漫画家になり、家を出た後も、辛い時は実家に帰り、父親に抱きついた。
ウォルトは、広報をお願いしている、アブに言った。
「とにかく。ウォルトディズニーは父親とは仲が悪い、ということでな。」
「え‥でも。この前も、お父さんが会社に来ていたでしょう。仲が悪いと?」
「そう。仲が良いなんて、家族に迷惑をかけるだろう!」
「父さん!」
「あ‥俺達のネズミ君は、こんなにでかくなったか。」
父は、ミッキーのポスターを見て行った。
「ちがう、これは、ポスター用だよぉ!原寸大はこのくらい。」
ウォルトは指で示した。
「父さん、これ見てよ。」
「なんだこれ。真っ黒じゃないか。」
「当たり前だ、黒人だよぉ。」
「‥いいか。黒人ってものは、こんなんじゃない。もっと恐ろしくて怖い人間なんだ。」
父は、物語を言う時の口調になった。
「お前は黒人なんて書かない方がいい。黒人はな、黒人だけのものだ。」
「いい?あなたと私の会話は聞かれているの。」
「ええっ。誰にだい?」
「その人は妖精よ。」
「妖精‥?ピノキオのブルーフェアリーのような人ですか?それともシンデレラのフェアリーゴッドマザー?」
パメラは首をふった。
「では、白雪姫の悪い魔女かい?あれは、君がモデルになってる。」
パメラは笑った。
「私がモデルですって?」
「ああ、そうさ。」
「そんなわけないでしょ。」
パメラは大笑いした。
2人は恋人‥だと思う関係だった。
しかし、ウォルトにとって、最大の試練が訪れる。
「ああ、もう信じられない!私のメアリを、映画化するだなんて!」
「そんなに怒らなくてもいいだろう。僕が一番好きな話だ。」
「言っておくけど、メアリは私だけの人なのよ!」
ウォルトはため息をついた。
「私だけの人なんて。では、なぜ、本を出版したんだ。」
「それにはいろいろな事情があるの。あなたには分からない、大人の事情ってものが!!」
ウォルトは黙って家を出た。
ウォルトは、1人で話す所が自分と似ていたし、食べる時も音をたてて食べる。そこがパメラを安心させた。
パメラにとってウォルトは、気軽なボーイフレンドだったのだ。
パメラは、ウォルトが自分よりもずっと大物で、ずっと仕事ができるということを考えないようにしていたせいで、一緒の仕事はうまく進まなかった。
「早く決めなよ。そうじゃなきゃ、僕は死んじゃうよ。」
「死ぬですって?あなたが?」
「ああ、そうなれば、君は誰とデートをするんだい?」
「あのね、私にはそういう人が他にもたくさんいるんです!」
ウォルトはまた、黙って家を出た。
ウォルトは、パメラの人柄だけでなく、才能にも惚れていた。
もちろん独身だし、そこも好きだった。
パメラには、自分のように、有名になってほしかったのだ。
ウォルトの時代の女性は、偉い人の奥さんになるしか、偉くなる方法がなかった。
「アブ。僕は結婚する。」
「えっ、結婚?もしかして、トラバースさんとですか?」
「違うよ。結婚したことにする。」
ウォルトは結婚したことにした。そして、子供が2匹いることにした。
「‥なんで、ネズミ君の名前がミッキーなのぉ?」
「それは秘密です。お父さんとお母さんのな。」
「ふーん。でもさ、いつか教えてくれるよね?」
「さあ、どうかな。でも、秘密を解くカギは、いつも君の胸の中だ。」
父はキラキラして答えた。
「困るなぁ。だってキャラ設定が出来ないんだもの。」
「設定?漫画を描く上でか。」
「うん‥彼女がいるとか、子供がいるとか。」
「子供?ミッキーには子供いるよ。」
「えっ。それ、何人?」
「2人。あっ、2匹か。」
「それだけぇ?変だなぁ。ネズミなら、もっと沢山生まれるはずだもん。」
「まあ、父さんのネズミには、子供はそんなに生まれなかったんだな。よし、今日は、このへんにしておくか。」
「ちょっと待って。ミッキーの奥さんの名前だけ教えて。」
「ミニー・マウス。世界で一番カワイイ、ネズミちゃんだ。」
「ミニー?名前が、似てるんだねぇ。」
「ミッキーとミニー。いいだろう?」
「ふーん、へ・ん・な・の!」
ウォルトは大きな声で言った。
「えーと、パメラ。いいね、ここは会社だ。」
「ええ、そうでしょうよ。そして、私は‥あなたの、上司。」
「いや、上司ってわけじゃない。」
「じゃあ、取引先の役員ってわけだ。」
「とにかくさ、仲間には優しくしてくれよ。色目を使え、ってわけじゃない。」
「承知、しました。」
パメラはシャキッとした。
しかし、パメラは怒り狂ってしまう。
「ところでディズニーさん、この会社はどうしてこう、ハゲが多いの?」
「さあ、どういうわけだろうねぇ。」
音楽の話し合いでは、ついにパメラは泣きだしてしまった。
「ミッキーさん、なんなの?これ。」
「パメラ、ミッキーは父のあだ名だ。父がミッキーで、母がミニー。多分、兄が生まれる前に2人でつけた。」
「そんなことどうでもいいわよ!!」
パメラは出て行ってしまった。
仕事は順調に進まなくなった。
そんな中、ウォルトは、ディズニーランドで働く、黒人青年と仲良くなる。
名前は、ルイという。
ウォルトがメリーゴーランドの馬に横座りしていたので、ルイが注意したのだ。
「お客様、すみませんが、横座りは危険ですので。」
「どうしてそんなこと言う?書いてなかったぞ。」
「すみません、でも決まりなんです。」
「決まり?ウォルトディズニーが決めた決まりか?」
ウォルトが引き下がらないので、2人は事務所で話すことになった。
「あの、僕、あなたがディズニーさんとは知らなくて。」
「いや、知らなくて当然だとも。写真の男とは全く違う。」
ポールは、今日は学校で、調理実習の日だった。
みんなでハンバーグを作るのだ。
「ポール。何、そのぐちゃぐちゃ。こう。こうやるの。」
チェルが、ポールにハンバーグの丸め方を教えた。
「マジでお前ら、付き合ってんのか?」
トイがニヤニヤと笑った。
「ばーか、違うっつーの。」
チェルが言った。
「ポール?」
「あの‥失礼かも、しれませんけど。お酒‥飲みすぎると、よくないって。」
「酒か?いや俺は、映画のストーリーを考えているんだ。あ~、次回作は、どんなストーリーにしよう。それで、どんなお姫様にしよう。」
「‥酒を飲むと、くるくる世界が回って面白いんだよ。でも、昔‥。」
ウォルトさんは笑いだした。
「どんな感じなのかなぁ‥?ドラッグをやるって。」
「さあ、分かりません。‥うちの母親が、昔、やったことがあって、酷い目にあったと言っていました。」
「へええ。なら、なんで、みんな、そんなものをやるんだろう。」
「さあ‥僕には、分かりません。」
ルイは本当にドラッグをやったことがなかったが、地元で人気のDJコングは、ドラッグをやっていると知っていた。
コングは、ルイの兄貴分である。
ルイは、コングのクラブに行った。
「よぉ、兄弟。久しぶりだぜ。」
「このクラブには、昔は、白人は入れなかったが、俺がやめさせたんだ。
見ろ。今では、黒人より、白人の方が多い。」
ルイはうつむき、顔をあげ、言った。
「兄さん、差別をしているのは、白人より黒人の方じゃないのかと、僕は思うんだ。」
「兄弟。白人は、俺達を船に乗せて運び、奴隷にした奴らだぜ。」
ルイは鼻をかき、首をかしげた。
コングは大笑いした。
「兄弟。そりゃ無茶な話だぜ。黒人差別については、教科書にも書いてある。」
黒人の仲間が酒を持ってきた。
イエーとか、ヒューヒューとか、歓声をあげている。
「ほらな。黒人はこうして、仲間うちだけで理解し合い、生きてきた。兄弟。」
次の日。明るくなって、ルイが散歩をしていると、コングが来た。
「ところでお前。どうしてこっちに来た。ディズニーで働いてるって聞いたぜ。」
ルイは、黙った。
「まさか、クビになったか?」
「いや‥兄さん、まだ、ドラッグ持ってるかな?」
ルイはコングの家の車庫に来ていた。
「ほら。昔の残りがまだここにある。」
ルイは、ドラッグを持った。
「ディズニーさんが、こんなものをやってみたいと?」
ルイはうつむいた。
2人は外に出た。
「いや~俺には、夢のような世界だぜ。」
「兄さん、今度、来てみないか?」
「いや、俺はいい。ラップとブルース。そして仲間。少しのレディー。俺には、それだけの世界で十分だ。」
コングは、余裕の表情で、ニヤリと笑った。
3日後の夕方5時。
夕日が差し込む窓際に、2人はいた。
「いいか。今から俺は、ドラッグをやる。2人でせーので飲もう。」
「僕も‥なんですか?」
「そうさ。当たり前だ。‥この会社にいたければね。」
ウォルトはニヤリと笑った。
気づいたら夜で、2人は、ゲイバーに来てしまっていた。
2人とも、ゲラゲラ笑っている。裸のオカマに、ウォルトはお札を渡した。
次の朝。
我に帰ったウォルトは、ドラッグをしても、なんの意味もないと実感した。
なんの夢も、見ることはできないし、危うく、犯罪に巻き込まれるところであった。
ルイは、疲れた顔でいつも通り出勤していた。
「ルイ。昨日のことは、これな。」
ウォルトは、人差し指を口に当てた。
ルイは無表情で、うなずいた。
ウォルトは、絵を描くことと、お茶とコーヒーをいれることと、スクランブルエッグを作ること以外は、まともにできるとは言えなかった。
掃除の仕方も、普通の人とは違い、窓を箒がけしてから、拭いたりしていた。
「俺は66才で死ぬことにした。亡くなるのには、理由がある。
親しい仲間はみんな孤独だったが、本制作が始まると、若いのが入ってきて、
みんな、恋をして、楽しんでいた。
ある日のことだ。
俺は、現場で泣いてしまった。
俺が、感動以外で泣いたことは、22才の時以来であった。
でも、それでようやく、楽しんでいた者達も気づいてくれた。
制作に集中し、恋もやめた。
もう、自分は、いない方がいい。
自分がいなくても、やっていける、それが、俺が死ぬ理由だった。
俺は、いつものように、ブランデーにドーナツを浸して食べた。
今日ならいけると思った。
そして、睡眠薬を服薬した。いつもの30倍の量だった。
俺はベッドに横たわり、眠るように死んだ。
第一発見者は、兄のロイだった。
俺が自殺したことに気づき、俺にすがりついて泣いた。
しかし、世界の子供達の夢を壊さないために、立ち上がり、自殺の証拠を隠滅した。
捨てた物は、睡眠薬だけでない。
俺の遺書まで捨てたのだ。
でも、絵だけは、のこしてくれた。
いつものように、ジュディスと旦那、息子のハル、ハルのガールフレンドのミカリが来た。
ジュディスは、「嘘でしょぉ!!」と叫び、俺にすがりついて大泣きした。
ジュディスの旦那のケイトは、俺の手を握って悲しんだ。
ハルのガールフレンドのミカリは、家を飛び出し、近所の女の子達を呼びに行ってしまった。
葬儀には、1000人以上の子供達が来た。
トイレが足りないと思ったが、みんなちゃんと我慢できた。
パメラは、悲しむファンの後ろの方で、腕を組み、俺の亡骸を見つめていた。
ロイが、外に出て風にあたっていると、
どこからともなく、声が聞こえた。
『ほら兄さん。俺の家の前に、遊園地を作った方がよかっただろう?』
ロイは涙をこぼした。
俺は貧しい方が好きだった。
なので、金持ちになってからも、小さな家に住んだ。
ディズニーランドも、こんなに大きなものではなく、
俺の家の庭にある、小さな遊園地でよかった。
ディズニーワールドリゾートの完成を見ることなく、俺はこの世を去る。
映画を作る時にいつも悩んでいたことは、ラッキーエンドにするか、ハッピーエンドにするかということだ。
俺は、どちらかというと、ラッキーエンドの方が好きだった。
ありがとう諸君。俺に生きる希望を与えてくれたのは、諸君なのだ。」
「いい話ね、ウォルト。」
パメラが、珍しいフレーバーティーを持って、後ろに立っていた。
「だけど、どうしてそんなに、未来のことが分かるの?あまりにも、リアルすぎるわ。」
「それは‥。」
「ねえ、どうして?もしかしてあなた、未来を見てきたということ?そうなの?」
「いや、未来を見てきたわけじゃない。今のは、俺が考えた作り話だ。」
パメラは高らかに笑った。
「あなたって面白いのね。‥従姉と仲が良いなんて羨ましいわ。私の従兄なんて、変な女と結婚して、10年前に交通事故で亡くなってしまったのよ。」
「今でも親しくしているのは、ジュディスだけだ。というか、そっちが親しくしてくる。俺の従弟も、変な人と結婚し、戦死した。いたたまれないよ。」
「自分の思い通りにいく人なんていない。自分が思い通りにできる人間は、自分だけだ。」
「ええ、ホント、そうよね。」
「なあポム。俺がメリーポピンズをどうして、実写にしたか分かるかい?」
パメラはウォルトを見た。
「それは、君に主役を務めてほしかったのさ。だって君は昔、女優だったんだろう?」
パメラは少し笑った。
「でもそれはずっと昔の話よ。いろいろしてしまったけど、本当にお気に入りの映画になったわ。」
パメラが泣いてから1カ月後、メリーポピンズの打ち合わせが再開した。
パメラは神妙な面持ちだったが、前よりも落ち着いて、打ち合わせに臨んでいた。
「パメラ‥今日はレストランに行かないか?」
普段は、外食が苦手なパメラだったが、渋々OKした。
2人は、いつもよりもお洒落な服で、少しだけ高級なディナーを食べた。
パメラが外食が苦手な理由は、ウォルトの隣だと、みんながジロジロ見るからだ。
でも本当は、みんな、美しいパメラを見ているのだった。
「美味いね。パメラの料理の方がもっとうまいけど。」
パメラは食べ終わると立ち上がって、スケッチブックを出した。
「私ね、あなたのように絵がうまくなりたくて、最近、お姫様の絵を描いているのよ。」
「へえ、見せてよ。」
「ほら。」
そこには、いろいろな国のお姫様の絵が、リアルに書かれていた。
「上手いじゃないか。」
パメラは満面の笑みで笑った。
「これはフィリピンのお姫様。こっちがベトナムのお姫様よ。私、アジアに興味があるの。いつか、アジアに行ってみたいわ。」
パメラは夢見心地で言った。
女子達は、落ち込んでいるチェルのまわりに集まって座っていた。
男子達はニヤニヤと見ている。
ルゥは、チェルの取り巻きの1人で、インド人と白人のハーフ、リランカのことが好きだった。
「あんなやつ、止めた方がいいよ。まじで。」
「絶対、チェルのこと、裏切るって。」
ポールが来た。
女子は無言で、ポールを見た。
チェルもちらりと見たが、またうつむいた。
最近のポールは、ディズニーキャラクターのキーホルダーを、カバンに10個以上つけている。服は毎日のようにキャラクターだ。
「おはよー。ポール。」
男子達が少し引き気味で話しかけた。
「どうした、これ。」
「いやぁ、ちょっと最近、ハマっちゃって。」
ポールはニヤニヤと笑った。
男子達も心配そうな表情でポールを見つめた。
ポールは、進路調査の紙に、『ディズニーカンパニー』と書いた。
担任の、アレクサンドラ先生が呼びだした。
「ポール。ディズニーに入るためには、何の勉強が必要?」
「必要なものは、両親の愛です。先生。」
「ポール。あなたがご両親から愛されているのは、よく分かってる。でも、なんの勉強をすればいいと思う?」
「それは‥絵‥です。」
「そう。本当に入りたいなら、アートスクールに通わせてもらうとか、今の推理研究会から、美術部に変えるとか、そういうことが必要でしょう。」
「はい‥。」
「1901年12月5日。俺は、イライアス・ディズニーとフローラ・ディズニーの2人目の息子として、産声をあげた。元気だったかどうかは分からない。なんせ2500グラムの未熟児だったと聞いている。その日は、晴れの曇りで、紫色の猫が家の前に来ていた。その猫がチシャ猫のモデルとなっている。ちなみにそれを教えてくれたのは、父のイライアス・ディズニーだ。父はいつも、私に生きるために必要なヒントをくれた‥。」
ウォルトさんは、窓の外を見ながら、1人でしゃべっている。
「あの‥ウォルトさん?」
「ん?‥おや。ポールか。」
「はい。また、来てしまって。」
「いや、いいよいいよ、客人は歓迎だ。今、お茶をいれよう。」
「チシャ猫を描いてくれたのは、父だ。俺が描いたチシャ猫は、どこにでもいる猫だった。」
ウォルトさんは、ハーブティーをいれてくれた。
「ハーブティーはいい。孤独を癒してくれる。」
ポールもハーブティーを飲んだ。
「アリスのうさぎを描いたのは、俺だけどね。」
ウォルトさんは満足そうに笑った。
「イライアス!!」
「ああ?なんだ。」
「じゃーん!!ミッキーの家族です。」
イライアスはメガネをつけ、ウォルトが描いたミッキーの家族を見た。
「沢山いるんだねぇ。」
「当たり前じゃん。ミッキーは二十日ネズミだもん。」
「この子がねぇ、ミッキーの妹のチッキー。」
うなずきながら、イライアスが言った。
「チミーじゃなくて、チッキーなのか?」
「そう!ミッキーのお父さんとお母さんは、子供達にキをつけたかったんだぁ!それはね、家に、キツツキが巣を作っていて、その音が、幸せの音だったからなんです!」
「それでね、この人がミッキーのおじいちゃん。この人がおばあちゃん。ミニーのおじいちゃんはね、もう亡くなってしまっていないんです。」
「ああ、そうなんだ。」
「ミッキーとミニーには、子供が沢山いる。ほら。」
「この子だけ、白いんだねぇ。」
「この子はホワイト君。黄色のワンピースの子はレイちゃんで、とても小さい。」
「ミッキーと家族は、いつも猫に怯えて暮らしているんです。」
「ああ、猫にね。」
イライアスはしげしげと絵を眺めた。
しかし、ウォルトが大人になって、登場人物が多すぎると、アニメ制作が大変という理由から、ミッキーとミニー以外、カットされてしまった。
「わああああ!!またクリス君に、遊ぼうって言っちゃったよおおお!!」
中学生のウォルトは、大泣きしていた。
『クリス君、今度また、遊ばない?みんなでさ。家に集まって。』
『いや?それならデートはぁ?僕と2人で。』
「おい。クリス君は、病弱すぎるから、誘っちゃダメだって、父さんが言ってただろう。」
「ウォル。父さんが言っているだろう。社会で生きていくためには、余計なことに口をだすなって。」
ウォルトはロイを見た。
「お前は絵しか描けない。だからそのことをしっかり覚えるんだ。」
イライアスとフローラは、なぜか、よく、ハプスブルク家の話をしていた。
「ねえそれ、なんの話?」
「それはそれは、怖い、人食い鬼の話です。」
イライアスは言った。
「じゃあそれを教えてよ。」
「いいけど‥今度、出かけた時にな。」
イライアスは、ウォルトが変な不良に引っ掛からないよう、昼間の黒人パブに連れて行った。ちなみにこの店にはすでに、ロイを何度か連れてきていた。
店員もお客も、黒人ばかりだ。
みんな、ウォルトとイライアスをジロジロと見た。
「ああ~めんどくせぇ。」
イライアスは、黒人を睨み、舌打ちをした。
「お父さん、やめなよ!」
「いいんだ。」
イライアスは、横柄な態度をとった。
「お前の友達の、黒人のボリ君の家は、貧乏すぎるからな。関わっちゃだめだぞ。」
「お父さん!しーっ!」
「ごめんなさい、僕のお父さんが。」
ウォルトは黒人に謝りに行くと、黒人はニンマリ笑った。
イライアスがやっていることの意味を分かっていたのだ。
「なんだ。お前、あの人に何言いやがった。」
イライアスが聞いた。
「何も。お父さんが馬鹿だから、謝っただけ。」
「余計なことを言うな。」
イライアスがウォルトをゴツンとしたので、ウォルトはそのパブで、大変、肩身の狭い思いをして過ごした。
家でウォルトは父に聞いた。
「それでさ、お父さん!聞き忘れちゃった、人食い鬼の話。」
「ああ、そうだった。ハプスブルク家はな、フランスの王族だったんだけど、実は、人を食って生活してたんだ。」
「人を食べて?!」
ウォルトは手で口をおおった。
「それでな‥。」
父はハプスブルク家について話した。
途中、話がそれ、「アハハ!面白い!!」ウォルトは無邪気に笑った。
ウォルトは発達障害だったので、いつまでも子供のようだった。
ディズニー一家は貧しく、ウォルトも新聞配達や郵便配達を手伝ったりした。
「これでも、少しは金になるかな。」
イライアスが言うと、フローラはうなずいた。
ウォルトは物語のように、仲の悪い家の郵便を交換したりしなかった。
「えらいな。」
イライアスはニッコリ笑った。
「フローラ、ウォルトは本当にいい子だな。‥それに絵も上手だ。天才かもしれん。」
イライアスは、ウォルトに聞こえるように、こそこそ話した。
時々、イライアスの友人が、牛肉をくれたので、ステーキを食べた。
父は毎回、「あ~今日もくたびれた。」と言って、椅子に座った。
「あの‥ご両親と仲がよかったなら、亡くなった時とか、すごく、辛かったですよね‥。」
「ああ、辛かったとも。」
「お父さん、ミニーが亡くなるシーンを描いてみた。ほら。ミッキーが泣いてるんだよ。」
「おや。どうしてそんなもの描くの。ミッキーとミニーは、永遠だよ。」
「ダメ。これはイライアスとフローラの未来の姿なんだよ。お父さん。お母さんを残して、先にいったら、絶対にダメだから。」
「母は俺が雇った修理工のせいで死んだんだ。」
「‥とても、悲しいですね。」
「ああ。俺はその時、フロリダにいたがね。すぐに駆け付けたよ。」
クラスの女子はまた、落ち込んでいるチェルのまわりに集まって話していた。
「チェル。本当にポールが好きなら、うちらも応援するよ。」
「でもさ。なんかあったら、スマホですぐに電話して。ポールに突然襲われたとか、そういう時は。」
ガラガラッ。
ポールが教室に入ってきたので、クラスのみんなは一斉にポールを見た。
「おはよーポール。」
ルーが声をかけると、他の男子達も、「おう。」などと声をかけた。
「おはよう。」
ポールは、ディズニーキーホルダーをじゃらじゃらつけ、夢見心地だ。
男子達はこそこそ話した。
ポールの学業態度にはなんの問題はなかった。
「ポール。」
チェルがポールの机に来た。
「えっ。」
「あの‥ポールがディズニーが好きみたいだから、私、ディズニーについて調べてみたんだ。」
「えっ。ホント?」
「うん。」
チェルはディズニーのイラストの切り抜きなどを貼った、ノートをみせた。
「これが、ウォルトディズニーさんの最初のキャラクター。オズワルド。」
「オズワルド??」
「うん。私達が生まれるずっと前に流行ったものだから。」
「へええ‥。」
放課後、チェルが言った。
「掃除、やっとくよ。今日こそ。」
「え。ホント?」
女子達がニヤニヤと笑っている。
ポールが玄関から出た時、教頭のヒーマス先生が声をかけた。
「ポール君。どこへ行くんだい?」
「えっ‥あの‥帰ります。」
「ダメだ。掃除をやってないじゃないか。」
ポールは校長室の掃除をやることになってしまった。
ポールは疲れ果て、今日も家に帰ると寝てしまった。
ウォルトさんは、コーヒーを飲みながら、ぷりぷりと怒っていた。
「‥俺が描いた女の中では、アリエルが一番好きだ。
アリエルが結婚するのは本当は許せない。」
「あの、ウォルトさん。」
「ん。」
「ポールです。」
「おお、ポール君か。久しぶりだね。」
「そう、ですか。」
「ああ。君に最後に会ったのは、もう19年前だ。」
「19年も前?」
「今、君がいるのは2025年だ。」
「‥じゃ、みんなもう、亡くなってる?」
「いや、そんなことない。」
ウォルトさんは、満足そうに言った。
「そう、ですか。」
ポールはうつむいた。
「パメラのことか?」
「はい。」
「パメラは死んだというか、小さくなった。」
「え‥。」
「100才の誕生日の朝、パメラは、赤ん坊に戻っていたんだ。パメラは、子供を持たなかったことに罪を感じていた。それで、自分自身が赤ん坊に戻ってしまったという訳だ。」
「‥本当にそんなことが?」
「ああ、本当だとも。」
「カフェインは好きか?うまいカフェラテの淹れ方を知ってる。」
「はい。」
ポールは少し顔をあげ、答えた。
ウォルトさんはぶつぶつ言いながら、カフェラテをいれてくれた。
「どうだ。」
「美味しい、です。」
「そうだろう。疲れた時は、いつもこれを飲む。」
ウォルトさんは満足そうに言った。
「何か、俺に、聞きたいことはあるかい。‥夢の中で紛れ込んで来た者に、この質問をすると、大体、ミッキーはどう考えたのかとたずねてくる。‥ポール。君にはもう教えただろう?」
「はい。」
「他人は、他人のモノだ。自分は自分だけのモノ。それは家族や両親でも同じだよ。ポール、それは分かるな?」
「はい、分かってます。それで、ウォルトさんに聞きたいことは、オズワルドについてなんです。オズワルドは‥どうやって生み出されたのですか?」
「いい質問だ。」
「やっぱり、キャラクターはお前が考えなきゃダメだ。」
ウォルトがもうすぐ有名になりそうな時、イライアスが言った。
「え‥僕だけじゃ無理だよ。父さんもいてくれなきゃ。」
「ダメだ。集中して、考えろ。」
ウォルトはしぶしぶ、新キャラクターを考えた。でも浮かばなかったので、父のネズミをウサギにしただけのキャラクターにした。
「これ‥。」
「いいよ、これ。それで、名前は。」
「名前‥。」
「おい。お前、友達の名前にするなんて言わないよな。その子にもお金をあげなきゃいけなくなるんだから。」
「じゃ、オズワルド。」
もともと、オズワルドはグーフィーにつけていた名前だった。
「よし。」
父はニヤリと笑った。
しかし、オズワルドは自分が先に書いていたという、ウォルトの中学時代の友人が現れたり、配給会社に権利を取られたりしてしまった。
そのせいで、ウォルトの最初の会社はつぶれてしまう。
ちなみに、5年後に、その中学時代の友人は自殺してしまい、そのことで、2年ほど、ウォルトは落ち込んでしまった。
「やっぱりミッキーにするよぉ。」
「じゃ、そうしろ。その前に、母さんに聞いてな。」
「どうして‥母さんに?」
「どんな時でも、大事なことは、女親に聞いて決めるもんだから。」
ウォルトはしぶしぶ、フローラに聞き、ミッキーを主要キャラクターに戻した。
王子のモデルは、大体、兄だった。
アブは昔からの友達で、生涯仲良くした。
「今までの話、嘘か誠か。決めるのは君次第だ。」
ウォルトさんは言った。
「信じてます。でもウォルトさんは今‥何歳ですか?」
「俺か?俺は130歳だ。」
「そんな‥。」
「ああ、本当だ。」
ウォルトさんは満足そうに言った。
「君とはまた会えるといいな。」
ウォルトさんの笑顔はだんだん遠くなる。
ポールは、自宅のベッドで起きた。
「これまでの話、信じるか信じないかは、君次第だ。」
ウォルトさんは画面に向かって言い、ニヤリと笑った。
「それにしても、人生は素晴らしい。」
そう言って、窓を開けた。
「アハハ!今日はいい日だ!」
窓を開けたまま、家のドアを開け、歩いて行ってしまった。
ウォルトさんは、途中、宙がえりを一回した。
まるでミッキーのように。
ディズニーランドで、ミッキーマウスは貧しいウォルト少年の手をとった。
偉大なアーティストとなったウォルトディズニーの手も、同じように。
The end
ワンクリックで応援できます。
(ログインが必要です)
(ログインが必要です)