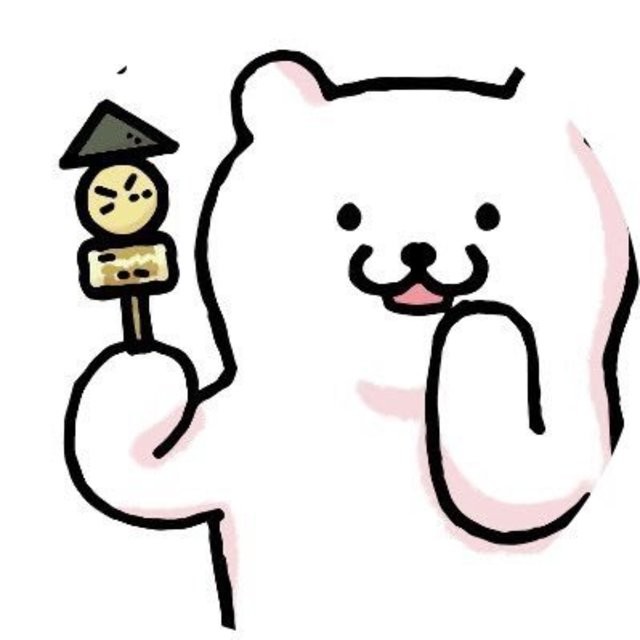第1話
文字数 2,916文字
桐の箱にいれられたそれは、我が家に先祖代々伝わっていた道具だった。我が家はこの地方の地主として、何代もこの土地に根ざし、さまざまな商売してきた。庭には立派な蔵があり、由緒ある品々が所狭しと並んでいた。その中のひとつがこの道具だ。
初めて見たのは、まだ年端もいかぬ子供のとき。それがなにかはわからなかったが、いまにも折れてしまいそうな繊細な形や、透きとおったガラスの美しさに心を打たれた。
しかし用途もわからぬ古道具などは蔵のなかにいくらでもあふれていて、めずらしくない。それに家の中にこもるよりも、外に出てころころと遊びまわる方が楽しい年ごろだ。いつしか蔵に立ちよること自体あまりなくなり、その存在を忘れてしまった。
その道具のことを思いだしたのは、私の元に二人目の嫁が来ることになったときだ。
私はずいぶん前に前妻をなくしており、長い間ひとりやもめであった。周りにはお手伝いのものがおり、特別不自由は感じていなかった。しかし年を重ねるごとにまず目が悪くなり、体も徐々にいうことを聞かなくなる。そしていまだに跡継ぎがいないことが頭の片隅にずっと懸念として残っていた。
そんなときに、ふってわいたように縁談の話があったのだ。
彼女は父方の親戚の娘であり、家は貿易業をしていた。商売が順風満帆というわけではないようだったが、我が家の商売も海外を見すえた展開を……と考えていた矢先だったので、互いに手をとるためのクサビにとして選ばれたのが、私と彼女の結婚だったというわけだ。会ったこともなければ、顔も見たことがなかったが、そんなことは別に珍しいことではない。
あまり器量の良くないお嬢さんだ。そのためにこれまで良縁に恵まれなかったのだ、と聞いていたが、実際にあってみると私にはとくに気にならなかった。それに出しゃばらないし色々気がつく性格で、うるさくしゃべり倒すこともない。特段の問題もなく結婚の話はつつがなくすすめられ、私たちは夫婦になった。
その日、いただいた贈り物を一度、蔵に入れて置こう……そう思いたち、私は久方ぶりに蔵に立ちよった。そして私は何年かぶりに例の道具に再会したのだ。
いったいこれはなんなのか。誰も真相がわからぬまま今まできてしまったが、もしかすると舶来ものに詳しい妻ならばなにか知っているかもしれない。そんな考えが私の頭をよぎった。
「おい……お前。これを知っているか?」そう言って例の道具を見せる。風呂敷をはずし、中をのぞいた彼女は、一瞬、平静をたもとうと努めたようだったが、その思惑は成功したとは言えなかった。
「これは……その、舶来から伝わるものです。――ですが、これを表に出してはなりません。ましてや実際に使うなど言語道断。――これは『不浄』を呼ぶ呪いの道具です」
私は思いつめた様子でそう語る妻の迫力に気おされた。それに「これ以上、この道具のことを詮索するようであれば、離縁させていただきます」とまで言うので、その日はそれ以上なにも聞くことができなかった。
妻はその後、道具をどこかにしまいこんでしまったらしく、その所在すらわからなくなってしまった
しかし、それで私が興味を失ったかと問われればそうではなかった。むしろ私は以前よりもその道具のことが気にかかって仕方がなかった。朝起きては、その道具のことを思いだし、メシを食いながら、どこか頭の片隅にあの道具がある。仕事をしながらも目にうかぶ。夜寝るときにまともに眠れない。かろうじて眠ったあとも、どうやらうなされているらしい。
流石に妻にも私の様子が奇異にうつったのだろう。なにかあったのか、調子でもわるいのか? と問いつめてきた。しばらくは「なんでもない」とくり返しすごしていたが、状態は一向に良くならない。なによりも自らの興味に強制的にフタをしてすごすということがこれほどつらいものなのか、ということを自覚しないわけにはいかなかった。
梅雨も終わりがけに差しかかった頃。
私はついに意を決して、妻にその悩みの丈を打ち明けた。どうしてもあの道具が気になって仕方がない。それが気になって夜も眠れないのだ。そう言って私は妻の前で泣き崩れた。
妻はよもやそんなことで悩んでいるのかと拍子抜けしたようだった。しかしそれが事実なのだから否定しようもない。妻も自分の言葉がそんなに私を苦しめているとは思いもよらなかっただろう。
妻はしばし悩んだようだが、こういった。
「申し上げましたように、あの道具は不浄を呼ぶ道具です。それでもあれを使ってみたいというのですね。あなたに不浄を受けいれる覚悟はありますか?」
私はどんなものでも受け入れると妻にすがった。実際のところ不浄がどうなどということよりも、自らのこの欲求にかたをつけないことには、この先、まともに生きていけるとは到底思えなかった。思い悩んだまま、苦しんで死ぬくらいなら、不浄とやらに取り込まれたほうがずっとましだ。
その決意を告げると、妻は意を決したようだった。
「わかりました。そこまで言うのであれば止めません。どうぞアレを使ってみてくださいませ。ご自身の目で、その呪いを感じてください。私は忠告しましたから……」
そういって、どこからか例の道具を持ってきて、こちらにしずしずと差し出してきた。
私は我慢できずにその道具に飛びついた。麻薬の禁断症状が出た人を見たことはないが、おそらく今の私も同じような顔をしていたに違いない。恥も外聞も脳裏にはなく、もはやそれしか目に入らない。かきむしるように、風呂敷を開け、それを取りだす。
繊細な、細い金属でできたそれはにぶく光りかがやいていた。不思議なことにそれをどう使うのかはすぐにわかった。長きにわたってこの道具のことだけを考え、眠ることもできなかった時期は、必要な時間だったのかもしれない。
落とさないように細心の注意を払いながら、その両端をつまみ、斜めにして顔に近づける。緩やかに曲がった部分を耳にかけ、丁度顔に、そして私の両目にガラスの部分があたるように、鼻にあたった部分の位置を調節する。
よし。これでいいはずだ。妻もなにも言ってこない。これで正解なのだ。そして私はその真価を図るべく、透き通ったガラスを通して、目の前に座る妻の顔を眺めた。
――そこには、まったく知らない女がいた。
いや、違う。背格好は妻とおなじだ。服の雰囲気もおなじ。いやしかしその服はこんなに薄汚れていただろうか。そして決定的に違うのはその顔だ。造作は似ているものの、ニキビやシミがそこら中にあふれまるで砂利道のような顔をしているではないか。目鼻だってまるで、子供がきままにやって散らかした福笑いのようだ。
――いったい全体私の妻はどこにいってしまったのだ。
「だからあれほど言ったのに……やめておけと。私はあなたの妻で間違いありません。それは『メガネ』と呼ばれる古来の道具。普段は見えぬ不浄のモノまで見てしまう呪われた逸品。あなたは目が悪いと聞いていましたから……、何事もなく私を受け入れてくれた時はほんとうに嬉しかったんです。できれば、そんな道具には一生出会って欲しくなかったわ……」
初めて見たのは、まだ年端もいかぬ子供のとき。それがなにかはわからなかったが、いまにも折れてしまいそうな繊細な形や、透きとおったガラスの美しさに心を打たれた。
しかし用途もわからぬ古道具などは蔵のなかにいくらでもあふれていて、めずらしくない。それに家の中にこもるよりも、外に出てころころと遊びまわる方が楽しい年ごろだ。いつしか蔵に立ちよること自体あまりなくなり、その存在を忘れてしまった。
その道具のことを思いだしたのは、私の元に二人目の嫁が来ることになったときだ。
私はずいぶん前に前妻をなくしており、長い間ひとりやもめであった。周りにはお手伝いのものがおり、特別不自由は感じていなかった。しかし年を重ねるごとにまず目が悪くなり、体も徐々にいうことを聞かなくなる。そしていまだに跡継ぎがいないことが頭の片隅にずっと懸念として残っていた。
そんなときに、ふってわいたように縁談の話があったのだ。
彼女は父方の親戚の娘であり、家は貿易業をしていた。商売が順風満帆というわけではないようだったが、我が家の商売も海外を見すえた展開を……と考えていた矢先だったので、互いに手をとるためのクサビにとして選ばれたのが、私と彼女の結婚だったというわけだ。会ったこともなければ、顔も見たことがなかったが、そんなことは別に珍しいことではない。
あまり器量の良くないお嬢さんだ。そのためにこれまで良縁に恵まれなかったのだ、と聞いていたが、実際にあってみると私にはとくに気にならなかった。それに出しゃばらないし色々気がつく性格で、うるさくしゃべり倒すこともない。特段の問題もなく結婚の話はつつがなくすすめられ、私たちは夫婦になった。
その日、いただいた贈り物を一度、蔵に入れて置こう……そう思いたち、私は久方ぶりに蔵に立ちよった。そして私は何年かぶりに例の道具に再会したのだ。
いったいこれはなんなのか。誰も真相がわからぬまま今まできてしまったが、もしかすると舶来ものに詳しい妻ならばなにか知っているかもしれない。そんな考えが私の頭をよぎった。
「おい……お前。これを知っているか?」そう言って例の道具を見せる。風呂敷をはずし、中をのぞいた彼女は、一瞬、平静をたもとうと努めたようだったが、その思惑は成功したとは言えなかった。
「これは……その、舶来から伝わるものです。――ですが、これを表に出してはなりません。ましてや実際に使うなど言語道断。――これは『不浄』を呼ぶ呪いの道具です」
私は思いつめた様子でそう語る妻の迫力に気おされた。それに「これ以上、この道具のことを詮索するようであれば、離縁させていただきます」とまで言うので、その日はそれ以上なにも聞くことができなかった。
妻はその後、道具をどこかにしまいこんでしまったらしく、その所在すらわからなくなってしまった
しかし、それで私が興味を失ったかと問われればそうではなかった。むしろ私は以前よりもその道具のことが気にかかって仕方がなかった。朝起きては、その道具のことを思いだし、メシを食いながら、どこか頭の片隅にあの道具がある。仕事をしながらも目にうかぶ。夜寝るときにまともに眠れない。かろうじて眠ったあとも、どうやらうなされているらしい。
流石に妻にも私の様子が奇異にうつったのだろう。なにかあったのか、調子でもわるいのか? と問いつめてきた。しばらくは「なんでもない」とくり返しすごしていたが、状態は一向に良くならない。なによりも自らの興味に強制的にフタをしてすごすということがこれほどつらいものなのか、ということを自覚しないわけにはいかなかった。
梅雨も終わりがけに差しかかった頃。
私はついに意を決して、妻にその悩みの丈を打ち明けた。どうしてもあの道具が気になって仕方がない。それが気になって夜も眠れないのだ。そう言って私は妻の前で泣き崩れた。
妻はよもやそんなことで悩んでいるのかと拍子抜けしたようだった。しかしそれが事実なのだから否定しようもない。妻も自分の言葉がそんなに私を苦しめているとは思いもよらなかっただろう。
妻はしばし悩んだようだが、こういった。
「申し上げましたように、あの道具は不浄を呼ぶ道具です。それでもあれを使ってみたいというのですね。あなたに不浄を受けいれる覚悟はありますか?」
私はどんなものでも受け入れると妻にすがった。実際のところ不浄がどうなどということよりも、自らのこの欲求にかたをつけないことには、この先、まともに生きていけるとは到底思えなかった。思い悩んだまま、苦しんで死ぬくらいなら、不浄とやらに取り込まれたほうがずっとましだ。
その決意を告げると、妻は意を決したようだった。
「わかりました。そこまで言うのであれば止めません。どうぞアレを使ってみてくださいませ。ご自身の目で、その呪いを感じてください。私は忠告しましたから……」
そういって、どこからか例の道具を持ってきて、こちらにしずしずと差し出してきた。
私は我慢できずにその道具に飛びついた。麻薬の禁断症状が出た人を見たことはないが、おそらく今の私も同じような顔をしていたに違いない。恥も外聞も脳裏にはなく、もはやそれしか目に入らない。かきむしるように、風呂敷を開け、それを取りだす。
繊細な、細い金属でできたそれはにぶく光りかがやいていた。不思議なことにそれをどう使うのかはすぐにわかった。長きにわたってこの道具のことだけを考え、眠ることもできなかった時期は、必要な時間だったのかもしれない。
落とさないように細心の注意を払いながら、その両端をつまみ、斜めにして顔に近づける。緩やかに曲がった部分を耳にかけ、丁度顔に、そして私の両目にガラスの部分があたるように、鼻にあたった部分の位置を調節する。
よし。これでいいはずだ。妻もなにも言ってこない。これで正解なのだ。そして私はその真価を図るべく、透き通ったガラスを通して、目の前に座る妻の顔を眺めた。
――そこには、まったく知らない女がいた。
いや、違う。背格好は妻とおなじだ。服の雰囲気もおなじ。いやしかしその服はこんなに薄汚れていただろうか。そして決定的に違うのはその顔だ。造作は似ているものの、ニキビやシミがそこら中にあふれまるで砂利道のような顔をしているではないか。目鼻だってまるで、子供がきままにやって散らかした福笑いのようだ。
――いったい全体私の妻はどこにいってしまったのだ。
「だからあれほど言ったのに……やめておけと。私はあなたの妻で間違いありません。それは『メガネ』と呼ばれる古来の道具。普段は見えぬ不浄のモノまで見てしまう呪われた逸品。あなたは目が悪いと聞いていましたから……、何事もなく私を受け入れてくれた時はほんとうに嬉しかったんです。できれば、そんな道具には一生出会って欲しくなかったわ……」