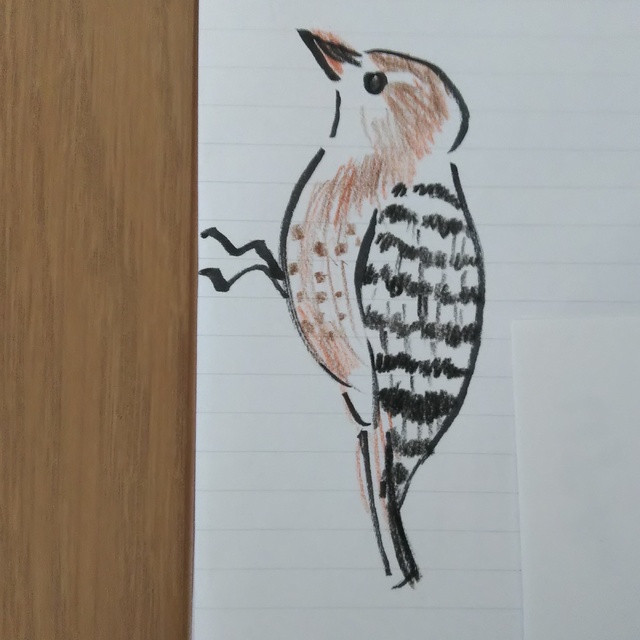王都にてDAY.04 ①『帰省』
文字数 4,971文字
屋敷には5つの応接室があった。
どうしてそんなに部屋が必要で、どうしてそんなに父に客が来るのか、幼い頃の私にはわからなかったが……父の"厄介な立場"を知った今ならその理由がわかる気がした。
私の育った家庭は、いわゆる平民以上の階級だった。当時から父が医学院の院長を勤めていたのだから当然と言えば当然かもしれない。広い屋敷。広い庭。無数の部屋。無数の使用人……。そんな人と物に囲まれた暮らしが、私の日常だった。
なに不自由のない生活。
きっと、言葉にするならそんな暮らしだったと思う。
それにも関わらず、母は使用人達に全てを任せるという事をせず、むしろ先頭に立って家事を取り仕切っていた。
使用人を雇っている家庭の中で"それ"が珍しいという事を知ったのは、学習院の低学科に入学した頃だった。同じ様な境遇の子ども達と接するうちに、裕福な暮らしにも関わらず率先して働く母の姿は"普通"ではないという事を、そして夫に言い返す妻の姿もまた普通ではないらしいという事を知った。
けれど、そもそも母が好きだった私にとってそんな母の姿が普通であり、主人が家事をする事も女が男に言い返す事も当たり前だと思っていた。まだ母が健在だった頃は母や使用人達の手伝いを進んでしていたし、兄達や学習院の男子とも喧嘩をした。それが私の日常だった。
そんな私の日常は、母の死で一変した。
一度は悲しみに暮れていた日々が、"真相"を知った事で怒りに変わった。その矛先をどこに向ければよいのかわからなかった幼い私は、目に見える全てを憎み、暴れ、壊した。
一人の使用人が矛先を向けるべき場所を示してくれた事で、この世界で生きていけるようになったが……"それ"が無かったら、私はきっと私になってはいなかったに違いない。
"病気を殺せる医者になる"という生きる目的は見つけたものの憎しみに囚われていた私は、その後医学に関する知識以外の一切の吸収をやめた。母のお陰で覚え始めていた家事の類も含めて。
そこからの数年間、医学院の入学試験に受かるまで、学習院に通う以外に屋敷の敷地から出る事はほぼ無かった。
この屋敷は母と一緒の時間を過ごした大切な場所であり、母の居ない時間を過ごした辛い場所でもあった。いい思い出も、嫌な思い出も詰まった場所。
もう戻らないと誓ったそんな屋敷 に、もう一度足を踏み入れなけらばならない。それは思ったよりも実行し難いものだと初めて分かった。
「……」
屋敷を目の前にして、私はなかなか一歩目を踏み出せずにいたからだ。
外から眺めているだけで思い出が勝手に頭を駆け巡り、足に絡みつき、どんどん重くなっていった。あれこれ考えてしまう前に、屋敷に到着した勢いのまま足を踏み入れなかったのが間違いだったと、気づいた頃には遅かった。
「失礼致します」
そんな私の背中を押したのは、文字通り背後から飛んできたその女性の弾んだ声だった。
「旦那様に御用でしょうか?」
「……ええ。そうです」
"その声"の主が誰なのか直ぐにわかった私は、振り返らずあえて他人のフリを続けた。
「院長殿と少しお話をしたい事があって参ったのですが、今日はお忙しいですか?」
「はい。申し訳ありませんが、旦那様は間もなくお客様との御面会があります。後程、旦那様に確認した後にご予約をお取りしますので、お名前を頂戴しても宜しいでしょうか?」
「……名前か」
その懐かしい声を前に、私は笑みを我慢する事が出来なかった。
「出来れば名乗らずにお目通り願いたいのだが、可能だろうか?」
「……まぁ⁈」
私が振り返ると、女性の小さな目がそれ以上開かない位に大きく見開かれた。それと同時に、彼女は胸の前で抱えていた大きな袋を地面に落とした。袋から果実が2、3個転がった。
その女性 は"昔から"体格がよかった。船医の大男に比べれば小さく見えるかもしれないが、背丈で言えば眼鏡の男とほとんど変わらない。横に大きい分、むしろ大きく見えるくいらいだ。使用人の制服が窮屈そうに見えるその豊満な体型も、あの頃のままだった。
「……まぁ、まぁ!まぁ‼」
そう言いながら私の元に駆け寄ると、両手を私の肩にかけた。
「まぁ!」
「ふふ、他に言う事はないのか?」
眼鏡の男の時と同じような台詞を言った自分がおかしくて、私は再び笑ってしまった。
「おお、おおお……おかえり、なさいませぇ!」
反対に、体の割りに小さな彼女の目からは大粒の涙が溢れてきた。思わず、私も喉が鳴った。
「……お嬢様ぁ!」
そして、彼女は地面に膝を折って、私を抱きしめて泣き出した。
「ああ、ただいま。クエル」
彼女の名は"クエル"。
私が生まれる前から屋敷の使用人として働き、歳が近かった生前の母とも公私を越えて親交が深かった人。そして――
「そんなにお母上の命を奪った者が憎いのならば、お医者様におなりなさい!」
そう言って、私に医者としての道を示してくれた人。母の命と共に人の心を失っていた私が、この王都 で唯一心を開いていた人だった。
「おおぅ、お、おおぅ…」
「そんなに泣く事ないだろう?」
クエルの嗚咽が落ち着くまで、私はその広い背中をさすった。あの村で泣き虫娘の背中をさすった事を思い出し、再び笑みが零れた。
素直に嬉しい。そんな気持ちだった。私の為に泣いてくれる人がこの屋敷に居てくれた事が嬉しかった。
「大丈夫か?買い物に出ていたのだろう?」
「ももも、申し訳ございません」
私が地面に転がった果実を拾い上げると、クエルは屋敷の使用人の証でもある白地に赤い糸で縫い上げられたエプロンで顔を覆ったまま答えた。
「旦那様から、近々お嬢様がお戻りになられると聞いてはいましたが、まさかこんなに早くお会い出来るとは思っておらず……取り乱してしまいました」
クエルは鼻をすすりながら改めて私の顔を見ると、頭の先から足の先まで舐めるように何度も見た。昨日、小男にも似たような事をされたが、その時とは全く違う気分だった。
幼い頃から知っているクエルは、私にとって家族のようなものであり、母を亡くしてからは母の代わりにいろいろな事を教えてくれた人だった。
ちなみに、護身術と称して、"罪にならない"人の殴り方を教えてくれたのもクエルだった。
「お嬢様……ご立派になられて!少しお痩せになられたのではありませんか⁈田舎での暮らしはお辛くありませんでしたか⁈」
「ああ、元気だったぞ。立派になったのではなく、ただ歳をとっただけだ。クエルの方こそ少し痩せたか?」
「お嬢様の居らっしゃらない暮らしが寂しくて寂しくて……食事も日に3度しか喉を通りませんでしたので」
「日に3度も通れば十分だろう」
「……」
私が笑うと、クエルは再び泣き出しそうな顔をした。
「……どうした?やっぱり私が笑うとおかしいか?」
同期の男達をはじめ、昔の私を知る者にとって私の笑みは相当違和感のあるものだったようだから……クエルにとってもそうだったのだろうと思った。
「いいえ!いいえ!そんな事はありません!ただ――」
クエルはもう一度エプロンで目を拭いてから答えた。
「お笑いになったお嬢様のお顔が、あまりにも奥様に似てらしたので……」
クエルの言葉に、胸が締め付けられる感覚がした。辛いのとは違う感覚。
「申し訳ありません」
「……いや。そう言ってもらえて嬉しい」
私は、素直にそう思えた。大好きだった母に似ていると言われた事は、私にとってこの上ない喜びだったから。私もようやく母のように笑える人間に近づいた、その証明のようなものだった。
「さ、参りましょうお嬢様!旦那様もお待ちです」
「父にはこの後に客が居るのだろう?」
「お嬢様より大切なお客様はいません!ご予定を取りやめてでも直ぐに会っていただきます!」
とても使用人とは思えない言葉と共に、クエルは私の手を引いて正門をくぐった。
「お嬢様のお帰りです!屋敷の者全てに伝えなさい!旦那様へも早急に!」
屋敷に入るなり、クエルは声を張り上げた。
その口ぶりから、使用人の中でも随分昇格しただろう事がわかった。15年も勤め続ければ当然かもしれないが。
他の若い使用人達は、クエルに手を引かれながら廊下の真ん中をズンズン歩く私に目を丸くし、慌てて頭を下げた。若い使用人も多く、顔が知らない者が殆どだった。当然、向こうも私の事など知らないはずだ。
「……手を離せ恥ずかしい。自分で歩ける」
「失礼しました。昔の癖で、つい」
「それに、私が戻った事はあまり大事 にしないでくれ。用が済んだら直ぐに帰るんだ」
「そういう訳にはまいりません。主人をもてなさずは、使用人の恥にございます。せめてご夕食は召し上がって頂きます。積もる話もありましょうから」
「……いや、正直、父とはそんなに長く話すつもりはないんだが」
「私が積もる話があるのです。お嬢様のお話が聞きたいのです!」
「……」
昔以上に強引なクエルに、私は返す言葉もなかった。
15年流れた月日の中で変わった事も多かった。けれど、変わらないものにもまた安堵できる。改めてそう思った。
「旦那様、旦那様!」
二階の奥にある父の書斎。クエルは随分強めに扉をノックすると、随分強めに父を呼んだ。
「聞こえている」
扉の奥から、籠った低い声がした。
「……」
15年振りに聞く、父の声に緊張している自分が居た。15年の月日を経ても、"あの頃"の逆らえなかった自分は間違いなく私の中に眠っていたようだった。
「お嬢様がお帰りになられました」
「……そうか。これから客に会う。待つよう言ってくれ」
「何を仰っているんです!?」
私のそんな緊張を振り払うように、クエルは声を張り上げた。
「そういう訳にはまいりません。先にお嬢様にお会い下さい!」
「……ちょっと待てクエル」
冗談ではなく、本気で主人の予定を潰そうとする使用人 を私は制した。
「別に急いでいるわけではない。どこでもいいから待たせてくれ」
「そういう訳にはまいりません」
クエルは改めて強い口調で言うと、私に一瞬だけ向けた視線を、直ぐに扉に戻した。
「旦那様、もしも今直ぐにお嬢様にお会いにならないと仰るのでしたら、私は本日限りでこの屋敷の使用人を辞めさせていただきます」
「クエルッ⁈」
さらに予想しなかった話の展開に、私は慌てた。
「何を言っているんだ!お前がムキになる事ではないだろう?それに、父上は私に会わないと言っているわけではないのだし、むしろ予約もせず急に来たのは私の方なんだ」
「お嬢様まで何を仰っているのです?!家族が家に帰って親と話すのに、予約がいりましょうか?」
「それは……そうだが」
「これは、旦那様の"器"に関わる問題です」
「……器?」
クエルは鼻息を荒くしながらもう一度扉に向き直った。
「旦那様、私がどういう人間か、今更説明する必要はございませんね?」
「……」
扉の向こう側からは、何も聞こえてはこなかった。
「これ以上、お嬢様の"時間"をお奪いになるようでしたら、私は旦那様を見限らせていただきます。そんな器の小さい男にこれ以上仕えるのは、真っ平御免でございます」
「お、おい」
とても主人に仕える使用人のものの言い方とは思えなかった。少なくとも、15年前までクエルは父にこんな態度をとるような使用人ではなかった。私の知らない15年の間に何があったのかはわからなかったけれど……。
「旦那様に媚びを売りに来ただけの者と、長年に渡る職務を全うして帰省した最愛の娘。どちらと先に会うか迷う必要がどこにありましょうか⁈医学院の長ともあろうお方が、そんな事もわからなくなってしまわれたのですか?」
「……」
クエルの遠慮のない物言いの数々に、私はただ圧倒されていた。きっとこの後に返って来るであろう、父からの叱責を想像しながら。
「……わかった」
ところが、扉の向こうから聞こえてきたのは予想もしなかった返事だった。
私は更に驚いた。"あの"父がクエルの言う事を素直に聞き入れるとは思えなかったからだ。
「客には日を改めるよう伝えてくれ」
「言い訳は"いつもの急患 "で宜しいですか?」
「任せる。聞こえの悪い言い方をするな」
「かしこまりました」
クエルは扉越しに深く会釈をすると、私を扉の前に招いた。
「ささ、どうぞお嬢様」
「……ああ」
満面の笑みを浮かべるクエルを前に、私はただ茫然とする事しかできなかった。父を前にした緊張は、どこかへ消えてしまっていた。
つづく。
どうしてそんなに部屋が必要で、どうしてそんなに父に客が来るのか、幼い頃の私にはわからなかったが……父の"厄介な立場"を知った今ならその理由がわかる気がした。
私の育った家庭は、いわゆる平民以上の階級だった。当時から父が医学院の院長を勤めていたのだから当然と言えば当然かもしれない。広い屋敷。広い庭。無数の部屋。無数の使用人……。そんな人と物に囲まれた暮らしが、私の日常だった。
なに不自由のない生活。
きっと、言葉にするならそんな暮らしだったと思う。
それにも関わらず、母は使用人達に全てを任せるという事をせず、むしろ先頭に立って家事を取り仕切っていた。
使用人を雇っている家庭の中で"それ"が珍しいという事を知ったのは、学習院の低学科に入学した頃だった。同じ様な境遇の子ども達と接するうちに、裕福な暮らしにも関わらず率先して働く母の姿は"普通"ではないという事を、そして夫に言い返す妻の姿もまた普通ではないらしいという事を知った。
けれど、そもそも母が好きだった私にとってそんな母の姿が普通であり、主人が家事をする事も女が男に言い返す事も当たり前だと思っていた。まだ母が健在だった頃は母や使用人達の手伝いを進んでしていたし、兄達や学習院の男子とも喧嘩をした。それが私の日常だった。
そんな私の日常は、母の死で一変した。
一度は悲しみに暮れていた日々が、"真相"を知った事で怒りに変わった。その矛先をどこに向ければよいのかわからなかった幼い私は、目に見える全てを憎み、暴れ、壊した。
一人の使用人が矛先を向けるべき場所を示してくれた事で、この世界で生きていけるようになったが……"それ"が無かったら、私はきっと私になってはいなかったに違いない。
"病気を殺せる医者になる"という生きる目的は見つけたものの憎しみに囚われていた私は、その後医学に関する知識以外の一切の吸収をやめた。母のお陰で覚え始めていた家事の類も含めて。
そこからの数年間、医学院の入学試験に受かるまで、学習院に通う以外に屋敷の敷地から出る事はほぼ無かった。
この屋敷は母と一緒の時間を過ごした大切な場所であり、母の居ない時間を過ごした辛い場所でもあった。いい思い出も、嫌な思い出も詰まった場所。
もう戻らないと誓ったそんな
「……」
屋敷を目の前にして、私はなかなか一歩目を踏み出せずにいたからだ。
外から眺めているだけで思い出が勝手に頭を駆け巡り、足に絡みつき、どんどん重くなっていった。あれこれ考えてしまう前に、屋敷に到着した勢いのまま足を踏み入れなかったのが間違いだったと、気づいた頃には遅かった。
「失礼致します」
そんな私の背中を押したのは、文字通り背後から飛んできたその女性の弾んだ声だった。
「旦那様に御用でしょうか?」
「……ええ。そうです」
"その声"の主が誰なのか直ぐにわかった私は、振り返らずあえて他人のフリを続けた。
「院長殿と少しお話をしたい事があって参ったのですが、今日はお忙しいですか?」
「はい。申し訳ありませんが、旦那様は間もなくお客様との御面会があります。後程、旦那様に確認した後にご予約をお取りしますので、お名前を頂戴しても宜しいでしょうか?」
「……名前か」
その懐かしい声を前に、私は笑みを我慢する事が出来なかった。
「出来れば名乗らずにお目通り願いたいのだが、可能だろうか?」
「……まぁ⁈」
私が振り返ると、女性の小さな目がそれ以上開かない位に大きく見開かれた。それと同時に、彼女は胸の前で抱えていた大きな袋を地面に落とした。袋から果実が2、3個転がった。
その
「……まぁ、まぁ!まぁ‼」
そう言いながら私の元に駆け寄ると、両手を私の肩にかけた。
「まぁ!」
「ふふ、他に言う事はないのか?」
眼鏡の男の時と同じような台詞を言った自分がおかしくて、私は再び笑ってしまった。
「おお、おおお……おかえり、なさいませぇ!」
反対に、体の割りに小さな彼女の目からは大粒の涙が溢れてきた。思わず、私も喉が鳴った。
「……お嬢様ぁ!」
そして、彼女は地面に膝を折って、私を抱きしめて泣き出した。
「ああ、ただいま。クエル」
彼女の名は"クエル"。
私が生まれる前から屋敷の使用人として働き、歳が近かった生前の母とも公私を越えて親交が深かった人。そして――
「そんなにお母上の命を奪った者が憎いのならば、お医者様におなりなさい!」
そう言って、私に医者としての道を示してくれた人。母の命と共に人の心を失っていた私が、この
「おおぅ、お、おおぅ…」
「そんなに泣く事ないだろう?」
クエルの嗚咽が落ち着くまで、私はその広い背中をさすった。あの村で泣き虫娘の背中をさすった事を思い出し、再び笑みが零れた。
素直に嬉しい。そんな気持ちだった。私の為に泣いてくれる人がこの屋敷に居てくれた事が嬉しかった。
「大丈夫か?買い物に出ていたのだろう?」
「ももも、申し訳ございません」
私が地面に転がった果実を拾い上げると、クエルは屋敷の使用人の証でもある白地に赤い糸で縫い上げられたエプロンで顔を覆ったまま答えた。
「旦那様から、近々お嬢様がお戻りになられると聞いてはいましたが、まさかこんなに早くお会い出来るとは思っておらず……取り乱してしまいました」
クエルは鼻をすすりながら改めて私の顔を見ると、頭の先から足の先まで舐めるように何度も見た。昨日、小男にも似たような事をされたが、その時とは全く違う気分だった。
幼い頃から知っているクエルは、私にとって家族のようなものであり、母を亡くしてからは母の代わりにいろいろな事を教えてくれた人だった。
ちなみに、護身術と称して、"罪にならない"人の殴り方を教えてくれたのもクエルだった。
「お嬢様……ご立派になられて!少しお痩せになられたのではありませんか⁈田舎での暮らしはお辛くありませんでしたか⁈」
「ああ、元気だったぞ。立派になったのではなく、ただ歳をとっただけだ。クエルの方こそ少し痩せたか?」
「お嬢様の居らっしゃらない暮らしが寂しくて寂しくて……食事も日に3度しか喉を通りませんでしたので」
「日に3度も通れば十分だろう」
「……」
私が笑うと、クエルは再び泣き出しそうな顔をした。
「……どうした?やっぱり私が笑うとおかしいか?」
同期の男達をはじめ、昔の私を知る者にとって私の笑みは相当違和感のあるものだったようだから……クエルにとってもそうだったのだろうと思った。
「いいえ!いいえ!そんな事はありません!ただ――」
クエルはもう一度エプロンで目を拭いてから答えた。
「お笑いになったお嬢様のお顔が、あまりにも奥様に似てらしたので……」
クエルの言葉に、胸が締め付けられる感覚がした。辛いのとは違う感覚。
「申し訳ありません」
「……いや。そう言ってもらえて嬉しい」
私は、素直にそう思えた。大好きだった母に似ていると言われた事は、私にとってこの上ない喜びだったから。私もようやく母のように笑える人間に近づいた、その証明のようなものだった。
「さ、参りましょうお嬢様!旦那様もお待ちです」
「父にはこの後に客が居るのだろう?」
「お嬢様より大切なお客様はいません!ご予定を取りやめてでも直ぐに会っていただきます!」
とても使用人とは思えない言葉と共に、クエルは私の手を引いて正門をくぐった。
「お嬢様のお帰りです!屋敷の者全てに伝えなさい!旦那様へも早急に!」
屋敷に入るなり、クエルは声を張り上げた。
その口ぶりから、使用人の中でも随分昇格しただろう事がわかった。15年も勤め続ければ当然かもしれないが。
他の若い使用人達は、クエルに手を引かれながら廊下の真ん中をズンズン歩く私に目を丸くし、慌てて頭を下げた。若い使用人も多く、顔が知らない者が殆どだった。当然、向こうも私の事など知らないはずだ。
「……手を離せ恥ずかしい。自分で歩ける」
「失礼しました。昔の癖で、つい」
「それに、私が戻った事はあまり
「そういう訳にはまいりません。主人をもてなさずは、使用人の恥にございます。せめてご夕食は召し上がって頂きます。積もる話もありましょうから」
「……いや、正直、父とはそんなに長く話すつもりはないんだが」
「私が積もる話があるのです。お嬢様のお話が聞きたいのです!」
「……」
昔以上に強引なクエルに、私は返す言葉もなかった。
15年流れた月日の中で変わった事も多かった。けれど、変わらないものにもまた安堵できる。改めてそう思った。
「旦那様、旦那様!」
二階の奥にある父の書斎。クエルは随分強めに扉をノックすると、随分強めに父を呼んだ。
「聞こえている」
扉の奥から、籠った低い声がした。
「……」
15年振りに聞く、父の声に緊張している自分が居た。15年の月日を経ても、"あの頃"の逆らえなかった自分は間違いなく私の中に眠っていたようだった。
「お嬢様がお帰りになられました」
「……そうか。これから客に会う。待つよう言ってくれ」
「何を仰っているんです!?」
私のそんな緊張を振り払うように、クエルは声を張り上げた。
「そういう訳にはまいりません。先にお嬢様にお会い下さい!」
「……ちょっと待てクエル」
冗談ではなく、本気で主人の予定を潰そうとする
「別に急いでいるわけではない。どこでもいいから待たせてくれ」
「そういう訳にはまいりません」
クエルは改めて強い口調で言うと、私に一瞬だけ向けた視線を、直ぐに扉に戻した。
「旦那様、もしも今直ぐにお嬢様にお会いにならないと仰るのでしたら、私は本日限りでこの屋敷の使用人を辞めさせていただきます」
「クエルッ⁈」
さらに予想しなかった話の展開に、私は慌てた。
「何を言っているんだ!お前がムキになる事ではないだろう?それに、父上は私に会わないと言っているわけではないのだし、むしろ予約もせず急に来たのは私の方なんだ」
「お嬢様まで何を仰っているのです?!家族が家に帰って親と話すのに、予約がいりましょうか?」
「それは……そうだが」
「これは、旦那様の"器"に関わる問題です」
「……器?」
クエルは鼻息を荒くしながらもう一度扉に向き直った。
「旦那様、私がどういう人間か、今更説明する必要はございませんね?」
「……」
扉の向こう側からは、何も聞こえてはこなかった。
「これ以上、お嬢様の"時間"をお奪いになるようでしたら、私は旦那様を見限らせていただきます。そんな器の小さい男にこれ以上仕えるのは、真っ平御免でございます」
「お、おい」
とても主人に仕える使用人のものの言い方とは思えなかった。少なくとも、15年前までクエルは父にこんな態度をとるような使用人ではなかった。私の知らない15年の間に何があったのかはわからなかったけれど……。
「旦那様に媚びを売りに来ただけの者と、長年に渡る職務を全うして帰省した最愛の娘。どちらと先に会うか迷う必要がどこにありましょうか⁈医学院の長ともあろうお方が、そんな事もわからなくなってしまわれたのですか?」
「……」
クエルの遠慮のない物言いの数々に、私はただ圧倒されていた。きっとこの後に返って来るであろう、父からの叱責を想像しながら。
「……わかった」
ところが、扉の向こうから聞こえてきたのは予想もしなかった返事だった。
私は更に驚いた。"あの"父がクエルの言う事を素直に聞き入れるとは思えなかったからだ。
「客には日を改めるよう伝えてくれ」
「言い訳は"いつもの
「任せる。聞こえの悪い言い方をするな」
「かしこまりました」
クエルは扉越しに深く会釈をすると、私を扉の前に招いた。
「ささ、どうぞお嬢様」
「……ああ」
満面の笑みを浮かべるクエルを前に、私はただ茫然とする事しかできなかった。父を前にした緊張は、どこかへ消えてしまっていた。
つづく。