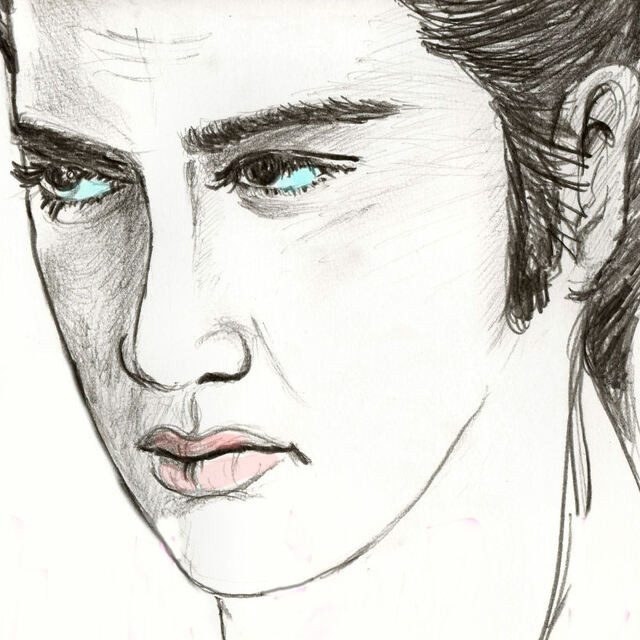花火
文字数 2,888文字
「こう毎日が暑くては、やり切れないな」と太郎は呟く。
今、太郎は東京の夜空に舞い上がる花火を見上げていた。
大輪 の華を咲かせるように続けざまに打ち上げられる花火は夜空を真昼のような明るさにしていた。
(それにしても今夜はくそ暑いな……)
ずっと前に田舎暮らしが厭で家を飛び出し、やってきた東京の街。夜空の色が鮮やかに変わり、威勢の良いかけ声と共に打ち上がる花火の嵐。降り掛かり、燃え尽きた花火のかけらが散る。
(いいなあ、花火は……)
ふと、太郎は飛び出してきた田舎を思い出した。
田舎にいた頃の夏、いろいろな思い出があった。子供の頃は暑くなれば悪童仲間とパンツ一枚で近くの川に飛び込んだり、潜り込んで川魚やザリガニ等を穫ったりしていた。
夏と言えばやはり夏祭りが良い。縁日で盛り上がる神社の境内は賑やかだった。そこでは、沢山の珍しい出店が出て賑わいとても活気がある。
焼きソバ、金魚すくい、駄菓子屋などが一杯境内の空き地を占める。子供達は親からもらった小遣いでそれを買ったり食べたりする。
それは彼等にとっては夏休みの楽しみだった。
綺麗なお姉さん達が浴衣を着て歩く姿が太郎少年には眩しかった。
そんな人混みの中に同級生の雪枝の浴衣姿を太郎はみつけた。いつもは地味な服で赤い顔をしていた雪枝が、その日は浴衣を着て少し化粧をしていた。
雪枝が着ている浴衣は多分姉のお下がりだろう。綺麗な姉と連れ添って雪枝は出店を覗いている。それは髪飾りや小物など女の子が好きそうな店だった。店と言っても地面に箱を置き、その上に板を置いただけの臨時の店である。
「おい、雪枝、姉ちゃんと一緒かい」
「ああ、太郎ちゃん、なにしてんの」
「べつにぃ……」
雪枝に声を掛けたのは、別に雪枝に話したいわけではない。隣の綺麗な姉の「まり子」が気になったからである。まり子はあまりたちの良くない太郎を無視している。
「雪枝、いこうよう……」
あんな太郎を相手にしないでもっと別の所へ行こうと妹の手を引っ張る。
「うん、ごめんね、太郎ちゃん、姉ちゃんが言うから」
それにむかついた太郎は言う。
「なんだよ、まり子、俺がそんなに嫌いかよ」
「だってぇ、あんた評判良くないもん、いこっ……雪枝」
生意気なまり子は、妹の手を引いて行ってしまった。
「なんだよ、このクソまり子っ!」
たしかに太郎は不良の仲間入りをしていた時期がある。その夜は一人でブラブラ境内をうろついていた。悪ガキの太郎は店の駄菓子や食い物をこっそり盗み境内の裏で食べるのが好きだった。小遣いが無いわけではないが悪童に教わり、そういうことに染まっていた。
その味は格別だった、人の眼を欺き、ちょろまかす醍醐味は何とも言えない。あの頃から憶えたわるさの楽しみが今でも忘れられない。
しかし、そんなことは直ぐばれる。境内の裏で盗んだ物を食べているとき、太郎はふと背後に人がいるのに気が付いた。振り返ると恐い顔をした屈強な大人が立っていた。
「こらぁ、この餓鬼、また盗んだな、今度は許さんぞ!」
いきなり入り込んできた私服刑事に太郎は捕まった。
「あれっ、いけねぇ」
草の上に座り込んで食べていた太郎は逃げようがなかった。
首根っこを押さえられ、身動きが出来ない。
「今度こそ、放り込むからな」
「あっ、許してよ、おじさん、これは貰った物なんだよぉ」
「嘘をつけっ、誰に貰ったんだ、言ってみろ」
「それは、あの……」
「そらみろ、みえすいた嘘を付くんじゃない!」
騒ぎを聞きつけ、何人かの人達が周りを取り囲む。
「また、あの子だな……」というような人の囁きが漏れる。
そのとき、誰かが叫んだ。
「あたしよ、あたしなの、この子にあたしが上げたんだもん」
その声の主は雪枝だった、顔を真っ赤にして立っていた。
「あっ、雪枝……」
太郎は雪枝をみた、そのときの彼女はいつもと違う凛としていて別人のように綺麗に見えた。刑事はじろりと雪枝をみた。
太郎と同じくらいの子供ではあるが、その眼からは何かの強い意志を感じ取った。
「あ、いや……お嬢ちゃん、庇う気持ちはわからなく無いがね」
「だって、あたしお金を払ったわよ。なんなら聞いてきてよ、そのお店で」
「ふむ、それまで言うのなら一緒に私が確認しよう」
渋々刑事は言った。
「うん、いいわよ」
刑事は口を尖らせている雪枝を見ると、振り返り太郎を見た。
「おい、餓鬼、待ってろよ。このお嬢さんのいうことが間違いだったら、わかってるな」
「うん……」
太郎はべそを掻きながら、今にも泣きそうな顔をしていた。
やがて、刑事と雪枝は戻ってきた。
「たしかに、この人の言うとおりだった」
刑事はそういって太郎を一瞥 するとどこかへ行ってしまった。人々は期待していた出来事が何もなかったので、期待はずれの顔をしながらそれぞれに境内に散っていった。
太郎は、雪枝に聞いた。
「どうしてなんだよ、雪枝」
感謝して良い雪枝にまるで余計なことをした、と言わんばかりに太郎は言う。
「ばかねえ、だって同級生じゃん」
それだけ言って笑いながら、彼女は夜の境内(けいだい)に消えた。
姉のまり子は黙って木の陰に隠れていて雪枝の後を追った。
「待ってよぉ、雪枝ったら……もうっ」
その夜の寺の境内では花火が打ち上げられて夜空を美しく飾っていた。
あの夜は熱帯夜だった。
或る日、それから中学を卒業した太郎は、毎日ぶらぶらしていた。そんな日に、父親と言い争っていた。
「なにもしないでそんなに田舎が嫌なら出ていけ、戻るんじゃないぞ、太郎っ!」
「わかったよ、こんな家、帰るもんかい!」
父親と言い合い家を飛び出そうとしたとき、目に涙を浮かべ内緒でそっと母が金を包んで太郎に渡してくれた。
「東京が嫌になったら戻っておいで、そのときにはお父さんに謝るんだよ」
「うん、わかってる、ごめんな母さん」
そういって家を飛び出して、もう何年も経った。
東京の空を見ながら、再び上がる花火が美しい。
「あ、雪枝……また花火が上がったよ」
「え、どこどこ?」
そう言いながら、太郎の妻の雪枝は生まれたばかりの赤ん坊を抱き空を見上げている。
「太郎ちゃんとはあの花火の夜が懐かしいわね」
「うん、俺はあのときほど雪枝が綺麗だとは思わなかったな」
「そうかな、太郎ちゃんは姉さんばっかり見ていたし」
「ええ、どうだったかな、忘れた」
「あはは」若い夫婦は微笑む。
「ねえ、そろそろ田舎に帰ってお父さんに謝ってきたら? 私も付いて行くから」
「そうだね、孫の顔でも見れば少しは機嫌が直るかもな」
「ねえ、実は……」
「なんだい、雪枝」
「あのね、じつはあたし……太郎さんの実家に電話しちゃったの」
「えっ?」
「そうしたら、お母さんが出て心配していたわよ、あたしがお嫁さんになったのも知っていて……」
「え、ほんとかい?」
「うん、早く孫の顔が見たいって、お父さんもそう言ってるって、あなた」
「ふうぅ、知らなかったな、じゃあ今度の連休に親子で里帰りするか」
「そうしましょ、あなた」
ボンボンッという花火は空に高く上がった。
その夜もあの夜のように暑い熱帯夜だった。
今、太郎は東京の夜空に舞い上がる花火を見上げていた。
(それにしても今夜はくそ暑いな……)
ずっと前に田舎暮らしが厭で家を飛び出し、やってきた東京の街。夜空の色が鮮やかに変わり、威勢の良いかけ声と共に打ち上がる花火の嵐。降り掛かり、燃え尽きた花火のかけらが散る。
(いいなあ、花火は……)
ふと、太郎は飛び出してきた田舎を思い出した。
田舎にいた頃の夏、いろいろな思い出があった。子供の頃は暑くなれば悪童仲間とパンツ一枚で近くの川に飛び込んだり、潜り込んで川魚やザリガニ等を穫ったりしていた。
夏と言えばやはり夏祭りが良い。縁日で盛り上がる神社の境内は賑やかだった。そこでは、沢山の珍しい出店が出て賑わいとても活気がある。
焼きソバ、金魚すくい、駄菓子屋などが一杯境内の空き地を占める。子供達は親からもらった小遣いでそれを買ったり食べたりする。
それは彼等にとっては夏休みの楽しみだった。
綺麗なお姉さん達が浴衣を着て歩く姿が太郎少年には眩しかった。
そんな人混みの中に同級生の雪枝の浴衣姿を太郎はみつけた。いつもは地味な服で赤い顔をしていた雪枝が、その日は浴衣を着て少し化粧をしていた。
雪枝が着ている浴衣は多分姉のお下がりだろう。綺麗な姉と連れ添って雪枝は出店を覗いている。それは髪飾りや小物など女の子が好きそうな店だった。店と言っても地面に箱を置き、その上に板を置いただけの臨時の店である。
「おい、雪枝、姉ちゃんと一緒かい」
「ああ、太郎ちゃん、なにしてんの」
「べつにぃ……」
雪枝に声を掛けたのは、別に雪枝に話したいわけではない。隣の綺麗な姉の「まり子」が気になったからである。まり子はあまりたちの良くない太郎を無視している。
「雪枝、いこうよう……」
あんな太郎を相手にしないでもっと別の所へ行こうと妹の手を引っ張る。
「うん、ごめんね、太郎ちゃん、姉ちゃんが言うから」
それにむかついた太郎は言う。
「なんだよ、まり子、俺がそんなに嫌いかよ」
「だってぇ、あんた評判良くないもん、いこっ……雪枝」
生意気なまり子は、妹の手を引いて行ってしまった。
「なんだよ、このクソまり子っ!」
たしかに太郎は不良の仲間入りをしていた時期がある。その夜は一人でブラブラ境内をうろついていた。悪ガキの太郎は店の駄菓子や食い物をこっそり盗み境内の裏で食べるのが好きだった。小遣いが無いわけではないが悪童に教わり、そういうことに染まっていた。
その味は格別だった、人の眼を欺き、ちょろまかす醍醐味は何とも言えない。あの頃から憶えたわるさの楽しみが今でも忘れられない。
しかし、そんなことは直ぐばれる。境内の裏で盗んだ物を食べているとき、太郎はふと背後に人がいるのに気が付いた。振り返ると恐い顔をした屈強な大人が立っていた。
「こらぁ、この餓鬼、また盗んだな、今度は許さんぞ!」
いきなり入り込んできた私服刑事に太郎は捕まった。
「あれっ、いけねぇ」
草の上に座り込んで食べていた太郎は逃げようがなかった。
首根っこを押さえられ、身動きが出来ない。
「今度こそ、放り込むからな」
「あっ、許してよ、おじさん、これは貰った物なんだよぉ」
「嘘をつけっ、誰に貰ったんだ、言ってみろ」
「それは、あの……」
「そらみろ、みえすいた嘘を付くんじゃない!」
騒ぎを聞きつけ、何人かの人達が周りを取り囲む。
「また、あの子だな……」というような人の囁きが漏れる。
そのとき、誰かが叫んだ。
「あたしよ、あたしなの、この子にあたしが上げたんだもん」
その声の主は雪枝だった、顔を真っ赤にして立っていた。
「あっ、雪枝……」
太郎は雪枝をみた、そのときの彼女はいつもと違う凛としていて別人のように綺麗に見えた。刑事はじろりと雪枝をみた。
太郎と同じくらいの子供ではあるが、その眼からは何かの強い意志を感じ取った。
「あ、いや……お嬢ちゃん、庇う気持ちはわからなく無いがね」
「だって、あたしお金を払ったわよ。なんなら聞いてきてよ、そのお店で」
「ふむ、それまで言うのなら一緒に私が確認しよう」
渋々刑事は言った。
「うん、いいわよ」
刑事は口を尖らせている雪枝を見ると、振り返り太郎を見た。
「おい、餓鬼、待ってろよ。このお嬢さんのいうことが間違いだったら、わかってるな」
「うん……」
太郎はべそを掻きながら、今にも泣きそうな顔をしていた。
やがて、刑事と雪枝は戻ってきた。
「たしかに、この人の言うとおりだった」
刑事はそういって太郎を
太郎は、雪枝に聞いた。
「どうしてなんだよ、雪枝」
感謝して良い雪枝にまるで余計なことをした、と言わんばかりに太郎は言う。
「ばかねえ、だって同級生じゃん」
それだけ言って笑いながら、彼女は夜の境内(けいだい)に消えた。
姉のまり子は黙って木の陰に隠れていて雪枝の後を追った。
「待ってよぉ、雪枝ったら……もうっ」
その夜の寺の境内では花火が打ち上げられて夜空を美しく飾っていた。
あの夜は熱帯夜だった。
或る日、それから中学を卒業した太郎は、毎日ぶらぶらしていた。そんな日に、父親と言い争っていた。
「なにもしないでそんなに田舎が嫌なら出ていけ、戻るんじゃないぞ、太郎っ!」
「わかったよ、こんな家、帰るもんかい!」
父親と言い合い家を飛び出そうとしたとき、目に涙を浮かべ内緒でそっと母が金を包んで太郎に渡してくれた。
「東京が嫌になったら戻っておいで、そのときにはお父さんに謝るんだよ」
「うん、わかってる、ごめんな母さん」
そういって家を飛び出して、もう何年も経った。
東京の空を見ながら、再び上がる花火が美しい。
「あ、雪枝……また花火が上がったよ」
「え、どこどこ?」
そう言いながら、太郎の妻の雪枝は生まれたばかりの赤ん坊を抱き空を見上げている。
「太郎ちゃんとはあの花火の夜が懐かしいわね」
「うん、俺はあのときほど雪枝が綺麗だとは思わなかったな」
「そうかな、太郎ちゃんは姉さんばっかり見ていたし」
「ええ、どうだったかな、忘れた」
「あはは」若い夫婦は微笑む。
「ねえ、そろそろ田舎に帰ってお父さんに謝ってきたら? 私も付いて行くから」
「そうだね、孫の顔でも見れば少しは機嫌が直るかもな」
「ねえ、実は……」
「なんだい、雪枝」
「あのね、じつはあたし……太郎さんの実家に電話しちゃったの」
「えっ?」
「そうしたら、お母さんが出て心配していたわよ、あたしがお嫁さんになったのも知っていて……」
「え、ほんとかい?」
「うん、早く孫の顔が見たいって、お父さんもそう言ってるって、あなた」
「ふうぅ、知らなかったな、じゃあ今度の連休に親子で里帰りするか」
「そうしましょ、あなた」
ボンボンッという花火は空に高く上がった。
その夜もあの夜のように暑い熱帯夜だった。