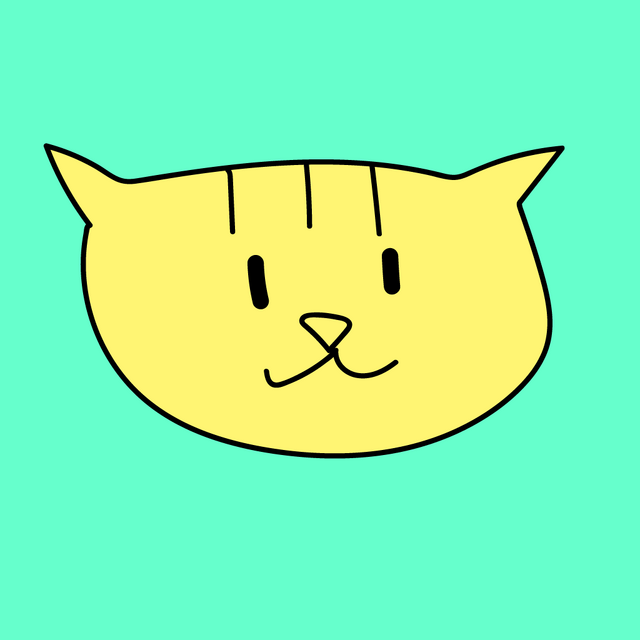第1話
文字数 3,389文字
「終わった」
「あぁ、終わったな」
昨日のことを思い出し、ついこぼれてしまった正樹の声に哲也は同調した。
駄菓子屋で購入したソーダ味のアイスの袋を開け、店の前にあるベンチに座り、シャリっと一口かじる。
雲一つない晴天の下、ゆっくり時間を過ごすのはいつぶりだろうか。
そよ風が肌に触れる度、気持ちいいと思うと同時に昨日までのことを思い出す。
仲間と汗を流しながら必死に努力した日々が、とても懐かしく感じる。
哲也はぼーっと青空を眺める。
青空は青いな。
そんな当たり前のことを考えていると、隣から悔しそうな、申し訳なさそうな「俺のせいだ」という声がした。
「正樹だけのせいじゃない」
「いや、俺が、俺があの時」
「違うって言ってんだろ」
「でも!」
歯を食いしばり、目をきつく閉じている。
罪悪感に押しつぶされて自分を責めずにはいられないのだろう。
その気持ちは痛いほど分かった。
「俺が、打たれたから」
震える声に、哲也は何も返さなかった。
打たれたのは事実だ。
しかし、正樹一人の責任ではない。
もっと打てたら、もっと足が速かったら、もっと練習していたら。そんな思いは仲間全員が抱えている。誰かが悪いのではない。誰か一人のせいではない。
昨日の決勝戦。
甲子園に出場するための切符を手にするために戦い、敗れた。
九回裏、同点、満塁。
頭上から降り注がれる熱に耐えながら、正樹は全力で投球した。正樹の球を受けとめた哲也が一番分かっている。正樹は精一杯頑張った。
汗が髪から額、頬を濡らす。熱気で視界が滲む中、仲間と共に挑んだ。
「正樹、大丈夫だ」
マウンドに立つ正樹にかける言葉が見つからず、どんな場面でも使える魔法の「大丈夫」を口にして、白いユニフォームを叩いた。
もっと他にいい言葉があったと思うが、気の利いた言葉は出てこなかった。
この言葉を最後に正樹から離れ、ミットを構えた。
あとストライクを一つとればいい。
そうすれば、このピンチは切り抜けられる。
正樹が足を上げ、腕を振る。
ミットに入るはずだった球は、カキーンと手本のような音を立てて正樹の頭上を通り、遠く遠くへ落ちていった。
観客から、相手のベンチから、歓声が沸いた。
空高く投げられる帽子、球場内に響く拍手、吹奏楽部の演奏。
それらすべて、自分たちへ向けられたのではない。
灰色のユニフォームを着た男たちが笑顔でホームへかえってくる。
ホームベースが踏まれるところを見たくなくて、哲也はマウンドで蹲る正樹を眺めていた。
あぁ、終わったんだ。
昔からの夢だった甲子園。
どんなピッチャーがいるのかとわくわくしながら入部し、仲間と切磋琢磨した高校生活。
正樹と出会ってから今までのことが走馬灯のように脳裏を駆け抜けた。
哲也は「並ぼう」と声をかけられるまで、ずっと正樹を見つめていた。
仲間に連れられ泣きながらマウンドを去る正樹とは対照的に、哲也は涙一粒も出なかった。
甲子園の切符を手にした彼等を前に帽子をとり、礼をする。
あちこちから拍手が送られる。
この拍手は、何を意味するのだろう。
勝った高校に対して、おめでとうの拍手だろうか。
いい試合だったという拍手だろうか。
後者であるならば、いい試合とはどういう試合だろう。
いや、もしかしたら、お疲れ様の拍手かもしれない。
拍手でお疲れ様を表すなんて、誰が考えたのだろう。
球場を去るまで、ずっと拍手の意味を考えていた。
「お前だけのせいじゃないって言ってんだろ」
昨日のことを思い出してまた泣きそうになっている正樹にそう言うが、正樹は「でも」「だって」を繰り返す。
不思議だった。
正樹の瞳には涙が溜まるのに、どうして自分は昨日から一滴も流れないのだろう。
この暑さで涙も乾いてしまったのだろうか。
敗北を突き付けられても、あぁ、終わったのだと思うだけだった。
昨日から頭がぼんやりしている。まだ事実を両手で受け止められていないような、そんな感じだ。
ぼーっと正樹の横顔を見つめていると、ついに正樹の瞳から涙がこぼれた。
哲也は正樹から視線を外す。
「お前だけのせいじゃない。俺がもっと賢かったら色んなリードができたかもしれねぇし、ショートがミスをしなかったら勝てたかもしれねぇ」
「ショートのせいじゃない」
「そうだ、そんでお前のせいでもない」
哲也の言いたいことを理解し、正樹は口を閉ざした。
近くの木にしがみ付いている蝉が鳴き始め、二人の沈黙に割って入る。
「夏の部活は地獄だったなぁ」
哲也の呟きに、正樹は軽い相槌を返す。
青く晴れ渡った空に向かって飛んでいく球、蝉によってかき消される監督の声、小さく聞こえてくる吹奏楽部の音。
暑くて暑くて、休憩中、頭に水をぶっかけたことは何度もある。
青い空も、蝉の声も、夏の練習を思い出させる。
これからは部活に参加する時間が減るだろう。後輩たちの練習に付き合うために参加するくらいだ。そして近いうちに引退する。
残りの高校生活で、泥だらけになることも、ユニフォームを洗う母に怒られることも、頭から水をぶっかけることもない。
真面目に授業を受けて、受験のぴりついた空気を感じ、一般入試を受けて、卒業式を迎えるのだ。
「哲也は、大学でも野球するんだよな?」
「まぁ、そうだな」
正樹はスポーツ推薦のため、大学はもう決まっている。
哲也に推薦の話は一つもこなかった。部活で忙しかったものの、成績は悪くないため正樹と同じ大学を第一志望にしているが、推薦の正樹に少しだけ引け目を感じている。同じ大学で野球をやることになっても、正樹とバッテリーが組めるとは限らない。正樹はマウンドに立ち、自分は観客席に座る。そんな惨めな目に遭う可能性だってある。そうなったら、もしかしたら、大好きな野球をやめるかもしれない。
そんなことを口に出せるはずもなく、大学の話はそこで終わった。
大学のことは考えても仕方がない。
つい昨日、甲子園の夢が絶たれたばかりだ。
今はまだこの余韻に浸りたい。
「静かだな」
アイスをかじりながら、正樹は言った。
そんなわけないだろ、蝉の声がうるさいぞ。
哲也はそう言おうとしてやめた。
「甲子園、行きたかったな」
代わりに口から出たのは、ずっと抱えていた夢だった。
甲子園に行くぞ。目指せ、甲子園。甲子園で勝つ。何度も仲間と言い合ったし、部室には誰かが書道の授業で書いた、それらの言葉が、へたくそな字で貼ってある。
正樹は「あぁ」と短く返した後、「あ」と何かに気づいたように声を出した。
「当たった」
正樹が食べ終えたアイスの棒にはあたりと書かれていた。
服の袖で涙を拭き、アイスの棒を持って、正樹は駄菓子屋に入った。
「おばちゃん、当たったからもう一個頂戴」
哲也はまだ半分以上残っているアイスにかじりついた。
ソーダの涼しい味が口内に広がる。
シャリシャリと音を立て、歯が痛くなる前に喉へ流し込んだ。
「甲子園、行きたかったな」
再度こぼれる本音。
正樹は駄菓子屋のおばちゃんと未だやりとりをしており、哲也の声を拾った者はいない。
負けたという実感が今になって襲ってきた。
幼い頃、テレビで見た甲子園。
勝ち残った者たちだけが立つことを許される場所。
高校球児の真剣な眼差しと闘志は、絶対に勝つのだと訴えていた。
そこではどんな景色が見えて、どんなことを考えるのだろう。
憧れ、夢を見て、いつかそこに自分も行くのだと思っていた。
激戦の末に勝利をもぎとり、一生の思い出にする。そんな思いを持って励んだ高校生活。
いくら悔いたところで時間が戻ってくるわけではない。
けれど、悔やまずにはいられない。
もっと練習をしていたら、勝てたかもしれない、甲子園に行くことができたかもしれない。
みんなとまだ野球をしたかった。
正樹の球をもっととりたかった。
あと少し、あともう少しだったのに。
頬をつたったものが、手に落ちる。
一度落ちるとぼろぼろと止まらなくなり、服やズボンにしみをつくっていく。
服の裾で顔を拭くと、誤魔化すように大きな口でアイスをかじった。
空色のアイスから顔を出した棒に、あたりの文字はない。
もう一口食べようと口を開けて気づいた。
いつの間にか静寂が訪れている。
ふと地面を見ると蝉が転がっていた。
哲也の夏は終わった。
「あぁ、終わったな」
昨日のことを思い出し、ついこぼれてしまった正樹の声に哲也は同調した。
駄菓子屋で購入したソーダ味のアイスの袋を開け、店の前にあるベンチに座り、シャリっと一口かじる。
雲一つない晴天の下、ゆっくり時間を過ごすのはいつぶりだろうか。
そよ風が肌に触れる度、気持ちいいと思うと同時に昨日までのことを思い出す。
仲間と汗を流しながら必死に努力した日々が、とても懐かしく感じる。
哲也はぼーっと青空を眺める。
青空は青いな。
そんな当たり前のことを考えていると、隣から悔しそうな、申し訳なさそうな「俺のせいだ」という声がした。
「正樹だけのせいじゃない」
「いや、俺が、俺があの時」
「違うって言ってんだろ」
「でも!」
歯を食いしばり、目をきつく閉じている。
罪悪感に押しつぶされて自分を責めずにはいられないのだろう。
その気持ちは痛いほど分かった。
「俺が、打たれたから」
震える声に、哲也は何も返さなかった。
打たれたのは事実だ。
しかし、正樹一人の責任ではない。
もっと打てたら、もっと足が速かったら、もっと練習していたら。そんな思いは仲間全員が抱えている。誰かが悪いのではない。誰か一人のせいではない。
昨日の決勝戦。
甲子園に出場するための切符を手にするために戦い、敗れた。
九回裏、同点、満塁。
頭上から降り注がれる熱に耐えながら、正樹は全力で投球した。正樹の球を受けとめた哲也が一番分かっている。正樹は精一杯頑張った。
汗が髪から額、頬を濡らす。熱気で視界が滲む中、仲間と共に挑んだ。
「正樹、大丈夫だ」
マウンドに立つ正樹にかける言葉が見つからず、どんな場面でも使える魔法の「大丈夫」を口にして、白いユニフォームを叩いた。
もっと他にいい言葉があったと思うが、気の利いた言葉は出てこなかった。
この言葉を最後に正樹から離れ、ミットを構えた。
あとストライクを一つとればいい。
そうすれば、このピンチは切り抜けられる。
正樹が足を上げ、腕を振る。
ミットに入るはずだった球は、カキーンと手本のような音を立てて正樹の頭上を通り、遠く遠くへ落ちていった。
観客から、相手のベンチから、歓声が沸いた。
空高く投げられる帽子、球場内に響く拍手、吹奏楽部の演奏。
それらすべて、自分たちへ向けられたのではない。
灰色のユニフォームを着た男たちが笑顔でホームへかえってくる。
ホームベースが踏まれるところを見たくなくて、哲也はマウンドで蹲る正樹を眺めていた。
あぁ、終わったんだ。
昔からの夢だった甲子園。
どんなピッチャーがいるのかとわくわくしながら入部し、仲間と切磋琢磨した高校生活。
正樹と出会ってから今までのことが走馬灯のように脳裏を駆け抜けた。
哲也は「並ぼう」と声をかけられるまで、ずっと正樹を見つめていた。
仲間に連れられ泣きながらマウンドを去る正樹とは対照的に、哲也は涙一粒も出なかった。
甲子園の切符を手にした彼等を前に帽子をとり、礼をする。
あちこちから拍手が送られる。
この拍手は、何を意味するのだろう。
勝った高校に対して、おめでとうの拍手だろうか。
いい試合だったという拍手だろうか。
後者であるならば、いい試合とはどういう試合だろう。
いや、もしかしたら、お疲れ様の拍手かもしれない。
拍手でお疲れ様を表すなんて、誰が考えたのだろう。
球場を去るまで、ずっと拍手の意味を考えていた。
「お前だけのせいじゃないって言ってんだろ」
昨日のことを思い出してまた泣きそうになっている正樹にそう言うが、正樹は「でも」「だって」を繰り返す。
不思議だった。
正樹の瞳には涙が溜まるのに、どうして自分は昨日から一滴も流れないのだろう。
この暑さで涙も乾いてしまったのだろうか。
敗北を突き付けられても、あぁ、終わったのだと思うだけだった。
昨日から頭がぼんやりしている。まだ事実を両手で受け止められていないような、そんな感じだ。
ぼーっと正樹の横顔を見つめていると、ついに正樹の瞳から涙がこぼれた。
哲也は正樹から視線を外す。
「お前だけのせいじゃない。俺がもっと賢かったら色んなリードができたかもしれねぇし、ショートがミスをしなかったら勝てたかもしれねぇ」
「ショートのせいじゃない」
「そうだ、そんでお前のせいでもない」
哲也の言いたいことを理解し、正樹は口を閉ざした。
近くの木にしがみ付いている蝉が鳴き始め、二人の沈黙に割って入る。
「夏の部活は地獄だったなぁ」
哲也の呟きに、正樹は軽い相槌を返す。
青く晴れ渡った空に向かって飛んでいく球、蝉によってかき消される監督の声、小さく聞こえてくる吹奏楽部の音。
暑くて暑くて、休憩中、頭に水をぶっかけたことは何度もある。
青い空も、蝉の声も、夏の練習を思い出させる。
これからは部活に参加する時間が減るだろう。後輩たちの練習に付き合うために参加するくらいだ。そして近いうちに引退する。
残りの高校生活で、泥だらけになることも、ユニフォームを洗う母に怒られることも、頭から水をぶっかけることもない。
真面目に授業を受けて、受験のぴりついた空気を感じ、一般入試を受けて、卒業式を迎えるのだ。
「哲也は、大学でも野球するんだよな?」
「まぁ、そうだな」
正樹はスポーツ推薦のため、大学はもう決まっている。
哲也に推薦の話は一つもこなかった。部活で忙しかったものの、成績は悪くないため正樹と同じ大学を第一志望にしているが、推薦の正樹に少しだけ引け目を感じている。同じ大学で野球をやることになっても、正樹とバッテリーが組めるとは限らない。正樹はマウンドに立ち、自分は観客席に座る。そんな惨めな目に遭う可能性だってある。そうなったら、もしかしたら、大好きな野球をやめるかもしれない。
そんなことを口に出せるはずもなく、大学の話はそこで終わった。
大学のことは考えても仕方がない。
つい昨日、甲子園の夢が絶たれたばかりだ。
今はまだこの余韻に浸りたい。
「静かだな」
アイスをかじりながら、正樹は言った。
そんなわけないだろ、蝉の声がうるさいぞ。
哲也はそう言おうとしてやめた。
「甲子園、行きたかったな」
代わりに口から出たのは、ずっと抱えていた夢だった。
甲子園に行くぞ。目指せ、甲子園。甲子園で勝つ。何度も仲間と言い合ったし、部室には誰かが書道の授業で書いた、それらの言葉が、へたくそな字で貼ってある。
正樹は「あぁ」と短く返した後、「あ」と何かに気づいたように声を出した。
「当たった」
正樹が食べ終えたアイスの棒にはあたりと書かれていた。
服の袖で涙を拭き、アイスの棒を持って、正樹は駄菓子屋に入った。
「おばちゃん、当たったからもう一個頂戴」
哲也はまだ半分以上残っているアイスにかじりついた。
ソーダの涼しい味が口内に広がる。
シャリシャリと音を立て、歯が痛くなる前に喉へ流し込んだ。
「甲子園、行きたかったな」
再度こぼれる本音。
正樹は駄菓子屋のおばちゃんと未だやりとりをしており、哲也の声を拾った者はいない。
負けたという実感が今になって襲ってきた。
幼い頃、テレビで見た甲子園。
勝ち残った者たちだけが立つことを許される場所。
高校球児の真剣な眼差しと闘志は、絶対に勝つのだと訴えていた。
そこではどんな景色が見えて、どんなことを考えるのだろう。
憧れ、夢を見て、いつかそこに自分も行くのだと思っていた。
激戦の末に勝利をもぎとり、一生の思い出にする。そんな思いを持って励んだ高校生活。
いくら悔いたところで時間が戻ってくるわけではない。
けれど、悔やまずにはいられない。
もっと練習をしていたら、勝てたかもしれない、甲子園に行くことができたかもしれない。
みんなとまだ野球をしたかった。
正樹の球をもっととりたかった。
あと少し、あともう少しだったのに。
頬をつたったものが、手に落ちる。
一度落ちるとぼろぼろと止まらなくなり、服やズボンにしみをつくっていく。
服の裾で顔を拭くと、誤魔化すように大きな口でアイスをかじった。
空色のアイスから顔を出した棒に、あたりの文字はない。
もう一口食べようと口を開けて気づいた。
いつの間にか静寂が訪れている。
ふと地面を見ると蝉が転がっていた。
哲也の夏は終わった。