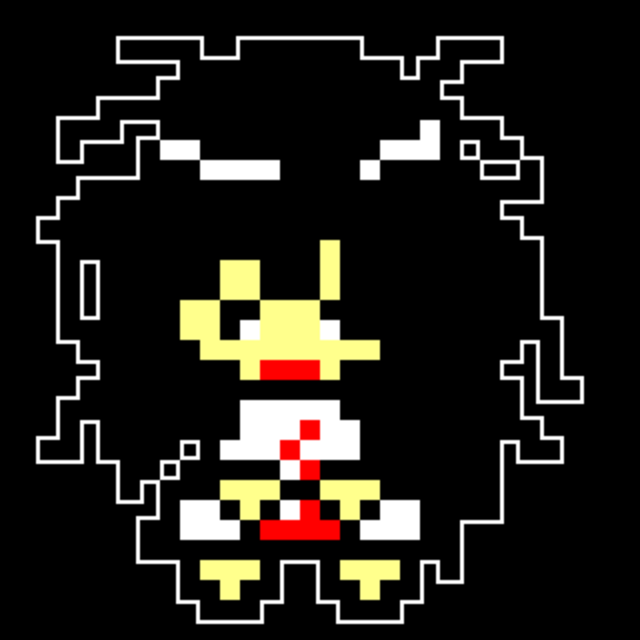AC7.3
文字数 2,116文字
それから二、三時間ぐらい――実際はもっと短いのかもしれないが、正確な時間がわからないのと歩くのにかなりの神経をつかうのでそのぐらいかかったように感じた――ひたすら歩き続けたはてにまた最初の十字路に戻ってきた。この道にはあれこれ別れ道があったものの右と同様にしかけは影すらなく、時間稼ぎなのかただ無駄に歩かされただけ。右も真ん中もお飾りだった。それをペットボトルを見て知ったとき、いらだちや落胆を通り越しておもわず笑ってしまった。とはいえ、ここに戻ってきたということは確実に出口に近づいているということでもあるから、この暗闇のなかを当てずっぽうで挑むよりかはだいぶマシだと思う。そう思うことにしてライターを消し最後の道に進んだ。
左の道も壁伝いに歩きながら、この先のことに考えをめぐらせた。
この道を進んだら必ずしかけが待っているはず。どんなものを用意しているのかは実際に見てみないとわからないけど、ひとつ言えるとしたらこの暗闇を利用していないはずがないということだ。もらったライターはそのためのものでもあると思う。しかし、いかんせん照らせる範囲がせまいからしかけに時間がかかって燃料を切らしてしまう可能性があり、もしそうなってしまったら……正直、想像もしたくない。何も見えずザラついた感触だけが延々とつづき、入口で味わった感覚の狂いに幾度となく襲われてはそのたびに追い払って、分岐路につくごとに点けたあのほの明るいオレンジと青の光とほのかに伝わってくる暖かさにどれだけ救われたことか。それなのにそのたった一つの救いの光さえもなく永遠の無の中をさまよい歩くのは絶望的だ。だから絶対に火を、灯りを絶やしてはいけない。なにがあっても……。
そんなことを考えていたら、突然足元でぴちゃと音がなった。完全に虚を突かれて見えるはずもないのに下に目をやってしまった。しばらくしても何も起こる様子がないので、ライターの火を灯して、恐る恐る足元を照らしてみた。
そこにはゆらゆらと揺れながら見つめ返してくる自分がいた。
なんらかの液体がはってありそれに映っているようだけど……。危ないとは思いつつも右手の人差指に液体をつけて調べてみたところ、なんてことはないただの水だった。安全なものだとわかったので今度は水がどこまであるのか調べるため立ち上がり水を蹴った。波紋が連なり水面を滑っていく。その最初の波紋を目で追いかけていくと、やがて光の届く範囲を超えて暗闇の中へゆるやかに飲み込まれていってしまった。まだまだあるみたいだ。あと気になるのは深さだけど、こればかりは進んでみて調べるほかない。視線を水面からライターに移しこのままつけていくのか消していくのか悩んだすえ、おそらく大丈夫だろうと判断して消していくことにした。親指を離し、もしものため胸より高くしたまま、地面があることを一歩一歩確認しながら用心して進んでいく。そして五歩目でついに地面は途絶えた。
とうとうきたなと心の中で呟き、ふちギリギリに立ってもう一度ライターをつけた。水はまだあるようで手にすくって飛ばしてみると遠くでぱちゃんと弾けた。ここを進んでいくのに変わりはないけどやはりそれでも……あたりを照らしてほかに道があるのか探した。見える範囲にはなかった。しかたないとため息をついて、体を時計回りに九十度回転させ右足できわに立ち、左足をのばして徐々に腰をおろしていった。つま先から水に沈んでいきくるぶしまで来ると靴の隙間からドンドン水が侵入してくる。それからふくらはぎ、膝をこえ太ももまで浸り、かなりキツイ体勢になってようやくつまさきが地面に触れた。そのまま左足をおろしていき、つま先立ちができるようになったら体重を移し、右足も水のなかへ沈めた。
「……つめたい」と口からこぼれた。
骨を刺すような冷たさに両脚を入れているだけでも全身から体温が奪われていきそうだ。このままじっとしていたら寒さにやられてしまいそうなのでとっとと抜け出すために重くなった脚を動かす。そして歩きだしてからまた五歩目で地面がとぎれた。今回もおなじ方法で降りはじめたがなかなか足がつかないので途中で切り上げ、左手のライターをくわえてふちにこしかけ、ゆっくりと降りていく。すると思っていたよりも深く、降り立ったときあやうく波立った水が口に流れ込むところだった。そこで波が落ち着くまでのあいだ顔を上げて待ち、波がおさまったところで顔をもどすとあごすれすれに水面があった。全身を水に浸しまるで氷漬けにされたようで冷気が体の芯まで沁みてくる。一方ですでに入っていたつまさきはもはや冷たさを感じなくなっている。このままでは本当にマズいのではやいところ上がりたい、でも道中なにがあるかわからないので最初に決めたことは守らないといけない。くわえているライターを左手に持ちかえ呼吸をしやすくし、それからこのさき火をつけていくのか考えて結局使わないことにした、というのも火をつけながらかつ濡らさないように気を配れる自信がなかったから。そういうわけでこの凍てつく水の中を、めいっぱい左手をかかげ、せいっぱい体を振ってかきわけていった。
左の道も壁伝いに歩きながら、この先のことに考えをめぐらせた。
この道を進んだら必ずしかけが待っているはず。どんなものを用意しているのかは実際に見てみないとわからないけど、ひとつ言えるとしたらこの暗闇を利用していないはずがないということだ。もらったライターはそのためのものでもあると思う。しかし、いかんせん照らせる範囲がせまいからしかけに時間がかかって燃料を切らしてしまう可能性があり、もしそうなってしまったら……正直、想像もしたくない。何も見えずザラついた感触だけが延々とつづき、入口で味わった感覚の狂いに幾度となく襲われてはそのたびに追い払って、分岐路につくごとに点けたあのほの明るいオレンジと青の光とほのかに伝わってくる暖かさにどれだけ救われたことか。それなのにそのたった一つの救いの光さえもなく永遠の無の中をさまよい歩くのは絶望的だ。だから絶対に火を、灯りを絶やしてはいけない。なにがあっても……。
そんなことを考えていたら、突然足元でぴちゃと音がなった。完全に虚を突かれて見えるはずもないのに下に目をやってしまった。しばらくしても何も起こる様子がないので、ライターの火を灯して、恐る恐る足元を照らしてみた。
そこにはゆらゆらと揺れながら見つめ返してくる自分がいた。
なんらかの液体がはってありそれに映っているようだけど……。危ないとは思いつつも右手の人差指に液体をつけて調べてみたところ、なんてことはないただの水だった。安全なものだとわかったので今度は水がどこまであるのか調べるため立ち上がり水を蹴った。波紋が連なり水面を滑っていく。その最初の波紋を目で追いかけていくと、やがて光の届く範囲を超えて暗闇の中へゆるやかに飲み込まれていってしまった。まだまだあるみたいだ。あと気になるのは深さだけど、こればかりは進んでみて調べるほかない。視線を水面からライターに移しこのままつけていくのか消していくのか悩んだすえ、おそらく大丈夫だろうと判断して消していくことにした。親指を離し、もしものため胸より高くしたまま、地面があることを一歩一歩確認しながら用心して進んでいく。そして五歩目でついに地面は途絶えた。
とうとうきたなと心の中で呟き、ふちギリギリに立ってもう一度ライターをつけた。水はまだあるようで手にすくって飛ばしてみると遠くでぱちゃんと弾けた。ここを進んでいくのに変わりはないけどやはりそれでも……あたりを照らしてほかに道があるのか探した。見える範囲にはなかった。しかたないとため息をついて、体を時計回りに九十度回転させ右足できわに立ち、左足をのばして徐々に腰をおろしていった。つま先から水に沈んでいきくるぶしまで来ると靴の隙間からドンドン水が侵入してくる。それからふくらはぎ、膝をこえ太ももまで浸り、かなりキツイ体勢になってようやくつまさきが地面に触れた。そのまま左足をおろしていき、つま先立ちができるようになったら体重を移し、右足も水のなかへ沈めた。
「……つめたい」と口からこぼれた。
骨を刺すような冷たさに両脚を入れているだけでも全身から体温が奪われていきそうだ。このままじっとしていたら寒さにやられてしまいそうなのでとっとと抜け出すために重くなった脚を動かす。そして歩きだしてからまた五歩目で地面がとぎれた。今回もおなじ方法で降りはじめたがなかなか足がつかないので途中で切り上げ、左手のライターをくわえてふちにこしかけ、ゆっくりと降りていく。すると思っていたよりも深く、降り立ったときあやうく波立った水が口に流れ込むところだった。そこで波が落ち着くまでのあいだ顔を上げて待ち、波がおさまったところで顔をもどすとあごすれすれに水面があった。全身を水に浸しまるで氷漬けにされたようで冷気が体の芯まで沁みてくる。一方ですでに入っていたつまさきはもはや冷たさを感じなくなっている。このままでは本当にマズいのではやいところ上がりたい、でも道中なにがあるかわからないので最初に決めたことは守らないといけない。くわえているライターを左手に持ちかえ呼吸をしやすくし、それからこのさき火をつけていくのか考えて結局使わないことにした、というのも火をつけながらかつ濡らさないように気を配れる自信がなかったから。そういうわけでこの凍てつく水の中を、めいっぱい左手をかかげ、せいっぱい体を振ってかきわけていった。