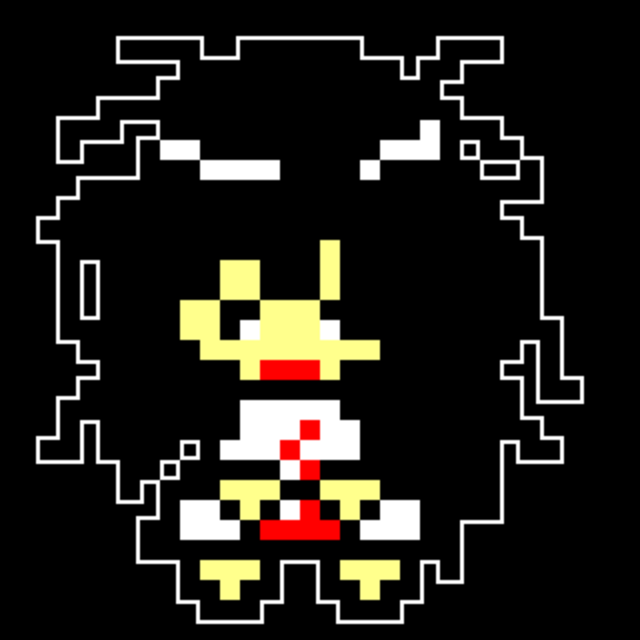AC9.15
文字数 1,419文字
小さな部屋の真ん中、椅子に腰かけた彼女と目が合った。すると、立ち上がり歩み寄ってきて
「お久しぶりです」
と、いまにも崩れてしまいそうなぎこちない笑顔で出迎えた。
そして「どうぞこちらに座ってください」と彼女が座っていた椅子に案内され、彼女は小さな丸天盤の机を挟んだ反対側の椅子に座った。
部屋は六畳間ぐらいで、あるのは照明がひとつといま二人が座っている椅子と机、そして黒く塗りつぶされた窓だけ。私と居ないときはこんな場所にいたのか。ここで何をしていたのか。そしてこんなところに私を連れてきていったいどんな用があるのか。視線を部屋から彼女へ移すと、彼女は私のことをジッと見つめていた。ドキッとして視線を落とすと今度は琥珀に揺らめく私と目があった。
私たちのまえにはおそろいのティーカップがあり、そこから微かに湯気がたちのぼって、私の好きな紅茶のほのかな香りが鼻をくすぐっている。
「喉が渇いていると思って、ここに来てからなにも口にしていませんし」
そう言われて、そう言えばそうだったと思い出し、暗褐色の液体をさらに深く覗き込むと匂いが強くなったような気がした。しかし、私がそれを見つめるばかりで手をつけずにいると
「毒や薬は入れてませんから大丈夫ですよ」と彼女は言った。
「……わかってるよ、そんなこと」
言い終わってすぐにしまったと上目づかいで彼女の様子をうかがった。彼女は微笑んでいた。が、無理をしているのはあきらかだった。その脆い微笑みを私は知っている。子どものころのことで一時期似たような関係だったことがあり、その時よく目にしていた。そのころと比べると私はある程度変わったところもあるが、彼女はまったく変わっていない。物心ついたころから目の前に座っているままの姿で、調子で、声だった。だからか私は彼女のことを姉のように慕っていて、その落ち着いた雰囲気やときどき見せる年上ぶった態度、容姿や声が好きだった。しかし、それは表面的な部分にすぎず内面は何ひとつとして知らない、というよりもしかしたら知るような何かが内側にあるとすら思っていなかったのかもしれない。彼女があんなことに関わっているとわかった時、裏切られたように感じたがそれはただ単に幻想を押し付けていただけに過ぎない。
私はもういちど赤錆色の透明な鏡の中に浮かぶ私を見つめて、それからカップを手に取り口に含んだ。
「いつもの味だ、美味しいよ」気の緩むような安心感を味わいながら私が言うと
「よかったです」と彼女も安心したように言った。
「誰が淹れたの?」
「秘密です」
いたずらっぽく彼女は笑った。その答えを聞いて私はため息をついた。
「……後ろの窓だけど、あの外には何があるの?」
「私が集めてきた情報です。見てみますか?」
「……いや、大丈夫」ほんの少しだけ間をおいたあと私は断った。
すると
「わかりました」と彼女はなぜか嬉しそうに微笑んだ。
そういうやりとりを済ませ私はもう一口飲んでカップを置き「それで」と切り出した。「今日は何の用があってこんなところに呼んだの?」
「それは……」言いづらそうに口をもごもごしたあと「一つお願いがあって」と少しうつむき加減に小さな声で答えた。
「お願い?」
「はい」
私からの問いに返事をしたのと同時に、彼女は目の前から電気を消したかのようにパッといなくなり、代わりに私の視界に白い画面が現れた。驚きつつその画面を見つめていると次々と文字が打ち込まれはじめた。
「お久しぶりです」
と、いまにも崩れてしまいそうなぎこちない笑顔で出迎えた。
そして「どうぞこちらに座ってください」と彼女が座っていた椅子に案内され、彼女は小さな丸天盤の机を挟んだ反対側の椅子に座った。
部屋は六畳間ぐらいで、あるのは照明がひとつといま二人が座っている椅子と机、そして黒く塗りつぶされた窓だけ。私と居ないときはこんな場所にいたのか。ここで何をしていたのか。そしてこんなところに私を連れてきていったいどんな用があるのか。視線を部屋から彼女へ移すと、彼女は私のことをジッと見つめていた。ドキッとして視線を落とすと今度は琥珀に揺らめく私と目があった。
私たちのまえにはおそろいのティーカップがあり、そこから微かに湯気がたちのぼって、私の好きな紅茶のほのかな香りが鼻をくすぐっている。
「喉が渇いていると思って、ここに来てからなにも口にしていませんし」
そう言われて、そう言えばそうだったと思い出し、暗褐色の液体をさらに深く覗き込むと匂いが強くなったような気がした。しかし、私がそれを見つめるばかりで手をつけずにいると
「毒や薬は入れてませんから大丈夫ですよ」と彼女は言った。
「……わかってるよ、そんなこと」
言い終わってすぐにしまったと上目づかいで彼女の様子をうかがった。彼女は微笑んでいた。が、無理をしているのはあきらかだった。その脆い微笑みを私は知っている。子どものころのことで一時期似たような関係だったことがあり、その時よく目にしていた。そのころと比べると私はある程度変わったところもあるが、彼女はまったく変わっていない。物心ついたころから目の前に座っているままの姿で、調子で、声だった。だからか私は彼女のことを姉のように慕っていて、その落ち着いた雰囲気やときどき見せる年上ぶった態度、容姿や声が好きだった。しかし、それは表面的な部分にすぎず内面は何ひとつとして知らない、というよりもしかしたら知るような何かが内側にあるとすら思っていなかったのかもしれない。彼女があんなことに関わっているとわかった時、裏切られたように感じたがそれはただ単に幻想を押し付けていただけに過ぎない。
私はもういちど赤錆色の透明な鏡の中に浮かぶ私を見つめて、それからカップを手に取り口に含んだ。
「いつもの味だ、美味しいよ」気の緩むような安心感を味わいながら私が言うと
「よかったです」と彼女も安心したように言った。
「誰が淹れたの?」
「秘密です」
いたずらっぽく彼女は笑った。その答えを聞いて私はため息をついた。
「……後ろの窓だけど、あの外には何があるの?」
「私が集めてきた情報です。見てみますか?」
「……いや、大丈夫」ほんの少しだけ間をおいたあと私は断った。
すると
「わかりました」と彼女はなぜか嬉しそうに微笑んだ。
そういうやりとりを済ませ私はもう一口飲んでカップを置き「それで」と切り出した。「今日は何の用があってこんなところに呼んだの?」
「それは……」言いづらそうに口をもごもごしたあと「一つお願いがあって」と少しうつむき加減に小さな声で答えた。
「お願い?」
「はい」
私からの問いに返事をしたのと同時に、彼女は目の前から電気を消したかのようにパッといなくなり、代わりに私の視界に白い画面が現れた。驚きつつその画面を見つめていると次々と文字が打ち込まれはじめた。