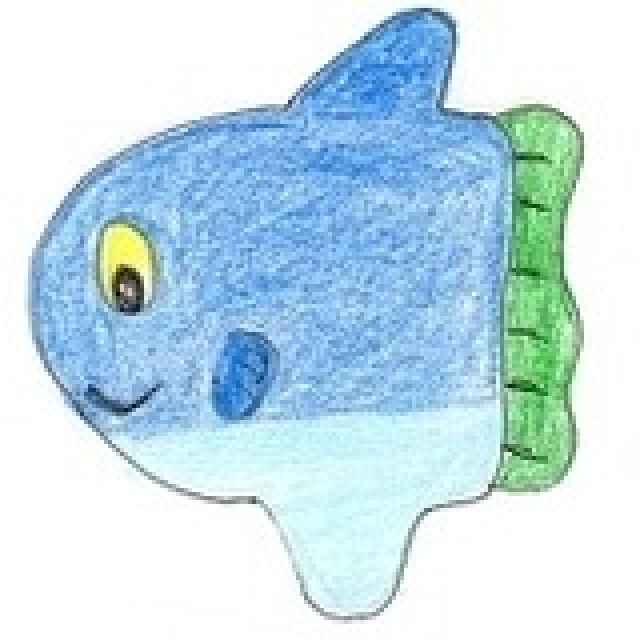天丼
文字数 2,672文字
玄関に置かれた、下駄箱の上にある小さな窓から夏の日差しが差し込んでいた。もうすぐ梅雨が明けると感じた。師匠の三回忌ももうすぐだった。
「それじゃ、この次は両親を連れて来なさい。二人揃っていなくても良いから」
「はい、必ず連れて来ます。また、ご連絡しても良いですか?」
「ああ、構わないよ。留守なら録音に入れておいてくれれば良いから」
「はい! 判りました。ありがとうございました! では失礼します」
高校を卒業したばかりの歳頃の青年はそう言って頭を下げて出て行った。玄関の引き戸を閉めても磨り硝子越しに扉の向こうでも頭を下げているのが判った。思えば自分の時もそうだった。
暫く前から自分が寄席の出番を終えて楽屋から出て来ると、密かに見つめている青年が居た。体中から発散してくるオーラからこの青年が自分に弟子入りを希望するのでは無いかと感じてはいたが、だからといってこちらから声を掛ける訳には行かない。
暫くそのままにしていたが、およそ三ヶ月も経った頃だろうか、上野の鈴本演芸場から中央通に出て来た所に声を掛けられた。
「あのう、柳星師匠! 弟子にして戴きたいのですが……」
最初は声が大きかったが、声の途中で私がそちらに気がついて向いたので、驚いたのだろう。次第に小さくなった。
「弟子に入りたいのかい?」
「はい、噺家になりたいのです。それも師匠の弟子に!」
情熱のある目をしていた。端は皆こうだ。だが、それが辛い修行期間中でも続くとは限らない。
「やめておきなさい。食えるまでは時間がかかるし、売れないと本当に貧乏だよ。サラリーマンの方が遥かに良いと思うがね」
無論、こんな事を言っても聞く耳なんか持ってはいないのは判っている。それは、自分も同じだったからだ。何回も断られて、それでも頼み続けて、やっと認められた。今から考えると、師匠は自分の覚悟を試していたのかも知れないと思った。だから、ちゃんと話を聞いてくれた時は本当に嬉しかったものだ。
「それでもなりたのです!」
「駄目だよ。やめておきなさい」
そう言って地下鉄の階段を降りて行った。本当にその気があるなら、これで諦められたら本物ではない。階段を降りながらも、後ろから何時迄も見つめられている気がした。
それから幾度と無く、彼は私の前に立ちはだかった。浅草や新宿、それに池袋の寄席にも出現した。どうやら本気らしいと思った。そこで家に来るように言ったのだ。
彼の気配が消えて、私は自分の時の事を思い出した。もうすぐ師匠の三回忌が来るが、その前に師匠の墓参りに行きたくなった。早速支度をして出かける。墓参りの帰りに浅草の寄席に寄るつもりだった。昼席の遅い出番なので時間はたっぷりとあった。
師匠の墓に花と線香を供えて手を合わせる。
「師匠、どうやら弟子が出来そうです。私に人を教える事が出来ますでしょうか? 前途ある青年を預かるなんて出来るでしょうか?」
これが偽りの無い自分の心だった。手を合わせた向こうから
『弟子を育てることで更に学ぶ事も沢山あるんだよ』
そう言ってくれた気がした。覚悟が決まった気がした。
自分の時も何回も断られて、それでも諦めきれなかった。十回以上頼んだ頃だろうか
「そんなになりたいなら、親を連れて来なさい。親を説得して諦めて貰うから」
そう言ってくれた。師匠は江戸っ子だから口が悪い。それを差し引いても心の底から有り難いと思った。
日にちを選んで母親に一緒に師匠の家まで付いて来て貰った。私には父親は居ない。私が幼い頃に亡くなっていた。
師匠の家は下町にあった。如何にも噺家の家と呼びたい造りで、玄関にはのれんが掛かっていて、植え込みには藤棚があった。その粋さに母が感心していた。
玄関の呼び鈴を押すと、女将さんが出てくれた。この人も元は玄人だったと判る感じだった。
「どうぞ。師匠はおりますから」
そう言ってスリッパを出してくれた。恐縮しながら、あがらせて貰う。師匠は奥の縁側の見える部屋に座っていた。噺家らしく普段着も着物姿だった。昭和の大師匠方は日常でも着物を着ている人がかなり居た。師匠もその一人だった。
師匠は母に、噺家が如何に苦労の多い職業なのか、真打になるまで早くても十年以上掛かる事。それに売れないと本当にお金に苦労すること。修行時代はアルバイト禁止な事や、禁酒禁煙な事。自分の自由になる時間が殆ど無い事などを話して噺家になるのを諦めるように言ってくれた。
「でも、どうしても噺家になりたいって言って利かないんです」
「そうですか……ならそれだけの覚悟があるんですね」
師匠の言葉は諦めにも聞こえた。
「はい、どうしてもなりたいのです」
そう言って頭を畳に擦り付けた。母も一緒に頭を下げてくれた。
「なら仕方ないですな。明日から通いなさい」
その瞬間、目の前が開けた気がした。師匠は女将さんを呼んで、天丼の出前を取るように言った。
暫くは寄席のしきたりなどを話してくれていたが、頼んだ天丼が来ると女将さんが出してくれた。蓋から大きめの海老の尻尾が三本覗いていた。
「ま、時分ですから食べましょう。それと、これだけは言っておきます。明日からは俺の弟子になる。だから、これからは自分の手銭で食べる時以外は天丼なんて高いものを頼んでは駄目だよ。お前さんは修行の身なのだから、一番安いものを頼むんだよ。ラーメン屋だったらラーメン。蕎麦屋だったら、かけかさるだ。それだけは覚えておきなさい。他の師匠からも気に入られるようになりなさい。明日からはカタギではなくなるのだから、覚えておきなさい。その意味で、今日は最後の食事だ。だから今日は天丼を取りました。出世しなさい! そして、自分の稼ぎでお母さんにも天丼を食べさせてあげる噺家になりなさい。お母さんそう言う訳です。さ、食べましょう」
師匠の言う事は痛いほど判った。学校に入るのでは無い。明日から噺家の最下層で修行をするのだ。それを天丼と言ったものを通して教えてくれた師匠に感謝の念しか湧かなかった。食べながらも想いがこみ上げて喉を通らなかった。横を見ると母も同じようにしていた。目に涙が滲んでいたのは天丼が喉に詰まって苦しいだからでは無いと思う。
あれから随分経った。師匠も今は居ない。でもその心と想いは私の中に伝わっている。彼が親を連れて来たら。私も天丼を注文することにしている。
<了>
「それじゃ、この次は両親を連れて来なさい。二人揃っていなくても良いから」
「はい、必ず連れて来ます。また、ご連絡しても良いですか?」
「ああ、構わないよ。留守なら録音に入れておいてくれれば良いから」
「はい! 判りました。ありがとうございました! では失礼します」
高校を卒業したばかりの歳頃の青年はそう言って頭を下げて出て行った。玄関の引き戸を閉めても磨り硝子越しに扉の向こうでも頭を下げているのが判った。思えば自分の時もそうだった。
暫く前から自分が寄席の出番を終えて楽屋から出て来ると、密かに見つめている青年が居た。体中から発散してくるオーラからこの青年が自分に弟子入りを希望するのでは無いかと感じてはいたが、だからといってこちらから声を掛ける訳には行かない。
暫くそのままにしていたが、およそ三ヶ月も経った頃だろうか、上野の鈴本演芸場から中央通に出て来た所に声を掛けられた。
「あのう、柳星師匠! 弟子にして戴きたいのですが……」
最初は声が大きかったが、声の途中で私がそちらに気がついて向いたので、驚いたのだろう。次第に小さくなった。
「弟子に入りたいのかい?」
「はい、噺家になりたいのです。それも師匠の弟子に!」
情熱のある目をしていた。端は皆こうだ。だが、それが辛い修行期間中でも続くとは限らない。
「やめておきなさい。食えるまでは時間がかかるし、売れないと本当に貧乏だよ。サラリーマンの方が遥かに良いと思うがね」
無論、こんな事を言っても聞く耳なんか持ってはいないのは判っている。それは、自分も同じだったからだ。何回も断られて、それでも頼み続けて、やっと認められた。今から考えると、師匠は自分の覚悟を試していたのかも知れないと思った。だから、ちゃんと話を聞いてくれた時は本当に嬉しかったものだ。
「それでもなりたのです!」
「駄目だよ。やめておきなさい」
そう言って地下鉄の階段を降りて行った。本当にその気があるなら、これで諦められたら本物ではない。階段を降りながらも、後ろから何時迄も見つめられている気がした。
それから幾度と無く、彼は私の前に立ちはだかった。浅草や新宿、それに池袋の寄席にも出現した。どうやら本気らしいと思った。そこで家に来るように言ったのだ。
彼の気配が消えて、私は自分の時の事を思い出した。もうすぐ師匠の三回忌が来るが、その前に師匠の墓参りに行きたくなった。早速支度をして出かける。墓参りの帰りに浅草の寄席に寄るつもりだった。昼席の遅い出番なので時間はたっぷりとあった。
師匠の墓に花と線香を供えて手を合わせる。
「師匠、どうやら弟子が出来そうです。私に人を教える事が出来ますでしょうか? 前途ある青年を預かるなんて出来るでしょうか?」
これが偽りの無い自分の心だった。手を合わせた向こうから
『弟子を育てることで更に学ぶ事も沢山あるんだよ』
そう言ってくれた気がした。覚悟が決まった気がした。
自分の時も何回も断られて、それでも諦めきれなかった。十回以上頼んだ頃だろうか
「そんなになりたいなら、親を連れて来なさい。親を説得して諦めて貰うから」
そう言ってくれた。師匠は江戸っ子だから口が悪い。それを差し引いても心の底から有り難いと思った。
日にちを選んで母親に一緒に師匠の家まで付いて来て貰った。私には父親は居ない。私が幼い頃に亡くなっていた。
師匠の家は下町にあった。如何にも噺家の家と呼びたい造りで、玄関にはのれんが掛かっていて、植え込みには藤棚があった。その粋さに母が感心していた。
玄関の呼び鈴を押すと、女将さんが出てくれた。この人も元は玄人だったと判る感じだった。
「どうぞ。師匠はおりますから」
そう言ってスリッパを出してくれた。恐縮しながら、あがらせて貰う。師匠は奥の縁側の見える部屋に座っていた。噺家らしく普段着も着物姿だった。昭和の大師匠方は日常でも着物を着ている人がかなり居た。師匠もその一人だった。
師匠は母に、噺家が如何に苦労の多い職業なのか、真打になるまで早くても十年以上掛かる事。それに売れないと本当にお金に苦労すること。修行時代はアルバイト禁止な事や、禁酒禁煙な事。自分の自由になる時間が殆ど無い事などを話して噺家になるのを諦めるように言ってくれた。
「でも、どうしても噺家になりたいって言って利かないんです」
「そうですか……ならそれだけの覚悟があるんですね」
師匠の言葉は諦めにも聞こえた。
「はい、どうしてもなりたいのです」
そう言って頭を畳に擦り付けた。母も一緒に頭を下げてくれた。
「なら仕方ないですな。明日から通いなさい」
その瞬間、目の前が開けた気がした。師匠は女将さんを呼んで、天丼の出前を取るように言った。
暫くは寄席のしきたりなどを話してくれていたが、頼んだ天丼が来ると女将さんが出してくれた。蓋から大きめの海老の尻尾が三本覗いていた。
「ま、時分ですから食べましょう。それと、これだけは言っておきます。明日からは俺の弟子になる。だから、これからは自分の手銭で食べる時以外は天丼なんて高いものを頼んでは駄目だよ。お前さんは修行の身なのだから、一番安いものを頼むんだよ。ラーメン屋だったらラーメン。蕎麦屋だったら、かけかさるだ。それだけは覚えておきなさい。他の師匠からも気に入られるようになりなさい。明日からはカタギではなくなるのだから、覚えておきなさい。その意味で、今日は最後の食事だ。だから今日は天丼を取りました。出世しなさい! そして、自分の稼ぎでお母さんにも天丼を食べさせてあげる噺家になりなさい。お母さんそう言う訳です。さ、食べましょう」
師匠の言う事は痛いほど判った。学校に入るのでは無い。明日から噺家の最下層で修行をするのだ。それを天丼と言ったものを通して教えてくれた師匠に感謝の念しか湧かなかった。食べながらも想いがこみ上げて喉を通らなかった。横を見ると母も同じようにしていた。目に涙が滲んでいたのは天丼が喉に詰まって苦しいだからでは無いと思う。
あれから随分経った。師匠も今は居ない。でもその心と想いは私の中に伝わっている。彼が親を連れて来たら。私も天丼を注文することにしている。
<了>