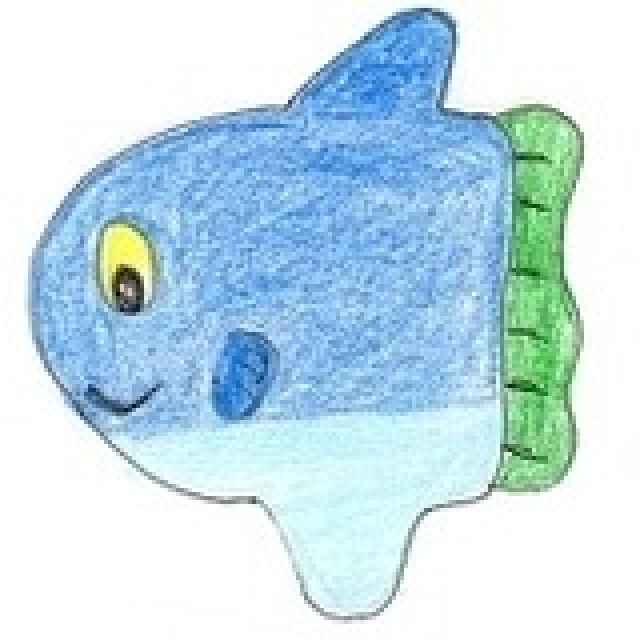第1話 時そば
文字数 5,229文字
都内の静かな住宅地。その一角に家はあった。
「師匠寄席に行く時間です」
弟子の柳星(りゅうせい)の声で柳生(りゅうしょう)は我に返った。今日高座にかける噺をサラッていたのだ。
「もうそんな時間か」
砂壁の日本間には似合わない、柱に掛かった大きめの電波時計を見て時間を確かめた。
「支度はもう出来ています」
朝、柳星が来た時に今日の高座で着る着物の事は伝えてあった。半分障子が開けられた部屋の縁側からは青木の葉が午後の陽を受けて青々とした葉を見せていた。もうすぐ実が赤く熟し、この家の者の目を楽しませてくれるはずだった。
青木の傍のには小さな池があり鯉が一匹泳いている。かなり前に近所の小学生が川で釣ったのだが自分の家では飼えないので、この池に放流させて欲しいと頼み込んで来たのだ。
素よりこの家に越して来た時から何も泳がせていなかった。水は張ったもののボウフラが湧いてるだけだった。
「構わないよ」
「ありがとうございます」
数人の小学生はそう言って持って来た鯉を池に放流した。時々様子を見に来て餌などもやっていたが、いつの間にか誰も来なくなった。その後は自分や弟子が餌をやっている。きちんと測った訳ではないが、二十センチ程だった鯉も今や五十センチはあるのではないか。それでも飼い主が判るのか柳生が池の淵に立って餌の袋をまさぐると、寄って来る。
「餌やっておいてくれな」
弟子で見習いの柳星にそう言いつけて、着物が入った鞄を持って家を出た。
「行ってらっしゃいませ」
その声を背に受けて歩き出す。柳星は入門して未だ一年未満の「見習い」だ。噺家の世界の仕来りや色々なことを覚えている最中なのだ。それが済むと、寄席に「前座」として入ることになる。そうなると自分の時間はほとんど持てなくなる。これを二~三年我慢すると晴れて二つ目となり噺家として出発点に立つ事が出来る。「真打」になるのにはそれから十数年経たねばならない。
柳生は十三年前に二十数名の先輩を抜いて真打に抜擢昇進したのだった。若い頃から抜群の上手さを見せて、それが評価されたのだった。
今、住んでいる家は支援者の紹介で十年ほど前に買ったものだった。独り身には広すぎるとは思ったが、支援者も
「いずれ女将さんを持ったり、弟子も入るだろうから、これぐらいの家には住んでいないとね」
そんな事を言っていたが、柳生としては別にアパートだろうがマンションだろうが一向に構わなかった。只、今までは結婚とは縁が無かった。言い寄って来る女性は次から次に来るが、どうしても、その気になれなかったのだ。だから柳生の事を「女に興味がない」などと陰口を唱える者も居る。柳生はそんな噂があるのは知っていたが気にして居なかった。
本来なら鞄持ちで柳星を連れて行くのだが、今日は寄席のトリだった。トリと言うのは寄席で最後に出る者のことを言う。その昔、寄席に電気が通じていなかった頃には高座に百目蝋燭が左右に立てられており、最後の出演者はその蝋燭の芯を鋏で切って明るさを調整したのだと言う。そんな所作から「真打」という言葉が出来、それが噺家の階級になったのだと言う。寄席に柳星を連れて行くのはもう少し慣れた頃が良いと考えていた。
今月の十一日から上野の鈴本演芸場の昼席のトリを受け持っている。柳生の人気は抜群で、本来なら寄席は前売りはしないのだが、彼がトリの時だけは前売りをするのだ。それは以前の事だが席の券を求めるお客が歩道に列を作り、周りの商店に迷惑を掛けてしまったからだ。それ以来前売りをしている。勿論、当日券も用意されているので窓口に並んでいたお客はいるのだが以前ほどではない。
地下鉄の階段を上がると目の前が寄席だ。入り口に近づくと前座が直ぐに寄って来て鞄を持ってくれた
「お早うございます。お疲れさまです」
「ああ、頼むよ」
前座に鞄を手渡すとそのまま上の楽屋に向かった。
「お早うございます! お疲れ様です!」
楽屋に入ると次から次に声が掛かる。それを一々返事を返して何時も自分が座ってる場所に陣取った。
楽屋ではその芝居に出る芸人や噺家によって順位が決められていて、自然と座る席が決まってるのだ。この鈴本の場合でも座卓に対して正面に座るか横に座るかで変わって来る。現に、今、柳生が座った場所には先程までは後輩の芸人が座っていた。後輩芸人は柳生が来たので場を空けたのだ。楽屋にはそんなヒエラルキーがある。
座ると直ぐに前座がお茶を持って来た。
「ありがとう」
そう言ってからその前座に
「今日は何人だい?」
そう尋ねると前座は
「今日は五人です」
そう答えた。すると柳生は着物の入った鞄とは別の小さな鞄からポチ袋を五つ取り出した。それを前座に渡す。
「ありがとうございます。柳生師匠から戴きました!」
その声に、前座が次々と柳生の前にお礼に現れる。中身は少ないがこれが彼らの大事な収入のひとつになるのだ。
その儀式が終わると柳生は前座に根多帳を持って来させる。これには今日を初め、この寄席でどんな噺を誰が演じたのかが書かれている。出演する噺家はこれを見て、その日に演じる演目を考えるのだ。
「今日は『時そば』出てないね」
前座に問いただすと彼は
「はい、今日は圓歳師匠が休席ですから演じる師匠はいないと思います」
圓歳とは三遊亭圓歳と言って柳生よりも香盤が上の噺家だが、この「時そば」が得意で寄席でも良く演じている。柳生は彼が休席と知っていて前座に確かめたのだ。
この日、柳生は「時そば」をかけるつもりだった。というのも先日贔屓の客から言われたのだった。
「先代の柳家小さん師匠は、蕎麦とうどんの食べ分けが出来たって言うけど本当だったのかい?」
今では伝説になりつつある話だが確かに五代目柳家小さんは蕎麦とうどんの食べ分けが出来た数少ない噺家だった。
「出来ましたよ。わたしも出来ますけどね」
そう言ってその場ではうどんの食べる仕草を見せたのだ。
「今度鈴本で昼トリがありますから『時そば』でもやりますよ。その時に違いを見に来て下さいよ」
そう言うと贔屓の客も
「それは是非見に行かせて貰うよ十日間通うからね」
そう言って喜んだのだった。だから、圓歳が休みの今日は打って付けだった。贔屓の客は今日も来てるはずだった。
柳生が楽屋入りしたのは出番の一時間前だった。寄席ではそれぞれが自分の出番に合わせて楽屋入りする。そこが芝居等とは違う。ちなみに落語の興業のことを「芝居」と呼ぶ。
トリの前に出る出番を「膝」と呼ぶ。ちなみに、その前は「膝前」と呼ぶ。柳生がトリの時の膝は大神楽だった。大神楽とは簡単に言うと、曲芸だ。本来は祭りなどで神に捧げる芸能だった。幾つかの流派があるが、今では国立演芸場で養成している。
高座では大神楽の芸人が顎の上に幾つもの茶碗や棒などを立ててお客をハラハラさせていた。全くトリック無しでやっているので見慣れていててもハラハラしてしまう。
大きな拍手で膝の出番が終わったことが判った。
続いて「小鍛冶」という出囃子が鳴り出す。これは柳生の専属の出囃子なのだ。噺家は通常、二つ目になると自分専用の出囃子を使う事が認められる。自分の好きな曲を使う者もいるが。殆どは下座の三味線のお師匠さんから
「あなたにはこれが似合ってる」
などと勧められて決める。柳生が所属してる「噺家協会」には居ないが、もう一つの大きな協会である「噺家芸術協会」には洋楽を使ってる師匠も居る。
柳生は自分のリズムで高座に出て行く。今日の着物は濃い緑の着物にこげ茶の羽織だ。これは今日の演目に合わせて家から持って来たのだった。鞄の中身である。
高座に用意された座布団に座ってお辞儀をする
「え~わたしがトリとなっております。わたしの高座が終われば、皆さんは開放されます。もう少しの辛抱です」
そう言って客席を笑わせた。そして噺に入って行く。
「今は屋台なんて言うとラーメン屋ぐらいですか。その昔は蕎麦屋が大層流行ったそうです。江戸の頃で一杯が十六文。時代によって若干違いますが、今で言うと三百二十円ぐらいですかねえ。今の感覚で言うと少し高いですかねえ」
柳生は江戸の頃の物価の噺を織り込んで噺を進めて行く。今の物価と比較することで客は噺の中に取り込まれて行くのが判った。こうなれば噺家の手の内に入ったも同然なので噺を進め易くなった。
この噺の筋を簡単に書いておくと、
江戸の夜、往来を流して歩く蕎麦屋にひとりの客がやって来る。男は「しっぽく」を頼むと「景気はどうだい?商売は商いというくらいだ、飽きずにやんなくちゃいけねえぜ」と亭主に話しかける。亭主が相手をすると客はつづけて屋号や蕎麦の味、ダシのとりかた、竹輪の切り方、箸、器までを褒めちぎり蕎麦一杯を食べる。蕎麦の値段は一杯十六文。客は一文銭十六枚で勘定を支払うと言うと小銭を取り出し、「……五つ、六う、七つ、八つ、蕎麦屋さん、いま何時だい」「へい九つです」「十、十一、十二……」。
男は勘定の途中で時刻を訪ね、一文ごまかすことに成功する。
その様子を脇で見ていた間抜けな男がこのからくりに気がつき、翌晩、自分も真似をしようと思う。翌日、昨日より早く出てしまった間抜けな男は、通りがかった蕎麦屋をやっとの思いで呼び止め、昨日の男と同じ事をやろうとするが、尽く反対になってしまう。おまけに蕎麦も、とてもじゃないが食べられたモノではない。早々に勘定にして貰います。
「ひい、ふう、みい、……今何時でい」とやると、「へい、四つで」と答える。「ん~五つ、六う……」
昨日より時間が早かったというオチなのだが、事前に今の時間と当時の時間の数え方を仕込んでおかないとならず、手間が掛かる噺なのだ。今日は贔屓の客に蕎麦とうどんの食べ方の違いを見せねばならない。最も違うのが麺の太さだ。それに弾力のあるうどんと細く折れそうな感じの蕎麦ではすする音さえ違わなければならない。
柳生は、最初の男のシーンで蕎麦特有の軽いすすり方を演じて見せた。
「ふう、ふうー」
とどんぶりを持って息を掛けて冷ます仕草も決まって、客席からはツバを飲み込む音が聞こえた。うどんなら「ずるずる」だが蕎麦なのでもっと軽い音を出す。するすると蕎麦が口の中に消えて行く様がハッキリと感じられた。その次に「ズルッ、ズルッ」と汁を啜る音を出して完全に客の視線を集めていた。
「兄さんは本当に蕎麦を食べてる様に見えるからなぁ。俺たちから見てもここまで出来る人はいないな」
高座の袖では「膝前」の出番だった古琴亭小駒が感心していた。ここの見事さが後半に繋がって行くのだ。前半の蕎麦が旨く見えれば見えるほど後半の蕎麦の不味さが際立つのだ。
やがてサゲを言って柳生が高座を降りて来た。
「お疲れ様でした」
前座や他の芸人が口々にねぎらいの言葉を掛ける。すると楽屋に贔屓の客がやって来た。
「いやぁ~見事だったよ。確かに蕎麦とうどんの違いがハッキリと判ったよ。お見事だった」
そう言って感心すると柳生は
「そうでしたか。それは良かったです」
そう返事をして着替えていると贔屓の客が
「ところで今日はこの後も仕事があるのかい?」
そんな事を尋ねる
「いいえ。今日はここだけです。トリの時は余り他の仕事を入れないんです」
そう返事をすると客はニッコリと笑って
「じゃあこの後少し呑まないかい? 是非、紹介したい店があるんだ。旨いものを食わせる店なんだ」
この客とは付き合いが長いが誘われたのは初めてだった。
「珍しいですね」
そんな軽口を言うと客は
「今日は良いものを見せて貰ったからさ」
結局、付き合うことになったので、家に連絡を入れて柳星に帰っても良いと連絡を入れた。
客は鈴本の前でタクシーを拾うと東京の下町の名前を言った。運転手は
「了解しました」
そう言って車が走り出した。
「俺もね、最近通いだしたのだけど、実に旨いものを食わせるんだよ。師匠はさ、あれだけ食べる仕草が見事なんだから実際に食べる事にも煩いんじゃ無いかと思ってね」
確かに食べる事には人一倍興味があった。旨いものがあると聞くと取り寄せて食べてみた事も一度や二度ではなかった。
やがてタクシーは一軒の小料理店の前で停まった。
「ここなんだよ」
タクシーから降りた客が紹介したのは一見、平凡な小料理屋に見えた。
「ここがですか?」
「まあまあ、百聞は一見にしかずだ。入った入った」
客に言われて入り口の扉を開けて暖簾を潜った。
「いらっしゃいませ~」
陽気な女性の声が耳に届いた。この時、柳生はこれから起きる事を全く予想していなかった。
「師匠寄席に行く時間です」
弟子の柳星(りゅうせい)の声で柳生(りゅうしょう)は我に返った。今日高座にかける噺をサラッていたのだ。
「もうそんな時間か」
砂壁の日本間には似合わない、柱に掛かった大きめの電波時計を見て時間を確かめた。
「支度はもう出来ています」
朝、柳星が来た時に今日の高座で着る着物の事は伝えてあった。半分障子が開けられた部屋の縁側からは青木の葉が午後の陽を受けて青々とした葉を見せていた。もうすぐ実が赤く熟し、この家の者の目を楽しませてくれるはずだった。
青木の傍のには小さな池があり鯉が一匹泳いている。かなり前に近所の小学生が川で釣ったのだが自分の家では飼えないので、この池に放流させて欲しいと頼み込んで来たのだ。
素よりこの家に越して来た時から何も泳がせていなかった。水は張ったもののボウフラが湧いてるだけだった。
「構わないよ」
「ありがとうございます」
数人の小学生はそう言って持って来た鯉を池に放流した。時々様子を見に来て餌などもやっていたが、いつの間にか誰も来なくなった。その後は自分や弟子が餌をやっている。きちんと測った訳ではないが、二十センチ程だった鯉も今や五十センチはあるのではないか。それでも飼い主が判るのか柳生が池の淵に立って餌の袋をまさぐると、寄って来る。
「餌やっておいてくれな」
弟子で見習いの柳星にそう言いつけて、着物が入った鞄を持って家を出た。
「行ってらっしゃいませ」
その声を背に受けて歩き出す。柳星は入門して未だ一年未満の「見習い」だ。噺家の世界の仕来りや色々なことを覚えている最中なのだ。それが済むと、寄席に「前座」として入ることになる。そうなると自分の時間はほとんど持てなくなる。これを二~三年我慢すると晴れて二つ目となり噺家として出発点に立つ事が出来る。「真打」になるのにはそれから十数年経たねばならない。
柳生は十三年前に二十数名の先輩を抜いて真打に抜擢昇進したのだった。若い頃から抜群の上手さを見せて、それが評価されたのだった。
今、住んでいる家は支援者の紹介で十年ほど前に買ったものだった。独り身には広すぎるとは思ったが、支援者も
「いずれ女将さんを持ったり、弟子も入るだろうから、これぐらいの家には住んでいないとね」
そんな事を言っていたが、柳生としては別にアパートだろうがマンションだろうが一向に構わなかった。只、今までは結婚とは縁が無かった。言い寄って来る女性は次から次に来るが、どうしても、その気になれなかったのだ。だから柳生の事を「女に興味がない」などと陰口を唱える者も居る。柳生はそんな噂があるのは知っていたが気にして居なかった。
本来なら鞄持ちで柳星を連れて行くのだが、今日は寄席のトリだった。トリと言うのは寄席で最後に出る者のことを言う。その昔、寄席に電気が通じていなかった頃には高座に百目蝋燭が左右に立てられており、最後の出演者はその蝋燭の芯を鋏で切って明るさを調整したのだと言う。そんな所作から「真打」という言葉が出来、それが噺家の階級になったのだと言う。寄席に柳星を連れて行くのはもう少し慣れた頃が良いと考えていた。
今月の十一日から上野の鈴本演芸場の昼席のトリを受け持っている。柳生の人気は抜群で、本来なら寄席は前売りはしないのだが、彼がトリの時だけは前売りをするのだ。それは以前の事だが席の券を求めるお客が歩道に列を作り、周りの商店に迷惑を掛けてしまったからだ。それ以来前売りをしている。勿論、当日券も用意されているので窓口に並んでいたお客はいるのだが以前ほどではない。
地下鉄の階段を上がると目の前が寄席だ。入り口に近づくと前座が直ぐに寄って来て鞄を持ってくれた
「お早うございます。お疲れさまです」
「ああ、頼むよ」
前座に鞄を手渡すとそのまま上の楽屋に向かった。
「お早うございます! お疲れ様です!」
楽屋に入ると次から次に声が掛かる。それを一々返事を返して何時も自分が座ってる場所に陣取った。
楽屋ではその芝居に出る芸人や噺家によって順位が決められていて、自然と座る席が決まってるのだ。この鈴本の場合でも座卓に対して正面に座るか横に座るかで変わって来る。現に、今、柳生が座った場所には先程までは後輩の芸人が座っていた。後輩芸人は柳生が来たので場を空けたのだ。楽屋にはそんなヒエラルキーがある。
座ると直ぐに前座がお茶を持って来た。
「ありがとう」
そう言ってからその前座に
「今日は何人だい?」
そう尋ねると前座は
「今日は五人です」
そう答えた。すると柳生は着物の入った鞄とは別の小さな鞄からポチ袋を五つ取り出した。それを前座に渡す。
「ありがとうございます。柳生師匠から戴きました!」
その声に、前座が次々と柳生の前にお礼に現れる。中身は少ないがこれが彼らの大事な収入のひとつになるのだ。
その儀式が終わると柳生は前座に根多帳を持って来させる。これには今日を初め、この寄席でどんな噺を誰が演じたのかが書かれている。出演する噺家はこれを見て、その日に演じる演目を考えるのだ。
「今日は『時そば』出てないね」
前座に問いただすと彼は
「はい、今日は圓歳師匠が休席ですから演じる師匠はいないと思います」
圓歳とは三遊亭圓歳と言って柳生よりも香盤が上の噺家だが、この「時そば」が得意で寄席でも良く演じている。柳生は彼が休席と知っていて前座に確かめたのだ。
この日、柳生は「時そば」をかけるつもりだった。というのも先日贔屓の客から言われたのだった。
「先代の柳家小さん師匠は、蕎麦とうどんの食べ分けが出来たって言うけど本当だったのかい?」
今では伝説になりつつある話だが確かに五代目柳家小さんは蕎麦とうどんの食べ分けが出来た数少ない噺家だった。
「出来ましたよ。わたしも出来ますけどね」
そう言ってその場ではうどんの食べる仕草を見せたのだ。
「今度鈴本で昼トリがありますから『時そば』でもやりますよ。その時に違いを見に来て下さいよ」
そう言うと贔屓の客も
「それは是非見に行かせて貰うよ十日間通うからね」
そう言って喜んだのだった。だから、圓歳が休みの今日は打って付けだった。贔屓の客は今日も来てるはずだった。
柳生が楽屋入りしたのは出番の一時間前だった。寄席ではそれぞれが自分の出番に合わせて楽屋入りする。そこが芝居等とは違う。ちなみに落語の興業のことを「芝居」と呼ぶ。
トリの前に出る出番を「膝」と呼ぶ。ちなみに、その前は「膝前」と呼ぶ。柳生がトリの時の膝は大神楽だった。大神楽とは簡単に言うと、曲芸だ。本来は祭りなどで神に捧げる芸能だった。幾つかの流派があるが、今では国立演芸場で養成している。
高座では大神楽の芸人が顎の上に幾つもの茶碗や棒などを立ててお客をハラハラさせていた。全くトリック無しでやっているので見慣れていててもハラハラしてしまう。
大きな拍手で膝の出番が終わったことが判った。
続いて「小鍛冶」という出囃子が鳴り出す。これは柳生の専属の出囃子なのだ。噺家は通常、二つ目になると自分専用の出囃子を使う事が認められる。自分の好きな曲を使う者もいるが。殆どは下座の三味線のお師匠さんから
「あなたにはこれが似合ってる」
などと勧められて決める。柳生が所属してる「噺家協会」には居ないが、もう一つの大きな協会である「噺家芸術協会」には洋楽を使ってる師匠も居る。
柳生は自分のリズムで高座に出て行く。今日の着物は濃い緑の着物にこげ茶の羽織だ。これは今日の演目に合わせて家から持って来たのだった。鞄の中身である。
高座に用意された座布団に座ってお辞儀をする
「え~わたしがトリとなっております。わたしの高座が終われば、皆さんは開放されます。もう少しの辛抱です」
そう言って客席を笑わせた。そして噺に入って行く。
「今は屋台なんて言うとラーメン屋ぐらいですか。その昔は蕎麦屋が大層流行ったそうです。江戸の頃で一杯が十六文。時代によって若干違いますが、今で言うと三百二十円ぐらいですかねえ。今の感覚で言うと少し高いですかねえ」
柳生は江戸の頃の物価の噺を織り込んで噺を進めて行く。今の物価と比較することで客は噺の中に取り込まれて行くのが判った。こうなれば噺家の手の内に入ったも同然なので噺を進め易くなった。
この噺の筋を簡単に書いておくと、
江戸の夜、往来を流して歩く蕎麦屋にひとりの客がやって来る。男は「しっぽく」を頼むと「景気はどうだい?商売は商いというくらいだ、飽きずにやんなくちゃいけねえぜ」と亭主に話しかける。亭主が相手をすると客はつづけて屋号や蕎麦の味、ダシのとりかた、竹輪の切り方、箸、器までを褒めちぎり蕎麦一杯を食べる。蕎麦の値段は一杯十六文。客は一文銭十六枚で勘定を支払うと言うと小銭を取り出し、「……五つ、六う、七つ、八つ、蕎麦屋さん、いま何時だい」「へい九つです」「十、十一、十二……」。
男は勘定の途中で時刻を訪ね、一文ごまかすことに成功する。
その様子を脇で見ていた間抜けな男がこのからくりに気がつき、翌晩、自分も真似をしようと思う。翌日、昨日より早く出てしまった間抜けな男は、通りがかった蕎麦屋をやっとの思いで呼び止め、昨日の男と同じ事をやろうとするが、尽く反対になってしまう。おまけに蕎麦も、とてもじゃないが食べられたモノではない。早々に勘定にして貰います。
「ひい、ふう、みい、……今何時でい」とやると、「へい、四つで」と答える。「ん~五つ、六う……」
昨日より時間が早かったというオチなのだが、事前に今の時間と当時の時間の数え方を仕込んでおかないとならず、手間が掛かる噺なのだ。今日は贔屓の客に蕎麦とうどんの食べ方の違いを見せねばならない。最も違うのが麺の太さだ。それに弾力のあるうどんと細く折れそうな感じの蕎麦ではすする音さえ違わなければならない。
柳生は、最初の男のシーンで蕎麦特有の軽いすすり方を演じて見せた。
「ふう、ふうー」
とどんぶりを持って息を掛けて冷ます仕草も決まって、客席からはツバを飲み込む音が聞こえた。うどんなら「ずるずる」だが蕎麦なのでもっと軽い音を出す。するすると蕎麦が口の中に消えて行く様がハッキリと感じられた。その次に「ズルッ、ズルッ」と汁を啜る音を出して完全に客の視線を集めていた。
「兄さんは本当に蕎麦を食べてる様に見えるからなぁ。俺たちから見てもここまで出来る人はいないな」
高座の袖では「膝前」の出番だった古琴亭小駒が感心していた。ここの見事さが後半に繋がって行くのだ。前半の蕎麦が旨く見えれば見えるほど後半の蕎麦の不味さが際立つのだ。
やがてサゲを言って柳生が高座を降りて来た。
「お疲れ様でした」
前座や他の芸人が口々にねぎらいの言葉を掛ける。すると楽屋に贔屓の客がやって来た。
「いやぁ~見事だったよ。確かに蕎麦とうどんの違いがハッキリと判ったよ。お見事だった」
そう言って感心すると柳生は
「そうでしたか。それは良かったです」
そう返事をして着替えていると贔屓の客が
「ところで今日はこの後も仕事があるのかい?」
そんな事を尋ねる
「いいえ。今日はここだけです。トリの時は余り他の仕事を入れないんです」
そう返事をすると客はニッコリと笑って
「じゃあこの後少し呑まないかい? 是非、紹介したい店があるんだ。旨いものを食わせる店なんだ」
この客とは付き合いが長いが誘われたのは初めてだった。
「珍しいですね」
そんな軽口を言うと客は
「今日は良いものを見せて貰ったからさ」
結局、付き合うことになったので、家に連絡を入れて柳星に帰っても良いと連絡を入れた。
客は鈴本の前でタクシーを拾うと東京の下町の名前を言った。運転手は
「了解しました」
そう言って車が走り出した。
「俺もね、最近通いだしたのだけど、実に旨いものを食わせるんだよ。師匠はさ、あれだけ食べる仕草が見事なんだから実際に食べる事にも煩いんじゃ無いかと思ってね」
確かに食べる事には人一倍興味があった。旨いものがあると聞くと取り寄せて食べてみた事も一度や二度ではなかった。
やがてタクシーは一軒の小料理店の前で停まった。
「ここなんだよ」
タクシーから降りた客が紹介したのは一見、平凡な小料理屋に見えた。
「ここがですか?」
「まあまあ、百聞は一見にしかずだ。入った入った」
客に言われて入り口の扉を開けて暖簾を潜った。
「いらっしゃいませ~」
陽気な女性の声が耳に届いた。この時、柳生はこれから起きる事を全く予想していなかった。