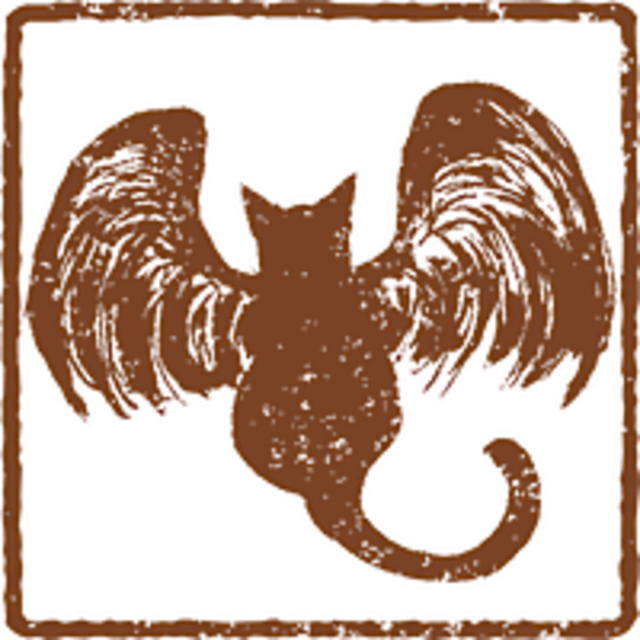その2冬ごもり
文字数 4,835文字
「何だって?」
ジェラルド・ロサーリオ・サーリス教授は目を見開いた。常によどみなくなめらかで音楽的な響きを奏でる声が、珍しくうわずった。
彼はただ問いかけただけなのだ。教え子の一人、ルドルフ・フォン・ベーレンドルフ……灰色の瞳に銀の髪、岩を刻んだがごとき堂々たる体躯の青年に。
「クリスマス休暇はどうするのかね?」と。
答えは迅速にして簡潔。
「あなたと一緒に」
「何だって?」
「いけませんか?」
「いや、それは、その」
ほお骨の周りが熱くなる。しかしぎりぎりの線で彼は持ちこたえた。恋人同士ではなく、教授と教え子との会話に留まった。
「ご家族は何と? 帰省するんじゃあないのかい? クリスマス休暇だよ?」
「教授の手伝いするって言ったらOKしてくれました」
「そ……そうか」
窓際にたたずむ青年は、こちらを見てちょこんと首をかしげている。
「休暇中は、コッツウォルズのお屋敷に戻られるんですよね? 蔵書の整理とか、庭の手入れとか、食料の買い出しとか、あと暖炉のまき割りとか。することはいくらでもありますよね? 力仕事はおまかせください」
「う、うぅむ」
ほっそりした繊細な指でこめかみをさする。
彼とて年下の恋人と過ごす時間は欲しい。
亡き両親から受け継いだ、蜂蜜色の石造りの屋敷に住む者は今は誰もいない。普段は管理人に任せている。大学を遠く離れた田舎であれば、人目を気にせずにすむ。一番近いお隣でさえ4キロは離れているのだ。
「車も運転します!」
「わかった。負けた。降参だよ、ルドルフ」
「……」
破顔一笑。
「OKってことですね!」
「ああ」
今にも飛びついて来そうなルドルフを、やんわりと片手で制する。そのたくましい体で本気で突進されたら抗いようもないが、ここは(扉が閉まってるとは言え)大学の中だ。研究室だ。いつ、ノックされるかわからない。うかつに熱い抱擁に埋もれる訳には行かないのだ。
「クリスマス休暇は私を手伝ってくれたまえ、ベーレンドルフくん」
「はい、サーリス教授」
※
「そんな訳だから母さん、クリスマス休暇は帰らないよ。うん、教授のお宅でのバイトなら安心だろ?」
電話で手短に伝えた。
さして追求することもなく、母は受け入れた。
学生が帰省よりアルバイトを優先するのはよくある話だ、と。
電話を切って、息を吐く。深く、深く、ゆっくりと。手の甲に風圧を感じるほど強く。
本当は、向こうだってほっとしてるのだ。ゲイの息子と顏を合わせるのは気まずいのだろう。あからさまに軽蔑こそされなくなったが、両親が自分をもてあましているのは明らかだった。ましてこの休暇中、兄がフィアンセを連れてくるとあってはなおさらに。
「だから、これでいいんですよ、ジェラルド……」
口付けを捧げる。ひそかにスマホに撮り溜めた愛しい人の写真に。
言ってしまったら、何だか楽になった。後に残るのは楽しい予定だけ。
「さっ、準備しようっと」
キャンプ用リュックを引っ張り出す。スマホで情報を確認しつつ、いそいそと荷物を詰めた。
「コッツウォルズ地方の気候は……わあ、さっすが冷え込むなあ。厚手のセーター持ってった方がいいな」
※
絵本から抜け出したような石畳の町並は次第にまばらとなり、ゆるやかな丘の間にひろがる畑を経て、やがては牧草地に変わる。時折、ぽつりぽつりと雲のような白い塊が見える。
「羊ですか?」
「ああ、羊だよ」
小高い丘の上に建つ、蜂蜜色の石造りの荘厳な屋敷。冠のように植わった防風林の間を抜けると、急に目の前に現れる。二人ですごすにはあまりにも広い。
「冬のにおいがする」
落ち葉と、一度霜柱で凍って溶けた土のにおい。ひくひくと鼻をうごかし、深呼吸。
「詩的な表現だね」
「あなたといるからです」
かつては馬車が通った道を抜け、車を玄関の前に横付けにした。トランクを開けて荷物を運び出す。
「ほんとうに君、荷物はそれだけでいいのかい?」
「はい。充分です」
キャンプ用のリュックを背負い、さらに使い込まれたスーツケースに手をかける。
「重いよ?」
「平気です」
言葉通り、軽々と運び出す。
「部屋は二階ですか?」
「ああ」
玄関ホールから、優雅にS字のカーブを描く幅広の階段をのぼる。
前日までに管理人が風を通しておいてくれたのだろう。中の空気は思ったより新鮮で、使う部屋はあらかじめ掃除されていた。薪のストックもたっぷりある。
「……けっこう近代化されてますね」
「両親は伝統と同じくらい、新しい物が好きな人たちだったからね」
教授は先に立ち、自分の部屋……正確には、この屋敷での自分の部屋の扉を開けた。
「積極的に文明を取り入れれば、その分使用人を減らせる」
「良かった。それじゃあ、雪が降っても心配ないですね」
「うむ、暖房システムは行き届いているし給湯システムのおかげでお湯は好きなだけ使える……しかし、ルドルフ」
「はい?」
「雪が降るのかい?」
「はい。そう言うにおいがします」
「だから、あんなに食料を買い込んだのかね」
「はい。あ、すごい。携帯の電波、ちゃんと入ってる!」
「かえって田舎の方がネットワークはしっかり整えられているのだよ。家同士が離れているからね」
「なるほど……」
「需要の問題だ、ベーレンドルフくん」
「じゃあ雪に閉ざされた山荘で連絡がとれなくて、なんてのは古典ミステリーでの話なんですね!」
彼の発想はいつも、意外性に満ちている。
「教授は荷ほどきしててください。残りの荷物、とってきます」
「ああ、頼んだよ」
荷解きの合間に窓から正面玄関を見守る。
ルドルフは大量の食料を下ろし、最後にカバーに入った折り畳み式の自転車を降ろしていた。
「まったく、意外性に満ちている」
「驚いた」
「そうですか?」
小枝に刺したマシュマロを火にかざす。石組みと鉄枠の中で静かに燃える暖炉の炎で。都会の家のスタイリッシュで現代的な暖炉より無骨で大きい。
焼く、といっても白いふわふわの塊を、決して直に炎に触れさせてはいけない。見えなくても熱は届く。ふくらんで、ほんのり表面に焦げ目がついた頃が食べごろ。
「君が旧式な暖炉で火をつけるのに、こんなに慣れているとはね」
「原理的には焚き火と同じですから」
「焚き火に慣れているのかい?」
「キャンプで覚えました……はい、どうぞ」
「ありがとう」
「中が熱いから気をつけて」
サーリス教授は形の良い唇をとがらせて、ふぅ、ふぅとマシュマロを吹いてさます。
「んっ」
白い歯でマシュマロをくわえて、ひっぱる。とろっとろに溶けた甘い糸がのびる。
「う」
垂れたマシュマロの糸をどうすればいいのか、とまどっている。この紳士は明らかにこの食べかたに慣れていないのだ。ルドルフは素早く手をのばして指先で白い糸をすくいとり、ちょっと考えてから自分の口に入れる。
「ごちそうさま」
「……ありがとう」
ぱちん、と薪が弾ける。心地よい香りを飛ばす椛の木。
暖炉の前に敷き詰めたふかふかのラグの上で二人はくつろいでいた。限られた時間の中で狂おしく求めあう週末の逢瀬とはちがった、ゆったりした時の流れに浸っていた……マイクロビーズのクッションに身を沈めて。
「久しぶりだよ、こんな風に焼いたマシュマロを食べるなんて」
「いっぺんやってみたかったんですよね、これはじっくり時間かけないとあっと言う間に燃えちゃうから」
「そのようだ」
「うわあっ」
当のルドルフの握る小枝の先で、マシュマロがぱっと炎をあげて燃え上がり、消し炭と化した。
「あーあ」
部屋の中には甘い空気が充満している。ちょっとやそっと換気した程度ではこの甘みは抜けない。しょんぼり肩を落とす青年に、サーリス教授はほっそりした指でマシュマロをつまみ、器用に小枝に刺した。流れるような優雅なしぐさに見とれる。
「さあ、これを」
「ありがとうございます」
ルドルフは慎重に小枝を手にして炎にかざす。今度こそ、うまく焼けるように。他愛のない楽しみだけど、時間を気にせず人目を気にせずのびのびとくつろぎ、ひたれる。これは、もう……
「最高の贅沢かもしれないね」
「はい」
その日、サーリス教授は二度寝した。一度目に起きたのは、ルドルフが枕元に運んできた朝食をとった後に。二度目に起きてから、洗面所で身支度を整えて、ガウンを羽織って下に降りた所で、出くわしたのだ。
「……ルドルフ、これは一体」
「クリスマスツリーです!」
「それはわかる」
ルドルフが、ネットに包まれたモミの木を軽々とかついで居間に入って来た所に。つんとした樹皮の香り。
「何故それがここにあるのだね?」
「来る途中にガーデンセンターがあったでしょ? 散歩がてらに寄ってきました」
「確かにガーデンセンターは町の端っこだが……この雪の中を?」
「歩くのは楽でしたよ? いい感じに固まってたし。ソリもあったし」
「ソリ!?」
「荷物運搬用の。納屋にありました」
言われてみれば子供の頃に見たことがある。薪を運ぶのに使っていた。
「しかし木だけあっても、飾る物がない」
「見つけました。屋根裏で」
居間の片隅に、見覚えのある箱があった。古びた赤い木箱。ルドルフはモミの木を下ろすと、箱のフタを開けた。
「サンタに、トナカイ、星、あと、これはベルかな? オーブに、ガラスのリンゴ」
「懐かしい……」
「豆電球はないのかな」
「代わりに本物のロウソクを下げるんだ。この金具で」
「わお」
「もう何年も、火を点したことはなかった。いや、この家にクリスマスツリーを飾ること自体が久しぶりだよ。しかもこんな大きなツリーを……」
まさか大人の背丈ほどもあるツリーをかついでくるなんて。
「足りなかったら、これも飾りましょう。サービスでもらいました」
ダウンジャケットのポケットから手品のように、きらきらした金色のモールが出てきた。
「せっかく、あなたと二人っきりのクリスマスですから」
「君にはかなわない」
そうして二人はツリーを飾った。
「このロウソク、いいにおいがする」
「蜜蝋を使ってるんだ」
「これが? わお」
くんくん、と念入りににおいを嗅ぐ。
「本物は初めて見た!」
ガラスの林檎、モザイク模様のオーブ、ブリキのサンタに木彫りの天使、蜜蝋のキャンドル、金色のモール。一つ残らず緑の枝に吊るす。最後に大きな星が残った。
「てっぺんの星だ。これをつけるには踏み台が必要だな」
「ちょっと待って……失礼」
あっと言う間にがっしりした手が腰にまきつき、高々と差し上げられる。
「ルドルフ? ルドルフ、いったい何をっ」
宙に浮いた足をばたつかせるが、腰を支える手は微動だにしない。
「これで、てっぺんまで手が届きますよね?」
「……全く、君の行動は意外性に満ちているよ」
「さ、どうぞ」
サーリス教授はその繊細な指先で注意深く、星をツリーの頂きに据えた。耳たぶ、うなじを薔薇色に染めて。
作業の終了を見届けてから、ルドルフはゆっくりと愛しい人を床に下ろす。そのままくるりと回して向きあうと、深く抱きしめ、耳元にささやいた。
「踏み台になろうかとも思ったんです。でも、それだとあなたの顏が見えない」
「君と言う子は」
とっさに制する動きに力が入らない。
二人きりの時間が続くにつれて、むしろためらいが無くなってきた。若い情熱に飲み込まれるのに。
「どうしたんですか、ジェラルド?」
「いや、何、大したことじゃないよ。ただ」
普段は言葉にせずに飲み込んでいた想いを、口にする。
「休暇が終わった時に、寂しくなりそうだなと思ってね」
「今はそんなこと、考えたくない」
ジェラルド・ロサーリオ・サーリス教授は目を見開いた。常によどみなくなめらかで音楽的な響きを奏でる声が、珍しくうわずった。
彼はただ問いかけただけなのだ。教え子の一人、ルドルフ・フォン・ベーレンドルフ……灰色の瞳に銀の髪、岩を刻んだがごとき堂々たる体躯の青年に。
「クリスマス休暇はどうするのかね?」と。
答えは迅速にして簡潔。
「あなたと一緒に」
「何だって?」
「いけませんか?」
「いや、それは、その」
ほお骨の周りが熱くなる。しかしぎりぎりの線で彼は持ちこたえた。恋人同士ではなく、教授と教え子との会話に留まった。
「ご家族は何と? 帰省するんじゃあないのかい? クリスマス休暇だよ?」
「教授の手伝いするって言ったらOKしてくれました」
「そ……そうか」
窓際にたたずむ青年は、こちらを見てちょこんと首をかしげている。
「休暇中は、コッツウォルズのお屋敷に戻られるんですよね? 蔵書の整理とか、庭の手入れとか、食料の買い出しとか、あと暖炉のまき割りとか。することはいくらでもありますよね? 力仕事はおまかせください」
「う、うぅむ」
ほっそりした繊細な指でこめかみをさする。
彼とて年下の恋人と過ごす時間は欲しい。
亡き両親から受け継いだ、蜂蜜色の石造りの屋敷に住む者は今は誰もいない。普段は管理人に任せている。大学を遠く離れた田舎であれば、人目を気にせずにすむ。一番近いお隣でさえ4キロは離れているのだ。
「車も運転します!」
「わかった。負けた。降参だよ、ルドルフ」
「……」
破顔一笑。
「OKってことですね!」
「ああ」
今にも飛びついて来そうなルドルフを、やんわりと片手で制する。そのたくましい体で本気で突進されたら抗いようもないが、ここは(扉が閉まってるとは言え)大学の中だ。研究室だ。いつ、ノックされるかわからない。うかつに熱い抱擁に埋もれる訳には行かないのだ。
「クリスマス休暇は私を手伝ってくれたまえ、ベーレンドルフくん」
「はい、サーリス教授」
※
「そんな訳だから母さん、クリスマス休暇は帰らないよ。うん、教授のお宅でのバイトなら安心だろ?」
電話で手短に伝えた。
さして追求することもなく、母は受け入れた。
学生が帰省よりアルバイトを優先するのはよくある話だ、と。
電話を切って、息を吐く。深く、深く、ゆっくりと。手の甲に風圧を感じるほど強く。
本当は、向こうだってほっとしてるのだ。ゲイの息子と顏を合わせるのは気まずいのだろう。あからさまに軽蔑こそされなくなったが、両親が自分をもてあましているのは明らかだった。ましてこの休暇中、兄がフィアンセを連れてくるとあってはなおさらに。
「だから、これでいいんですよ、ジェラルド……」
口付けを捧げる。ひそかにスマホに撮り溜めた愛しい人の写真に。
言ってしまったら、何だか楽になった。後に残るのは楽しい予定だけ。
「さっ、準備しようっと」
キャンプ用リュックを引っ張り出す。スマホで情報を確認しつつ、いそいそと荷物を詰めた。
「コッツウォルズ地方の気候は……わあ、さっすが冷え込むなあ。厚手のセーター持ってった方がいいな」
※
絵本から抜け出したような石畳の町並は次第にまばらとなり、ゆるやかな丘の間にひろがる畑を経て、やがては牧草地に変わる。時折、ぽつりぽつりと雲のような白い塊が見える。
「羊ですか?」
「ああ、羊だよ」
小高い丘の上に建つ、蜂蜜色の石造りの荘厳な屋敷。冠のように植わった防風林の間を抜けると、急に目の前に現れる。二人ですごすにはあまりにも広い。
「冬のにおいがする」
落ち葉と、一度霜柱で凍って溶けた土のにおい。ひくひくと鼻をうごかし、深呼吸。
「詩的な表現だね」
「あなたといるからです」
かつては馬車が通った道を抜け、車を玄関の前に横付けにした。トランクを開けて荷物を運び出す。
「ほんとうに君、荷物はそれだけでいいのかい?」
「はい。充分です」
キャンプ用のリュックを背負い、さらに使い込まれたスーツケースに手をかける。
「重いよ?」
「平気です」
言葉通り、軽々と運び出す。
「部屋は二階ですか?」
「ああ」
玄関ホールから、優雅にS字のカーブを描く幅広の階段をのぼる。
前日までに管理人が風を通しておいてくれたのだろう。中の空気は思ったより新鮮で、使う部屋はあらかじめ掃除されていた。薪のストックもたっぷりある。
「……けっこう近代化されてますね」
「両親は伝統と同じくらい、新しい物が好きな人たちだったからね」
教授は先に立ち、自分の部屋……正確には、この屋敷での自分の部屋の扉を開けた。
「積極的に文明を取り入れれば、その分使用人を減らせる」
「良かった。それじゃあ、雪が降っても心配ないですね」
「うむ、暖房システムは行き届いているし給湯システムのおかげでお湯は好きなだけ使える……しかし、ルドルフ」
「はい?」
「雪が降るのかい?」
「はい。そう言うにおいがします」
「だから、あんなに食料を買い込んだのかね」
「はい。あ、すごい。携帯の電波、ちゃんと入ってる!」
「かえって田舎の方がネットワークはしっかり整えられているのだよ。家同士が離れているからね」
「なるほど……」
「需要の問題だ、ベーレンドルフくん」
「じゃあ雪に閉ざされた山荘で連絡がとれなくて、なんてのは古典ミステリーでの話なんですね!」
彼の発想はいつも、意外性に満ちている。
「教授は荷ほどきしててください。残りの荷物、とってきます」
「ああ、頼んだよ」
荷解きの合間に窓から正面玄関を見守る。
ルドルフは大量の食料を下ろし、最後にカバーに入った折り畳み式の自転車を降ろしていた。
「まったく、意外性に満ちている」
「驚いた」
「そうですか?」
小枝に刺したマシュマロを火にかざす。石組みと鉄枠の中で静かに燃える暖炉の炎で。都会の家のスタイリッシュで現代的な暖炉より無骨で大きい。
焼く、といっても白いふわふわの塊を、決して直に炎に触れさせてはいけない。見えなくても熱は届く。ふくらんで、ほんのり表面に焦げ目がついた頃が食べごろ。
「君が旧式な暖炉で火をつけるのに、こんなに慣れているとはね」
「原理的には焚き火と同じですから」
「焚き火に慣れているのかい?」
「キャンプで覚えました……はい、どうぞ」
「ありがとう」
「中が熱いから気をつけて」
サーリス教授は形の良い唇をとがらせて、ふぅ、ふぅとマシュマロを吹いてさます。
「んっ」
白い歯でマシュマロをくわえて、ひっぱる。とろっとろに溶けた甘い糸がのびる。
「う」
垂れたマシュマロの糸をどうすればいいのか、とまどっている。この紳士は明らかにこの食べかたに慣れていないのだ。ルドルフは素早く手をのばして指先で白い糸をすくいとり、ちょっと考えてから自分の口に入れる。
「ごちそうさま」
「……ありがとう」
ぱちん、と薪が弾ける。心地よい香りを飛ばす椛の木。
暖炉の前に敷き詰めたふかふかのラグの上で二人はくつろいでいた。限られた時間の中で狂おしく求めあう週末の逢瀬とはちがった、ゆったりした時の流れに浸っていた……マイクロビーズのクッションに身を沈めて。
「久しぶりだよ、こんな風に焼いたマシュマロを食べるなんて」
「いっぺんやってみたかったんですよね、これはじっくり時間かけないとあっと言う間に燃えちゃうから」
「そのようだ」
「うわあっ」
当のルドルフの握る小枝の先で、マシュマロがぱっと炎をあげて燃え上がり、消し炭と化した。
「あーあ」
部屋の中には甘い空気が充満している。ちょっとやそっと換気した程度ではこの甘みは抜けない。しょんぼり肩を落とす青年に、サーリス教授はほっそりした指でマシュマロをつまみ、器用に小枝に刺した。流れるような優雅なしぐさに見とれる。
「さあ、これを」
「ありがとうございます」
ルドルフは慎重に小枝を手にして炎にかざす。今度こそ、うまく焼けるように。他愛のない楽しみだけど、時間を気にせず人目を気にせずのびのびとくつろぎ、ひたれる。これは、もう……
「最高の贅沢かもしれないね」
「はい」
その日、サーリス教授は二度寝した。一度目に起きたのは、ルドルフが枕元に運んできた朝食をとった後に。二度目に起きてから、洗面所で身支度を整えて、ガウンを羽織って下に降りた所で、出くわしたのだ。
「……ルドルフ、これは一体」
「クリスマスツリーです!」
「それはわかる」
ルドルフが、ネットに包まれたモミの木を軽々とかついで居間に入って来た所に。つんとした樹皮の香り。
「何故それがここにあるのだね?」
「来る途中にガーデンセンターがあったでしょ? 散歩がてらに寄ってきました」
「確かにガーデンセンターは町の端っこだが……この雪の中を?」
「歩くのは楽でしたよ? いい感じに固まってたし。ソリもあったし」
「ソリ!?」
「荷物運搬用の。納屋にありました」
言われてみれば子供の頃に見たことがある。薪を運ぶのに使っていた。
「しかし木だけあっても、飾る物がない」
「見つけました。屋根裏で」
居間の片隅に、見覚えのある箱があった。古びた赤い木箱。ルドルフはモミの木を下ろすと、箱のフタを開けた。
「サンタに、トナカイ、星、あと、これはベルかな? オーブに、ガラスのリンゴ」
「懐かしい……」
「豆電球はないのかな」
「代わりに本物のロウソクを下げるんだ。この金具で」
「わお」
「もう何年も、火を点したことはなかった。いや、この家にクリスマスツリーを飾ること自体が久しぶりだよ。しかもこんな大きなツリーを……」
まさか大人の背丈ほどもあるツリーをかついでくるなんて。
「足りなかったら、これも飾りましょう。サービスでもらいました」
ダウンジャケットのポケットから手品のように、きらきらした金色のモールが出てきた。
「せっかく、あなたと二人っきりのクリスマスですから」
「君にはかなわない」
そうして二人はツリーを飾った。
「このロウソク、いいにおいがする」
「蜜蝋を使ってるんだ」
「これが? わお」
くんくん、と念入りににおいを嗅ぐ。
「本物は初めて見た!」
ガラスの林檎、モザイク模様のオーブ、ブリキのサンタに木彫りの天使、蜜蝋のキャンドル、金色のモール。一つ残らず緑の枝に吊るす。最後に大きな星が残った。
「てっぺんの星だ。これをつけるには踏み台が必要だな」
「ちょっと待って……失礼」
あっと言う間にがっしりした手が腰にまきつき、高々と差し上げられる。
「ルドルフ? ルドルフ、いったい何をっ」
宙に浮いた足をばたつかせるが、腰を支える手は微動だにしない。
「これで、てっぺんまで手が届きますよね?」
「……全く、君の行動は意外性に満ちているよ」
「さ、どうぞ」
サーリス教授はその繊細な指先で注意深く、星をツリーの頂きに据えた。耳たぶ、うなじを薔薇色に染めて。
作業の終了を見届けてから、ルドルフはゆっくりと愛しい人を床に下ろす。そのままくるりと回して向きあうと、深く抱きしめ、耳元にささやいた。
「踏み台になろうかとも思ったんです。でも、それだとあなたの顏が見えない」
「君と言う子は」
とっさに制する動きに力が入らない。
二人きりの時間が続くにつれて、むしろためらいが無くなってきた。若い情熱に飲み込まれるのに。
「どうしたんですか、ジェラルド?」
「いや、何、大したことじゃないよ。ただ」
普段は言葉にせずに飲み込んでいた想いを、口にする。
「休暇が終わった時に、寂しくなりそうだなと思ってね」
「今はそんなこと、考えたくない」