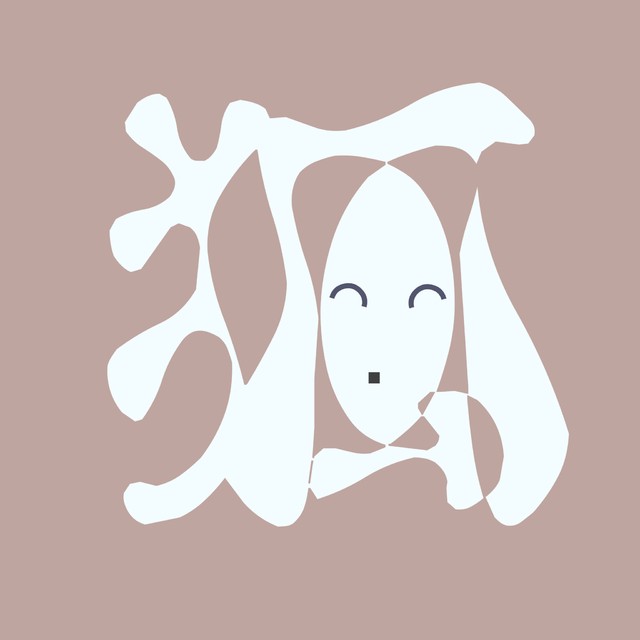(5) ここをキャンプ地とする
文字数 2,463文字
彼女との出会いは、そこからさらに六年前。中学一年のときに遡る。
春とはいえ、山の夜はそれなりに寒い。
総勢五人の天文部員は、草っ原の上に直接並べられた寝袋に入って寝転がり、大量のビー玉をまき散らしたかのような星空に身を委ねていた。
「紀元前の大昔から、人類は天文学に取り組んできたけれど、ある意味では天文学の歴史はまだまだ浅いとも言えるの。望遠鏡や観測技術が発達するたびに、宇宙は広く大きくなっていく。そして広がれば広がるほど、分からないことは増えていく」
かぐや部長は独り言のように語った。
太陽系が含まれる天の川銀河が宇宙の全てではないことに人類が気づいたのは、案外と最近のことだったりするらしい。
遠くにぼんやりと、まるで夜空についた擦 り傷のように見えた別の銀河たちは、長く天の川銀河の内部にあるものと考えられ、星雲と呼ばれていた。
それが多くの論争と観測を経て、天の川銀河の外、遥か彼方の宇宙空間に浮かぶ別の銀河であるということで、概ね人類の意見が一致したのは十九世紀前半のことだ。日本の年表で言えば大正時代の終わり。関東大震災よりも新しい歴史ということになる。
「一八九四年——日清戦争が起こった年にね、自然科学における基本法則や基本的な事実は、もう既に全てが明らかになっていて、今後の科学にできることはただ精度を高めるだけだって講演をぶった物理学者がいたらしいの。けれど、それは大間違いだった。大人になれば世の中のことが分かるなんてのも、きっと嘘。視野が広がれば広がるほど、遠くが見えるようになればなるほど、分からないことが増えていく。身につまされるのは、自分たちはまだまだ知らないことが多過ぎるってこと」
彼女は純粋に星空を愛する心と同時に、そんな、中学生にしては達観して冷めた視点の持ち主でもあった。
天文部に入ったのは偶々 だ。父親の趣味に付き合わされて、小学生の頃からテニススクールに通っていた。中学にはソフトテニス部しかなかったので、学校では天文部に籍を置きつつ、テニススクールに通い続けることにした。
天文学になど興味はなかったけれど、同じクラスで隣の席だった田口から名前だけ貸してくれと懇願されて、深く考えることもなく承諾してしまった。天文部は部員が少なくて、廃部の危機に瀕していたのだ。
田口は度のきつそうな眼鏡をかけて、ちょっとオタクっぽい雰囲気をもつ男だったけれど、名前くらい貸してもいいかと思わせる程度には良い奴だった。
それでもやっと三年生が三人と一年生が二人の五名だけ。部としてぎりぎり存続できるボーダーラインだ。一年経てば二人だけになってしまうわけだが、卒業まで望みを繋いだ三年生には随分と歓迎されて、悪い気はしなかった。
ただ名前だけという約束は三年生には伝わっていなかったらしく、いきなりゴールデンウィークの新歓キャンプに誘われた。
断る口実を探してはみたものの、結局は田口と二人で寝袋とテントを一つずつ担がされ、学校の裏山を越え、次の山までをも越えるはめになった。目的のキャンプ場は、そこからさらに次の山を目指してしばらく歩いた山中にあった。
それはキャンプ場だと知らなければ、山の中にしては木が少なくて平地が広がっているなあと感じる程度にしか見えない場所だった。キャンプ場名も読めないほど朽ち果てた看板に気づいた者ですら、せいぜいキャンプ場の跡地だと思うだろう。
それでもよくよく見れば簡易トイレと水道もあった。聞けば、付近の山一帯が天文部OBの実家の持ち物だそうで、ほぼ天文部のためだけに整備されたキャンプ場だという。
その広い平地の中央付近を、川とも呼べないような細い細い天然の水の流れが横切っていた。部員たちはそれを天の川と呼んでいた。
「ここをキャンプ地とするぞお」
先輩に言われるがまま、天の川を挟んで一つずつ、担いで来たテントを張った。
「わたし、こっちね」
唯一の女子部員であった部長が、一方のテントのポールに「男子禁制」と書かれた札をぶら下げた。途端に天の川の向こう側は聖域のように思えた。
「ああ、いい天気で良かった」
部長は空を見上げながら、自分の鼻の頭を右手の人差し指で二三度掻くように撫でた。それはキャンプ以前の数少ない部活の集まりの中でも、幾度となく目にしたことのある彼女の癖だった。
名前を貸しただけで興味などなかった天文部のキャンプに参加することになった本当の理由は、彼女が美人だったからに他ならない。
部長は同級生の男子部員からかぐやと呼ばれていた。由来は定かではなく、本名ではないし、実家が家具屋というわけでもなかった。ただ、竹から生まれたわけではないにせよ、天文部の美人部長にかぐやという名前はふさわしいように思えた。
山道を歩きながら、部長の後頭部で束ねられた髪が揺れるのを見て、たしかに馬の尻尾はこんなふうかもしれないと思った。その揺れる髪の向こうに見えた、透き通るように白い彼女のうなじが、うなじというものの艶 かしさを初めて教えてくれた。
中学一年生なんてつい数日前まで小学生だった、まだまだ尻の青い餓鬼だ。同じ中学生とはいえ、三年生の彼女は餓鬼から見れば十分に大人だった。
同級生の女子の背中にブラジャーのラインを見つけてどきどきしたり、人並みにエッチなことに対する興味は芽生えつつはあったけれど、同世代の生身の女性を本当に性的な対象として見たのは彼女が初めてかもしれない。
世間でどんなにキャンプがブームになろうとも、天文部はキャンプに余計な手間はかけない。
小さなガスストーブとケトルでお湯を沸かし、カップ麺だけの晩御飯をさっさと済ませると、草の上に五つの寝袋が並べられた。
「望遠鏡とか覗かないんですか」
田口の疑問を三年生が一蹴した。
「十年早い」
「中学は三年しかないじゃないっすか」
「よく気づいたな。冗談冗談。新歓キャンプは肉眼で宇宙を見て過ごすのが習わしなんだ」
習わしなどという古風なものに自分が巻き込まれるとは思ってもみなかった。
春とはいえ、山の夜はそれなりに寒い。
総勢五人の天文部員は、草っ原の上に直接並べられた寝袋に入って寝転がり、大量のビー玉をまき散らしたかのような星空に身を委ねていた。
「紀元前の大昔から、人類は天文学に取り組んできたけれど、ある意味では天文学の歴史はまだまだ浅いとも言えるの。望遠鏡や観測技術が発達するたびに、宇宙は広く大きくなっていく。そして広がれば広がるほど、分からないことは増えていく」
かぐや部長は独り言のように語った。
太陽系が含まれる天の川銀河が宇宙の全てではないことに人類が気づいたのは、案外と最近のことだったりするらしい。
遠くにぼんやりと、まるで夜空についた
それが多くの論争と観測を経て、天の川銀河の外、遥か彼方の宇宙空間に浮かぶ別の銀河であるということで、概ね人類の意見が一致したのは十九世紀前半のことだ。日本の年表で言えば大正時代の終わり。関東大震災よりも新しい歴史ということになる。
「一八九四年——日清戦争が起こった年にね、自然科学における基本法則や基本的な事実は、もう既に全てが明らかになっていて、今後の科学にできることはただ精度を高めるだけだって講演をぶった物理学者がいたらしいの。けれど、それは大間違いだった。大人になれば世の中のことが分かるなんてのも、きっと嘘。視野が広がれば広がるほど、遠くが見えるようになればなるほど、分からないことが増えていく。身につまされるのは、自分たちはまだまだ知らないことが多過ぎるってこと」
彼女は純粋に星空を愛する心と同時に、そんな、中学生にしては達観して冷めた視点の持ち主でもあった。
天文部に入ったのは
天文学になど興味はなかったけれど、同じクラスで隣の席だった田口から名前だけ貸してくれと懇願されて、深く考えることもなく承諾してしまった。天文部は部員が少なくて、廃部の危機に瀕していたのだ。
田口は度のきつそうな眼鏡をかけて、ちょっとオタクっぽい雰囲気をもつ男だったけれど、名前くらい貸してもいいかと思わせる程度には良い奴だった。
それでもやっと三年生が三人と一年生が二人の五名だけ。部としてぎりぎり存続できるボーダーラインだ。一年経てば二人だけになってしまうわけだが、卒業まで望みを繋いだ三年生には随分と歓迎されて、悪い気はしなかった。
ただ名前だけという約束は三年生には伝わっていなかったらしく、いきなりゴールデンウィークの新歓キャンプに誘われた。
断る口実を探してはみたものの、結局は田口と二人で寝袋とテントを一つずつ担がされ、学校の裏山を越え、次の山までをも越えるはめになった。目的のキャンプ場は、そこからさらに次の山を目指してしばらく歩いた山中にあった。
それはキャンプ場だと知らなければ、山の中にしては木が少なくて平地が広がっているなあと感じる程度にしか見えない場所だった。キャンプ場名も読めないほど朽ち果てた看板に気づいた者ですら、せいぜいキャンプ場の跡地だと思うだろう。
それでもよくよく見れば簡易トイレと水道もあった。聞けば、付近の山一帯が天文部OBの実家の持ち物だそうで、ほぼ天文部のためだけに整備されたキャンプ場だという。
その広い平地の中央付近を、川とも呼べないような細い細い天然の水の流れが横切っていた。部員たちはそれを天の川と呼んでいた。
「ここをキャンプ地とするぞお」
先輩に言われるがまま、天の川を挟んで一つずつ、担いで来たテントを張った。
「わたし、こっちね」
唯一の女子部員であった部長が、一方のテントのポールに「男子禁制」と書かれた札をぶら下げた。途端に天の川の向こう側は聖域のように思えた。
「ああ、いい天気で良かった」
部長は空を見上げながら、自分の鼻の頭を右手の人差し指で二三度掻くように撫でた。それはキャンプ以前の数少ない部活の集まりの中でも、幾度となく目にしたことのある彼女の癖だった。
名前を貸しただけで興味などなかった天文部のキャンプに参加することになった本当の理由は、彼女が美人だったからに他ならない。
部長は同級生の男子部員からかぐやと呼ばれていた。由来は定かではなく、本名ではないし、実家が家具屋というわけでもなかった。ただ、竹から生まれたわけではないにせよ、天文部の美人部長にかぐやという名前はふさわしいように思えた。
山道を歩きながら、部長の後頭部で束ねられた髪が揺れるのを見て、たしかに馬の尻尾はこんなふうかもしれないと思った。その揺れる髪の向こうに見えた、透き通るように白い彼女のうなじが、うなじというものの
中学一年生なんてつい数日前まで小学生だった、まだまだ尻の青い餓鬼だ。同じ中学生とはいえ、三年生の彼女は餓鬼から見れば十分に大人だった。
同級生の女子の背中にブラジャーのラインを見つけてどきどきしたり、人並みにエッチなことに対する興味は芽生えつつはあったけれど、同世代の生身の女性を本当に性的な対象として見たのは彼女が初めてかもしれない。
世間でどんなにキャンプがブームになろうとも、天文部はキャンプに余計な手間はかけない。
小さなガスストーブとケトルでお湯を沸かし、カップ麺だけの晩御飯をさっさと済ませると、草の上に五つの寝袋が並べられた。
「望遠鏡とか覗かないんですか」
田口の疑問を三年生が一蹴した。
「十年早い」
「中学は三年しかないじゃないっすか」
「よく気づいたな。冗談冗談。新歓キャンプは肉眼で宇宙を見て過ごすのが習わしなんだ」
習わしなどという古風なものに自分が巻き込まれるとは思ってもみなかった。