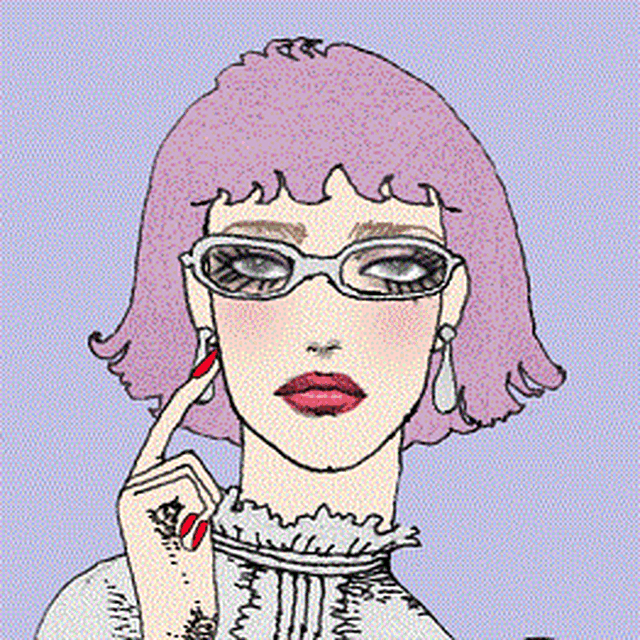第1話
文字数 3,326文字
二条大路から都を抜けて鴨川を渡ると、皇族の祈願による寺院や、院御所が造営された白河という場所がある。
都にむかって緩やかに傾斜するその土地の南端に、前摂政・近衛基実 の北政所だった平盛子が住まう邸 があった。白河押小路殿 という。
満開を迎えた山桜の香りに華やぐその邸では、数日前から若い女房たちがそわそわとして落ちつかず、それをたしなめる年配の女房の小言があちらこちらから聞こえていた。
その日も、つい盛子が何度目かの苦笑をもらすと、そばに控えていた冷泉局という女房が恐縮したように困った顔を見せた。
「申しわけございません。若い者たちが、すっかり浮かれているようでございます」
「いいのよ、あの桜梅の少将どのがいらっしゃるのですもの。わたしも、ひさしぶりに維盛 どのや資盛 どのにお会いできるのを、楽しみにしているのよ」
弟のように可愛がってきた甥たちの名を、盛子はうれしげに口にした。やわらかなほほ笑みにあわせて、髪の下がり端がさらさらとゆれる。
女主人のゆったりとした笑みにつられるように、冷泉局が「じつは、わたくしも落ちつきませんの」と打ち明けると、盛子は「そうでしょうね」と、いたずらっぽく笑った。
盛子の甥である維盛は、昨年の春に催された後白河法皇の五十の御賀で青海波の舞い手を務めた。そのあでやかな姿は光源氏にも例えられ、烏帽子に桜と梅の枝を挿していたことから「桜梅の少将」と呼ばれるようになった。
一年が過ぎた今でも、維盛の話となれば女房たちは熱に浮かされたように目を潤ませ、頬を紅潮させる。しかも、今回は彼女たちを花見へ連れ出すための訪問とあっては、夢見心地で浮足立つのも無理はない。
そのうえ、維盛がひとりで盛子に伺候することは稀で、弟の資盛や、平家から正室を迎えた右近衛府の同僚たちを伴うことが常だった。
宮中の花形である彼らの訪問は、いつでも盛子の邸を明るくしてくれる。そしてその顔ぶれのなかには、盛子の義理の息子である近衛基通 もいた。
夫であった基実が亡くなったのは、十一年前。わずか十一歳で寡婦となった盛子は、その翌年、基実の嫡子だった基通の養母となった。
元服してからも、基通はまめに盛子の御機嫌伺いに参上していたが、ここしばらくはそれが間遠になっている。今日の来訪は、盛子とてひそかに楽しみにしていたうちのひとりだった。
「基通どのがいらっしゃるのも、ずいぶんとひさしぶりだわ」
「北の方さまのご出産も、いよいよ近こうございますから」
「ええ、なにかとお忙しいのでしょうね」
冷泉局の言葉に、盛子も心得ているといったようにうなずいた。
基通の正室は盛子の異母妹で、まもなくはじめての出産を控えている。義理の息子と実の妹の慶事を他人事とも思えず、盛子も懐妊がわかってからはずっと気をもんでいた。
(わたしには経験のないことだけれど、御産は大変だと聞くし)
いまだ一度も会ったことのない妹の身体を、盛子は気遣った。
盛子よりもわずかに若いその妹は、衣通姫 にも例えられるほど肌が美しく、絹のようになめらかで白く輝いていると聞く。
その腹に子を宿す妹のことを考えるうち、薄闇のなかで白磁のような肌へ指をすべらせる基通と、しどけなく身体を預ける妹の姿が生々しく脳裏をかすめた。
まるで陽炎のようにゆらめく妖しい幻影に、盛子の胸に沈む濁った澱が、とぐろを巻く蛇のように渦巻きはじめる。
(いけないわ……。つまらないことを考えてはだめよ)
黒く塗りつぶされそうになった感情を押しとどめ、盛子はいつものように口もとへわずかな笑みを貼りつけた。
やがて、女房たちが装いをすっかり整えるのを見計らったように、維盛たちが姿を見せた。
六波羅様とも言われる華美な装束に身を包む彼らが簀子へ現れたとたん、ぱっと母屋 の奥まで明るくなり、爽やかに匂い立つような風が吹きこんでくる。
「母上、ご無沙汰しております。つつがなくお過ごしのようで、安心いたしました。もっと早くにご挨拶に伺いたかったのですが、妻の身体も気がかりで、つい足が遠のいておりました。申しわけございません」
「いいえ。妹も不安でしょうから」
「お心遣い、ありがとうございます」
基通の挨拶を言いわけのように感じてしまった自分に、盛子は気づかれぬように小さく息をついた。
(言いわけだなんて……こちらへ来ないからと言って、基通どのが言いわけをする必要なんてないのに)
盛子は御几帳のほころびから、日の当たる簀子に座る基通の姿を盗み見た。
盛子が過ごす母屋から庇の間、そして基通たちが座る簀子へと連なる空間には、御簾や御几帳が幾重にもしつらえられている。いまでは遠く隔たれた彼らの元服前とはちがい、女房を介して進む会話をもどかしく思うことも、とうになくなった。
十八歳になった基通は、若さゆえの万能感と傲慢さをこれでもかと身にまとっている。しかしそれは嫌味になるどころか、むしろ彼の家柄と育ちの良さを、効果的に印象づけることに成功していた。
(基実さまは、どうだったかしら……。お顔立ちは、よく似てらっしゃる気がするけれど)
幼い日に、ほんの短いあいだ夫婦 であった夫のことは、生絹 を通したようにぼんやりとしか思いだせない。小振りな耳の形、ほっそりとした顔の輪郭、首から肩へかけてのなだらかな線、どれもが基通のそれに取って代わってしまう。
結婚した当初、まだ初潮もみない九歳の盛子を、すでに二十二歳になっていた基実が扱いかねていたであろうことも、いまならわかる。
夫は同衾しても盛子に触れることはなく、二年後にあっけなくこの世を去った。
もっとも、おなじ邸内だというのに訪れも稀だった基実よりも、日参する平家の公達や、元服前の甥たちと過ごすことが多かった盛子は、ことさら夫の死を寂しく思うこともなかった。
そうして、夫に先立たれたという実感のないまま、盛子は四つしか違わない基通の養母となった。
(ああ……思い出したわ。基実さまが、お小さくなったのかと思ったのよ)
猶子となった基通とはじめて対面したとき、盛子は基実が幼い自分と似合いの年ごろになるために小さくなったのだと思った。そして、恥ずかしそうにうつむく少年の様子に、今度こそ仲良くなれそうだと胸が弾んだ。
しかし周囲からは、いずれ摂政・関白にもなる基通を後見するために、義理の親子になるのだと聞かされて、すこし残念に感じたことも覚えている。
とはいえ、十二歳と八歳では親子にはほど遠く、ふたりが並ぶ姿は雛人形のように愛らしかった。
しかも基通は鷹揚な盛子を姉のように慕い、ころころとよく懐いた。盛子もまた、そのような基通が可愛く思われ、彼が持つ生来の驕慢さすら好ましく感じていた。
だから、彼が十一歳で元服するのと同時に、盛子の妹を正室に迎えたときには、見知らぬ妹に掌中の珠を奪われたと感じた。
あの時の喪失感や、はじめて知った昏い感情は、いまでも忘れない。けれど、十五歳になっていた盛子には、その気持ちに蓋をするだけの分別があった。
(でも……もしも、あの時に蓋をあけていたら……)
次々によみがえる記憶の波は、まるで待ち構えていたかのように、昨年の春に起きた大地震の夜を思い出させた。とたんに大きく波立つ心を抑え、盛子はそっとため息をつくと、小さく首を振った。
(いいえ。わたしは……わたしたちは、道を誤らなかった)
盛子が胸の痛みを飲みこむように目を閉じたとき、冷泉局から遠慮がちに声をかけられた。いつのまにか、基通たちとの会話がおざなりになっていたらしい。
盛子はとっさに、無防備になっていた心を引き締めた。
冷泉局がうまく取り繕ってくれていたのか、基通たちは盛子の様子に気づくことなく談笑している。そのうち、去り際に基通が涼やかな笑顔で言い残した。
「中宮さまへお届けするのとごいっしょに、母上にも桜の枝をお持ちします」
「ありがとう」
彼らが若い女房たちを引き連れて邸から去ると、水を打ったような静けさが盛子の身体をひたひたと包んだ。頭上を渡る梁の奥に広がる暗闇が、じっと自分を見下ろしているような気がする。
(基通どの……)
盛子は心のうちで小さくつぶやいた。
都にむかって緩やかに傾斜するその土地の南端に、前摂政・近衛
満開を迎えた山桜の香りに華やぐその邸では、数日前から若い女房たちがそわそわとして落ちつかず、それをたしなめる年配の女房の小言があちらこちらから聞こえていた。
その日も、つい盛子が何度目かの苦笑をもらすと、そばに控えていた冷泉局という女房が恐縮したように困った顔を見せた。
「申しわけございません。若い者たちが、すっかり浮かれているようでございます」
「いいのよ、あの桜梅の少将どのがいらっしゃるのですもの。わたしも、ひさしぶりに
弟のように可愛がってきた甥たちの名を、盛子はうれしげに口にした。やわらかなほほ笑みにあわせて、髪の下がり端がさらさらとゆれる。
女主人のゆったりとした笑みにつられるように、冷泉局が「じつは、わたくしも落ちつきませんの」と打ち明けると、盛子は「そうでしょうね」と、いたずらっぽく笑った。
盛子の甥である維盛は、昨年の春に催された後白河法皇の五十の御賀で青海波の舞い手を務めた。そのあでやかな姿は光源氏にも例えられ、烏帽子に桜と梅の枝を挿していたことから「桜梅の少将」と呼ばれるようになった。
一年が過ぎた今でも、維盛の話となれば女房たちは熱に浮かされたように目を潤ませ、頬を紅潮させる。しかも、今回は彼女たちを花見へ連れ出すための訪問とあっては、夢見心地で浮足立つのも無理はない。
そのうえ、維盛がひとりで盛子に伺候することは稀で、弟の資盛や、平家から正室を迎えた右近衛府の同僚たちを伴うことが常だった。
宮中の花形である彼らの訪問は、いつでも盛子の邸を明るくしてくれる。そしてその顔ぶれのなかには、盛子の義理の息子である近衛
夫であった基実が亡くなったのは、十一年前。わずか十一歳で寡婦となった盛子は、その翌年、基実の嫡子だった基通の養母となった。
元服してからも、基通はまめに盛子の御機嫌伺いに参上していたが、ここしばらくはそれが間遠になっている。今日の来訪は、盛子とてひそかに楽しみにしていたうちのひとりだった。
「基通どのがいらっしゃるのも、ずいぶんとひさしぶりだわ」
「北の方さまのご出産も、いよいよ近こうございますから」
「ええ、なにかとお忙しいのでしょうね」
冷泉局の言葉に、盛子も心得ているといったようにうなずいた。
基通の正室は盛子の異母妹で、まもなくはじめての出産を控えている。義理の息子と実の妹の慶事を他人事とも思えず、盛子も懐妊がわかってからはずっと気をもんでいた。
(わたしには経験のないことだけれど、御産は大変だと聞くし)
いまだ一度も会ったことのない妹の身体を、盛子は気遣った。
盛子よりもわずかに若いその妹は、
その腹に子を宿す妹のことを考えるうち、薄闇のなかで白磁のような肌へ指をすべらせる基通と、しどけなく身体を預ける妹の姿が生々しく脳裏をかすめた。
まるで陽炎のようにゆらめく妖しい幻影に、盛子の胸に沈む濁った澱が、とぐろを巻く蛇のように渦巻きはじめる。
(いけないわ……。つまらないことを考えてはだめよ)
黒く塗りつぶされそうになった感情を押しとどめ、盛子はいつものように口もとへわずかな笑みを貼りつけた。
やがて、女房たちが装いをすっかり整えるのを見計らったように、維盛たちが姿を見せた。
六波羅様とも言われる華美な装束に身を包む彼らが簀子へ現れたとたん、ぱっと
「母上、ご無沙汰しております。つつがなくお過ごしのようで、安心いたしました。もっと早くにご挨拶に伺いたかったのですが、妻の身体も気がかりで、つい足が遠のいておりました。申しわけございません」
「いいえ。妹も不安でしょうから」
「お心遣い、ありがとうございます」
基通の挨拶を言いわけのように感じてしまった自分に、盛子は気づかれぬように小さく息をついた。
(言いわけだなんて……こちらへ来ないからと言って、基通どのが言いわけをする必要なんてないのに)
盛子は御几帳のほころびから、日の当たる簀子に座る基通の姿を盗み見た。
盛子が過ごす母屋から庇の間、そして基通たちが座る簀子へと連なる空間には、御簾や御几帳が幾重にもしつらえられている。いまでは遠く隔たれた彼らの元服前とはちがい、女房を介して進む会話をもどかしく思うことも、とうになくなった。
十八歳になった基通は、若さゆえの万能感と傲慢さをこれでもかと身にまとっている。しかしそれは嫌味になるどころか、むしろ彼の家柄と育ちの良さを、効果的に印象づけることに成功していた。
(基実さまは、どうだったかしら……。お顔立ちは、よく似てらっしゃる気がするけれど)
幼い日に、ほんの短いあいだ
結婚した当初、まだ初潮もみない九歳の盛子を、すでに二十二歳になっていた基実が扱いかねていたであろうことも、いまならわかる。
夫は同衾しても盛子に触れることはなく、二年後にあっけなくこの世を去った。
もっとも、おなじ邸内だというのに訪れも稀だった基実よりも、日参する平家の公達や、元服前の甥たちと過ごすことが多かった盛子は、ことさら夫の死を寂しく思うこともなかった。
そうして、夫に先立たれたという実感のないまま、盛子は四つしか違わない基通の養母となった。
(ああ……思い出したわ。基実さまが、お小さくなったのかと思ったのよ)
猶子となった基通とはじめて対面したとき、盛子は基実が幼い自分と似合いの年ごろになるために小さくなったのだと思った。そして、恥ずかしそうにうつむく少年の様子に、今度こそ仲良くなれそうだと胸が弾んだ。
しかし周囲からは、いずれ摂政・関白にもなる基通を後見するために、義理の親子になるのだと聞かされて、すこし残念に感じたことも覚えている。
とはいえ、十二歳と八歳では親子にはほど遠く、ふたりが並ぶ姿は雛人形のように愛らしかった。
しかも基通は鷹揚な盛子を姉のように慕い、ころころとよく懐いた。盛子もまた、そのような基通が可愛く思われ、彼が持つ生来の驕慢さすら好ましく感じていた。
だから、彼が十一歳で元服するのと同時に、盛子の妹を正室に迎えたときには、見知らぬ妹に掌中の珠を奪われたと感じた。
あの時の喪失感や、はじめて知った昏い感情は、いまでも忘れない。けれど、十五歳になっていた盛子には、その気持ちに蓋をするだけの分別があった。
(でも……もしも、あの時に蓋をあけていたら……)
次々によみがえる記憶の波は、まるで待ち構えていたかのように、昨年の春に起きた大地震の夜を思い出させた。とたんに大きく波立つ心を抑え、盛子はそっとため息をつくと、小さく首を振った。
(いいえ。わたしは……わたしたちは、道を誤らなかった)
盛子が胸の痛みを飲みこむように目を閉じたとき、冷泉局から遠慮がちに声をかけられた。いつのまにか、基通たちとの会話がおざなりになっていたらしい。
盛子はとっさに、無防備になっていた心を引き締めた。
冷泉局がうまく取り繕ってくれていたのか、基通たちは盛子の様子に気づくことなく談笑している。そのうち、去り際に基通が涼やかな笑顔で言い残した。
「中宮さまへお届けするのとごいっしょに、母上にも桜の枝をお持ちします」
「ありがとう」
彼らが若い女房たちを引き連れて邸から去ると、水を打ったような静けさが盛子の身体をひたひたと包んだ。頭上を渡る梁の奥に広がる暗闇が、じっと自分を見下ろしているような気がする。
(基通どの……)
盛子は心のうちで小さくつぶやいた。