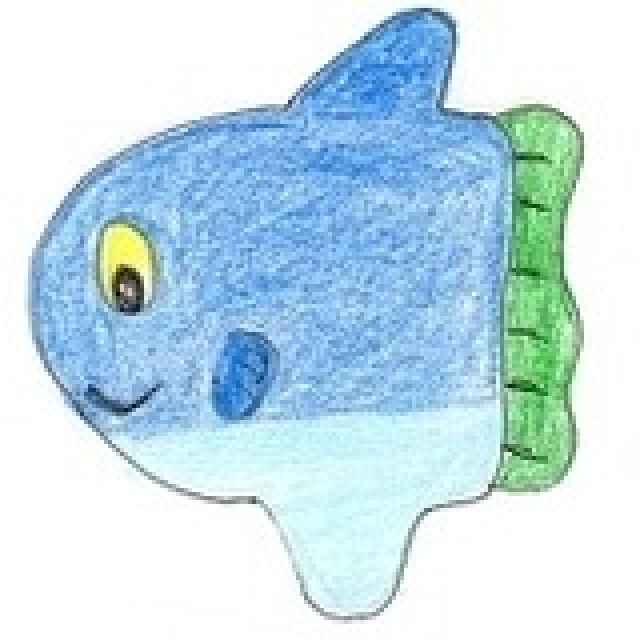第27話 覚醒 4
文字数 4,219文字
今年も東京の夏は暑い! 陽が暮れようとしてるのに汗が止まらないのだ。上野広小路駅で地下鉄を降りて中央通りを鈴本に向かって歩いている。僅かな距離なのだが、それでもドッと汗が出るのだ。
「あ~人生で一番暑い夏だわ」
目立って来たお腹で隣を歩く薫がハンカチを出して出てくる汗を拭ってる。確かに痩せてスタイルの良かった薫は夏は好きな季節だと言っていた。独身の頃は沖縄に良く遊びに行っていたほどだった。俺なんか一度一緒に夏の沖縄に行ったが、余りの暑さに夕方までホテルの部屋で過ごしていたくらいだ。良くこんな場所に来るな。と感心をしたのを思い出した。
「中に入ったら冷房効いてるから」
「それもよし悪しなんだけどね」
額に汗を浮かべながら薫はそれでもにこやかに笑って見せた。
上野鈴本演芸場は上野の山下と広小路の丁度中間にある。隣は福神漬の「酒悦」だ。中央通りに面していて立地条件は良い。特徴としては入り口のすぐ上に太鼓を叩く場所があり、前座さんがここで一番や二番、追い出しの太鼓を叩くのだ。実際に叩いてる所を見られるのは珍しい。
「あ~涼しい!」
薫の言葉が全てを語っている。たちまち汗が引いて行く。
モギリの女性に名前言って盛喬の名を出すと
「はい、伺っております。どうぞ」
そう言ってプログラムをくれた。念の為に確認するとちゃんと「本日の主任 三遊亭盛喬」と書かれてあった。
三階に上がり客席のドアを開けると七割ほどの入りだった。仲入りの少し前なので盛喬は未だ来ていないと前座さんが知らせてくれた。
「暫く座って聴いていよう」
俺の言葉に薫も頷き
「今日は楽しみなんだ。どんな噺が聴けるか」
そう言って後ろの方の席に並んで座った。
仲入りになると前座さんが近寄り
「盛喬師匠楽屋入りなさいました」
と教えてくれた。
「言ってみるか?」
俺がそう言う前に既に薫は腰を浮かせていた。気が早い!
楽屋を訪れて差し入れの菓子を渡すと奥から盛喬が出て来た。未だ着物には着替えていなかった。
「噺は決めたのかい?」
俺は今日、盛喬が何の噺をするか興味があった。人相が変わるほど稽古したとは言え、その時の「文違い」ではないと言う。ならば何なのか、それが知りたかった。夏の噺ならそうトリで演じる事の出来る噺は多くない。「唐茄子屋政談」などは逆に長すぎて寄席では掛けられない。浅草田圃のシーンで切る事も出来るが、まさか今日盛喬はそれはしないと思った。なぜなら目が違っていたからだ。
「今日は、圓生師匠ゆかりの噺をします……でも普通は黒門町かな?」
そう言って盛喬は笑うと再び奥に行ってしまった。気持ちを集中させる為だろう。
「客席で待つか?」
「うん」
薫の言葉で席に戻る。歩きながら俺にはひとつの噺が浮かんで来た。黒門町が演じて、圓生師も関わりのある噺。夏に関係する噺……
俺はそこまで考えて確信を持った。「圓生百席」にも入ってる噺だ。間違い無い……俺の表情を読んで薫が
「孝之さん、盛喬さんが何をやるか判ったのね?」
そう言って目を輝かす。
「ああ、間違い無いと思う」
俺は客席に戻ると俺の考えを話し、演目を言うと
「うん! 間違い無いと思う。どう噺を聴かせてくれるか楽しみになってきたわ」
キラキラした目でつぶやいた。
そして、膝代わりの太神楽が終わると「二上りたぬき」の出囃子が鳴り始めた。ほぼ満員となった客席が一瞬「ザワッ!」となる。こんな感じはかなりの噺家でないとならない。盛喬クラスではあり得ないのだ。今日のお客は何かを感じてるのだろうか?
拍手が鳴り止み、盛喬が頭を上げる。
「え~最後までお付き合い戴きありがとうございます! 今日は音武蔵師匠が遠方に参りまして、間に合いませんのでわたくしが急いで駆けつけて来た。という訳でございます。どうか宜しくお願い致します」
そう言って再び頭を下げると先ほどよりも大きな拍手に包まれた。
「暑いですねえ~ 東京の夏ってえのは何時からこんない暑くなったのでしょうねえ? あたしが子供の頃は三十度超えただけでニュースになりましたよ……全くねえ~」
時節のマクラが始まった。夏の暑さを強調している。やはりあの噺で間違い無いと思った。
「今は本当に少なくなった職業に幇間という職業がございます……」
やはりそうだ、「鰻の幇間」(うなぎのたいこ)だ。そんなに得意演目では無かったこの噺を圓生師はわざわざ「圓生百席」に残した。それは三遊亭の家元としての責任感だったのだろう。後世に間違いの無い噺をきちんとした形で残す。それが「圓生百席」の目的でもあったからだ。
それは黒門町が得意としていたこの噺だが、黒門町のは最初のシーンをカットしていたからだ。この噺は……
暑い夏の昼、野幇間(=置屋に所属しないフリーの幇間)の一八は、ただで昼食にありつこうと、手持ちの羊羹を持って遊廓で上客をたずね回るが、うまくいかない。通りへ出た一八は、浴衣を着た男が目に入る。一八は曖昧な記憶を頼りに、男がなじみの客であるかのように振る舞い、男を取り巻く。男が一八を覚えていると言うので、一八は安心し、男が「湯へ行こうとしたんだが、せっかくだからウナギでも食っていこう」と一八を寂れたウナギ屋に誘うのだった。
この羊羹を持って色々と廻るシーンを名人八代目文楽師はカットしていたのだ。この部分が無いとベテランの一八が簡単に騙される訳が無いと言うのが圓生師の理由だった。だからそんなに得意でもないこの噺を圓生師は記録に残したのだ。
六代目圓生一門でもある盛喬がどうのように演じるか、俺は興味があった。それは「ちゃんとやる」という期待込みだった。
果たして盛喬は夏の昼時分のけだるい雰囲気を上手く再現していた。お茶屋を回って苦労している感じが良く出ていた。やはり盛喬はこのシーンを外さなかったのだ。嬉しくなった。
その後の筋は……
ウナギ屋の二階に着いて蒲焼と酒を飲みながら、一八は男がどこの誰だったか思い出すために、店に対する見え透いたお世辞の合間に「ぜひそのうちにお宅へ」などと探りを入れるが、幇間にとって客のことを忘れることは無礼になるため、強く踏み込んで誰何することができない。
男はその一八の弱みを知ってか知らずか、のらりくらりとかわす。そのうち男は「はばかりへ行く」と言ったきり戻って来なくなる。一八は便所をのぞくと誰もおらず、「勘定を済ませて帰ったのだ。粋な旦那だ」とひとり合点して、勝手に感心する。そのとき中居が「勘定をお願いします」とやって来る。驚く一八。
店員は「浴衣のお連れさんが『おれは先に帰るが、あの羽織を着た旦那からもらってくれ』とおっしゃったので」と言って勘定書きを見せる。二人前にしては高額なので、一八がただすと、店員は「お連れさんが『お土産に』と、もう二人前持って帰ったと明かす。自腹を切ることになった一八は、前に男にしゃべったお世辞とは逆に、店の雰囲気の悪さや、蒲焼に添えられた漬物のまずさなどの悪口を店員にこぼしながら、泣く泣く金を支払う。一八が帰ろうとすると、履いてきた下駄が見当たらないので、店員にたずねると、
「お連れさんが履いてまいりました」
と落とすのだ。盛喬はやっと一八がうなぎ屋に入って行く所まで演じて来た。一八の焦りが上手く出ている。
『なんとしてでも』という感じが良く出ていた。
やがて物語は一八が仲居に悪態をつくシーンとなった。
「お前んところの漬け物。あれは何ですか! うなぎ屋は漬け物で呑ます。というくらいなんだ。それなのに、紅生姜が入っていたろう! お前、あれが何で漬けるか知ってますか?」
「いいえ知りません」
「それなら、教えてあげます。あれは梅酢で漬けるんですよ。卑しくもうなぎ屋なら梅干しとうなぎが食い合せが悪いくらいの事は知らないとは言わせませんよ! 第一、うなぎには奈良漬けって相場が決まってますでしょう。それさえ出やしない」
この噺でこの一八の啖呵が実はかなりの聴かせ所なのだ。「大工調べ」の棟梁の啖呵ほどでは無いが、かなり重要で、一八の怒りとこの後の哀れさに繋がるのだ。ここをきちんと演じない噺家は多い。俺はそれが嫌だったのだが、このシーンをきちんと描く事であの浴衣の男が実に嫌な人物となるのだ。それが判っていない噺家が多い。
盛喬は最後の「お連れさんが履いてまいりました」のサゲを言って頭を下げる。途端に怒涛のような拍手が降り注ぐ。驚きながらも「ありがとうございました!」と言って何回も頭を下げ続ける盛喬……
恐らく彼の噺家としての人生で一番の拍手ではなかったか……
お客が帰った後で楽屋を尋ねると着替えた盛喬が出て来た。
「一杯呑んで帰ろうか?」
誘うとやっと笑顔を見せた。
「初高座以来久しぶりに膝が震えましたよ。高座に上がるのが怖かったです。受けなかったらどうしよう?とかでは無く、噺をする行為そのものが怖かったんです。俺は人様を前にしてとんでも無い事をしてるんじゃ無いだろうか? 演じていてもそう思ってました。今日の高座も未だまだです。とても黒門町の師匠のレベルじゃありません。でも、いつかはこの噺で誰にも負けたく無いと思いました」
盛喬の言葉を受けて薫が
「膝が笑うって緊張ばかりじゃ無いんだよね。興奮していてもなるし、自信が無くてもなる……今日はどっちだと自分では思いました?」
俳優として訪ねていた。その答を盛喬は
「多分両方だったでしょうね。自信が無いんですが、その一方で『あれだけ稽古したから大丈夫だ』という変な自信もありましてね。でも多分本物では無かったんですよ。終わった今だから言えますけど……」
それから散々盛喬に呑ませてタクシーに乗せた。遠ざかる車を見ながら薫が
「上手くなる階段を登り始めたんだね。わたし達凄い高座を見たのかも知れないね」
そう言ったのが印象的だった。
これからも、名人への階段をあいつは登っていくのだろう。それは果てしない修行なのかも知れない。だが、噺家と言う道を選んでしまった以上、それは避けては通れないと思うのだった。
そして俺は最後まで見届ける覚悟を決めたのだった。
噺家奇談 <了>
「あ~人生で一番暑い夏だわ」
目立って来たお腹で隣を歩く薫がハンカチを出して出てくる汗を拭ってる。確かに痩せてスタイルの良かった薫は夏は好きな季節だと言っていた。独身の頃は沖縄に良く遊びに行っていたほどだった。俺なんか一度一緒に夏の沖縄に行ったが、余りの暑さに夕方までホテルの部屋で過ごしていたくらいだ。良くこんな場所に来るな。と感心をしたのを思い出した。
「中に入ったら冷房効いてるから」
「それもよし悪しなんだけどね」
額に汗を浮かべながら薫はそれでもにこやかに笑って見せた。
上野鈴本演芸場は上野の山下と広小路の丁度中間にある。隣は福神漬の「酒悦」だ。中央通りに面していて立地条件は良い。特徴としては入り口のすぐ上に太鼓を叩く場所があり、前座さんがここで一番や二番、追い出しの太鼓を叩くのだ。実際に叩いてる所を見られるのは珍しい。
「あ~涼しい!」
薫の言葉が全てを語っている。たちまち汗が引いて行く。
モギリの女性に名前言って盛喬の名を出すと
「はい、伺っております。どうぞ」
そう言ってプログラムをくれた。念の為に確認するとちゃんと「本日の主任 三遊亭盛喬」と書かれてあった。
三階に上がり客席のドアを開けると七割ほどの入りだった。仲入りの少し前なので盛喬は未だ来ていないと前座さんが知らせてくれた。
「暫く座って聴いていよう」
俺の言葉に薫も頷き
「今日は楽しみなんだ。どんな噺が聴けるか」
そう言って後ろの方の席に並んで座った。
仲入りになると前座さんが近寄り
「盛喬師匠楽屋入りなさいました」
と教えてくれた。
「言ってみるか?」
俺がそう言う前に既に薫は腰を浮かせていた。気が早い!
楽屋を訪れて差し入れの菓子を渡すと奥から盛喬が出て来た。未だ着物には着替えていなかった。
「噺は決めたのかい?」
俺は今日、盛喬が何の噺をするか興味があった。人相が変わるほど稽古したとは言え、その時の「文違い」ではないと言う。ならば何なのか、それが知りたかった。夏の噺ならそうトリで演じる事の出来る噺は多くない。「唐茄子屋政談」などは逆に長すぎて寄席では掛けられない。浅草田圃のシーンで切る事も出来るが、まさか今日盛喬はそれはしないと思った。なぜなら目が違っていたからだ。
「今日は、圓生師匠ゆかりの噺をします……でも普通は黒門町かな?」
そう言って盛喬は笑うと再び奥に行ってしまった。気持ちを集中させる為だろう。
「客席で待つか?」
「うん」
薫の言葉で席に戻る。歩きながら俺にはひとつの噺が浮かんで来た。黒門町が演じて、圓生師も関わりのある噺。夏に関係する噺……
俺はそこまで考えて確信を持った。「圓生百席」にも入ってる噺だ。間違い無い……俺の表情を読んで薫が
「孝之さん、盛喬さんが何をやるか判ったのね?」
そう言って目を輝かす。
「ああ、間違い無いと思う」
俺は客席に戻ると俺の考えを話し、演目を言うと
「うん! 間違い無いと思う。どう噺を聴かせてくれるか楽しみになってきたわ」
キラキラした目でつぶやいた。
そして、膝代わりの太神楽が終わると「二上りたぬき」の出囃子が鳴り始めた。ほぼ満員となった客席が一瞬「ザワッ!」となる。こんな感じはかなりの噺家でないとならない。盛喬クラスではあり得ないのだ。今日のお客は何かを感じてるのだろうか?
拍手が鳴り止み、盛喬が頭を上げる。
「え~最後までお付き合い戴きありがとうございます! 今日は音武蔵師匠が遠方に参りまして、間に合いませんのでわたくしが急いで駆けつけて来た。という訳でございます。どうか宜しくお願い致します」
そう言って再び頭を下げると先ほどよりも大きな拍手に包まれた。
「暑いですねえ~ 東京の夏ってえのは何時からこんない暑くなったのでしょうねえ? あたしが子供の頃は三十度超えただけでニュースになりましたよ……全くねえ~」
時節のマクラが始まった。夏の暑さを強調している。やはりあの噺で間違い無いと思った。
「今は本当に少なくなった職業に幇間という職業がございます……」
やはりそうだ、「鰻の幇間」(うなぎのたいこ)だ。そんなに得意演目では無かったこの噺を圓生師はわざわざ「圓生百席」に残した。それは三遊亭の家元としての責任感だったのだろう。後世に間違いの無い噺をきちんとした形で残す。それが「圓生百席」の目的でもあったからだ。
それは黒門町が得意としていたこの噺だが、黒門町のは最初のシーンをカットしていたからだ。この噺は……
暑い夏の昼、野幇間(=置屋に所属しないフリーの幇間)の一八は、ただで昼食にありつこうと、手持ちの羊羹を持って遊廓で上客をたずね回るが、うまくいかない。通りへ出た一八は、浴衣を着た男が目に入る。一八は曖昧な記憶を頼りに、男がなじみの客であるかのように振る舞い、男を取り巻く。男が一八を覚えていると言うので、一八は安心し、男が「湯へ行こうとしたんだが、せっかくだからウナギでも食っていこう」と一八を寂れたウナギ屋に誘うのだった。
この羊羹を持って色々と廻るシーンを名人八代目文楽師はカットしていたのだ。この部分が無いとベテランの一八が簡単に騙される訳が無いと言うのが圓生師の理由だった。だからそんなに得意でもないこの噺を圓生師は記録に残したのだ。
六代目圓生一門でもある盛喬がどうのように演じるか、俺は興味があった。それは「ちゃんとやる」という期待込みだった。
果たして盛喬は夏の昼時分のけだるい雰囲気を上手く再現していた。お茶屋を回って苦労している感じが良く出ていた。やはり盛喬はこのシーンを外さなかったのだ。嬉しくなった。
その後の筋は……
ウナギ屋の二階に着いて蒲焼と酒を飲みながら、一八は男がどこの誰だったか思い出すために、店に対する見え透いたお世辞の合間に「ぜひそのうちにお宅へ」などと探りを入れるが、幇間にとって客のことを忘れることは無礼になるため、強く踏み込んで誰何することができない。
男はその一八の弱みを知ってか知らずか、のらりくらりとかわす。そのうち男は「はばかりへ行く」と言ったきり戻って来なくなる。一八は便所をのぞくと誰もおらず、「勘定を済ませて帰ったのだ。粋な旦那だ」とひとり合点して、勝手に感心する。そのとき中居が「勘定をお願いします」とやって来る。驚く一八。
店員は「浴衣のお連れさんが『おれは先に帰るが、あの羽織を着た旦那からもらってくれ』とおっしゃったので」と言って勘定書きを見せる。二人前にしては高額なので、一八がただすと、店員は「お連れさんが『お土産に』と、もう二人前持って帰ったと明かす。自腹を切ることになった一八は、前に男にしゃべったお世辞とは逆に、店の雰囲気の悪さや、蒲焼に添えられた漬物のまずさなどの悪口を店員にこぼしながら、泣く泣く金を支払う。一八が帰ろうとすると、履いてきた下駄が見当たらないので、店員にたずねると、
「お連れさんが履いてまいりました」
と落とすのだ。盛喬はやっと一八がうなぎ屋に入って行く所まで演じて来た。一八の焦りが上手く出ている。
『なんとしてでも』という感じが良く出ていた。
やがて物語は一八が仲居に悪態をつくシーンとなった。
「お前んところの漬け物。あれは何ですか! うなぎ屋は漬け物で呑ます。というくらいなんだ。それなのに、紅生姜が入っていたろう! お前、あれが何で漬けるか知ってますか?」
「いいえ知りません」
「それなら、教えてあげます。あれは梅酢で漬けるんですよ。卑しくもうなぎ屋なら梅干しとうなぎが食い合せが悪いくらいの事は知らないとは言わせませんよ! 第一、うなぎには奈良漬けって相場が決まってますでしょう。それさえ出やしない」
この噺でこの一八の啖呵が実はかなりの聴かせ所なのだ。「大工調べ」の棟梁の啖呵ほどでは無いが、かなり重要で、一八の怒りとこの後の哀れさに繋がるのだ。ここをきちんと演じない噺家は多い。俺はそれが嫌だったのだが、このシーンをきちんと描く事であの浴衣の男が実に嫌な人物となるのだ。それが判っていない噺家が多い。
盛喬は最後の「お連れさんが履いてまいりました」のサゲを言って頭を下げる。途端に怒涛のような拍手が降り注ぐ。驚きながらも「ありがとうございました!」と言って何回も頭を下げ続ける盛喬……
恐らく彼の噺家としての人生で一番の拍手ではなかったか……
お客が帰った後で楽屋を尋ねると着替えた盛喬が出て来た。
「一杯呑んで帰ろうか?」
誘うとやっと笑顔を見せた。
「初高座以来久しぶりに膝が震えましたよ。高座に上がるのが怖かったです。受けなかったらどうしよう?とかでは無く、噺をする行為そのものが怖かったんです。俺は人様を前にしてとんでも無い事をしてるんじゃ無いだろうか? 演じていてもそう思ってました。今日の高座も未だまだです。とても黒門町の師匠のレベルじゃありません。でも、いつかはこの噺で誰にも負けたく無いと思いました」
盛喬の言葉を受けて薫が
「膝が笑うって緊張ばかりじゃ無いんだよね。興奮していてもなるし、自信が無くてもなる……今日はどっちだと自分では思いました?」
俳優として訪ねていた。その答を盛喬は
「多分両方だったでしょうね。自信が無いんですが、その一方で『あれだけ稽古したから大丈夫だ』という変な自信もありましてね。でも多分本物では無かったんですよ。終わった今だから言えますけど……」
それから散々盛喬に呑ませてタクシーに乗せた。遠ざかる車を見ながら薫が
「上手くなる階段を登り始めたんだね。わたし達凄い高座を見たのかも知れないね」
そう言ったのが印象的だった。
これからも、名人への階段をあいつは登っていくのだろう。それは果てしない修行なのかも知れない。だが、噺家と言う道を選んでしまった以上、それは避けては通れないと思うのだった。
そして俺は最後まで見届ける覚悟を決めたのだった。
噺家奇談 <了>