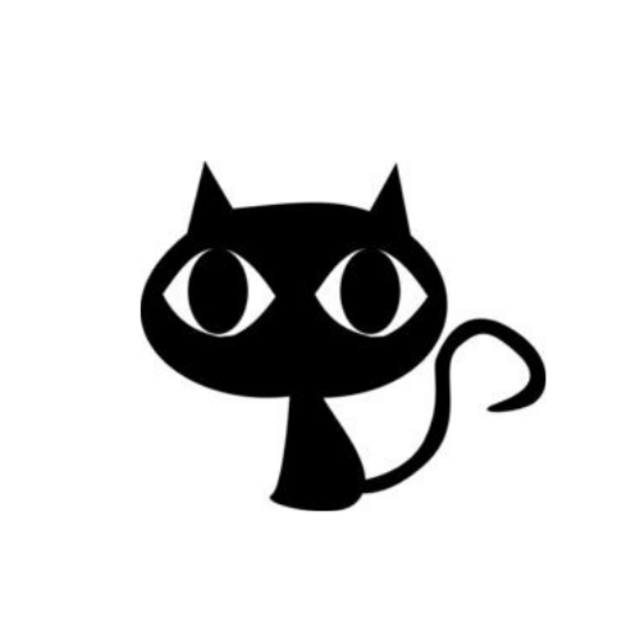或る三人の話
文字数 8,521文字
いまから、三人の人間の話をしようと思う。とても不幸だった三人の話だ。
人間とはいかなるものか、人間に生まれた意味とはどういうものか——偉い哲学の先生だけではなく、そこらの思春期の中学生でも考えるようなことを、一度も考えたこともない三人だった。それどころか、その一人は自分を人間であると思ったことすらなかった。
まず、一人目の話をしよう。彼は男性で、体型は「ずんぐりむっくり」。食生活がどうとか、運動歴がどうというわけではなく、生まれつきの体格だ。その体つきがあまりに特異だったせいで、彼は幼い頃から周りにいじめられてきた。あだ名の「ずんぐりむっくり」は、彼の友達ではなく、その母親が笑いながら言った言葉が、そのまま村の子供達の間で使われた。妙に語呂の良いこの言葉で、子供達は楽しそうに彼を囃し立てた。
『ずんぐりむっくり、黴菌 うんこ!』
『ずんぐりむっくり、のっぺらぼう!』
黴菌うんこはともかくとして、のっぺらぼうというのは、彼の目鼻があまりに小さいころからつけられた、もう一つのあだ名のようなものであった。
卵に目鼻、という言い回しが女性の美を表していたのは過去の話で、この昭和の時代、お茶の間を賑わすアイドルたちは、外国人風の大きな目をした者ばかりである。母親はそんな我が子を庇わないでもなかったが、「ずんぶりむっくり、のっぺらぼう!」、そんな声を聞くたびに、「ああ確かにその通りだ」などと、ふと納得してしまった頃から、彼を邪険にするようになった。
『お前は一体、誰に似たのかねぇ』
そんなことを言い始めたのも、その頃である。これが彼には衝撃であった。
俺にはどんな血が流れているのだろう——。
彼は正真正銘、彼の父と母の子であった。それゆえ「どんな血」ということもないのだが、これ以来、彼は自分の体の中には、得体の知れないものの血が流れていると、自然にそう思うようになったのである。
しかし、ここで注釈を入れておくと、その「思うようになった」という表現には、少々語弊がある。というのも、彼は元来、物をよく考えられぬ人間であった。無論、彼の頭の中のことだ。他人に理解できることなど、ほんの僅かに過ぎないだろう。それでも彼はものを思わぬ人間であったことを、私はここに念押ししておく。
だから、彼が自らの血を得体の知れないものと思ったということも、さらには母親の言葉による衝撃も、彼の中では決して理路整然とした形を取らなかった。それは思考ではなく、言語化による整理でもなく、それ以前の、ただ混沌の状態だった。その混沌は暗い霧となって、彼の心の中に棲み着いた。
結果、彼は恐ろしいほどの癇癪持ちとなった。
言葉を話せぬ赤ん坊が喚くしかないように、考えることさえできない彼は、怒りでそれを表現した。もちろんこの場合も、彼自身、なぜ自分がこんなに苛々しているのか、なぜ周囲に怒鳴り散らしているのか、まったく理解できていなかった。また、理解しようとさえせず、また、しようとしたとしてもできなかった。
そして、それは不幸にも、彼が大人になるまで続いた。いじめられて高校を中退し、癇癪のせいで仕事も続かない彼に、周りの人間は「どうしようもないやつだ」と関わりを避けるようになっていた。「あの『ずんぐりむっくり』は手の施しようがないよ」、と。
大人になっても、ずんぐりむっくりの体躯は相変わらずで、どこへ行っても、彼は子供の頃と同じに「ずんぐりむっくり」と呼ばれ続けた。けれど、かつて彼をからかった子供達は、当たり前のように成長していたため、もう面と向かって彼に意地悪をしなかった。きちんと彼から見えない場所で、通りを歩く「ずんぐりむっくり」を見ては、悪口を言い合ったり、くすくす笑ったりするだけなのであった。
ここで二人目の話に移ろう。二人目の主人公は女性であり、先の「ずんぐりむっくり」とは同い年でもある。彼女のあだ名は「みっちゃん」。本名の「三智子」を縮めただけの、可愛らしいものである。背は低く、色白でぽっちゃりしている。仕事はパンを作ること。彼女は障碍者の作業所に勤めており、その事実から判るように、彼女には軽度の知的障碍があった。
お金の勘定ができず、漢字や長い文章を読むことができない。外見は立派な大人だが、中身は幼稚園児という表現がぴったりくるような女性だった。
作業所を仕切っているのは、三間という物腰の柔らかい女性で、彼女は「この人がわたしのお母さんだったらいいのに」と思うほど気に入っていた。彼女はもう何年も「お母さん」に会っていない。三間の運営するこの作業所には寮が付属していて、彼女はほかの仲間たちと一緒にそこで暮らし、働いている。
食事や作業服、彼女のお小遣い、寮費、もろもろを引いた残りの給料はすべて「お母さん」へ送られているが、彼女はそれを知らないし、また、それがどういうことなのか理解できない。子供が毎日幼稚園へ行くように、働き、お小遣いをもらっているだけだ。体も頑丈そのものだったが、作業所へ来てからは何回か、腹痛で医者にかかることになった。かかるのはいつも同じ医者で、スポーツ選手のようにがっしりとした男の医者だ。その処置の恐ろしさのせいで、彼女は大きな男の人が怖かった。
けれど、「その人」のことは初めから怖くなかった。
それは、彼女が売り場にパンを並べていたときである。一人の男性が来店し、たまたまレジにいた三間を突然、怒鳴りつけた。怒声の内容は聞き取れなかったが、雷のような声だと彼女は思った。
雷は好きだった。空が光って、しばらくすると、どーんと体の中心に響くような音がする。それがとても気持ち良い。その雷のような声をあげながら、男は三間を殴った。三間は悲鳴をあげ、そこにぼうっと突っ立ったままの彼女に向かって「警察、警察を呼んでちょうだい!」と叫んだ。
——ケイサツはひゃくとおばん。
いくら彼女でもそれくらいは知っていたが、肝心の電話はレジの奥、三間と男が争う向こう側にある。どうしたらいいのかわからずに目をパチパチしていると、振り返った男と目が合った。大きな顔に似合わない、小さな目鼻。
ミーコちゃんみたい、反射的にそう思った。ミーコちゃんは優しい人がきふ してくれた、手作りのぬいぐるみだ。男の顔はそれに似ていた。そうと思って見れば、彼の短躯もミーコちゃんにそっくりだった。
「お願い、警察を呼んで」、もう一度、三間は彼女に懇願した。その顔は血だらけだった。しかし、彼女はその三間を無視して、男に近づいた。そして、その手を握り、微笑んだ。
三間の顔が苦く歪んだ。微笑む彼女は、あっけにとられたような男を連れ、店を出て行く。十八の年から、彼女の面倒を十四年も見て来た三間は、これから起こることを完全に理解していた。彼女はいまからあの男と寝る。そして、その後始末は、監督責任のある三間と、かかりつけの医者——スポーツ選手のようにがっしりとした、男性産科医なのであった。
そして話は三人目へと移る。
名前はひまわり 。病室の壁に飾ってあった向日葵の絵からとられた名前である。
軽度とはいえ、知的障碍のある母親の出産に、総合病院の若い女性産科医はあらん限りのサポート体制を敷いて挑んだのだが、その本番は、子供の父親である男性によって、めちゃくちゃになってしまった。
彼は土足で分娩室へと踏み入り、そこにいた助産師たちを怒鳴り散らした。何が気に入らないのか、力任せに機器をひっくり返し、いま、まさに出産中の母親を家に連れ帰ろうとした。そして、何を思ったか、その母親も夫に従おうと、分娩台を降りてしまった。そのとき、胎児はようやく頭を出そうとしているところだった。
医師は慌てて警備員を呼び、駆けつけた彼らによって男は取り押さえられ、母親も再び分娩台へと戻された。しかし騒動の間に、胎児の心音は落ち、ようやく生まれ落ちたときには、その体は紫色で、あろうことか息をしていなかった。
その後、医師の適切な処置により、赤ん坊は息を吹き返した。けれど、出産中の騒動から、この両親に子育てが可能かと心配した医師により、児童相談所に連絡が入った。
『おじいさんやおばあさんなど、頼れる人はいますか』
『旦那さんに暴力は受けていないですか』
『子育てに必要なお金はありますか』
それらの質問に、母親は押し黙ったままだった。聞いているのかいないのか、それさえも判らないような態度だった。けれど、その態度は次の提案で一変した。
『もし、大変なようであったら、お子さんを乳児院で預かることもできますが』
そう言った瞬間、母親は断末魔のような叫びを上げた。驚いた看護師が『何事ですか!』、部屋に飛び込んで来る。
『あかちゃんは、わたしの! わたしのあかちゃん! どこ、あかちゃん、どこ!』
叫ぶ母親をなだめるために、新生児室から赤ん坊が連れてこられた。母親は赤ん坊が泣き出すほどに、きつく抱きしめた。その様子を見て、児童相談所の職員は曖昧な言葉を残し、病室を出た。現制度下では何よりも親権——産みの親の権利が強い、それをよく知っていたからである。親権に比べれば、子供の権利など鼻糞のようなものなのだ。
こうして、ひまわりと名付けられた赤ん坊は、癇癪持ちの父親と、軽度知的障碍のある母親の元で育てられることとなった。
とはいえ、父親はその性格のせいで仕事がなく、グループホームを逃げ出して来た母親にも金を得る術はなかった。それでも生活できたのは、物余りの時代のせいだった。
早朝、父親は自転車で町を一周し、住民が出したゴミを漁ってくる。その中には賞味期限切れの食べ物や、まだ十分に使える布団や衣類があり、それらはすべて家族の暮らす家に持ち込まれた。
父親が亡き両親から受け継いだ家は古く、雨風がしのげるだけマシといった代物で、その上、周囲を新築のマンションに囲まれて日も当たらない始末だったが、彼らがそれを気にすることはなかった。
それは赤ん坊——ひまわりも同じだ。廃棄弁当や、半分腐ったような果物から作られた母乳で、ひまわりはすくすくと育った。彼女は大人しく、まったく泣かない赤ん坊だった。母親は外出をしなかったため、ひまわりの世界は四畳半の部屋だけだった。それもひどく散らかっていて、いつでも生ゴミの匂いがプンプンしていた。母親は日がな一日、そのゴミの中から食べられるものを選んでもそもそと食べ、父親が帰ってくると、その機嫌に応じてひまわりをゴミの中に隠したり、たまに抱かせたりもした。
そんなときも大人しいひまわりを、父親はシケモクを咥えながらまんざらでもなさそうに見つめ、こう言うのだった。
『こんな俺でも子供が持てるなんてなあ』
それから決まって母親の方を睨みつけ、
『てめえは俺が拾ってやったんだからな、このできそこない!』
心無い言葉を浴びせるのだったが、すると母親は急に瞳を潤ませ、父親の口に吸い付いていくのだった。それから二人は服をはだけ、獣のような声をあげ始める。ゴミの山に放られたひまわりは、やはり泣き声をあげることもなく、じっと天井を見つめていた。声のする方へ顔を向けようとしても、未だ彼女の首は座っていない。
このとき、ひまわりは四ヶ月。泣きもしない代わりに笑いもしない赤ん坊は、その後、二歳になっても言葉を話すことはなく、小学校へ上がる年を過ぎても、座ったまま壁をじっと見つめているだけだった。
地域の保健師を名乗る女性が、児童調査と称してやってきたのはこの頃だ。実は、出産当時、ひまわりの出生届は出されておらず、彼女の戸籍はつくられていなかった。つまり、ひまわりはいままで、その存在の記録がまったくなかったのである。そのため、いまにも崩れそうな、この古い家に住んでいるのは、両親だけであると認識されていたのである。
その存在がなぜ明るみに出たのかといえば、近所からの情報だった。ちょうどひと月前、母親はひまわりの弟となる男子を出産しており、その泣き声が『うるさい』と話題になっていたのだ。
かくして家を訪ねた保健師が見たものは、異臭の中、来訪者を見ようともしない痩せたひまわりと、ゴミの上に寝かされた赤ん坊であった。
『ちょっと、お話を聞かせてもらいたいんですがね——』
そして、その新生児は一度も病院へかからずに自宅で生まれたこと、姉のひまわりはいつもあんな風だということ——つまり少しも笑わず、言葉も喋らないことを聞き出すと、顔色を変えてこう言った。
『一度、病院で検査を受けたほうがいいと思います』
『病院?』
折り悪く、そのとき父親がゴミ漁りから帰ったところだった。
『何だ、てめえ、うちのひまわりがおかしいとでもいいたいのか!』
検査を受けたほうがいい、そう言われただけで反応した父親も、薄々ひまわりがどこかおかしいと思っていたのだろう。彼は激昂し、保健師を怒鳴りつけた。
『出てけ! もう一度来てみろ、てめえの家族皆殺しにするぞ!』
泡を食った保健師は、転がるように家から飛び出していった。そのあとを父親は追いかけ、しばらくすると顔を真っ赤にしたまま帰宅した。怒りはまだ治まっていないらしい。恐ろしい顔で母親に言い渡した。
『三智子、ひまわりを学校へなんかやるんじゃねえぞ』
『どうして』
『やるんじゃねえって言ってんだよ! 俺みてえになっちまうだろうが!』
『どうなるの』
『うるせえ、てめえはもう黙ってろ!』
怒鳴られ、母親はいつものように父親の口に吸い付こうとしたが、このときばかりは拒否された。わけがわからず、母親はわんわん泣いた。大切にしていたはずのひまわりをハエたたきでバシバシと叩いた。それでもひまわりは壁を見つめていた。火がついたように、大人しく寝ていた赤ん坊が泣き出した。
『弁償だ、弁償してもらわねえと』
シケモクを咥え、ライターをカチカチ言わせながら、父親がつぶやいた。
『あの医者のせいだ。俺ぁずっとおかしいと思ってたんだ』
『なにが』
涙をぬぐいながら母親が聞き返した。
『あのときだよ、ひまわりが産まれたとき』
父親の顔色が赤を通り越して黒くなっていく。火花を散らすばかりのライターが、その怒りを加速させていく。
『忘れたのか? 産まれたとき、こいつは泣かなかったじゃねえか。あの医者のミスだ。ひまわりはあいつにおかしくされたんだ』
『ひまわり、おかしくないよ』
『てめえは黙ってろ!』
父親が怒鳴ったが、母親はもうその口に吸い付こうとはしなかった。
肌の白さからしろ と名付けられた弟は、泣き続けていた。『絶対あの医者に弁償させてやる』、ライターを壁に向かって投げつけると、父親は再び家を走り出て行った。母親も再びひまわりを叩き続けた。
あのとき物言わぬひまわりが何を考えていたのか、思い出すと私は涙が出そうになる。
それまであの部屋の中だけが世界であったひまわりにとって、外界からの訪問者がもたらしたものは大きかった。それを表す手段こそなかったが、彼女は訪問者の話を母親以上に理解し、小さな絶望を感じていたのだ。私は誰よりもそれを知っている。
そしてその絶望は、日を追って深くなった。
ゴミ漁りをやめ、毎日病院で喚き散らすことが日課となった父親と、弟を泣かせ、人が変わったようにひまわりを叩くようになった母親。父親の剣幕に恐れをなしてか、あの保健師の再訪はなく、日常の急激な変化に、ひまわりは少しずつ壊れていった。そしてあのとき、胸の靄が晴れていくように思いついたのだ。
この日常となった絶望から逃れる方法を。
そのとき、ひまわりは十二歳になっていた。同じ年に生まれた子供たちはもうすぐ小学校を卒業し、中学へ入る年だった。
小さな石油ストーブ一つしかない部屋は冷え込んでおり、窓は防寒のつもりか、母親によってダンボールで塞がれていて、開けようとしても開かなかった。外の光が入らない部屋はとても暗かった。そのせいで夜だと勘違いしているのか、それとも泣く元気すらないのか、しろ は一日中眠り続けていた。その隣で、母親も眠っていた。父親の高いびきが二階から聞こえていた。
壁を見つめていたひまわりは、いつか父親が投げ捨てたライターを握りしめていた。それを見よう見まねでカチリと握り込んだ。火花しか出ないライターは、それでもこの乾燥した空気とゴミの山に火をつけるのに十分な役割を果たした。
果たして、数回目の握り込みによる火花で、ビニル袋がじわりと溶けた。と思うと、炎はパッと燃え上がり、部屋を明るく照らし出した。その暖かさに、ひまわりはしばらくじっと見つめていた。眠っている母親が心地よさげにうーんと唸った。
——早くしなければ、火が回る。
私は動かないひまわりに懸命に呼びかけた。
——その前にやらなければならないことがある。
私の声が聞こえたのか、ひまわりはやっと炎から目を離し、よろよろと立ち上がった。不器用にしろ の足を掴み、ずるずると引きずるようにして部屋から出る。ごつん、敷居に後頭部を打ったしろ が小さく声をあげた。それも構わず、ひまわりは彼をゴミの中から引きずり出すと、玄関の鍵を開け、外へ弟を放り出した。うああああああ、泣き出したしろ の声を遮るようにドアを閉める。
——よくやったね、ひまわり。
私はそう彼女を励ました。
——でも忘れないで。もう一つ、やらなければならないことがある。
体を動かしたことのないひまわりは、傍目から見てもすでに疲労困憊だった。私の声を聞くだけでも彼女にとっては負担に違いないのだ。
——これで最後だから。
酷と知りながら、それでも私はそう言った。彼女は私に応えるように、精一杯体を動かし、四畳半に詰まっていたゴミを、玄関の前に積み上げた。
——そう、これでいい。
早くも古い柱を、染みだらけの天井板を舐め始めた炎を見つめ、私はつぶやいた。
——これで誰も逃げられない。
そのとき、ひまわりの見つめる先で、炎が石油ストーブに近づいた。
異変に気付いた母親が目を覚まし、奇声をあげる。二階からはいびきの代わりに、煙を吸い込んだような咳が聞こえる。
さようなら、そのとき私は話せないはずのひまわりの声を聞いた。
さようなら、私は返した。
次の瞬間、目の前のストーブが爆発した。
そしていま、私の前には三人の遺体が並べられている。父親と母親、それにひまわりの遺体だ。ひまわりが生み出した炎は、三人を焼き、家を焼いて、駆けつけた消防隊の手によって、ようやく収まった。
こうして三人の物語は終わりを迎えた。この話はこれでおしまいだ。
おしまいにするつもりだったのだが、ここで四人目のことを——物語の語り手である私のことを、最後に少しだけ、話しておくことにしよう。
私は死んだひまわりとは別の、もう一人のひまわりだ。ひまわりの肉体から離れてしまった、意識の部分と言ってもいい。私はひまわりとともに生まれ、ともに死ぬはずの存在であった。私はひまわりの一部だった。
それはこういうことだとも言える。
ひまわりが話したり考えたりできなかったのは、私という存在がいたからなのだ。ひまわりは肉体を、私が意識を担当していたからこそ、現実に目に見える形で存在していたひまわりは、自分では動けない人形だった。私という意識が、他人に見えることはないのだから。
けれど、確かに私はひまわりだった。ひまわりとして、その父親が酔って話す生い立ちを聞き、母親の意味不明な言葉の断片から、これまでの生活を理解した。
だからこそ、私はこうして三人の人生を語ることができたのだ。これで、私という意識がそれなりに優秀であることがわかってもらえたに違いない。
けれど、その優秀な意識をひまわりという肉体は表すことができなかった。
私は彼女だ。しかし、どんなに私がまとも な考えを持っていたとしても、彼女という肉体がそれを受け付けなかったのだ。
意識と肉体の不整合。
現実世界では、見えるものだけが尊重される。だからつまり、彼女は保健師の言った「検査」を受ければ、「障碍がある」ということになってしまうのだろう。
それは、両親も同じだっただろうか——私はおぼろげに考える。
考えることができなかった彼も、子供のようだった彼女も、その意識は鋭利でありながら、肉体がそれを表すことができないだけだったのかもしれない。
「赤ん坊は生きてるぞ!」
そのとき、誰かの声が聞こえて、私という意識は急にふにゃふにゃと形を失くしていく。
——ああ、このためだったのか。
私はひまわりという肉体が死んでなお、現実に残っていた意味を初めて理解する。
ひまわりは——私はしろ のことが心配だったのだ。
しろ が泣く声がひときわ大きくなり、それを慰める声とともに徐々に遠くなる。救急車のサイレンが鳴る。白い車体が慌ただしく発進する。
——さよなら、しろ 。
その後ろ姿を見送りながら、願わくば彼の肉体と意識が整合していますよう、私はそんな祈りを最後に光へ溶けて消えたのだった。
人間とはいかなるものか、人間に生まれた意味とはどういうものか——偉い哲学の先生だけではなく、そこらの思春期の中学生でも考えるようなことを、一度も考えたこともない三人だった。それどころか、その一人は自分を人間であると思ったことすらなかった。
まず、一人目の話をしよう。彼は男性で、体型は「ずんぐりむっくり」。食生活がどうとか、運動歴がどうというわけではなく、生まれつきの体格だ。その体つきがあまりに特異だったせいで、彼は幼い頃から周りにいじめられてきた。あだ名の「ずんぐりむっくり」は、彼の友達ではなく、その母親が笑いながら言った言葉が、そのまま村の子供達の間で使われた。妙に語呂の良いこの言葉で、子供達は楽しそうに彼を囃し立てた。
『ずんぐりむっくり、
『ずんぐりむっくり、のっぺらぼう!』
黴菌うんこはともかくとして、のっぺらぼうというのは、彼の目鼻があまりに小さいころからつけられた、もう一つのあだ名のようなものであった。
卵に目鼻、という言い回しが女性の美を表していたのは過去の話で、この昭和の時代、お茶の間を賑わすアイドルたちは、外国人風の大きな目をした者ばかりである。母親はそんな我が子を庇わないでもなかったが、「ずんぶりむっくり、のっぺらぼう!」、そんな声を聞くたびに、「ああ確かにその通りだ」などと、ふと納得してしまった頃から、彼を邪険にするようになった。
『お前は一体、誰に似たのかねぇ』
そんなことを言い始めたのも、その頃である。これが彼には衝撃であった。
俺にはどんな血が流れているのだろう——。
彼は正真正銘、彼の父と母の子であった。それゆえ「どんな血」ということもないのだが、これ以来、彼は自分の体の中には、得体の知れないものの血が流れていると、自然にそう思うようになったのである。
しかし、ここで注釈を入れておくと、その「思うようになった」という表現には、少々語弊がある。というのも、彼は元来、物をよく考えられぬ人間であった。無論、彼の頭の中のことだ。他人に理解できることなど、ほんの僅かに過ぎないだろう。それでも彼はものを思わぬ人間であったことを、私はここに念押ししておく。
だから、彼が自らの血を得体の知れないものと思ったということも、さらには母親の言葉による衝撃も、彼の中では決して理路整然とした形を取らなかった。それは思考ではなく、言語化による整理でもなく、それ以前の、ただ混沌の状態だった。その混沌は暗い霧となって、彼の心の中に棲み着いた。
結果、彼は恐ろしいほどの癇癪持ちとなった。
言葉を話せぬ赤ん坊が喚くしかないように、考えることさえできない彼は、怒りでそれを表現した。もちろんこの場合も、彼自身、なぜ自分がこんなに苛々しているのか、なぜ周囲に怒鳴り散らしているのか、まったく理解できていなかった。また、理解しようとさえせず、また、しようとしたとしてもできなかった。
そして、それは不幸にも、彼が大人になるまで続いた。いじめられて高校を中退し、癇癪のせいで仕事も続かない彼に、周りの人間は「どうしようもないやつだ」と関わりを避けるようになっていた。「あの『ずんぐりむっくり』は手の施しようがないよ」、と。
大人になっても、ずんぐりむっくりの体躯は相変わらずで、どこへ行っても、彼は子供の頃と同じに「ずんぐりむっくり」と呼ばれ続けた。けれど、かつて彼をからかった子供達は、当たり前のように成長していたため、もう面と向かって彼に意地悪をしなかった。きちんと彼から見えない場所で、通りを歩く「ずんぐりむっくり」を見ては、悪口を言い合ったり、くすくす笑ったりするだけなのであった。
ここで二人目の話に移ろう。二人目の主人公は女性であり、先の「ずんぐりむっくり」とは同い年でもある。彼女のあだ名は「みっちゃん」。本名の「三智子」を縮めただけの、可愛らしいものである。背は低く、色白でぽっちゃりしている。仕事はパンを作ること。彼女は障碍者の作業所に勤めており、その事実から判るように、彼女には軽度の知的障碍があった。
お金の勘定ができず、漢字や長い文章を読むことができない。外見は立派な大人だが、中身は幼稚園児という表現がぴったりくるような女性だった。
作業所を仕切っているのは、三間という物腰の柔らかい女性で、彼女は「この人がわたしのお母さんだったらいいのに」と思うほど気に入っていた。彼女はもう何年も「お母さん」に会っていない。三間の運営するこの作業所には寮が付属していて、彼女はほかの仲間たちと一緒にそこで暮らし、働いている。
食事や作業服、彼女のお小遣い、寮費、もろもろを引いた残りの給料はすべて「お母さん」へ送られているが、彼女はそれを知らないし、また、それがどういうことなのか理解できない。子供が毎日幼稚園へ行くように、働き、お小遣いをもらっているだけだ。体も頑丈そのものだったが、作業所へ来てからは何回か、腹痛で医者にかかることになった。かかるのはいつも同じ医者で、スポーツ選手のようにがっしりとした男の医者だ。その処置の恐ろしさのせいで、彼女は大きな男の人が怖かった。
けれど、「その人」のことは初めから怖くなかった。
それは、彼女が売り場にパンを並べていたときである。一人の男性が来店し、たまたまレジにいた三間を突然、怒鳴りつけた。怒声の内容は聞き取れなかったが、雷のような声だと彼女は思った。
雷は好きだった。空が光って、しばらくすると、どーんと体の中心に響くような音がする。それがとても気持ち良い。その雷のような声をあげながら、男は三間を殴った。三間は悲鳴をあげ、そこにぼうっと突っ立ったままの彼女に向かって「警察、警察を呼んでちょうだい!」と叫んだ。
——ケイサツはひゃくとおばん。
いくら彼女でもそれくらいは知っていたが、肝心の電話はレジの奥、三間と男が争う向こう側にある。どうしたらいいのかわからずに目をパチパチしていると、振り返った男と目が合った。大きな顔に似合わない、小さな目鼻。
ミーコちゃんみたい、反射的にそう思った。ミーコちゃんは優しい人が
「お願い、警察を呼んで」、もう一度、三間は彼女に懇願した。その顔は血だらけだった。しかし、彼女はその三間を無視して、男に近づいた。そして、その手を握り、微笑んだ。
三間の顔が苦く歪んだ。微笑む彼女は、あっけにとられたような男を連れ、店を出て行く。十八の年から、彼女の面倒を十四年も見て来た三間は、これから起こることを完全に理解していた。彼女はいまからあの男と寝る。そして、その後始末は、監督責任のある三間と、かかりつけの医者——スポーツ選手のようにがっしりとした、男性産科医なのであった。
そして話は三人目へと移る。
名前は
軽度とはいえ、知的障碍のある母親の出産に、総合病院の若い女性産科医はあらん限りのサポート体制を敷いて挑んだのだが、その本番は、子供の父親である男性によって、めちゃくちゃになってしまった。
彼は土足で分娩室へと踏み入り、そこにいた助産師たちを怒鳴り散らした。何が気に入らないのか、力任せに機器をひっくり返し、いま、まさに出産中の母親を家に連れ帰ろうとした。そして、何を思ったか、その母親も夫に従おうと、分娩台を降りてしまった。そのとき、胎児はようやく頭を出そうとしているところだった。
医師は慌てて警備員を呼び、駆けつけた彼らによって男は取り押さえられ、母親も再び分娩台へと戻された。しかし騒動の間に、胎児の心音は落ち、ようやく生まれ落ちたときには、その体は紫色で、あろうことか息をしていなかった。
その後、医師の適切な処置により、赤ん坊は息を吹き返した。けれど、出産中の騒動から、この両親に子育てが可能かと心配した医師により、児童相談所に連絡が入った。
『おじいさんやおばあさんなど、頼れる人はいますか』
『旦那さんに暴力は受けていないですか』
『子育てに必要なお金はありますか』
それらの質問に、母親は押し黙ったままだった。聞いているのかいないのか、それさえも判らないような態度だった。けれど、その態度は次の提案で一変した。
『もし、大変なようであったら、お子さんを乳児院で預かることもできますが』
そう言った瞬間、母親は断末魔のような叫びを上げた。驚いた看護師が『何事ですか!』、部屋に飛び込んで来る。
『あかちゃんは、わたしの! わたしのあかちゃん! どこ、あかちゃん、どこ!』
叫ぶ母親をなだめるために、新生児室から赤ん坊が連れてこられた。母親は赤ん坊が泣き出すほどに、きつく抱きしめた。その様子を見て、児童相談所の職員は曖昧な言葉を残し、病室を出た。現制度下では何よりも親権——産みの親の権利が強い、それをよく知っていたからである。親権に比べれば、子供の権利など鼻糞のようなものなのだ。
こうして、ひまわりと名付けられた赤ん坊は、癇癪持ちの父親と、軽度知的障碍のある母親の元で育てられることとなった。
とはいえ、父親はその性格のせいで仕事がなく、グループホームを逃げ出して来た母親にも金を得る術はなかった。それでも生活できたのは、物余りの時代のせいだった。
早朝、父親は自転車で町を一周し、住民が出したゴミを漁ってくる。その中には賞味期限切れの食べ物や、まだ十分に使える布団や衣類があり、それらはすべて家族の暮らす家に持ち込まれた。
父親が亡き両親から受け継いだ家は古く、雨風がしのげるだけマシといった代物で、その上、周囲を新築のマンションに囲まれて日も当たらない始末だったが、彼らがそれを気にすることはなかった。
それは赤ん坊——ひまわりも同じだ。廃棄弁当や、半分腐ったような果物から作られた母乳で、ひまわりはすくすくと育った。彼女は大人しく、まったく泣かない赤ん坊だった。母親は外出をしなかったため、ひまわりの世界は四畳半の部屋だけだった。それもひどく散らかっていて、いつでも生ゴミの匂いがプンプンしていた。母親は日がな一日、そのゴミの中から食べられるものを選んでもそもそと食べ、父親が帰ってくると、その機嫌に応じてひまわりをゴミの中に隠したり、たまに抱かせたりもした。
そんなときも大人しいひまわりを、父親はシケモクを咥えながらまんざらでもなさそうに見つめ、こう言うのだった。
『こんな俺でも子供が持てるなんてなあ』
それから決まって母親の方を睨みつけ、
『てめえは俺が拾ってやったんだからな、このできそこない!』
心無い言葉を浴びせるのだったが、すると母親は急に瞳を潤ませ、父親の口に吸い付いていくのだった。それから二人は服をはだけ、獣のような声をあげ始める。ゴミの山に放られたひまわりは、やはり泣き声をあげることもなく、じっと天井を見つめていた。声のする方へ顔を向けようとしても、未だ彼女の首は座っていない。
このとき、ひまわりは四ヶ月。泣きもしない代わりに笑いもしない赤ん坊は、その後、二歳になっても言葉を話すことはなく、小学校へ上がる年を過ぎても、座ったまま壁をじっと見つめているだけだった。
地域の保健師を名乗る女性が、児童調査と称してやってきたのはこの頃だ。実は、出産当時、ひまわりの出生届は出されておらず、彼女の戸籍はつくられていなかった。つまり、ひまわりはいままで、その存在の記録がまったくなかったのである。そのため、いまにも崩れそうな、この古い家に住んでいるのは、両親だけであると認識されていたのである。
その存在がなぜ明るみに出たのかといえば、近所からの情報だった。ちょうどひと月前、母親はひまわりの弟となる男子を出産しており、その泣き声が『うるさい』と話題になっていたのだ。
かくして家を訪ねた保健師が見たものは、異臭の中、来訪者を見ようともしない痩せたひまわりと、ゴミの上に寝かされた赤ん坊であった。
『ちょっと、お話を聞かせてもらいたいんですがね——』
そして、その新生児は一度も病院へかからずに自宅で生まれたこと、姉のひまわりはいつもあんな風だということ——つまり少しも笑わず、言葉も喋らないことを聞き出すと、顔色を変えてこう言った。
『一度、病院で検査を受けたほうがいいと思います』
『病院?』
折り悪く、そのとき父親がゴミ漁りから帰ったところだった。
『何だ、てめえ、うちのひまわりがおかしいとでもいいたいのか!』
検査を受けたほうがいい、そう言われただけで反応した父親も、薄々ひまわりがどこかおかしいと思っていたのだろう。彼は激昂し、保健師を怒鳴りつけた。
『出てけ! もう一度来てみろ、てめえの家族皆殺しにするぞ!』
泡を食った保健師は、転がるように家から飛び出していった。そのあとを父親は追いかけ、しばらくすると顔を真っ赤にしたまま帰宅した。怒りはまだ治まっていないらしい。恐ろしい顔で母親に言い渡した。
『三智子、ひまわりを学校へなんかやるんじゃねえぞ』
『どうして』
『やるんじゃねえって言ってんだよ! 俺みてえになっちまうだろうが!』
『どうなるの』
『うるせえ、てめえはもう黙ってろ!』
怒鳴られ、母親はいつものように父親の口に吸い付こうとしたが、このときばかりは拒否された。わけがわからず、母親はわんわん泣いた。大切にしていたはずのひまわりをハエたたきでバシバシと叩いた。それでもひまわりは壁を見つめていた。火がついたように、大人しく寝ていた赤ん坊が泣き出した。
『弁償だ、弁償してもらわねえと』
シケモクを咥え、ライターをカチカチ言わせながら、父親がつぶやいた。
『あの医者のせいだ。俺ぁずっとおかしいと思ってたんだ』
『なにが』
涙をぬぐいながら母親が聞き返した。
『あのときだよ、ひまわりが産まれたとき』
父親の顔色が赤を通り越して黒くなっていく。火花を散らすばかりのライターが、その怒りを加速させていく。
『忘れたのか? 産まれたとき、こいつは泣かなかったじゃねえか。あの医者のミスだ。ひまわりはあいつにおかしくされたんだ』
『ひまわり、おかしくないよ』
『てめえは黙ってろ!』
父親が怒鳴ったが、母親はもうその口に吸い付こうとはしなかった。
肌の白さから
あのとき物言わぬひまわりが何を考えていたのか、思い出すと私は涙が出そうになる。
それまであの部屋の中だけが世界であったひまわりにとって、外界からの訪問者がもたらしたものは大きかった。それを表す手段こそなかったが、彼女は訪問者の話を母親以上に理解し、小さな絶望を感じていたのだ。私は誰よりもそれを知っている。
そしてその絶望は、日を追って深くなった。
ゴミ漁りをやめ、毎日病院で喚き散らすことが日課となった父親と、弟を泣かせ、人が変わったようにひまわりを叩くようになった母親。父親の剣幕に恐れをなしてか、あの保健師の再訪はなく、日常の急激な変化に、ひまわりは少しずつ壊れていった。そしてあのとき、胸の靄が晴れていくように思いついたのだ。
この日常となった絶望から逃れる方法を。
そのとき、ひまわりは十二歳になっていた。同じ年に生まれた子供たちはもうすぐ小学校を卒業し、中学へ入る年だった。
小さな石油ストーブ一つしかない部屋は冷え込んでおり、窓は防寒のつもりか、母親によってダンボールで塞がれていて、開けようとしても開かなかった。外の光が入らない部屋はとても暗かった。そのせいで夜だと勘違いしているのか、それとも泣く元気すらないのか、
壁を見つめていたひまわりは、いつか父親が投げ捨てたライターを握りしめていた。それを見よう見まねでカチリと握り込んだ。火花しか出ないライターは、それでもこの乾燥した空気とゴミの山に火をつけるのに十分な役割を果たした。
果たして、数回目の握り込みによる火花で、ビニル袋がじわりと溶けた。と思うと、炎はパッと燃え上がり、部屋を明るく照らし出した。その暖かさに、ひまわりはしばらくじっと見つめていた。眠っている母親が心地よさげにうーんと唸った。
——早くしなければ、火が回る。
私は動かないひまわりに懸命に呼びかけた。
——その前にやらなければならないことがある。
私の声が聞こえたのか、ひまわりはやっと炎から目を離し、よろよろと立ち上がった。不器用に
——よくやったね、ひまわり。
私はそう彼女を励ました。
——でも忘れないで。もう一つ、やらなければならないことがある。
体を動かしたことのないひまわりは、傍目から見てもすでに疲労困憊だった。私の声を聞くだけでも彼女にとっては負担に違いないのだ。
——これで最後だから。
酷と知りながら、それでも私はそう言った。彼女は私に応えるように、精一杯体を動かし、四畳半に詰まっていたゴミを、玄関の前に積み上げた。
——そう、これでいい。
早くも古い柱を、染みだらけの天井板を舐め始めた炎を見つめ、私はつぶやいた。
——これで誰も逃げられない。
そのとき、ひまわりの見つめる先で、炎が石油ストーブに近づいた。
異変に気付いた母親が目を覚まし、奇声をあげる。二階からはいびきの代わりに、煙を吸い込んだような咳が聞こえる。
さようなら、そのとき私は話せないはずのひまわりの声を聞いた。
さようなら、私は返した。
次の瞬間、目の前のストーブが爆発した。
そしていま、私の前には三人の遺体が並べられている。父親と母親、それにひまわりの遺体だ。ひまわりが生み出した炎は、三人を焼き、家を焼いて、駆けつけた消防隊の手によって、ようやく収まった。
こうして三人の物語は終わりを迎えた。この話はこれでおしまいだ。
おしまいにするつもりだったのだが、ここで四人目のことを——物語の語り手である私のことを、最後に少しだけ、話しておくことにしよう。
私は死んだひまわりとは別の、もう一人のひまわりだ。ひまわりの肉体から離れてしまった、意識の部分と言ってもいい。私はひまわりとともに生まれ、ともに死ぬはずの存在であった。私はひまわりの一部だった。
それはこういうことだとも言える。
ひまわりが話したり考えたりできなかったのは、私という存在がいたからなのだ。ひまわりは肉体を、私が意識を担当していたからこそ、現実に目に見える形で存在していたひまわりは、自分では動けない人形だった。私という意識が、他人に見えることはないのだから。
けれど、確かに私はひまわりだった。ひまわりとして、その父親が酔って話す生い立ちを聞き、母親の意味不明な言葉の断片から、これまでの生活を理解した。
だからこそ、私はこうして三人の人生を語ることができたのだ。これで、私という意識がそれなりに優秀であることがわかってもらえたに違いない。
けれど、その優秀な意識をひまわりという肉体は表すことができなかった。
私は彼女だ。しかし、どんなに私が
意識と肉体の不整合。
現実世界では、見えるものだけが尊重される。だからつまり、彼女は保健師の言った「検査」を受ければ、「障碍がある」ということになってしまうのだろう。
それは、両親も同じだっただろうか——私はおぼろげに考える。
考えることができなかった彼も、子供のようだった彼女も、その意識は鋭利でありながら、肉体がそれを表すことができないだけだったのかもしれない。
「赤ん坊は生きてるぞ!」
そのとき、誰かの声が聞こえて、私という意識は急にふにゃふにゃと形を失くしていく。
——ああ、このためだったのか。
私はひまわりという肉体が死んでなお、現実に残っていた意味を初めて理解する。
ひまわりは——私は
——さよなら、
その後ろ姿を見送りながら、願わくば彼の肉体と意識が整合していますよう、私はそんな祈りを最後に光へ溶けて消えたのだった。