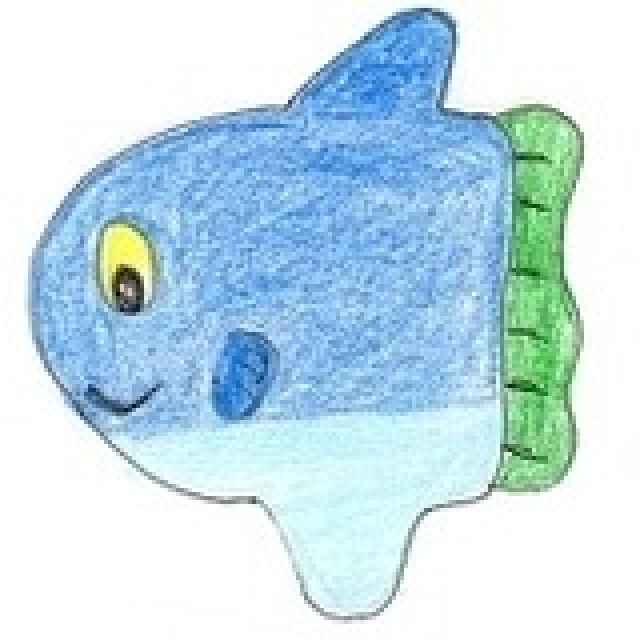第1話 年の暮に
文字数 3,658文字
木枯らしが身を刻むように吹いている。松蔵が仕事で使う藁を大八車に乗せて家に戻って見ると、地主でもある庄屋の使いが待っていた。知った顔だった。下男をしている作造と言う四十過ぎの背の低い男だと思い出した。
「帰って来るのを待っていたんだよ」
作造は躰を小刻みにゆすりながらホッとした表情を浮かべた。
「それはすいませんね。正月用の注連縄を作る藁を実家に取りに行っていたものでして」
作造が躰を揺すっていたのは、木枯らしで体が冷えないようにするためだった。もう十二月で江戸では木枯らしが吹き始めていた。今年は冬が長くなりそうだと松蔵は思っていた。彼の仕事は藁を使って注連縄や松飾り等を作る事だった。それを作造が下男をしている庄屋に納める。庄屋はそれを将軍家や大名に納めるのだった。松蔵は庄屋から報酬を得て暮らしていた。
「庄屋さんが話があるから、遅くなっても良いから顔を出してくれと」
作造が用事の内容を伝える。松蔵は何の用事か大凡想像出来た。
「判りました。これを片付けたら伺いますとお伝え下さい」
「判った。頼んだよ」
作造はそう言うと踵を返して小走りに帰って行った。
「ごめんください。松蔵でございます」
二間ほどある門の脇の木戸をくぐり抜けて勝手口に回った。すると歳の頃なら十八歳ほどの丸顔の下女のたきが顔を出した。
「ああ、松蔵さん。旦那さまが待っているよ。足を洗って奥の間に行って」
「そうか奥の間か……やはり大事な用なのかな?」
「そうだね。出入りの者が奥の間に通されるなんて普通は無いからね」
松蔵はたきが出してくれた桶で脚を洗って、雑巾で拭いて土間から家の中に上がった。勝手知ったる屋敷だ。奥の間の場所も判っている。
長い廊下を足音をさせぬ様に進む。屋敷の中では奉公人が幾人も自分の仕事をしていた。この庄屋の家は先祖は武士だったそうだ。南北朝の戦いで破れ、仲間数人とこの地に逃げ延びたのだと言う。そして当時未開だったこの地を仲間と開拓して住み着いたのだそうだ。だから隣の村も、その隣の村の庄屋もその仲間だった者の子孫だ。今でも交流があり仲が良いそうだ。でも、松蔵にはそんな云わくは、全く関係の無い事だ。関係があるのは将軍家や大名に松飾りや注連縄を納める時に松蔵も同行する事で、大八車には何やら物々しい事が書かれた立て札が刺さっており、何でもそれ自体が十万石の格式があるのだという。江戸城は庶民は入れないので、格式だけでも大名と同格になる必要がある。その札はその印なのだそうだ。
廊下の先座敷には灯りが灯っていた。その座敷の障子の前で座り
「松蔵でございます」
そう声を掛けると座敷の中から
「おお、ご苦労様、入ってくれ」
聞き慣れた声が返って来た。その声でに静かに障子を開けると座敷には庄屋の他に見知った顔が二つあった。一人は松蔵の女房のしずだった。もう一人はしずが手伝いに行っている酒屋の伊勢屋の番頭だった。二人がここに居ると言う事で、松蔵は呼び出された訳が自分の想像通りだったと直感した。
女房のしずは松蔵の稼ぎだけでは苦しいので村外れにある酒屋の伊勢屋に手伝いに行っていた。伊勢屋はこのあたりでは一番大きな店で手広く事業を行っていた。
松蔵は庄屋の前に座った。その庄屋の後ろに二人が控えていた。
「この二人がここに居ると言う事で大体の事は判ったと思うがな。実はお前に三行半を書いて欲しいのだよ」
庄屋は言い難そうに語ると
「実はな、しずさんのお腹には番頭さんの子が居るそうなんだ。番頭さんは年が明ければ暖簾分けして貰えるそうだ。つまりお前さんが別れてくれたら暖簾分けした新しい店の女将さんになると言う事なんだ。お前にも色々とあるだろうが、ここは黙って別れてくれないだろうか」
女房のしずが勤め先の番頭と深い関係だと言う事は判っていた。一月に数日
「棚卸しで忙しいから今夜は店に泊まるから」
とか、あるいは
「明日の朝は早いから今夜のうちに店に行っているから」
などと言って家に帰って来なかったからだ。いくら何でもそれがおかしいと言う事は判る。その相手が店の一番番頭だと言う事も知っていた。
松蔵は、本気にならなければ、それでも良いと思っていた。今年二十四になるしずとの間には子供も居なかった。作らない訳ではなかったが出来なかったのだ。相性が悪かったのだと思っていた。
しずが伊勢屋に行くようになってからは夫婦の間には関係がほとんど無くなった。番頭と関係を持ったのも、そんな事が影響したのも知れなかった。
「どうかね」
庄屋が松蔵の返事を促す。
「そうですか、子供まで出来たんじゃしょうがないですね。判りました」
半分は決断していた。庄屋の後ろで手を握り合ってる二人を見ては未練は起きなかった。松蔵は二人に向かって
「一刻でも早く荷物を取りに来てくれ」
そう告げると庄屋に
「それでは、ごめんください」
そう言って頭を下げて座敷を後にした。
松蔵が座敷から出て行くのを確認したしずは
「ああよかった。庄屋さん本当にありがとうございます! これで晴れて好いた人と夫婦になれます」
「しかし、番頭さんも結局は奉公人に手を付けた訳なんだが……」
庄屋の言葉にそれまで黙っていた番頭が
「はあ、申し訳ありません。でも、しずから夫婦のことや家の事を色々相談されているうちに情が移りましてね。それにしずは手前の好みだったもので」
「まあ、出来てしまったものは仕方ないが、しずさんや、そんなに松蔵が肌に合わなかったのかね」
庄屋に言われてしずは
「そうですね。わたし、嫌だったんです。藁まみれで汚くて陰気で口数が少なくて、面白い事を言う訳でもなく、黙って黙々と仕事ばかりしていて、しめ縄や松飾りなんて一年の半分しか仕事が無いじゃありませんか、だから暇な時は庄屋さんの所で働かせて貰えばって言っても、生返事ばかりで、元々親が決めた相手だったので情も移らなかったのですよ。それに比べ番頭さんは器量良しだし仕事は出来るし、優しいし」
庄屋はしずが番頭の惚気を言い出したので
「ああ、そうかい。判ったよ。伊勢屋さんとウチの関係だから今回は間に入ったが、番頭さん、こんなのはこれきりにしておくれよ。お前さんだって来年は支店の主になるんだから。しずさんお前さんも同じだ。一軒の店の女将さんになるんだからね」
庄屋の言葉に二人は項垂れるばかりだった。
二人を帰すと庄屋は煙草をくゆらせて
「松蔵には色々他にも仕事を斡旋させてやろう」
そう呟いて煙管を叩いた。
松蔵は台所の勝手口に向かっていた。さばさばした気持ちだった。これで家に帰って来ない女房の事を心配せずに済むと思った。たきが
「聞こえて来たから聴いちゃった。しずさん凄いね」
「ああ、知らぬは亭主ばかりなり。なんて言うけど亭主も知っていたからな。これで収まる所に収まって良かったのじゃ無いかな。幸い子供も居なかったしな」
土間の上がり口に腰掛けて草鞋を履いていると、脇の木戸からしずと番頭が手を繋いで出て行くのが見えた。何とも大胆だと思った。自分の前ではついぞそんな様子は見せた事が無かったと思った。
そんな事を考えていたら、たきが声を掛けた。
「ねえ松蔵さん。わたし、あとニ年で奉公が開けるの。そうしたらわたしを貰ってくれる?」
いきなり、そんな事を言いだした。確かにたきは今十八で奉公が開けると二十歳を過ぎてしまう。でも江戸では圧倒的に女性が少ないのだ。ここの江戸の在の村でもそれは同じで、だから亭主持ちのしずが簡単に亭主を乗り換える事が出来たのだ。法律的には女から離婚は出来なくても実際は数が少ない女性の思うがままだったのだ。だから江戸の男のかなりは一生独身と言うのも珍しく無かった。だから、たきの申し出が意外だった。
「たきちゃんならもっと色男が出来るんじゃないのかい。それに俺は今年二十六だぜ」
「わたし、面食いじゃ無いから。それに旦那さんはきっとこれから松蔵さんに色々な仕事を頼むと思うよ。旦那さんはそんな所があるから」
たきの言葉を信用した訳では無いが、自分には仕事しか無いと思っていた。
「半分だけ信じて二年待つよ」
そんな言葉が口から出た
「あ、松蔵さん笑った」
たきのその言葉で、暫く笑っていない事に気がついた。
「そうか、そうだったか」
それを思い出させてくれた、たきに感謝した。
「じゃあな。また来るから。他に浮気するなよ」
「しないよ」
そんな声に送られて表に出ると白いものがちらほらと舞っていた。
「おい、たきちゃんや。初雪だぞ。どうりで寒いと思ったよ」
「ああ本当だ。もう正月だからね」
松蔵は、たきと並んでいつまでも雪を眺めていたいと思った。
<了>
「帰って来るのを待っていたんだよ」
作造は躰を小刻みにゆすりながらホッとした表情を浮かべた。
「それはすいませんね。正月用の注連縄を作る藁を実家に取りに行っていたものでして」
作造が躰を揺すっていたのは、木枯らしで体が冷えないようにするためだった。もう十二月で江戸では木枯らしが吹き始めていた。今年は冬が長くなりそうだと松蔵は思っていた。彼の仕事は藁を使って注連縄や松飾り等を作る事だった。それを作造が下男をしている庄屋に納める。庄屋はそれを将軍家や大名に納めるのだった。松蔵は庄屋から報酬を得て暮らしていた。
「庄屋さんが話があるから、遅くなっても良いから顔を出してくれと」
作造が用事の内容を伝える。松蔵は何の用事か大凡想像出来た。
「判りました。これを片付けたら伺いますとお伝え下さい」
「判った。頼んだよ」
作造はそう言うと踵を返して小走りに帰って行った。
「ごめんください。松蔵でございます」
二間ほどある門の脇の木戸をくぐり抜けて勝手口に回った。すると歳の頃なら十八歳ほどの丸顔の下女のたきが顔を出した。
「ああ、松蔵さん。旦那さまが待っているよ。足を洗って奥の間に行って」
「そうか奥の間か……やはり大事な用なのかな?」
「そうだね。出入りの者が奥の間に通されるなんて普通は無いからね」
松蔵はたきが出してくれた桶で脚を洗って、雑巾で拭いて土間から家の中に上がった。勝手知ったる屋敷だ。奥の間の場所も判っている。
長い廊下を足音をさせぬ様に進む。屋敷の中では奉公人が幾人も自分の仕事をしていた。この庄屋の家は先祖は武士だったそうだ。南北朝の戦いで破れ、仲間数人とこの地に逃げ延びたのだと言う。そして当時未開だったこの地を仲間と開拓して住み着いたのだそうだ。だから隣の村も、その隣の村の庄屋もその仲間だった者の子孫だ。今でも交流があり仲が良いそうだ。でも、松蔵にはそんな云わくは、全く関係の無い事だ。関係があるのは将軍家や大名に松飾りや注連縄を納める時に松蔵も同行する事で、大八車には何やら物々しい事が書かれた立て札が刺さっており、何でもそれ自体が十万石の格式があるのだという。江戸城は庶民は入れないので、格式だけでも大名と同格になる必要がある。その札はその印なのだそうだ。
廊下の先座敷には灯りが灯っていた。その座敷の障子の前で座り
「松蔵でございます」
そう声を掛けると座敷の中から
「おお、ご苦労様、入ってくれ」
聞き慣れた声が返って来た。その声でに静かに障子を開けると座敷には庄屋の他に見知った顔が二つあった。一人は松蔵の女房のしずだった。もう一人はしずが手伝いに行っている酒屋の伊勢屋の番頭だった。二人がここに居ると言う事で、松蔵は呼び出された訳が自分の想像通りだったと直感した。
女房のしずは松蔵の稼ぎだけでは苦しいので村外れにある酒屋の伊勢屋に手伝いに行っていた。伊勢屋はこのあたりでは一番大きな店で手広く事業を行っていた。
松蔵は庄屋の前に座った。その庄屋の後ろに二人が控えていた。
「この二人がここに居ると言う事で大体の事は判ったと思うがな。実はお前に三行半を書いて欲しいのだよ」
庄屋は言い難そうに語ると
「実はな、しずさんのお腹には番頭さんの子が居るそうなんだ。番頭さんは年が明ければ暖簾分けして貰えるそうだ。つまりお前さんが別れてくれたら暖簾分けした新しい店の女将さんになると言う事なんだ。お前にも色々とあるだろうが、ここは黙って別れてくれないだろうか」
女房のしずが勤め先の番頭と深い関係だと言う事は判っていた。一月に数日
「棚卸しで忙しいから今夜は店に泊まるから」
とか、あるいは
「明日の朝は早いから今夜のうちに店に行っているから」
などと言って家に帰って来なかったからだ。いくら何でもそれがおかしいと言う事は判る。その相手が店の一番番頭だと言う事も知っていた。
松蔵は、本気にならなければ、それでも良いと思っていた。今年二十四になるしずとの間には子供も居なかった。作らない訳ではなかったが出来なかったのだ。相性が悪かったのだと思っていた。
しずが伊勢屋に行くようになってからは夫婦の間には関係がほとんど無くなった。番頭と関係を持ったのも、そんな事が影響したのも知れなかった。
「どうかね」
庄屋が松蔵の返事を促す。
「そうですか、子供まで出来たんじゃしょうがないですね。判りました」
半分は決断していた。庄屋の後ろで手を握り合ってる二人を見ては未練は起きなかった。松蔵は二人に向かって
「一刻でも早く荷物を取りに来てくれ」
そう告げると庄屋に
「それでは、ごめんください」
そう言って頭を下げて座敷を後にした。
松蔵が座敷から出て行くのを確認したしずは
「ああよかった。庄屋さん本当にありがとうございます! これで晴れて好いた人と夫婦になれます」
「しかし、番頭さんも結局は奉公人に手を付けた訳なんだが……」
庄屋の言葉にそれまで黙っていた番頭が
「はあ、申し訳ありません。でも、しずから夫婦のことや家の事を色々相談されているうちに情が移りましてね。それにしずは手前の好みだったもので」
「まあ、出来てしまったものは仕方ないが、しずさんや、そんなに松蔵が肌に合わなかったのかね」
庄屋に言われてしずは
「そうですね。わたし、嫌だったんです。藁まみれで汚くて陰気で口数が少なくて、面白い事を言う訳でもなく、黙って黙々と仕事ばかりしていて、しめ縄や松飾りなんて一年の半分しか仕事が無いじゃありませんか、だから暇な時は庄屋さんの所で働かせて貰えばって言っても、生返事ばかりで、元々親が決めた相手だったので情も移らなかったのですよ。それに比べ番頭さんは器量良しだし仕事は出来るし、優しいし」
庄屋はしずが番頭の惚気を言い出したので
「ああ、そうかい。判ったよ。伊勢屋さんとウチの関係だから今回は間に入ったが、番頭さん、こんなのはこれきりにしておくれよ。お前さんだって来年は支店の主になるんだから。しずさんお前さんも同じだ。一軒の店の女将さんになるんだからね」
庄屋の言葉に二人は項垂れるばかりだった。
二人を帰すと庄屋は煙草をくゆらせて
「松蔵には色々他にも仕事を斡旋させてやろう」
そう呟いて煙管を叩いた。
松蔵は台所の勝手口に向かっていた。さばさばした気持ちだった。これで家に帰って来ない女房の事を心配せずに済むと思った。たきが
「聞こえて来たから聴いちゃった。しずさん凄いね」
「ああ、知らぬは亭主ばかりなり。なんて言うけど亭主も知っていたからな。これで収まる所に収まって良かったのじゃ無いかな。幸い子供も居なかったしな」
土間の上がり口に腰掛けて草鞋を履いていると、脇の木戸からしずと番頭が手を繋いで出て行くのが見えた。何とも大胆だと思った。自分の前ではついぞそんな様子は見せた事が無かったと思った。
そんな事を考えていたら、たきが声を掛けた。
「ねえ松蔵さん。わたし、あとニ年で奉公が開けるの。そうしたらわたしを貰ってくれる?」
いきなり、そんな事を言いだした。確かにたきは今十八で奉公が開けると二十歳を過ぎてしまう。でも江戸では圧倒的に女性が少ないのだ。ここの江戸の在の村でもそれは同じで、だから亭主持ちのしずが簡単に亭主を乗り換える事が出来たのだ。法律的には女から離婚は出来なくても実際は数が少ない女性の思うがままだったのだ。だから江戸の男のかなりは一生独身と言うのも珍しく無かった。だから、たきの申し出が意外だった。
「たきちゃんならもっと色男が出来るんじゃないのかい。それに俺は今年二十六だぜ」
「わたし、面食いじゃ無いから。それに旦那さんはきっとこれから松蔵さんに色々な仕事を頼むと思うよ。旦那さんはそんな所があるから」
たきの言葉を信用した訳では無いが、自分には仕事しか無いと思っていた。
「半分だけ信じて二年待つよ」
そんな言葉が口から出た
「あ、松蔵さん笑った」
たきのその言葉で、暫く笑っていない事に気がついた。
「そうか、そうだったか」
それを思い出させてくれた、たきに感謝した。
「じゃあな。また来るから。他に浮気するなよ」
「しないよ」
そんな声に送られて表に出ると白いものがちらほらと舞っていた。
「おい、たきちゃんや。初雪だぞ。どうりで寒いと思ったよ」
「ああ本当だ。もう正月だからね」
松蔵は、たきと並んでいつまでも雪を眺めていたいと思った。
<了>