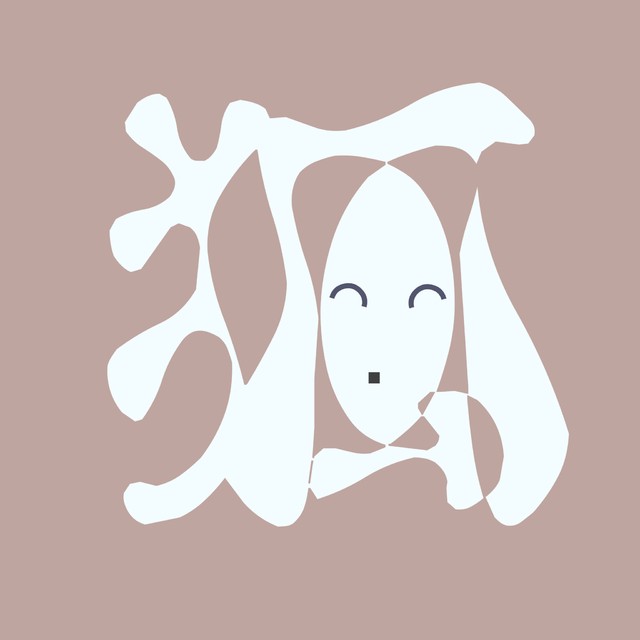どんまい
文字数 3,138文字
「バレンタインって春の季語なんだって」
二月十四日の昼休み。学校の屋上の、さらに上の階段室の上。冬らしからぬ陽気につられて来てみたら、また先客に結奈がいて、そんなことを言う。
寒凪 というのだろうか。朝の冷え込みは冬らしいものだったけれど、陽が高くなるにつれてウォーターブルーの空は優しさを増している。風もほとんどなく、季節外れのと言うか、まさに春の季語に相応しい穏やかな日和になっていた。
「暦の上では立春を過ぎているから、春なんだろうな」
二人並んで北側の出っ張りに腰掛けて、南の空を見上げていた。ここに座っていると陽が良く当たって暖かい。屋上に誰か来ても見えないけれど、向こうから見られることもない。もともとは一人になれる場所として見つけたのに、最近では結奈のせいで二人でいることが増えている。
「ああ、暦。そういうことか。わたしはてっきり告白が上手くいったら春が来るからだと思ったよ」
結奈は去年の秋に転校してきた。可憐という言葉を具現化したかのような容姿に目が眩んで多くの男子が彼女に推し変したのも束 の間 、そのドライで男前な性格が知れ渡るや、彼らは蜘蛛の子のように散ってしまった。
「義理チョコのひとつも貰 えない男子にしてみたら春どころじゃない。厳冬真っ只中だぞ。小島よしおばりにバレンタインなんか関係ねえって自分に言い聞かせている五軍男子の心中も察して欲しいもんだ」
「誰よ、小島よしおって」
「知らないのか? 芸人だよ」
「ああ、大島って呼ばれて小島だよって返す、あの」
「違う」
チョコのやり取りをしない男女間では暗黙の禁句であるはずのバレンタインという言葉。それをさらりと口にするあたりからも彼女の性格の一端が窺 い知れる。
「それにしてもバレンタイン当日に屋上になんか来るもんじゃないな」
先ほどからカップルが二組、ちょうど入れ替わるようにやって来てはチョコ贈呈の儀式が行われていた。
「ま、バレンタインだからね」
その矢先、また扉が開く音がした。この昼休み三組目のカップルの入場だ。生徒会あたりが整理券でも配布しているのか、うまい具合に時間をずらしてやって来る。
「妬かない妬かない。モテない男の僻 みはみっともないよ」
「妬いてないし」
「可哀想に。誰からも貰えそうにないの?」
「うるさい。こんなふうにおまえと一緒にいることが多くなって、他の女子が遠慮してるんだ。きっとそうだ」
「おまえって言うな」
彼女はすぐにそう言って怒る。けれど、じゃあ何と呼べばいいのか分からない。
君?
あなた?
結奈……いやいや。
だから結局またすぐにおまえと言ってしまう。
「チョコを貰えないのがわたしのせいだって言うの? 人のせいにするなんて潔くないなあ。自分に男としての魅力が足りてないからだって思わないの?」
「余計なお世話だ」
「あ、そういえば桐田先輩からもチョコを貰ったことないのかしら?」
唐突かつ無神経に、内角高めにエグい剛速球を投げられた。ほとんどビーンボールだ。
「な、何でそんなこと訊くんだよ」
「別に。ただの好奇心」
飲み込んだ言葉が喉に詰まりそうになった。立ち上がって結奈から離れ、その場に寝転がった。素直に認めよう。逃げたのだ。けれど、あろうことか彼女も隣に並んで寝転ぶではないか。
「制服が汚れるぞ……」
屋上も土足ではなく上履きで来てはいるものの、吹きっさらしには違いない。
「自分だって」
座っていた時と距離感は変わらない。なのに妙な緊張感に包まれるのを感じた。
結奈が言った桐田先輩——真衣は僕の幼馴染で、下の名前で呼び合う仲だった。真衣の方が学年が一つ上になる。家が近所で今でも家族ぐるみの付き合いは続いている。幼い頃は一つの年齢差なんて有って無きが如し。なのに中学高校と進むに連れて開くはずのない年齢差が開いたかの如く、二人の距離は遠のいた。その距離に比例するかのように僕ばかりが一方的に恋心を募らせている。
結奈は転校して来てすぐに真衣が部長を務める茶道部に入った。それをきっかけに、どうやってか僕たちが幼馴染みであることを嗅ぎつけたらしいのだ。
三組目のカップルが退場したかと思ったら、またすぐに四組目が入場してきた。こうなると、いよいよ他に何組も階段に並んで順番待ちをしているとしか思えない。
——とっとと済ませていなくなってくれ。
頭の中で悪態をついた時、今上がって来たカップルの話し声が聞こえてきた。盗み聞きをしようなどと思ってはいないのだけれど、前の三組よりも近くで儀式を始めたらしく、勝手に聞こえてきてしまう。
そして、その女子の方の声はどこか琴線に触れる声でもあった。
「……くん、ごめんね。昼休みに呼び出したりして。放課後は練習で忙しそうだからさ——」
間違いない。真衣の声だ。
確信しつつも認めたくない自分がいた。
静かに立ち上がって壁際まで進み、そっと下を覗き見た。
向かい合う男女が見えた。チョコが入っているのであろう小さな箱を持っている女子——それは間違いなく真衣だった。ついでに男子の方にも見覚えがあった。
「うわっ、立脇 弦 だ」
小さく驚きの声を上げたのは、いつの間にかすぐ隣に来て同じように覗き込んでいた結奈だった。さらに彼女は余計な解説を加える。
「サッカー部のキャプテン。我が校最強キャラ。まさにラスボス」
僕は見るのをやめ、壁にもたれ掛かるようにしてその場に座り込んだ。
少し前、サッカー部が何かの大会で優勝したとかで全校朝礼で表彰されていたのを覚えている。そうでなくてもばりばりのヒエラルキートップたるサッカー部。しかもキャプテン。しかもイケメン。結奈の言う通り最強だ。
義理チョコ——のわけがない。
身体の中心に鉛の棒を突っ込まれたような気分になった。
「次の試合も頑張って」
「サンキュ。悪いな。なかなか約束が果たせなくて。忘れたわけじゃないから、必ず一緒に行こうな」
「大丈夫。分かってる。楽しみに待ってるから」
見るのをやめても音は届く。聞きたくもない会話が聞こえてしまう。デートの約束でもしているのだろうか。どうやら最近つき合い始めたばかりという関係でもなさそうだ。サッカー部のキャプテンと茶道部の部長。しかも美男美女とくれば、まるで漫画の主人公だ。
馬鹿だなあ、僕は。
何も知らないで、一人勝手に想いをこじらせて。
二人の距離が開いたなんて、錯覚でも勘違いでもなかった。
真衣はいつの間にか遠くに——、ずっと前に進んでいた。
僕は——、僕は——。
小さくため息をついたところで視線を感じた。
首を捻ると、またいつの間にか隣に座り込んでいた結奈と目が合った。
「何だよ?」
ほとんど声にはなっていなかったものの、口の動きだけでも伝わったらしい。同じくほとんど口の動きだけで言い返して来た。
「どんまい」
優しい空を見上げ、今度は体中の空気を入れ替えるほどの大きなため息をついた。
真衣たち二人の退場に合わせたかのように予鈴が鳴り、僕たちは黙って立ち上がった。
壁に埋め込まれた梯子 を伝 って屋上まで下りる。先に下りていた結奈が優しく俺の背中を払ってくれながら、容赦のない言葉を投げつけてきた。
「他人の初恋が終わった瞬間に立ち会ったのは初めてだよ」
まさにビーンボール。
「よくそんなふうに他人の傷口に塩を塗り込めるよな」
僕の文句はスルーされた。
「わたしの背中も払ってよ」
「……」
仕方なく払ってやる。
「ありがと」
結奈はこちらに向き直ると、ポケットから小さなチョコを一粒だけ取り出して差し出した。
「はい。残念賞」
「るせぇ」
それでも素直に受け取った僕は、その場でチョコの包装を解いて口に放り込んで噛み砕き、春の遠さを噛み締めた。
——了——
二月十四日の昼休み。学校の屋上の、さらに上の階段室の上。冬らしからぬ陽気につられて来てみたら、また先客に結奈がいて、そんなことを言う。
「暦の上では立春を過ぎているから、春なんだろうな」
二人並んで北側の出っ張りに腰掛けて、南の空を見上げていた。ここに座っていると陽が良く当たって暖かい。屋上に誰か来ても見えないけれど、向こうから見られることもない。もともとは一人になれる場所として見つけたのに、最近では結奈のせいで二人でいることが増えている。
「ああ、暦。そういうことか。わたしはてっきり告白が上手くいったら春が来るからだと思ったよ」
結奈は去年の秋に転校してきた。可憐という言葉を具現化したかのような容姿に目が眩んで多くの男子が彼女に推し変したのも
「義理チョコのひとつも
「誰よ、小島よしおって」
「知らないのか? 芸人だよ」
「ああ、大島って呼ばれて小島だよって返す、あの」
「違う」
チョコのやり取りをしない男女間では暗黙の禁句であるはずのバレンタインという言葉。それをさらりと口にするあたりからも彼女の性格の一端が
「それにしてもバレンタイン当日に屋上になんか来るもんじゃないな」
先ほどからカップルが二組、ちょうど入れ替わるようにやって来てはチョコ贈呈の儀式が行われていた。
「ま、バレンタインだからね」
その矢先、また扉が開く音がした。この昼休み三組目のカップルの入場だ。生徒会あたりが整理券でも配布しているのか、うまい具合に時間をずらしてやって来る。
「妬かない妬かない。モテない男の
「妬いてないし」
「可哀想に。誰からも貰えそうにないの?」
「うるさい。こんなふうにおまえと一緒にいることが多くなって、他の女子が遠慮してるんだ。きっとそうだ」
「おまえって言うな」
彼女はすぐにそう言って怒る。けれど、じゃあ何と呼べばいいのか分からない。
君?
あなた?
結奈……いやいや。
だから結局またすぐにおまえと言ってしまう。
「チョコを貰えないのがわたしのせいだって言うの? 人のせいにするなんて潔くないなあ。自分に男としての魅力が足りてないからだって思わないの?」
「余計なお世話だ」
「あ、そういえば桐田先輩からもチョコを貰ったことないのかしら?」
唐突かつ無神経に、内角高めにエグい剛速球を投げられた。ほとんどビーンボールだ。
「な、何でそんなこと訊くんだよ」
「別に。ただの好奇心」
飲み込んだ言葉が喉に詰まりそうになった。立ち上がって結奈から離れ、その場に寝転がった。素直に認めよう。逃げたのだ。けれど、あろうことか彼女も隣に並んで寝転ぶではないか。
「制服が汚れるぞ……」
屋上も土足ではなく上履きで来てはいるものの、吹きっさらしには違いない。
「自分だって」
座っていた時と距離感は変わらない。なのに妙な緊張感に包まれるのを感じた。
結奈が言った桐田先輩——真衣は僕の幼馴染で、下の名前で呼び合う仲だった。真衣の方が学年が一つ上になる。家が近所で今でも家族ぐるみの付き合いは続いている。幼い頃は一つの年齢差なんて有って無きが如し。なのに中学高校と進むに連れて開くはずのない年齢差が開いたかの如く、二人の距離は遠のいた。その距離に比例するかのように僕ばかりが一方的に恋心を募らせている。
結奈は転校して来てすぐに真衣が部長を務める茶道部に入った。それをきっかけに、どうやってか僕たちが幼馴染みであることを嗅ぎつけたらしいのだ。
三組目のカップルが退場したかと思ったら、またすぐに四組目が入場してきた。こうなると、いよいよ他に何組も階段に並んで順番待ちをしているとしか思えない。
——とっとと済ませていなくなってくれ。
頭の中で悪態をついた時、今上がって来たカップルの話し声が聞こえてきた。盗み聞きをしようなどと思ってはいないのだけれど、前の三組よりも近くで儀式を始めたらしく、勝手に聞こえてきてしまう。
そして、その女子の方の声はどこか琴線に触れる声でもあった。
「……くん、ごめんね。昼休みに呼び出したりして。放課後は練習で忙しそうだからさ——」
間違いない。真衣の声だ。
確信しつつも認めたくない自分がいた。
静かに立ち上がって壁際まで進み、そっと下を覗き見た。
向かい合う男女が見えた。チョコが入っているのであろう小さな箱を持っている女子——それは間違いなく真衣だった。ついでに男子の方にも見覚えがあった。
「うわっ、
小さく驚きの声を上げたのは、いつの間にかすぐ隣に来て同じように覗き込んでいた結奈だった。さらに彼女は余計な解説を加える。
「サッカー部のキャプテン。我が校最強キャラ。まさにラスボス」
僕は見るのをやめ、壁にもたれ掛かるようにしてその場に座り込んだ。
少し前、サッカー部が何かの大会で優勝したとかで全校朝礼で表彰されていたのを覚えている。そうでなくてもばりばりのヒエラルキートップたるサッカー部。しかもキャプテン。しかもイケメン。結奈の言う通り最強だ。
義理チョコ——のわけがない。
身体の中心に鉛の棒を突っ込まれたような気分になった。
「次の試合も頑張って」
「サンキュ。悪いな。なかなか約束が果たせなくて。忘れたわけじゃないから、必ず一緒に行こうな」
「大丈夫。分かってる。楽しみに待ってるから」
見るのをやめても音は届く。聞きたくもない会話が聞こえてしまう。デートの約束でもしているのだろうか。どうやら最近つき合い始めたばかりという関係でもなさそうだ。サッカー部のキャプテンと茶道部の部長。しかも美男美女とくれば、まるで漫画の主人公だ。
馬鹿だなあ、僕は。
何も知らないで、一人勝手に想いをこじらせて。
二人の距離が開いたなんて、錯覚でも勘違いでもなかった。
真衣はいつの間にか遠くに——、ずっと前に進んでいた。
僕は——、僕は——。
小さくため息をついたところで視線を感じた。
首を捻ると、またいつの間にか隣に座り込んでいた結奈と目が合った。
「何だよ?」
ほとんど声にはなっていなかったものの、口の動きだけでも伝わったらしい。同じくほとんど口の動きだけで言い返して来た。
「どんまい」
優しい空を見上げ、今度は体中の空気を入れ替えるほどの大きなため息をついた。
真衣たち二人の退場に合わせたかのように予鈴が鳴り、僕たちは黙って立ち上がった。
壁に埋め込まれた
「他人の初恋が終わった瞬間に立ち会ったのは初めてだよ」
まさにビーンボール。
「よくそんなふうに他人の傷口に塩を塗り込めるよな」
僕の文句はスルーされた。
「わたしの背中も払ってよ」
「……」
仕方なく払ってやる。
「ありがと」
結奈はこちらに向き直ると、ポケットから小さなチョコを一粒だけ取り出して差し出した。
「はい。残念賞」
「るせぇ」
それでも素直に受け取った僕は、その場でチョコの包装を解いて口に放り込んで噛み砕き、春の遠さを噛み締めた。
——了——