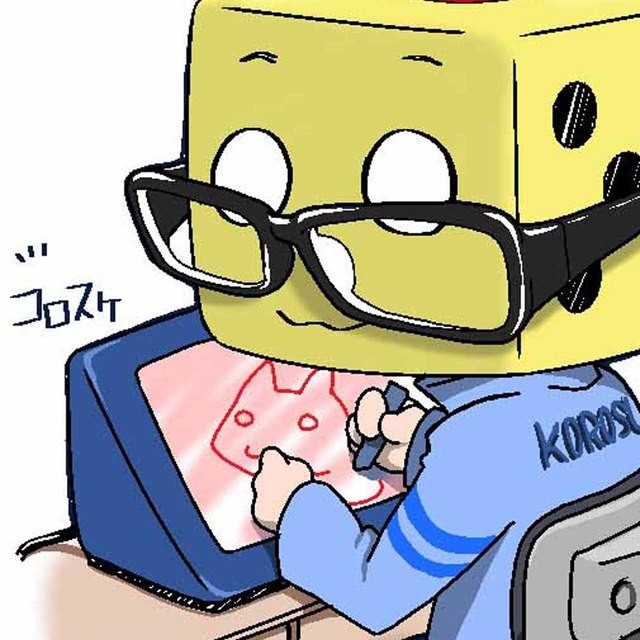第1話
文字数 22,161文字
ウラ×オモテ=
一枚のコインの、裏かオモテかと選択を迫られたとする。僕はこういう時、裏でも表でもないそれ以外の選択肢を探してしまう。それは子供のわがままなのか、それとも大人の妥協なのか。
「ただいま」
照りつける日差しから逃れるように、ひんやりとした玄関にカバンを置いた。
8月に入り、ますます蝉の合唱が盛んになって来た。世間はお盆休みでも、ゆっくり休めないのが受験生の哀しいところだ。高校からの帰宅を知らせる僕の声に、返事をする者は無く、シンとした静寂が孤独を知らせる。無言でワイシャツをソファに放り投げ、冷蔵庫へと直行する。確か昨日覗いた時点では、コーラがまだ残っていたはずだ。CMのように、シュワシュワと小気味よい音を立てて、氷に弾ける琥珀の液体。僕は喉にくる刺激を楽しみながら一気に飲み干した。
「ナニ飲んでんのよ」
「!ビックリした!いるなら返事ぐらいしろよ姉ちゃん……」
危うくコーラを吹き出しそうになった。突然背後から話しかけた姉は、Tシャツ短パンで濡れ髪を拭きながら立っていた。
「アタシが飲もうと思ってたのに、勝手に飲むなよバカ」
「蹴るなよ暴力姉!アネハラで訴えるぞ!」
姉は、高校を卒業するまで空手をやっていたせいか、とにかく気が荒い。気分が良くても悪くても、口と同時に手足が飛んでくるので、取り扱いに困ってしまう。
「コンビニ行って来いよ、今すぐダッシュで」
「やだよ外暑いし。自分で行けばいいじゃん」
「……仕方ないなあ。リョータが買いに行かないからアタシはコレで我慢してやろう」
そう言うと、姉は冷蔵庫の奥から缶ビールを取り出し、勢い良く栓を開けた。なんだよ最初っからそっちが目的だったんじゃん。ややこしい。
「そう言やリョータ宛に小包来てたわ」
「小包?誰から?」
「知らない」
「どこに?」
「知らない」
「ナニその分かんないもの見た!みたいな情報」
姉は自由すぎる。優しさとか、思いやりとか、そういう心のクッション的な柔らかさは、オークションに出したに違いない。
「アンタの友達なら見たわよ。なんとかって名前の悪ガキ。杉屋の前で突っ立ってわ」
「あいにく知り合いにナントカさんなんて人はいまセーン ……ゲフッ!」
姉は器用にも、冷蔵庫のドアを足で閉めながら、同時に肘で僕の横腹にツッこみを入れる。
僕は追撃を避けながら、今のクラスのメンバーの顔を浮かべてみるが、近所に住んでいるやつはいない、と首を傾げた。
「いたっつーの!賭けトランプかなんかで問題起こした、杉屋の横のマンションに住んでた」
「杉屋の横……?ひょっとしてオノケン!?」
「そう!それそれ!忘れもしないわあのガキ、初対面の私にカンチョーダッシュしやがって。乙女の肛門に指を突き立てるとか、万死に値するわ!今度見かけたら超殺すし」
たった今まで忘れてたくせに。何が忘れもしないだよ。それと、乙女は肛門とか超殺すとか口に出さん。
僕は姉の愚痴を聞きながら、小学生の時の苦い思い出を思い出していた。
5年生の時、僕には小野賢至という同級生がいた。
オノケンはとても明るい性格で、スポーツ万能、背も高くてクラスの中でも目立つ存在だった。特別頭が良いわけではなかったが、いたずらにかけては天才的で、先生や地域の大人達も彼には手を焼いていた。かと思えば、下級生の面倒をかいがいしく見たり、ボランティア清掃に積極的に参加したりと、真面目で優しい所もあった為、とにかく人気者だった。
同時期、TVかなにかのきっかけで、賭けトランプが流行したことがあった。
オノケンはそれを「お楽しみ会」と名付けて仲間内で遊んでいた。最初は少人数で、1円を賭けるだけのシンプルなルールだった。僕は最初、子供がやるようなギャンブルの真似事なんて、すぐに禁止されるとタカを括っていた。しかしイタズラの天才オノケンは、巧妙に、精緻に、賭けトランプのシステムを改革していった。
まず絶対大人には悟られないようにする。これがまず第1に守るべき絶対のルールだった。子供が隠れてやるような事に、渋い顔をしない大人なんているはず無いからだ。そして金銭のやり取りがバレ無いように、色分けした金券を作ったり、参加費として全員一律の金額を徴収することで、公平感を出したり、勝者を一人だけにする事で優越感を演出。さらにはトーナメント戦、タッグ戦、高額線と次々にイベントを開催した。その効果は絶大で、このブームが始まって1ヶ月足らずで、クラスのほとんどが参加するまでになっていた。
しかし、僕らを夢中にさせたこの「お楽しみ会」は、何の前触れもなく終わりを告げた。
オノケンが突然転校してしまったのだ。
週明けに担任からこの事実を聞かされた時、僕らはそれを理解できずにボーゼンとなった。
それからというもの、クラスはこの ”オノケンショック” からしばらく立ち直る事が出来ず、教室がどんよりと通夜のようになってしまった事を覚えている。
しかし、この後に起こった事と比較すると、”オノケンショック”さえもまだいい方だったと言わざるを得ないだろう。
僕は心にモヤモヤを抱えたまま自室へと戻った。ろくに別れを惜しむこともできなかったオノケンに再会したとしたら、どんな顔でいればいいのだろう。昔のように、子供の時のように、尊敬の眼差しを向けられるオノケンであって欲しいと朧げに考えていた。
再開の時は、意外にもすぐに訪れた。
自室には、姉の言っていた小包が僕の机の上に置いてあった。クッキーの缶ぐらいの大きさで、古びた新聞紙に包まれている。重さは片手で持ち上げられるほど、左右に振ってみると、カタカタという音ともに、何か硬いものが金属に当たる音がする。
僕はこんな物に全く覚えがなかった。また姉のイタズラかと思ったが、表面には住所と名前が達筆で書いてある。住所は近所、歩いて10分もかからない。そして宛名を読んで僕はドキッとした。
小野賢至
たった今、姉と話していた小学校時代の友人、オノケンの名前がそこにあった。
姉に問いただそうとリビングへ降りたが、そんなもの知らないと一蹴された。それどころか、再び飲み物を買ってこいとワガママを言う始末。結局僕は姉の暴力に屈し、飲み物を買いに行かされることになった。姉曰く、ビールとジュースは飲み物としてのコンセプトが違うので、ビールを飲んだ直後にジュースを所望することは全く正常であるとのことだった。将来、姉が結婚する事になったら、相手の男性に心から同情するとともに、茨の道を歩き出す今の気持ちを是非訪ねてみようと思った。
ついで、と言っては語弊があるが、小包を持って、元オノケンのウチに行ってみようと思った。確か聞いた話では、オノケンの父親はまだあそこに住んでいるらしい。
夏の季候特有の強烈な日差しも、徐々に陰り始めた道を進み、先にコンビニにいくかそれとも杉屋に行くか、迷った時、何となく杉屋の方向に足が向いた。
遠目からも、非常に怪しく見える人物がそこに立っていた。そいつは僕よりも10c mは背が高い男で、このクソ暑い中、黒いパーカーを着て目深にフードを被っている。ポケットに手をつっ込んだ姿勢で、ぼうっと杉屋の前で突っ立っていた。僕がそいつを目撃してから近づくまでの間、一向に動く気配を見せず、立ち尽くしたままだった。
僕はなんだか気味が悪いなと思いつつも、確認のため立ち止まる。そしてさりげなく視線を向けた瞬間に、そいつと目が合ってしまった。
数年ぶりと言えども、記憶の中の彼とイメージが一致するのに一秒とかからなかった。
間違いない。髪は伸びて、顔は大人っぽくなっていたが、あの切れ長な目は間違いなく小野賢至、オノケンだ。
オノケンは、自分からたった数メートルの場所で、不審な態度をとっている僕を明らかに見ていたが、突然くるりと背を向け、そのまま歩き出した。
「オノケン……」
思わず口をついて出た声は、彼の耳に届かなかったのか。それともあえてなのか。
オノケンは歩みを止める事なくそのまま小さくなって行く。
「オノケン!」
今度は、明らかに呼び止める意思を込めた声。
オノケンは立ち止まり、ゆるりと振り返る。そしてにやりと笑って見せた。
「リョータ……だよな?酒井 リョータ」
「ああ、久しぶりオノケン。もしかして今、スルーしようとした?」
「悪ぃ……その名前で呼ばれるの久しぶりでよ、自分の事だと思わなくて」
僕は最初、目の前にいる人物があのオノケンだという事に自信を持てなかった。
低い声のトーン、ゆっくりとした話し方。
真顔とも微笑とも取れる曖昧な表情、うつろな目の輝き。
記憶の中では、常に強烈なエネルギーを発散している太陽のようだったヤツが、本当に同一人物なのか?
「なんか……雰囲気変わったね、大人になった?」
「そう言うリョータは変わンねえな。何つーか戦隊モノのブルー?みてえな?」
しばらく話していると、次第に安心してきた。人間の芯の部分には、間違いなくあのオノケンがいる事を感じる。変わったと思ったのは、流れた時間と考えてよさそうだ。
「さっきウチの姉ちゃんがお前の事を見かけたって言ってたから、もしかしたらって思ってさ。気をつけろよ、カンチョーダッシュの件で姉ちゃんから殺害予告でてたから」
「お前ん家の姉ちゃんいつもそれな。それで何度も蹴られてっから俺」
ようやく安心する笑顔。
「今日は何か用事?またこっちに戻って来たとかなのか」
「ん……そういうワケじゃねえンだ。ま……ちょっとな」
しばしの沈黙。
じわじわと時間が経ち、どれ程深刻な理由を抱えているのか、僕の想像の選択肢が十を超えたあたりで、ようやくオノケンは口を開いた。
「杉屋のばーさん死んだんだってな」
「ああ……”100まで生きる”が口癖だったのに、あんな絵に描いたようなクソババアが、本当に死ぬなんて」
「俺なんて隣に住んでたから、顔を見る度に小言を言われてたンだぜ」
「オノケンは知らないかもだけど、杉屋が閉店セールやったんだ。その時、ばーさんの遺言で小学生は、タダだったらしいよ」
「何だよソレ!小学生の夢じゃん。駄菓子食べ放題とか」
杉屋は、オノケンの住んでいたマンションの隣りにあった駄菓子屋で、子供の頃毎日通った思い出がある。腰の曲がった妖怪みたいなばーさんが居て、礼儀とか挨拶に非常にうるさく、大声で挨拶しないと絶対に駄菓子売ってくれないのだ。近所の悪ガキ共の天敵みたいな存在だったが、ただうるさいだけのばーさんではなかった。悩みは親兄弟より、まずは杉屋のばーさんってほど頼りにされていた。子供の他愛のない小さな悩みを、人生の一大事であるかのように親身になって相談に乗り、それを乗り越えた時には誰よりも褒めて喜んでくれた。それゆえ杉屋はひっきりなしに子供が出入りして、ばーさんの怒鳴り声が絶えなかった。
「リョータは知らねえかも知んねえけど、あのばーさん”すず”って名前なんだぜ」
「ホントかよ!今年で一番知りたくなかった事実だわー」
軽口を叩いてみても、二人の笑いは湿り気を帯びていた。
身長はとうにばーさんを越えて、どんなに大人っぽくなっても、あのしわくちゃの笑顔の前ではいつだって子供に戻れた。
寂しくないわけがない。
オノケンはぼんやりとシャッターの閉まった杉屋を見ていた。
懐かしさのあまりつい忘れていたが、さっきの小包は、ひょっとしたらオノケンが直接僕の家に届けたのかもしれないと思いついた。何しろ数年ぶりに会った友人の名前が書かれた小包が、偶然にも再会した同じ日に、僕のうちに届けられるなんて都合のいい事があるワケない。
「オノケン。コレさっき家に届けられたらしいんだけど何か知ってる?」
オノケンは小包を一瞥しただけで、何も言わなかった。知っているなら知っている、知らないなら、思い出すようなリアクションがあってしかるべきだと思うが。
しかし彼は平坦な口調で答えた。
「リョータ。”お楽しみ会”の真実を知りたくないか?」
そう呟いた後の彼の目は、先ほどと変わらず、虚ろなままだった。
「小学生の賭けトランプぐらいで真実とか大袈裟な」
「そうかもな。でも何があったか全部は知らないだろう?」
「分かった、何だか面白そうだし。何をすればいい?」
「情報が欲しい。特に俺がなぜ”裏切り者”になったのかとか」
「知ってたのか……”セカンドインパクト”のこと……」
お楽しみ会は、管理者であるオノケンの転校を機に空中分解した。その存在と罪は、大人達に知られる事なく消え去るはずだった。オノケンがいなくなった事で、参加者のお金の貸し借りがわからなくなってしまっていた。それゆえゼロからの再開を望む声もあるにはあった。だが同時にその悪事が明るみに出て、糾弾される事を恐れていたし、絶対的なカリスマ性と、明晰な頭脳を持っていたオノケンの代わりをやろうという者は現れなかった。決して固く結束していた会ではなかったが、一様に連帯感みたいなものは、確かに感じていた。何より、絶対のルールとしてあった「大人に悟られないようにする」を守れなくなっては、デメリットしか存在しないだろう。
しかしお楽しみ会の思い出が、記憶の片隅に追いやられる前、突然僕は担任の山崎先生に呼び出された。
参加者の誰かが裏切り、“お楽しみ会”を告発したのだ。
後に僕らは”オノケンショック”に続く”セカンドインパクト”と呼び、吹き荒れる非難の嵐に翻弄された。クラス会議、児童会、職員会議、PTA。あらゆる所で議題に上り、繰り返し批判された。さすがに警察沙汰にはならなかったが、参加者の多さやシステムの巧妙さが問題視され、学校でも家でも厳しい監視がしばらく続いた。
個別の聴取は、オノケンが管理していた出納ノートを元に行われた。仲間内では、タイミング良く転校したオノケンが、バラしてお金を持ち逃げしたという噂が、まことしやかに囁かれていた。大人達が把握していた内容は、それ程に詳細だったし、本人が不在、更に批判される事に疲れ切っていた事も手伝って、誰かを張本人として吊るし上げなければ、日常生活をマトモに送れないまでになっていた。
しかし僕は、この噂を肯定する気にはなれなかった。オノケンが転校して、糾弾が始まるまで1ヶ月近く空いていたし、そうする理由が見つからない。突然理由も言わずいなくなるという、ある種裏切りにも等しい行為からすると、何か特殊な理由があった事は想像できるが。でもそこまで行けば、僕の想像以上の事があったしか言いようがない。
幸か不幸か、何年かぶりに、その答えを持つ本人に再会する事が出来た。
「お楽しみ会」の遺産
僕は、お金なんか欲しくないなんて言えるほど、善人でもない。しかし子供の頃の苦い思い出に関係するお金だとすれば、正直なところあまり関わりたくないのが本音だった。
「親父がさ、まだここに住んでんだ。それで流れてくるウワサを聞いて」
「……そう」
ウワサとはどこまでのウワサだろう。
単にお楽しみ会の事が明るみに出た、ぐらいか。それともオノケンが裏切り者と言われていた事なのか。8年ぶりに会った友人に、いきなり核心を突くような質問は出来ない。何しろ平和第一主義の戦隊ブルーの僕には、そんな必殺技が可能な心臓は装備されていない。
「じゃ行くか」
オノケンは立ち上がり、軽く尻の埃を叩く。
「ん?場所を変える?」
「場所というか、人かな」
「オノケン、もっと凡人でも分かるように解説してくれないか。誰もが君を理解できるほど、君の言動は分かりやすくないんだから」
「すぐにわかる」
悪戯小僧の笑い。
僕も立ち上がり、オノケンに続いた。ほんの数年前のことなのに、ずっと忘れていたこの感覚。それこそ一定の手順を必ず踏襲するお約束のように”すぐわかる”と先頭を歩くオノケンの背中を追った。
まだ空は明るく、時々体に当たる陽光にもはっきりと熱を感じる。暑さ寒さも彼岸までと言うが、夕暮れに近づくにつれて、急に過ごしやすくなった。
子供の頃は同じ道を歩きたくなくて、横道をへ逸れることがよくあった。それどころか人の家の庭先を、時には道なき道を突き進み、叱られることよりも、怪我をすることよりも、小さなドキドキを最優先して。
「この辺りは昔から変わらないな」
「古い家が多いからね」
僕らは、白壁の続く道を進み、立派な門構えの日本家屋の前を通りかかった。この一画は戦明治維新以前に建てられた家だと聞いた事がある。広く手入れされた日本庭園や大きな木造家屋が並び、ここだけ時代の流れなから取り残されたようにいつまでも変わらない。
途中、一件の家の門柱に野菜で作られた馬と牛が置いてあった。お盆の時期によく置いてある迎え火と送り火の精霊馬だ。死んだ人があの世から帰ってくる時は足の速い馬に乗り、帰る時は歩みの遅い牛に乗って帰る為に飾ってあり、出来るだけ長い時間家に滞在して欲しいと言う願いが込められていると言ういわれがある。
「ガキの頃はコレの意味も分かんねえで、よくイタズラしたなあ」
「僕は勝手にチワワとかにした事ある」
旧友と再会したせいか、どうしても昔を思い出すような発言になってしまう。昔のTV番組なんかを見て、父さんがよく言っていた。この頃は学生だったとか、あの頃は大変だったとか、今のやつらは楽をしすぎだとか。そんな姿をカッコ悪いなと苦々しく思っていた。
でもカッコ悪い僕は、いざ自分がその立場になってみると、やはりカッコ悪い。ばーさんが生きていれば、オノケンが転校していなければ、もっと幸せだっただろうと想像せずにはいられなかった。
後ろから走り寄ってくる足音に気づいたときはもう遅かった。
突然僕は突き飛ばされ、前へとよろめく。そしてその人物を確認する前に、容赦なく顎に掌底を喰らってしまう。
「よくも今更私の前に顔を出せたものね、賢至!覚悟しなさい!」
「久しぶり。お前は変わらねえな、元気……なことはたった今確認したぜ」
「なんだよいきなり、いったい誰……」
油断してた事もあって、かなり顎が痛い。しょっちゅう姉から攻撃されているので、咄嗟に受け身を取る習慣が身についてるとは言え、やはり痛いものは痛い。
「うるさいリョータ!でかくて邪魔なのよ!アンタはとりあえずこれ持って」
そう言うと彼女はそれを放り投げる。僕は慌てて手を伸ばし、何とかそれをキャッチした。
何コレ?シャベル?
彼女の破れたGジャンには、どこかで見たような『危険人物』と漢字で書かれたワッペン、薄い青のフレアスカートをひるがえし、両手を腰に仁王立ち。そして面倒くさそうに黒髪を背中へ払い、オノケンへと向き直った。
「言い訳があるなら今のうちに言いなさい。どんな訳でも許さないけど!」
「もしかして……桜井か?」
「もしかしなくても桜井よ。私がウルトラマンか新幹線に見えるなら今すぐ眼科に行きなさい」
この威嚇する猫みたいな女は、桜井れいなという生き物だ。5、6年生と同じクラスで、中学校も同じだった。吊り上がった大きな瞳でギロリと睨む。身長や髪型が、小学校の時からほとんど変わっていないので幼く見えるが、性格は猛獣のそれである。どんな有名人に似ているかと訊かれれば、ウルトラマンに似ている。どんな乗り物に似ているかと訊かれれば、新幹線に似ている。強さも早さもだ。
とにかく意味不明な理論をふりかざして、強引に物事を押し進めようとする為、その行動は理解しがたい。5年当時、体育の着替えで女子が教室を使うから、男子は渡り廊下で着替えろと言い出した。百歩譲って教室以外で着替えるにしても、何で夏暑く冬寒い渡り廊下なのかと反論すると、囮に決まっているじゃないバカと。
桜井曰く、アンタ達の裸なんて一円の価値もないんだから、せめて女子が着替えている間の囮になればいい。それが世の為人の為。抵抗は無意味、諦めなさいと。
あまりに僕の常識範囲外にあるものだから、女の子とか人間とかじゃなく、桜井れいなという生き物だと思うことにしている。
「いきなり酷すぎるだろ。僕が何したってんだ」
「私は賢至を狙ったわ。アンタが勝手に当たって来たのよ」
「加害者の台詞とは思えない……」
「リョータ、黙って。コイツったら、私に宝石をくれるって約束したくせに、次の週にいきなり転校して逃げたのよ!今度会ったら絶対掌底かますって決めてたわ!」
そう言って、オノケンの鼻先ギリギリまで人差し指を突きつける桜井。
ま、実際に掌底を喰らったのは酒井リョータな訳だが、そのあたりの事は誤差範囲らしい。
しかしオノケンのストライクゾーンは謎すぎるな。前世でどんな大罪を犯したのか知らないが、罪滅ぼしにしては過酷過ぎる。
恐らく身長180cm近くあるオノケンに、140cm代の桜井が思い切りつま先立ちで指差ししている為、滑稽以外の何ものでも無いポーズ。オノケンはオノケンで、挨拶より掌底を繰り出してきた桜井を恐れるでもなく、かと言って怒るでもなく、昔を懐かしむような暖かい眼差しで彼女を見ていた。それにつられて、きっと僕も微妙な顔をしていたのだろうと思う。桜井はオノケンと僕の顔を交互に見て、その表情から何かを悟ったのか再び目を吊り上げ牙をむいた。
「何二人してニヤニヤしてんのよ気持ち悪っ!どうせ昔と変わらずチビのままとか思ってるんでしょ、失礼ね!すごく失礼だわ!私がチビなんじゃなくてアンタ達がデカすぎるのよ!日照権侵害で訴訟を起こされるレベルだわ!」
「いや、それは誤解だ桜井れいな。俺の言う“変わらず”は、変わってなくて安心した。って意味だ。キミは俺が恋したあの頃と変わらず魅力的で、チャーミングな女性のままだ」
オノケンはそう言って、桜井の目を正面から見つめる。そして恐らくは少女マンガなら間違いなく背後に壮麗なバラを背負っていたであろう最高の笑顔を見せた。
「なっ……えっ……バカッ!アンタバカでしょ!バカバカっ」
みるみるうちに桜井の顔は真っ赤になり、ブンブンと腕を振り回す。
うーんオノケンめ、そんなにイケメンでも無いくせに。成長して女性を扱うスキルを身につけたと見える。
「なあ、リョータもそう思うだろ」
おっと、こっちにトスが来た。ここは上手く打ち返さねば。
「まったくその通りだ。今も昔も桜井はチャーミングだ。どれぐらいかと言うと、チャーミングといったら桜井。桜井といったらチャーミングぐらいだな。うん」
「あそ。そりゃドーモ」
桜井は半目で僕をにらみ、ぶっきらぼうに答える。さっきとは540°ぐらいかけ離れた態度だ。せっかくオノケンに打ちごろのトスを上げてもらったのに、大空振りだったか。言い訳を言わせてもらうと、オノケンとの経験の差もあるのだろうが、僕の姉の影響が大きいと思う。なにしろ機嫌が良くても悪くても蹴られることに変わりはない。結果が分かりきっているなら、あえて努力しようとしなくなるのは自然だと思うのだが。
「二人ともそろそろ行くぜ。今日中に終わらせねえと時間がないんだ」
オノケンはくるりと背を向け、枝分かれした細い道の方へと静かに歩き出した。
「行くってどこへよ」
「よく知らない」
「何で知らないのよアンタ、バカじゃないの」
「僕は杉屋の前で偶然会っただけだよ。桜井こそ何しに来たんだよ」
「私は賢至に呼び出されたから来ただけよ。急にシャベル持ってきてくれないかって」
「悪いなリョータ。本当はあそこでお前を待ち伏せしてたんだ。たぶん通ると思って」
「何だよ、用事があるなら最初からウチに訪ねてくればいいじゃないか。まわりくどい」
「ヤダよ。お前ん家の姉ちゃん怖えし」
「それは本当にすまないと思っている。こんど玄関に”モンスター在住”って貼っとくわ」
並んで歩く3人の足元から伸びる影は、長く長く伸び、遠くの塀へと届いている。オノケンの言う暗くなる前にーーの意味がわからないけども、辺りが見えなくなるまでに1時間も無いかもしれない。
僕は、なんとなく隣を歩く桜井の横顔を見て気がついた。
(口紅……化粧をしているのか……あとネックレスも)
18歳の年齢からすると、化粧をするのは常識の範囲内かもしれない。しかし桜井れいなの家庭と個性を考慮した時、疑問符が付く。彼女は体を動かす事が好きないわゆるスポーツ少女だ。ファッションなども動き易さ最優先だと本人も公言していたし、私服でスカート、という格好も見たことがない。というかジャージしか見たことがない。
クラス皆んなで行ったUSJ。めかしこむ大勢の女の子達の中、桜井は一人だけジャージで現れて”私は今日伝説になるから”と高らかに宣言し、ゲート開放と同時に全力ダッシュ。そして全力で転んで、開門5分で救護室に運ばれるという伝説を持つツワモノだ。
そして3人の兄の存在。年子の男三人の後に産まれた彼女は、かなり甘やかされていたように思う。天気が悪い時の送迎は当然として、父兄参観日は運動会は桜井家の一大イベント。そんな日に、桜井れいなと会話をしているところを見られようなものなら、兄+父の四人の男に囲まれ強迫されるという地獄を味わうことになる。彼女自身もそういった被害者を出す事を好ましく思っていないらしく、出来るだけ色恋沙汰は避けていると聞いたことがある。
僕はふと我に返った。
桜井れいながメイクをしてスカートを履き、男と並んで歩いている。もしこの状況を誰かに目撃され、それが桜井家に知られたら本人の意思はどうあれ、厳しい糾弾は免れない。そう思いついた時、本能的に危険を察知し、半歩、ほんの半歩だけ桜井から離れてしまった。
「リョータ!なに離れてんのよ、コッチ来なさい!」
こともあろうに桜井は腕を絡ませて、強引に僕を引っ張り、オノケンの横に並ぶ。さながら捕らえられた宇宙人の如くだか、本人はご満悦の様子だ。
「こういうの一度やってみたかったんだあ♪」
「さっ桜井には兄弟が三人もいるじゃないか」
「お兄ちゃん達はダメよ。小さい頃一度やったら、誰と誰の間を歩くかで大ゲンカしたのよ。それ以来ウチでは並んで歩くのは禁止になったわ」
不埒にも、腕に当たる柔らかい感触を意識してドキドキしてしまう。今が夕方で良かったとつくづく思う。オレンジ色の夕陽は、きっと僕の上気した恥ずかしい顔を誤魔化してくれているに違いない。
「こんな美少女と腕を組めてラッキーとか思ってるんでしょリョータ」
「いやチョット、何を言っているのか理解できませんケド……痛い!」
思い切り足を踏まれた。照れ隠しのツッコミなんて可愛いものではない。足の甲の辺りを踵で踏みつけるという、完全に壊しに来ている踏み方だ。のんきにラッキーとか思えるわけがない。
桜井に合わせて小さくなった歩みは、砂利ばかりの不安定な小道を進む。両側を垣根にはさまれたここを抜け、溜め池へと流れ込む小川を越えると、僕たちが通った小学校への近道になるのだ。
「賢至、そろそろ何をするつもりなのか教えなさいよ。小学校に用事?」
「……“お楽しみ会”、覚えているな。アレの真実を探る」
オノケンの言葉に桜井の歩みが二歩三歩と鈍化し、ゆっくりと止まった。
「何ソレ……何で今更そんな事するわけ?もう何年も前のことでしょう⁉︎」
「いや、俺は明らかにすべきだと思う。2人とも俺に会ってまずその事を思い出したんじゃないか?」
「……っ確かに、クラスの誰かが山崎先生にバラしたかもしれないけど、でもそれが判ったところで過去は変えられないし、良いことなんて何も無いわ!」
桜井に掴まれている腕が痛い。こんなに強く拒否感を露わにするなんて少し意外だ。彼女の性格なら面白そうとか言って、喜んで協力しそうなものだが。でも反対する気持ちも理解できないわけでは無い。
今もし犯人がわかったとしても、当時の僕らが助かるわけでは無い。それどころか少年時代のつらい記憶に、裏切り者がいたという新しい記憶が付け足されて、また苦しむ事になりかねない。けれども誰が、何故、といった長年の疑問を解消して、初めてあの事件を完結させることができるとも考えられる。
要はうずく古傷を放置するか、完治させるためもう一度痛い思いをするかの二択なのか。果たして僕はどちらを望んでいるのだろうか……
「リョータはどう思う?」
「そうよ、リョータはどっちなの?私と同じよね?」
2人の目が僕へと注がれる。2人とも僕の大事な友達で、双方の言いたい事も理解できる。でもこれは本当に真ん中に線を引ける事なのか、白と黒にはっきりと分かれている事なのか。
「……えと、その前に、二、三確認しても良いかな?」
僕は桜井の手を丁寧に下ろして、ちょうど2人の間に立った。
「お楽しみ会の真実って何?何故僕と桜井の2人を誘った?」
「真実を知る事で、俺が犯人でない事がわかるはずだ。それを証明する」
「じゃじゃあ!あの事をバラしたのは賢至じゃないのね?」
桜井はわずかに安堵した表情で、長年僕らの間で度々話題に上がる、答えの出ない疑問を口にした。答えはオノケンが持っている、オノケンにしか答えられない。いつも堂々巡りで終わっていた迷路の答えを。
「俺なわけないだろう。それに勘違いすんなよ、俺の目的は犯人探しじゃねえ。自分の無実を証明したいだけだ」
僕と桜井は目を合わせて大きく息を吐いた。やはりオノケンは僕たちの信頼できるリーダーだったオノケンだ。たとえ急な別れで、言葉を充分に交わせなかったとしても、疑うべきではなかった。僕は、ほんの少しでも彼を疑ってしまった事を恥じた。
「オノケンごめん。ハッキリとした理由も分からず、周りの意見に流されて、もしかしたら、と疑った事がある。謝るよ」
「いいんだ。弁解できない状況では仕方が無かった。せめて別れを言う機会があったら、こんな事にはならなかったのにな」
ぽんと軽く僕の方を叩く。その何気ない仕草がなつかしく、妙に嬉しかった。
さよなら、また会おうと言えていれば、皆の心がオノケンから離れてしまうことは無かったかもしれない。心にもやもやとしたものがあると分かっていながら、自分には何も出来ない、仕方がない、と諦めてしまっていた。今日もしオノケンが僕の前に現れなかったら、このもやもやを抱えながら過ごしていただろう。奇跡、と簡単に言ってしまうのも憚られるが、数年の時を経て再び僕らは友達に戻れたと、深く深く実感した。
「ま、まあ私は、最初から賢至が犯人だなんて思っていませんでしたケドも」
取ってつけたような桜井の主張に、一瞬時が止まり、なんとも言えない軽薄な空気が流れた。
「お前はこのタイミングでよくそんなことが言えるな」
「なんつったっけ?KYか。ケーワイ桜井に改名だな」
「ななな何よ!元はと言えば賢至がいきなり転校するのが悪いんでしょお⁉︎この桜井れいな様に!断りもなく!」
俺の後ろに隠れて偉そうなこと言ったって、どうにもならないぞ。
しかし桜井もまた、オノケンの事を疑いつつも心のどこかで信じていたのだろう。“本当の事を明らかにする”と言っていたオノケンの言葉は、罪の告白とも解釈できる。男っぽくて乱暴者の桜井だが、僕と同じように、オノケンとの再会にとまどっていたと思う。素直に喜びたいが、変わってしまったオノケンは見たくない。そう考えると、先ほどの強い拒否反応も、ほっとした安堵の表情も理解できる。
「転校のことは悪かったと思っているよ。特に桜井にはな。でも俺だけではどうしようも無かった。あの日も“お楽しみ会”の帰り、離婚が決まった母親が俺を待ち構えていてよ、いきなり車に乗せられてハイ、さようならだ。こっちの都合なんか関係ナシさ」
「それならそれで言ってくれれば良いものを。山崎先生は何も言ってなかったし」
「親父はまだあそこのマンションに住んでるからな、口止めしたんだろう。家族に逃げられることを恥だと思うような小さい人間だし」
オノケンの言葉にはわずかに怒気を感じる。他人の家庭の事情に深く踏み込むべきではないけれども、離婚したという父親とはうまく行ってなかったのかもしれない。
「そうするとだ、先生に呼び出された時に見せられた証拠のノート。あれはオノケンが持っていたお楽しみ会のノートじゃないっていうことなのかな」
「でも参加者とかお金のやり取りとか全部書いてあるから、言い逃れできないって。実際参加者全員呼び出されてたし」
「お前たち、そのノートの中身は見たのか?確かに俺のノートだったのか?」
「うーん……そう言われると自信ないなあ。中身は見てないし、表紙をちらっと見ただけだったし」
オノケンが転校して、一ヶ月ほど経ったあの日、僕らは1人ずつ担任の山崎先生の元に呼び出された。そしてお楽しみ会の存在と、参加していたかどうかを確認され、言い澱む者には証拠とされるノートの存在を示し、きちんと真実を言うように促された。参加者は皆んな、オノケンがお楽しみ会の内容と結果、お金の動きなどをノートに記録していたことを知っていたので、もはや言い逃れはできないと覚悟していた。
「だとすると、状況から見て、そのノートは間違いなく偽物だ」
「どういうこと?誰か……ってか犯人が偽物を先生に渡したってのか?」
「で、でも先生は全てここに書いてあるって言ってたし、参加してた人は全員……」
「少し思い出してくれ。俺たちのクラスで誰がいつどれだけ参加していたか全て覚えている人物はいるか?俺でさえ毎回は参加していなかった。他のクラスも合わせれば、なおさらだ。つまり正確に把握するにはノートの書かれていた名前を照合するしかない」
不特定多数の人が、複数回行われている”お楽しみ会”に参加していた。
会は数十回開催さてれいたし、場所も毎回違う。管理者役だったオノケンも都合で参加せず、結果報告だけをノートにまとめていたとしたら、全てを把握するにはやはりノート見るしか手段は無いはずだ。
「当時は追求され、そうとう叱られただろう。しかし個人の名前を挙げて、晒し者にするにするような事はしなかったはずだ。外へ名前が出ないよう、一定の配慮があったように思う。つまり、いちいちノートを見て、参加者の真偽を確認できなくても、子供達の反省を促すことができればそれで良かった」
たしかに思い出すと、子供の遊びの範疇を逸脱した行為には容赦なく批判され、叱責を受けた。しかしオノケンの言うように、人前で誰とハッキリ分かるような方法は取られなかったように思う。
「大人の立場からすると、誰がお金をいくら儲けたとかいくら損したなんてのは問題じゃない。賭けトランプが行われていたという事実が問題だった。そして直接関係の無かった生徒にも注意喚起する、目的としちゃそんなとこだろう。なにしろ俺はそうなるように参加人数を調節していたんだから」
お楽しみ会を始めた当初、数人の仲間内での開催に止まらず、参加者を積極的に増やそうとしていた。僕は“お楽しみ会”という皮肉なネーミングの通り、隠れて少人数で行うのかと思っていたので、とても意外に思った。普通、秘密を共有している人数が増えるに従い、大人達にバレる可能性は高くなる。しかしオノケンの行動と結果、今の発言を総合すると、バレた時に世間的にどの程度騒ぎになり、誰に叱られるかまで考えてやっていた、と思わざるをえない。すなわち、小規模で個人に迷惑をかけるタイプのイタズラなら少人数で。大規模で多人数に迷惑をかけるタイプのイタズラなら多人数で。数学的に解釈するなら、責任を測れる単位があるとして、一人が負う責任の量が一定になるように参加人数を調整し、一人にかかる心のダメージを減らしていたという事になる。流石というか何というか、当時からイタズラの天才だと思っていたが、その言葉の意味は、僕の想像の域をはるかに超えるレベルに達してたようだ。
「大人達の目的からすると、ノートの真偽はどうでもよかった、と。それで、オノケンがノートを偽物だとする根拠は何?」
オノケンは無言で、僕の持っている小包を顎でさした。
「何よそれ。宝物?」
「ある意味そうだな」
ニヤリと笑うオノケン。
「ホンモノはそこにある」
僕が担任の山崎先生に呼び出された時、証拠のノートがあると確かに言っていた。心当たりのあるノートは1冊しかなく、それが本物か偽物かなんて考えもしなかった。
”お楽しみ会”のノートはもともとオノケンが管理し、いつも持ち歩いていたものだ。本物がちゃんと保管しててあって、ここにあるという事は
山崎先生が言っていた証拠のノートとは偽物か、全く別のノートということになる。
「転校することになったあの日、俺はノートと貸し借りしていたお金を、保管しなければ思った。このまま家に置いておくと、どうなるかわからないからな。一番良い方法は仲間の誰かに事情を話して、託すことだったのだろうが、そんな事をする時間は全く無かった」
「家もダメ。渡す時間も無いじゃどうしようもないじゃない」
「ああ、俺はそれで一か八か箱に入れて埋めようと思い、外へ飛び出したんだが、そこである人が目に止まった。
杉屋のばーさんだ」
杉屋はオノケンが住んでいたマンションの隣にあった駄菓子屋だ。店が開いている時は、近くにいるはずだし、あのばーさんなら信用できる。
「必ず取りに来るからと言って、ばーさんにコレを預けた。しかし、そんな機会は訪れることなくばーさんは死に、箱だけ残された」
「じゃじゃあ、何で偽物なんかを作ってバラしたりするワケ?何も良いことないじゃない
「これは半分俺の想像なんだが……」
オノケンは腕を組んで大きく息を吐いた。いささか大げさな行為だけれども、僕がオノケンの立場だったらきっと同じようにしたと思う。仲間を地獄に引きずり落とすようなことをする理由など、想像とはいえ考えたくもない。
「ギャンブルをやめたいと思う時って、いったいどういう時だと思う?」
「お金がなくなった時かしら、もう続けられないーって」
「大勝ちした時かな。勝ち逃げできる、みたいな」
「俺は借金を作ってしまい、それから逃げられなくなった時ではないかと思う」
断っておくが、この会話の中で出てくるギャンブルとか借金なんてのは、あくまで小学生レベルでの話である。もらっている小遣いの額に差がある事は分かった上で、それに合わせて掛け金とか賞金を設定していた。大勝ち、と言っても杉屋で買う駄菓子が一個増える程度の事だ。借金の額にしても同様なのは言うまでもない。
「借金までしてギャンブルとかサイテーだわ」
「逃げ出したくなるほどの借金って僕達には当てはまらないんじゃない?」
「俺がいた頃はそうだった。だが、その後はどうだ?たしか一ヶ月ほど期間があって、騒ぎになった。妙だと思わないか?」
僕と桜井は顔を見合わせた。
オノケンが突然転校した”オノケンショック”の後、再び”お楽しみ会”をやろうとした動きがあった事は知っている。だが実際に開催されたかどうか、誰が参加したか、どんな状況だったか等は、全く知らなかった。
「私もあまり知らないけど、隣のクラスの男子が”今日は勝ったからおごってやる”と言って、イカ串をケースごと買おうとして、おばあちゃんに怒られてたの覚えてるわ」
「じゃやっぱり”お楽しみ会”を再開してたってこと?」
「しかもかなりのハイレートだ」
勝ったからといって、イカ串をケースごと買おうなんて、僕らの”お楽しみ会”ではとうてい考えられない額だ。おそらく掛け金自体が、一桁か二桁は違ったのだろう。それだけ勝ったやつがいるということは、それだけ負けたやつがいるということに他ならない。小学生の財力などたかが知れているから、かなり逼迫した状況になる事は容易に想像ができる。
’オノケンショック”から”セカンドインパクト”までおよそ一ヶ月、お楽しみ会を再開し、借金で首が回らなくなるには十分な時間だ。
「ニセモノのノートは、そこで使われていたノートなのね」
「その可能性は無くはないが、俺は低いと思っている」
「え?でもノートはニセモノだってさっき言ってたわよ」
「結果から考えてみてくれ。刑事ドラマなんかによくある”事件が起きたことによって誰が一番得したか”ってやつだ」
「えと……この場合”お楽しみ会”が無くなって、得したヤツ?」
「そうか!借金してたヤツが、”セカンドインパクト”でお金のやり取りが禁止されたから、結果として借金帳消しになって、得したのか」
「その通りだ。恐らく犯人は俺が転校したことよりも、持っていたノートが無くなったことにより一度借金が消えたことに注目した。そして再び借金を作ってしまい、同じように借金を消そうとした。が、そもそもお金のやり取りをノートで管理していなかった」
「だから……」
「だから、何よ」
「俺のノートのニセモノを作り”お楽しみ会”の全てを告発する事で、大人達に借金を帳消しにさせた……といったところだろう」
「流石だわ賢章!その場にいなかったのに伝聞だけで全部わかっちゃうなんてアンタ探偵とかやんなさいよ、マンガとか映画みたいな」
そう言って桜井はその場でスカートを広げ、くるくると回ってみせた。
はっきりと何かコレという理由があったわけではない。ただ少し違和感を感じた。
一寸の先も見えない暗闇の中で、手を伸ばしても伸ばしても、空を切る虚しさ。助けを求める声は誰の耳にも届かず、手を差し伸べてくれる者は誰もいない。
そんな中、暗闇に一筋の光が射したとしよう。僕を含めたほとんどの人が希望を求め走りだすに違いない。足元に転がっている石も穴も罠も、顧みる事なく。
オノケンは何かを焦っている。
よく考えると、ニセモノのノートの存在。ノートである必要は無いのではないか。大人達を動かし、“お楽しみ会”の存在を暴露する目的なら、密告や手紙でもいいのではないか。事がコトだけに僅かな疑いさえあれば、調査に乗り出す十分な動機になる。
それに犯人の行動。借金のために場をひっくり返すなんてのは、天才オノケンならではの発想ではないか。僕ならまず、姉か杉屋のばーさんあたりに泣きつくと思うが。
「リョータ!聞いてる?」
「え?……何なに?なんだって?」
「小学校に行くわよ」
「学校?なんで?」
「本来なら、クラスのみんなの前で、俺の無実を証明したいとこなんだが、もう全員が集まる機会なんてほぼ無い。だが、山崎先生を含めた大勢が集まる予定の日が1日だけある」
「……成人式!それで僕と桜井なのか」
僕と桜井は、5年のクラスのタイムカプセル係だった。
タイムカプセルとは、もはや説明不要のアレである。僕らのクラスでは、未来の自分へ向けた手紙や思い出の写真を入れ、成人式の日に掘り起こす事になっていた。イタズラで勝手に掘り起こされないように、埋めた場所については、タイムカプセル係である僕と桜井、それに担任の山崎先生しか知らない。一応は三人の同意のもと、掘り起こす事になっているが、成人式にここに来れない可能性も考えて、最低一人は立ち合いが必要なルールになっていた。
僕ら三人は、学校の裏手にある垣根の切れ目から、敷地内に入った。ここからなら、校舎から見られる心配は無いはずだ。そしてそこには丁度目印になるような大きな桜の木が生えているし、宝物を埋めるにはうってつけの場所だ。
「ところで何でわざわざここに埋めるワケ?リョータに預かって貰えばいいじゃないの」
そこは、自分が預かるじゃないのか。
シャベルを使っているとはいえ、意外に堅い土に苦戦を強いられる。こんな所にデカイ穴を掘るなんてやった事がない上に、帰宅部軟弱男子には辛い作業だ。
「成人の日。つまりクラスの皆んなが出来るだけ揃う日に、遺産がここにある事が重要なんだ。タイムカプセル係のお前達がいれば、俺の無実を証明できる」
「なに他人事みたいに言ってんのよ。アンタが成人の日にここに来ればいいだけの話じゃない」
「俺、実は……遠く……外国へ行くんだ。しばらくは帰ってこれない」
「外国って留学とか?」
「そうだな……そんな感じだ」
「そう……」
ウソだ。オノケンはウソを言っている。
桜井はオノケンから視線を外して遠くを見ている。ザクザクと土を掻く音が、暗闇迫る校舎の壁に反響して寂しさを増していく。
僕らにも言えない事情があるのかも知れないが、それならせめてウソをつかないで欲しかった。これでは5年生のあの日、何も言わず転校してしまった時と同じじゃないか。
突然の別れから8年ほどの月日が流れ、その間何があったかはお互い知る由もない。今回オノケンが突然現れて、図らずも昔の記憶を思い起こすことになり、小学生に戻ったような感覚になった。しかし、本当の自分はあれから成長し、多少の苦いも甘いも経験して大きくなったつもりだ。
「……やっぱりこんなことはやめよう」
僕は大きく息を吐いて、シャベルを動かす手を止めた。
「リョータ?」
「今さら昔の事をほじくり出すべきじゃないよ。山崎先生には僕から話しておく。成人式の日に先生の口からオノケンの無実を語ってもらう。それでいいだろ」
「ダメだ。大人は信用できない」
「成人の日には大人の仲間入りをしている!僕だってその日にハイどうぞと大人になるものじゃないことは知ってるさ。でも、ゆっくりと確実にその信用できない大人になって行く。僕も桜井もそしてオノケンキミもだ!」
思わず放り出したシャベルが、穴の縁に置いてあった小包に当たり、甲高い音を立てた。僕は構わず、オノケンへの追求を続ける。
「外国へ行く……なんてウソだろ?本当の事を言えない事情があるならそう言えばいいのに……僕ら……友達じゃなかったのかよ……それとも君はもう信用できない大人になってしまったのか」
僕は悔しかった。
スポーツも勉強も恋愛も友情も、熱を持って挑まずにいた自分が。
どこかに冷めた目で見ている自分がいて、そうする事が恥ずかしく、周りの友達と違うところに立っている自分が。
そして羨ましかった。
嫌いなものを嫌いと、好きなのもを好きと言える強さを持ったオノケンを。
それだけに、彼から信頼されていない自分を、同じ熱を持てなかった自分を、後悔した。
だからせめて、今は同じ温度で悔しさをぶつける。もうすぐそれさえも出来なくなるのだから。
「リョータ……残念だが俺は…………!」
深く、重苦しい沈黙。
見るとオノケンは、僕でもなく桜井でもなく、シャベルがぶつかって一部新聞紙が剥がれている小包に視線を送っていた。
「どういう事だ……アレは俺の預けた箱じゃない……」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
拝啓 小野賢至様
まずは貴方から預かった箱を勝手に開けてしまった事をお詫び致します。
最初、ノートの中身を見て驚きました。いたずら好きで、近所の子供達のリーダーだった貴方が、犯罪者まがいの真似をして非常に残念な思いがしました。ですが、貴方が私を信頼し、ノートとお金を預けてくれた心に応えるためにも、他言するつもりはありませんでした。しかし、私のもとへ一人の小学生が訪れ、涙ながらに相談されました。その子は軽い気持ちから、賭けトランプに参加し、そのうち子供ではなかなか返せないほどの借金を作ってしまったという事でした。
同じ時期、私の店では駄菓子を大量に買おうとする子供が、時々現れるようになり、疑問に思っていました。
私は、子供は子供らしく、みんな笑顔で遊んで欲しい。誰かが泣くような遊びは止めるべきだと思い立ち、小学校の先生に相談しました。
貴方から預かったノートは、誰か特定の個人が責められる事の無いよう条件を出し、使っていただきました。
叱られた子供達は、辛い思いをして大変だったでしょうが、これも大切な経験のひとつとして大きく成長し、また先生や親御さんたちも、陰で大変な努力をされていた事も理解してほしいと思います。
ほとぼりが冷めた頃、先生からノートを返却して頂きましたので、いずれ貴方の手に戻る事を願い、手紙をしたためました。
一緒に入っていたお金は、貴方の欲しがっていた物と交換しました。恋の悩みを打ち明けてくれたお嬢さんへ、是非貴方の手で渡してあげてください。私のせめてもの罪滅ぼしです。
杉屋のばーさん 杉野 すず
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
箱の中には、オノケンのノート、おもちゃの宝石、そして一通の手紙が入っていた。
僕の読む手紙は、昔の真実を語り、想いを語った。
それは思ったより単純で純粋だった。
「オノケンこれは……」
動揺し、動けずにいるオノケンに代わり、手紙を読み終わった。そして振り返ってみるとそこに僕の友人の姿は無かった。
僕は隣にいる桜井と顔を見合わせ、オノケンは?と聞いてみたが、彼女もまた僕と同様にオノケンの姿を見失っていた。
現れた時と同じように、突然消えてしまった。
次の日、僕は桜井に誘われ、オノケンの父親のいるマンションを訪ねる事にした。
あの後、いくら探してもオノケンの姿は見当たらなかった。死者が帰るお盆の日に突然現れて、突然消えた。
最初に再開した印象といい、暑い日のパーカーといい、どうも普通じゃない。
一応は、お盆に合わせてオノケンが帰ってきたのではないかという事で落ち着いた。
「賢至の推理、半分は外れていたわね」
「頭が良すぎたのさ。どうにか白黒つけたくて、自分と他人が同じ考えを持つと思い込んでしまった。皆んなが皆んなオノケンほど頭は良くない」
「リョータはさ、自分が大人だと思う?」
「途中、としか。ゴールがあるならって話だけどね」
僕らが一緒に過ごした数時間は、あまりにも現実的すぎて、未だにオノケンが霊的な何かだったとは信じがたい。
夏場の怪談として、何百キロも離れたゆかりのある場所に現れて、別れの挨拶を言ったなんて話は聞くが、実際に体験した後でも本当だったのかどうか自信がない。
良く思い出すと、桜井はオノケンを叩こうとして空振りしていたし、僕ら以外に会話をした者もいない。
「結局、お楽しみ会の事が心残りで化けて出たのかしら」
「化けて出たってか、丁度お盆だったから、帰って来た。でいいんじゃない?」
「そうだアイツまた、宝石くれないでどこか行きやがったわ。代わりにアンタ貢ぎなさいよ」
「“行きやがった”と“代わりに”の間にどういう理論があったのか、僕に説明しろよ。話はそれからだ」
照りつける陽光が降り注ぎ、容赦なく肌を焼く。彼岸は過ぎても残暑がおさまるのはまだまだ先になりそうだ。桜井のかぶるつばの大きな帽子は、それをものともせず、濃い影を落とす。緩やかに波打つロングスカートを押さえる仕草は、映画のヒロインのようだ。
不覚にも、中身が桜井れいなだということを一瞬忘れそうなってしまった。
「そういえばさ」
少し前を歩く桜井は、くるりと振り返る。
「賢至が“お楽しみ会”をやり始めた理由、聞いたことある?」
僕は無言で首を振る。あまりそこに疑問を持ったことはないが、特別な理由とかあったのか?
「杉屋の駄菓子クジを買い占めて、特賞のおもちゃの宝石を手に入れる為だってさ。笑っちゃうわ」
ばーさんの手紙にあった、恋の悩みを相談したお嬢さんというのが、桜井だったかどうかは分からない。箱に入っていたおもちゃの宝石は、実は僕が持っているのだが、コレを桜井に渡すべきかどうか正直迷っている。オノケンの心残りはお楽しみ会の事じゃなくて、コレを桜井に渡せなかった事だろうから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
酒井リョータが小野賢至と再開する数時間前に遡る。
「よっ、桜井。久しぶり」
「アンタ……賢至じゃん。何しに来たのよ」
「冷たい反応だなあ。何年かぶりに友達が訪ねてきたんだぜ、もっと歓迎してくれよ」
「いきなり転校しといて無責任ね。あの後私たちがどんな目になったか」
「おうそれそれ。今日はそれもあってわざわざ九州から来たんだ」
「話が見えないわ。もっと手短に分かりやすく言いなさいよ」
「じゃ、手短に。まだリョータのこと好きなのか?」
「なっ!……なんでアンタがそんな事知ってんのよ。むむむ昔の話よ」
「まだ好きなんだな?」
「…………ぐぐっ……だだだだから何よ!いいでしょ別に!違うクラスだから接点が無いだけだし、文化祭とか超誘うつもりだし!」
「リョータはアホだから、桜井の態度から気づいてくれるなんて思うなよ。あいつはお前のこと女だと思っちゃいねよ」
「うるさいわね!アンタわざわざ九州から喧嘩売りに来たの!」
「んなわけあるか。お節介&罪滅ぼし&イタズラさ。お前とリョータの仲を取り持ってやるよ、めかし込んで後で小学校に来いよ」
「ええっ!?わわ私ジャージしか持ってないんだけど……」
「借りればいいだろう?リョータは意外にギャップに弱い。乱暴者の桜井が、女性らしい格好をするなんて思ってもみないはずだから、きっと意識するはずさ」
「何よ何をするつもり!?ちゃんと教えなさいよ!」
「お前はプレッシャーに弱いから、詳しく知らない方がいい。俺は幽霊になって戻ってきたという設定でよろしく。後はなんとなく話を合わせればいい」
「無理ムリむり!絶対ムリ!出来ないって!」
「俺はなあ桜井、お前のその過激なスキンシップに耐えられるのは、あの怪獣姉をもつリョータしかいないと思ってるんだ。知ってるだろ?」
「うん。酒井こいとさんでしょ、お兄ちゃんと同級生だし、道場で一緒だし」
「頑張れ桜井、お前の魅力でリョータをメロメロにするんだ!」
「メロメロに……わわわ分かった、ややってみる」
「うまく行ったら、明日にでも俺の住んでたマンションに来いよ。ネタばらしするから」
「えっ、ばらしちゃうの?」
「当たり前だ。イタズラはバレるからイタズラなんだ。じゃ待ってるからすぐ来いよ」
冒頭へと続く。
一枚のコインの、裏かオモテかと選択を迫られたとする。僕はこういう時、裏でも表でもないそれ以外の選択肢を探してしまう。それは子供のわがままなのか、それとも大人の妥協なのか。
「ただいま」
照りつける日差しから逃れるように、ひんやりとした玄関にカバンを置いた。
8月に入り、ますます蝉の合唱が盛んになって来た。世間はお盆休みでも、ゆっくり休めないのが受験生の哀しいところだ。高校からの帰宅を知らせる僕の声に、返事をする者は無く、シンとした静寂が孤独を知らせる。無言でワイシャツをソファに放り投げ、冷蔵庫へと直行する。確か昨日覗いた時点では、コーラがまだ残っていたはずだ。CMのように、シュワシュワと小気味よい音を立てて、氷に弾ける琥珀の液体。僕は喉にくる刺激を楽しみながら一気に飲み干した。
「ナニ飲んでんのよ」
「!ビックリした!いるなら返事ぐらいしろよ姉ちゃん……」
危うくコーラを吹き出しそうになった。突然背後から話しかけた姉は、Tシャツ短パンで濡れ髪を拭きながら立っていた。
「アタシが飲もうと思ってたのに、勝手に飲むなよバカ」
「蹴るなよ暴力姉!アネハラで訴えるぞ!」
姉は、高校を卒業するまで空手をやっていたせいか、とにかく気が荒い。気分が良くても悪くても、口と同時に手足が飛んでくるので、取り扱いに困ってしまう。
「コンビニ行って来いよ、今すぐダッシュで」
「やだよ外暑いし。自分で行けばいいじゃん」
「……仕方ないなあ。リョータが買いに行かないからアタシはコレで我慢してやろう」
そう言うと、姉は冷蔵庫の奥から缶ビールを取り出し、勢い良く栓を開けた。なんだよ最初っからそっちが目的だったんじゃん。ややこしい。
「そう言やリョータ宛に小包来てたわ」
「小包?誰から?」
「知らない」
「どこに?」
「知らない」
「ナニその分かんないもの見た!みたいな情報」
姉は自由すぎる。優しさとか、思いやりとか、そういう心のクッション的な柔らかさは、オークションに出したに違いない。
「アンタの友達なら見たわよ。なんとかって名前の悪ガキ。杉屋の前で突っ立ってわ」
「あいにく知り合いにナントカさんなんて人はいまセーン ……ゲフッ!」
姉は器用にも、冷蔵庫のドアを足で閉めながら、同時に肘で僕の横腹にツッこみを入れる。
僕は追撃を避けながら、今のクラスのメンバーの顔を浮かべてみるが、近所に住んでいるやつはいない、と首を傾げた。
「いたっつーの!賭けトランプかなんかで問題起こした、杉屋の横のマンションに住んでた」
「杉屋の横……?ひょっとしてオノケン!?」
「そう!それそれ!忘れもしないわあのガキ、初対面の私にカンチョーダッシュしやがって。乙女の肛門に指を突き立てるとか、万死に値するわ!今度見かけたら超殺すし」
たった今まで忘れてたくせに。何が忘れもしないだよ。それと、乙女は肛門とか超殺すとか口に出さん。
僕は姉の愚痴を聞きながら、小学生の時の苦い思い出を思い出していた。
5年生の時、僕には小野賢至という同級生がいた。
オノケンはとても明るい性格で、スポーツ万能、背も高くてクラスの中でも目立つ存在だった。特別頭が良いわけではなかったが、いたずらにかけては天才的で、先生や地域の大人達も彼には手を焼いていた。かと思えば、下級生の面倒をかいがいしく見たり、ボランティア清掃に積極的に参加したりと、真面目で優しい所もあった為、とにかく人気者だった。
同時期、TVかなにかのきっかけで、賭けトランプが流行したことがあった。
オノケンはそれを「お楽しみ会」と名付けて仲間内で遊んでいた。最初は少人数で、1円を賭けるだけのシンプルなルールだった。僕は最初、子供がやるようなギャンブルの真似事なんて、すぐに禁止されるとタカを括っていた。しかしイタズラの天才オノケンは、巧妙に、精緻に、賭けトランプのシステムを改革していった。
まず絶対大人には悟られないようにする。これがまず第1に守るべき絶対のルールだった。子供が隠れてやるような事に、渋い顔をしない大人なんているはず無いからだ。そして金銭のやり取りがバレ無いように、色分けした金券を作ったり、参加費として全員一律の金額を徴収することで、公平感を出したり、勝者を一人だけにする事で優越感を演出。さらにはトーナメント戦、タッグ戦、高額線と次々にイベントを開催した。その効果は絶大で、このブームが始まって1ヶ月足らずで、クラスのほとんどが参加するまでになっていた。
しかし、僕らを夢中にさせたこの「お楽しみ会」は、何の前触れもなく終わりを告げた。
オノケンが突然転校してしまったのだ。
週明けに担任からこの事実を聞かされた時、僕らはそれを理解できずにボーゼンとなった。
それからというもの、クラスはこの ”オノケンショック” からしばらく立ち直る事が出来ず、教室がどんよりと通夜のようになってしまった事を覚えている。
しかし、この後に起こった事と比較すると、”オノケンショック”さえもまだいい方だったと言わざるを得ないだろう。
僕は心にモヤモヤを抱えたまま自室へと戻った。ろくに別れを惜しむこともできなかったオノケンに再会したとしたら、どんな顔でいればいいのだろう。昔のように、子供の時のように、尊敬の眼差しを向けられるオノケンであって欲しいと朧げに考えていた。
再開の時は、意外にもすぐに訪れた。
自室には、姉の言っていた小包が僕の机の上に置いてあった。クッキーの缶ぐらいの大きさで、古びた新聞紙に包まれている。重さは片手で持ち上げられるほど、左右に振ってみると、カタカタという音ともに、何か硬いものが金属に当たる音がする。
僕はこんな物に全く覚えがなかった。また姉のイタズラかと思ったが、表面には住所と名前が達筆で書いてある。住所は近所、歩いて10分もかからない。そして宛名を読んで僕はドキッとした。
小野賢至
たった今、姉と話していた小学校時代の友人、オノケンの名前がそこにあった。
姉に問いただそうとリビングへ降りたが、そんなもの知らないと一蹴された。それどころか、再び飲み物を買ってこいとワガママを言う始末。結局僕は姉の暴力に屈し、飲み物を買いに行かされることになった。姉曰く、ビールとジュースは飲み物としてのコンセプトが違うので、ビールを飲んだ直後にジュースを所望することは全く正常であるとのことだった。将来、姉が結婚する事になったら、相手の男性に心から同情するとともに、茨の道を歩き出す今の気持ちを是非訪ねてみようと思った。
ついで、と言っては語弊があるが、小包を持って、元オノケンのウチに行ってみようと思った。確か聞いた話では、オノケンの父親はまだあそこに住んでいるらしい。
夏の季候特有の強烈な日差しも、徐々に陰り始めた道を進み、先にコンビニにいくかそれとも杉屋に行くか、迷った時、何となく杉屋の方向に足が向いた。
遠目からも、非常に怪しく見える人物がそこに立っていた。そいつは僕よりも10c mは背が高い男で、このクソ暑い中、黒いパーカーを着て目深にフードを被っている。ポケットに手をつっ込んだ姿勢で、ぼうっと杉屋の前で突っ立っていた。僕がそいつを目撃してから近づくまでの間、一向に動く気配を見せず、立ち尽くしたままだった。
僕はなんだか気味が悪いなと思いつつも、確認のため立ち止まる。そしてさりげなく視線を向けた瞬間に、そいつと目が合ってしまった。
数年ぶりと言えども、記憶の中の彼とイメージが一致するのに一秒とかからなかった。
間違いない。髪は伸びて、顔は大人っぽくなっていたが、あの切れ長な目は間違いなく小野賢至、オノケンだ。
オノケンは、自分からたった数メートルの場所で、不審な態度をとっている僕を明らかに見ていたが、突然くるりと背を向け、そのまま歩き出した。
「オノケン……」
思わず口をついて出た声は、彼の耳に届かなかったのか。それともあえてなのか。
オノケンは歩みを止める事なくそのまま小さくなって行く。
「オノケン!」
今度は、明らかに呼び止める意思を込めた声。
オノケンは立ち止まり、ゆるりと振り返る。そしてにやりと笑って見せた。
「リョータ……だよな?酒井 リョータ」
「ああ、久しぶりオノケン。もしかして今、スルーしようとした?」
「悪ぃ……その名前で呼ばれるの久しぶりでよ、自分の事だと思わなくて」
僕は最初、目の前にいる人物があのオノケンだという事に自信を持てなかった。
低い声のトーン、ゆっくりとした話し方。
真顔とも微笑とも取れる曖昧な表情、うつろな目の輝き。
記憶の中では、常に強烈なエネルギーを発散している太陽のようだったヤツが、本当に同一人物なのか?
「なんか……雰囲気変わったね、大人になった?」
「そう言うリョータは変わンねえな。何つーか戦隊モノのブルー?みてえな?」
しばらく話していると、次第に安心してきた。人間の芯の部分には、間違いなくあのオノケンがいる事を感じる。変わったと思ったのは、流れた時間と考えてよさそうだ。
「さっきウチの姉ちゃんがお前の事を見かけたって言ってたから、もしかしたらって思ってさ。気をつけろよ、カンチョーダッシュの件で姉ちゃんから殺害予告でてたから」
「お前ん家の姉ちゃんいつもそれな。それで何度も蹴られてっから俺」
ようやく安心する笑顔。
「今日は何か用事?またこっちに戻って来たとかなのか」
「ん……そういうワケじゃねえンだ。ま……ちょっとな」
しばしの沈黙。
じわじわと時間が経ち、どれ程深刻な理由を抱えているのか、僕の想像の選択肢が十を超えたあたりで、ようやくオノケンは口を開いた。
「杉屋のばーさん死んだんだってな」
「ああ……”100まで生きる”が口癖だったのに、あんな絵に描いたようなクソババアが、本当に死ぬなんて」
「俺なんて隣に住んでたから、顔を見る度に小言を言われてたンだぜ」
「オノケンは知らないかもだけど、杉屋が閉店セールやったんだ。その時、ばーさんの遺言で小学生は、タダだったらしいよ」
「何だよソレ!小学生の夢じゃん。駄菓子食べ放題とか」
杉屋は、オノケンの住んでいたマンションの隣りにあった駄菓子屋で、子供の頃毎日通った思い出がある。腰の曲がった妖怪みたいなばーさんが居て、礼儀とか挨拶に非常にうるさく、大声で挨拶しないと絶対に駄菓子売ってくれないのだ。近所の悪ガキ共の天敵みたいな存在だったが、ただうるさいだけのばーさんではなかった。悩みは親兄弟より、まずは杉屋のばーさんってほど頼りにされていた。子供の他愛のない小さな悩みを、人生の一大事であるかのように親身になって相談に乗り、それを乗り越えた時には誰よりも褒めて喜んでくれた。それゆえ杉屋はひっきりなしに子供が出入りして、ばーさんの怒鳴り声が絶えなかった。
「リョータは知らねえかも知んねえけど、あのばーさん”すず”って名前なんだぜ」
「ホントかよ!今年で一番知りたくなかった事実だわー」
軽口を叩いてみても、二人の笑いは湿り気を帯びていた。
身長はとうにばーさんを越えて、どんなに大人っぽくなっても、あのしわくちゃの笑顔の前ではいつだって子供に戻れた。
寂しくないわけがない。
オノケンはぼんやりとシャッターの閉まった杉屋を見ていた。
懐かしさのあまりつい忘れていたが、さっきの小包は、ひょっとしたらオノケンが直接僕の家に届けたのかもしれないと思いついた。何しろ数年ぶりに会った友人の名前が書かれた小包が、偶然にも再会した同じ日に、僕のうちに届けられるなんて都合のいい事があるワケない。
「オノケン。コレさっき家に届けられたらしいんだけど何か知ってる?」
オノケンは小包を一瞥しただけで、何も言わなかった。知っているなら知っている、知らないなら、思い出すようなリアクションがあってしかるべきだと思うが。
しかし彼は平坦な口調で答えた。
「リョータ。”お楽しみ会”の真実を知りたくないか?」
そう呟いた後の彼の目は、先ほどと変わらず、虚ろなままだった。
「小学生の賭けトランプぐらいで真実とか大袈裟な」
「そうかもな。でも何があったか全部は知らないだろう?」
「分かった、何だか面白そうだし。何をすればいい?」
「情報が欲しい。特に俺がなぜ”裏切り者”になったのかとか」
「知ってたのか……”セカンドインパクト”のこと……」
お楽しみ会は、管理者であるオノケンの転校を機に空中分解した。その存在と罪は、大人達に知られる事なく消え去るはずだった。オノケンがいなくなった事で、参加者のお金の貸し借りがわからなくなってしまっていた。それゆえゼロからの再開を望む声もあるにはあった。だが同時にその悪事が明るみに出て、糾弾される事を恐れていたし、絶対的なカリスマ性と、明晰な頭脳を持っていたオノケンの代わりをやろうという者は現れなかった。決して固く結束していた会ではなかったが、一様に連帯感みたいなものは、確かに感じていた。何より、絶対のルールとしてあった「大人に悟られないようにする」を守れなくなっては、デメリットしか存在しないだろう。
しかしお楽しみ会の思い出が、記憶の片隅に追いやられる前、突然僕は担任の山崎先生に呼び出された。
参加者の誰かが裏切り、“お楽しみ会”を告発したのだ。
後に僕らは”オノケンショック”に続く”セカンドインパクト”と呼び、吹き荒れる非難の嵐に翻弄された。クラス会議、児童会、職員会議、PTA。あらゆる所で議題に上り、繰り返し批判された。さすがに警察沙汰にはならなかったが、参加者の多さやシステムの巧妙さが問題視され、学校でも家でも厳しい監視がしばらく続いた。
個別の聴取は、オノケンが管理していた出納ノートを元に行われた。仲間内では、タイミング良く転校したオノケンが、バラしてお金を持ち逃げしたという噂が、まことしやかに囁かれていた。大人達が把握していた内容は、それ程に詳細だったし、本人が不在、更に批判される事に疲れ切っていた事も手伝って、誰かを張本人として吊るし上げなければ、日常生活をマトモに送れないまでになっていた。
しかし僕は、この噂を肯定する気にはなれなかった。オノケンが転校して、糾弾が始まるまで1ヶ月近く空いていたし、そうする理由が見つからない。突然理由も言わずいなくなるという、ある種裏切りにも等しい行為からすると、何か特殊な理由があった事は想像できるが。でもそこまで行けば、僕の想像以上の事があったしか言いようがない。
幸か不幸か、何年かぶりに、その答えを持つ本人に再会する事が出来た。
「お楽しみ会」の遺産
僕は、お金なんか欲しくないなんて言えるほど、善人でもない。しかし子供の頃の苦い思い出に関係するお金だとすれば、正直なところあまり関わりたくないのが本音だった。
「親父がさ、まだここに住んでんだ。それで流れてくるウワサを聞いて」
「……そう」
ウワサとはどこまでのウワサだろう。
単にお楽しみ会の事が明るみに出た、ぐらいか。それともオノケンが裏切り者と言われていた事なのか。8年ぶりに会った友人に、いきなり核心を突くような質問は出来ない。何しろ平和第一主義の戦隊ブルーの僕には、そんな必殺技が可能な心臓は装備されていない。
「じゃ行くか」
オノケンは立ち上がり、軽く尻の埃を叩く。
「ん?場所を変える?」
「場所というか、人かな」
「オノケン、もっと凡人でも分かるように解説してくれないか。誰もが君を理解できるほど、君の言動は分かりやすくないんだから」
「すぐにわかる」
悪戯小僧の笑い。
僕も立ち上がり、オノケンに続いた。ほんの数年前のことなのに、ずっと忘れていたこの感覚。それこそ一定の手順を必ず踏襲するお約束のように”すぐわかる”と先頭を歩くオノケンの背中を追った。
まだ空は明るく、時々体に当たる陽光にもはっきりと熱を感じる。暑さ寒さも彼岸までと言うが、夕暮れに近づくにつれて、急に過ごしやすくなった。
子供の頃は同じ道を歩きたくなくて、横道をへ逸れることがよくあった。それどころか人の家の庭先を、時には道なき道を突き進み、叱られることよりも、怪我をすることよりも、小さなドキドキを最優先して。
「この辺りは昔から変わらないな」
「古い家が多いからね」
僕らは、白壁の続く道を進み、立派な門構えの日本家屋の前を通りかかった。この一画は戦明治維新以前に建てられた家だと聞いた事がある。広く手入れされた日本庭園や大きな木造家屋が並び、ここだけ時代の流れなから取り残されたようにいつまでも変わらない。
途中、一件の家の門柱に野菜で作られた馬と牛が置いてあった。お盆の時期によく置いてある迎え火と送り火の精霊馬だ。死んだ人があの世から帰ってくる時は足の速い馬に乗り、帰る時は歩みの遅い牛に乗って帰る為に飾ってあり、出来るだけ長い時間家に滞在して欲しいと言う願いが込められていると言ういわれがある。
「ガキの頃はコレの意味も分かんねえで、よくイタズラしたなあ」
「僕は勝手にチワワとかにした事ある」
旧友と再会したせいか、どうしても昔を思い出すような発言になってしまう。昔のTV番組なんかを見て、父さんがよく言っていた。この頃は学生だったとか、あの頃は大変だったとか、今のやつらは楽をしすぎだとか。そんな姿をカッコ悪いなと苦々しく思っていた。
でもカッコ悪い僕は、いざ自分がその立場になってみると、やはりカッコ悪い。ばーさんが生きていれば、オノケンが転校していなければ、もっと幸せだっただろうと想像せずにはいられなかった。
後ろから走り寄ってくる足音に気づいたときはもう遅かった。
突然僕は突き飛ばされ、前へとよろめく。そしてその人物を確認する前に、容赦なく顎に掌底を喰らってしまう。
「よくも今更私の前に顔を出せたものね、賢至!覚悟しなさい!」
「久しぶり。お前は変わらねえな、元気……なことはたった今確認したぜ」
「なんだよいきなり、いったい誰……」
油断してた事もあって、かなり顎が痛い。しょっちゅう姉から攻撃されているので、咄嗟に受け身を取る習慣が身についてるとは言え、やはり痛いものは痛い。
「うるさいリョータ!でかくて邪魔なのよ!アンタはとりあえずこれ持って」
そう言うと彼女はそれを放り投げる。僕は慌てて手を伸ばし、何とかそれをキャッチした。
何コレ?シャベル?
彼女の破れたGジャンには、どこかで見たような『危険人物』と漢字で書かれたワッペン、薄い青のフレアスカートをひるがえし、両手を腰に仁王立ち。そして面倒くさそうに黒髪を背中へ払い、オノケンへと向き直った。
「言い訳があるなら今のうちに言いなさい。どんな訳でも許さないけど!」
「もしかして……桜井か?」
「もしかしなくても桜井よ。私がウルトラマンか新幹線に見えるなら今すぐ眼科に行きなさい」
この威嚇する猫みたいな女は、桜井れいなという生き物だ。5、6年生と同じクラスで、中学校も同じだった。吊り上がった大きな瞳でギロリと睨む。身長や髪型が、小学校の時からほとんど変わっていないので幼く見えるが、性格は猛獣のそれである。どんな有名人に似ているかと訊かれれば、ウルトラマンに似ている。どんな乗り物に似ているかと訊かれれば、新幹線に似ている。強さも早さもだ。
とにかく意味不明な理論をふりかざして、強引に物事を押し進めようとする為、その行動は理解しがたい。5年当時、体育の着替えで女子が教室を使うから、男子は渡り廊下で着替えろと言い出した。百歩譲って教室以外で着替えるにしても、何で夏暑く冬寒い渡り廊下なのかと反論すると、囮に決まっているじゃないバカと。
桜井曰く、アンタ達の裸なんて一円の価値もないんだから、せめて女子が着替えている間の囮になればいい。それが世の為人の為。抵抗は無意味、諦めなさいと。
あまりに僕の常識範囲外にあるものだから、女の子とか人間とかじゃなく、桜井れいなという生き物だと思うことにしている。
「いきなり酷すぎるだろ。僕が何したってんだ」
「私は賢至を狙ったわ。アンタが勝手に当たって来たのよ」
「加害者の台詞とは思えない……」
「リョータ、黙って。コイツったら、私に宝石をくれるって約束したくせに、次の週にいきなり転校して逃げたのよ!今度会ったら絶対掌底かますって決めてたわ!」
そう言って、オノケンの鼻先ギリギリまで人差し指を突きつける桜井。
ま、実際に掌底を喰らったのは酒井リョータな訳だが、そのあたりの事は誤差範囲らしい。
しかしオノケンのストライクゾーンは謎すぎるな。前世でどんな大罪を犯したのか知らないが、罪滅ぼしにしては過酷過ぎる。
恐らく身長180cm近くあるオノケンに、140cm代の桜井が思い切りつま先立ちで指差ししている為、滑稽以外の何ものでも無いポーズ。オノケンはオノケンで、挨拶より掌底を繰り出してきた桜井を恐れるでもなく、かと言って怒るでもなく、昔を懐かしむような暖かい眼差しで彼女を見ていた。それにつられて、きっと僕も微妙な顔をしていたのだろうと思う。桜井はオノケンと僕の顔を交互に見て、その表情から何かを悟ったのか再び目を吊り上げ牙をむいた。
「何二人してニヤニヤしてんのよ気持ち悪っ!どうせ昔と変わらずチビのままとか思ってるんでしょ、失礼ね!すごく失礼だわ!私がチビなんじゃなくてアンタ達がデカすぎるのよ!日照権侵害で訴訟を起こされるレベルだわ!」
「いや、それは誤解だ桜井れいな。俺の言う“変わらず”は、変わってなくて安心した。って意味だ。キミは俺が恋したあの頃と変わらず魅力的で、チャーミングな女性のままだ」
オノケンはそう言って、桜井の目を正面から見つめる。そして恐らくは少女マンガなら間違いなく背後に壮麗なバラを背負っていたであろう最高の笑顔を見せた。
「なっ……えっ……バカッ!アンタバカでしょ!バカバカっ」
みるみるうちに桜井の顔は真っ赤になり、ブンブンと腕を振り回す。
うーんオノケンめ、そんなにイケメンでも無いくせに。成長して女性を扱うスキルを身につけたと見える。
「なあ、リョータもそう思うだろ」
おっと、こっちにトスが来た。ここは上手く打ち返さねば。
「まったくその通りだ。今も昔も桜井はチャーミングだ。どれぐらいかと言うと、チャーミングといったら桜井。桜井といったらチャーミングぐらいだな。うん」
「あそ。そりゃドーモ」
桜井は半目で僕をにらみ、ぶっきらぼうに答える。さっきとは540°ぐらいかけ離れた態度だ。せっかくオノケンに打ちごろのトスを上げてもらったのに、大空振りだったか。言い訳を言わせてもらうと、オノケンとの経験の差もあるのだろうが、僕の姉の影響が大きいと思う。なにしろ機嫌が良くても悪くても蹴られることに変わりはない。結果が分かりきっているなら、あえて努力しようとしなくなるのは自然だと思うのだが。
「二人ともそろそろ行くぜ。今日中に終わらせねえと時間がないんだ」
オノケンはくるりと背を向け、枝分かれした細い道の方へと静かに歩き出した。
「行くってどこへよ」
「よく知らない」
「何で知らないのよアンタ、バカじゃないの」
「僕は杉屋の前で偶然会っただけだよ。桜井こそ何しに来たんだよ」
「私は賢至に呼び出されたから来ただけよ。急にシャベル持ってきてくれないかって」
「悪いなリョータ。本当はあそこでお前を待ち伏せしてたんだ。たぶん通ると思って」
「何だよ、用事があるなら最初からウチに訪ねてくればいいじゃないか。まわりくどい」
「ヤダよ。お前ん家の姉ちゃん怖えし」
「それは本当にすまないと思っている。こんど玄関に”モンスター在住”って貼っとくわ」
並んで歩く3人の足元から伸びる影は、長く長く伸び、遠くの塀へと届いている。オノケンの言う暗くなる前にーーの意味がわからないけども、辺りが見えなくなるまでに1時間も無いかもしれない。
僕は、なんとなく隣を歩く桜井の横顔を見て気がついた。
(口紅……化粧をしているのか……あとネックレスも)
18歳の年齢からすると、化粧をするのは常識の範囲内かもしれない。しかし桜井れいなの家庭と個性を考慮した時、疑問符が付く。彼女は体を動かす事が好きないわゆるスポーツ少女だ。ファッションなども動き易さ最優先だと本人も公言していたし、私服でスカート、という格好も見たことがない。というかジャージしか見たことがない。
クラス皆んなで行ったUSJ。めかしこむ大勢の女の子達の中、桜井は一人だけジャージで現れて”私は今日伝説になるから”と高らかに宣言し、ゲート開放と同時に全力ダッシュ。そして全力で転んで、開門5分で救護室に運ばれるという伝説を持つツワモノだ。
そして3人の兄の存在。年子の男三人の後に産まれた彼女は、かなり甘やかされていたように思う。天気が悪い時の送迎は当然として、父兄参観日は運動会は桜井家の一大イベント。そんな日に、桜井れいなと会話をしているところを見られようなものなら、兄+父の四人の男に囲まれ強迫されるという地獄を味わうことになる。彼女自身もそういった被害者を出す事を好ましく思っていないらしく、出来るだけ色恋沙汰は避けていると聞いたことがある。
僕はふと我に返った。
桜井れいながメイクをしてスカートを履き、男と並んで歩いている。もしこの状況を誰かに目撃され、それが桜井家に知られたら本人の意思はどうあれ、厳しい糾弾は免れない。そう思いついた時、本能的に危険を察知し、半歩、ほんの半歩だけ桜井から離れてしまった。
「リョータ!なに離れてんのよ、コッチ来なさい!」
こともあろうに桜井は腕を絡ませて、強引に僕を引っ張り、オノケンの横に並ぶ。さながら捕らえられた宇宙人の如くだか、本人はご満悦の様子だ。
「こういうの一度やってみたかったんだあ♪」
「さっ桜井には兄弟が三人もいるじゃないか」
「お兄ちゃん達はダメよ。小さい頃一度やったら、誰と誰の間を歩くかで大ゲンカしたのよ。それ以来ウチでは並んで歩くのは禁止になったわ」
不埒にも、腕に当たる柔らかい感触を意識してドキドキしてしまう。今が夕方で良かったとつくづく思う。オレンジ色の夕陽は、きっと僕の上気した恥ずかしい顔を誤魔化してくれているに違いない。
「こんな美少女と腕を組めてラッキーとか思ってるんでしょリョータ」
「いやチョット、何を言っているのか理解できませんケド……痛い!」
思い切り足を踏まれた。照れ隠しのツッコミなんて可愛いものではない。足の甲の辺りを踵で踏みつけるという、完全に壊しに来ている踏み方だ。のんきにラッキーとか思えるわけがない。
桜井に合わせて小さくなった歩みは、砂利ばかりの不安定な小道を進む。両側を垣根にはさまれたここを抜け、溜め池へと流れ込む小川を越えると、僕たちが通った小学校への近道になるのだ。
「賢至、そろそろ何をするつもりなのか教えなさいよ。小学校に用事?」
「……“お楽しみ会”、覚えているな。アレの真実を探る」
オノケンの言葉に桜井の歩みが二歩三歩と鈍化し、ゆっくりと止まった。
「何ソレ……何で今更そんな事するわけ?もう何年も前のことでしょう⁉︎」
「いや、俺は明らかにすべきだと思う。2人とも俺に会ってまずその事を思い出したんじゃないか?」
「……っ確かに、クラスの誰かが山崎先生にバラしたかもしれないけど、でもそれが判ったところで過去は変えられないし、良いことなんて何も無いわ!」
桜井に掴まれている腕が痛い。こんなに強く拒否感を露わにするなんて少し意外だ。彼女の性格なら面白そうとか言って、喜んで協力しそうなものだが。でも反対する気持ちも理解できないわけでは無い。
今もし犯人がわかったとしても、当時の僕らが助かるわけでは無い。それどころか少年時代のつらい記憶に、裏切り者がいたという新しい記憶が付け足されて、また苦しむ事になりかねない。けれども誰が、何故、といった長年の疑問を解消して、初めてあの事件を完結させることができるとも考えられる。
要はうずく古傷を放置するか、完治させるためもう一度痛い思いをするかの二択なのか。果たして僕はどちらを望んでいるのだろうか……
「リョータはどう思う?」
「そうよ、リョータはどっちなの?私と同じよね?」
2人の目が僕へと注がれる。2人とも僕の大事な友達で、双方の言いたい事も理解できる。でもこれは本当に真ん中に線を引ける事なのか、白と黒にはっきりと分かれている事なのか。
「……えと、その前に、二、三確認しても良いかな?」
僕は桜井の手を丁寧に下ろして、ちょうど2人の間に立った。
「お楽しみ会の真実って何?何故僕と桜井の2人を誘った?」
「真実を知る事で、俺が犯人でない事がわかるはずだ。それを証明する」
「じゃじゃあ!あの事をバラしたのは賢至じゃないのね?」
桜井はわずかに安堵した表情で、長年僕らの間で度々話題に上がる、答えの出ない疑問を口にした。答えはオノケンが持っている、オノケンにしか答えられない。いつも堂々巡りで終わっていた迷路の答えを。
「俺なわけないだろう。それに勘違いすんなよ、俺の目的は犯人探しじゃねえ。自分の無実を証明したいだけだ」
僕と桜井は目を合わせて大きく息を吐いた。やはりオノケンは僕たちの信頼できるリーダーだったオノケンだ。たとえ急な別れで、言葉を充分に交わせなかったとしても、疑うべきではなかった。僕は、ほんの少しでも彼を疑ってしまった事を恥じた。
「オノケンごめん。ハッキリとした理由も分からず、周りの意見に流されて、もしかしたら、と疑った事がある。謝るよ」
「いいんだ。弁解できない状況では仕方が無かった。せめて別れを言う機会があったら、こんな事にはならなかったのにな」
ぽんと軽く僕の方を叩く。その何気ない仕草がなつかしく、妙に嬉しかった。
さよなら、また会おうと言えていれば、皆の心がオノケンから離れてしまうことは無かったかもしれない。心にもやもやとしたものがあると分かっていながら、自分には何も出来ない、仕方がない、と諦めてしまっていた。今日もしオノケンが僕の前に現れなかったら、このもやもやを抱えながら過ごしていただろう。奇跡、と簡単に言ってしまうのも憚られるが、数年の時を経て再び僕らは友達に戻れたと、深く深く実感した。
「ま、まあ私は、最初から賢至が犯人だなんて思っていませんでしたケドも」
取ってつけたような桜井の主張に、一瞬時が止まり、なんとも言えない軽薄な空気が流れた。
「お前はこのタイミングでよくそんなことが言えるな」
「なんつったっけ?KYか。ケーワイ桜井に改名だな」
「ななな何よ!元はと言えば賢至がいきなり転校するのが悪いんでしょお⁉︎この桜井れいな様に!断りもなく!」
俺の後ろに隠れて偉そうなこと言ったって、どうにもならないぞ。
しかし桜井もまた、オノケンの事を疑いつつも心のどこかで信じていたのだろう。“本当の事を明らかにする”と言っていたオノケンの言葉は、罪の告白とも解釈できる。男っぽくて乱暴者の桜井だが、僕と同じように、オノケンとの再会にとまどっていたと思う。素直に喜びたいが、変わってしまったオノケンは見たくない。そう考えると、先ほどの強い拒否反応も、ほっとした安堵の表情も理解できる。
「転校のことは悪かったと思っているよ。特に桜井にはな。でも俺だけではどうしようも無かった。あの日も“お楽しみ会”の帰り、離婚が決まった母親が俺を待ち構えていてよ、いきなり車に乗せられてハイ、さようならだ。こっちの都合なんか関係ナシさ」
「それならそれで言ってくれれば良いものを。山崎先生は何も言ってなかったし」
「親父はまだあそこのマンションに住んでるからな、口止めしたんだろう。家族に逃げられることを恥だと思うような小さい人間だし」
オノケンの言葉にはわずかに怒気を感じる。他人の家庭の事情に深く踏み込むべきではないけれども、離婚したという父親とはうまく行ってなかったのかもしれない。
「そうするとだ、先生に呼び出された時に見せられた証拠のノート。あれはオノケンが持っていたお楽しみ会のノートじゃないっていうことなのかな」
「でも参加者とかお金のやり取りとか全部書いてあるから、言い逃れできないって。実際参加者全員呼び出されてたし」
「お前たち、そのノートの中身は見たのか?確かに俺のノートだったのか?」
「うーん……そう言われると自信ないなあ。中身は見てないし、表紙をちらっと見ただけだったし」
オノケンが転校して、一ヶ月ほど経ったあの日、僕らは1人ずつ担任の山崎先生の元に呼び出された。そしてお楽しみ会の存在と、参加していたかどうかを確認され、言い澱む者には証拠とされるノートの存在を示し、きちんと真実を言うように促された。参加者は皆んな、オノケンがお楽しみ会の内容と結果、お金の動きなどをノートに記録していたことを知っていたので、もはや言い逃れはできないと覚悟していた。
「だとすると、状況から見て、そのノートは間違いなく偽物だ」
「どういうこと?誰か……ってか犯人が偽物を先生に渡したってのか?」
「で、でも先生は全てここに書いてあるって言ってたし、参加してた人は全員……」
「少し思い出してくれ。俺たちのクラスで誰がいつどれだけ参加していたか全て覚えている人物はいるか?俺でさえ毎回は参加していなかった。他のクラスも合わせれば、なおさらだ。つまり正確に把握するにはノートの書かれていた名前を照合するしかない」
不特定多数の人が、複数回行われている”お楽しみ会”に参加していた。
会は数十回開催さてれいたし、場所も毎回違う。管理者役だったオノケンも都合で参加せず、結果報告だけをノートにまとめていたとしたら、全てを把握するにはやはりノート見るしか手段は無いはずだ。
「当時は追求され、そうとう叱られただろう。しかし個人の名前を挙げて、晒し者にするにするような事はしなかったはずだ。外へ名前が出ないよう、一定の配慮があったように思う。つまり、いちいちノートを見て、参加者の真偽を確認できなくても、子供達の反省を促すことができればそれで良かった」
たしかに思い出すと、子供の遊びの範疇を逸脱した行為には容赦なく批判され、叱責を受けた。しかしオノケンの言うように、人前で誰とハッキリ分かるような方法は取られなかったように思う。
「大人の立場からすると、誰がお金をいくら儲けたとかいくら損したなんてのは問題じゃない。賭けトランプが行われていたという事実が問題だった。そして直接関係の無かった生徒にも注意喚起する、目的としちゃそんなとこだろう。なにしろ俺はそうなるように参加人数を調節していたんだから」
お楽しみ会を始めた当初、数人の仲間内での開催に止まらず、参加者を積極的に増やそうとしていた。僕は“お楽しみ会”という皮肉なネーミングの通り、隠れて少人数で行うのかと思っていたので、とても意外に思った。普通、秘密を共有している人数が増えるに従い、大人達にバレる可能性は高くなる。しかしオノケンの行動と結果、今の発言を総合すると、バレた時に世間的にどの程度騒ぎになり、誰に叱られるかまで考えてやっていた、と思わざるをえない。すなわち、小規模で個人に迷惑をかけるタイプのイタズラなら少人数で。大規模で多人数に迷惑をかけるタイプのイタズラなら多人数で。数学的に解釈するなら、責任を測れる単位があるとして、一人が負う責任の量が一定になるように参加人数を調整し、一人にかかる心のダメージを減らしていたという事になる。流石というか何というか、当時からイタズラの天才だと思っていたが、その言葉の意味は、僕の想像の域をはるかに超えるレベルに達してたようだ。
「大人達の目的からすると、ノートの真偽はどうでもよかった、と。それで、オノケンがノートを偽物だとする根拠は何?」
オノケンは無言で、僕の持っている小包を顎でさした。
「何よそれ。宝物?」
「ある意味そうだな」
ニヤリと笑うオノケン。
「ホンモノはそこにある」
僕が担任の山崎先生に呼び出された時、証拠のノートがあると確かに言っていた。心当たりのあるノートは1冊しかなく、それが本物か偽物かなんて考えもしなかった。
”お楽しみ会”のノートはもともとオノケンが管理し、いつも持ち歩いていたものだ。本物がちゃんと保管しててあって、ここにあるという事は
山崎先生が言っていた証拠のノートとは偽物か、全く別のノートということになる。
「転校することになったあの日、俺はノートと貸し借りしていたお金を、保管しなければ思った。このまま家に置いておくと、どうなるかわからないからな。一番良い方法は仲間の誰かに事情を話して、託すことだったのだろうが、そんな事をする時間は全く無かった」
「家もダメ。渡す時間も無いじゃどうしようもないじゃない」
「ああ、俺はそれで一か八か箱に入れて埋めようと思い、外へ飛び出したんだが、そこである人が目に止まった。
杉屋のばーさんだ」
杉屋はオノケンが住んでいたマンションの隣にあった駄菓子屋だ。店が開いている時は、近くにいるはずだし、あのばーさんなら信用できる。
「必ず取りに来るからと言って、ばーさんにコレを預けた。しかし、そんな機会は訪れることなくばーさんは死に、箱だけ残された」
「じゃじゃあ、何で偽物なんかを作ってバラしたりするワケ?何も良いことないじゃない
「これは半分俺の想像なんだが……」
オノケンは腕を組んで大きく息を吐いた。いささか大げさな行為だけれども、僕がオノケンの立場だったらきっと同じようにしたと思う。仲間を地獄に引きずり落とすようなことをする理由など、想像とはいえ考えたくもない。
「ギャンブルをやめたいと思う時って、いったいどういう時だと思う?」
「お金がなくなった時かしら、もう続けられないーって」
「大勝ちした時かな。勝ち逃げできる、みたいな」
「俺は借金を作ってしまい、それから逃げられなくなった時ではないかと思う」
断っておくが、この会話の中で出てくるギャンブルとか借金なんてのは、あくまで小学生レベルでの話である。もらっている小遣いの額に差がある事は分かった上で、それに合わせて掛け金とか賞金を設定していた。大勝ち、と言っても杉屋で買う駄菓子が一個増える程度の事だ。借金の額にしても同様なのは言うまでもない。
「借金までしてギャンブルとかサイテーだわ」
「逃げ出したくなるほどの借金って僕達には当てはまらないんじゃない?」
「俺がいた頃はそうだった。だが、その後はどうだ?たしか一ヶ月ほど期間があって、騒ぎになった。妙だと思わないか?」
僕と桜井は顔を見合わせた。
オノケンが突然転校した”オノケンショック”の後、再び”お楽しみ会”をやろうとした動きがあった事は知っている。だが実際に開催されたかどうか、誰が参加したか、どんな状況だったか等は、全く知らなかった。
「私もあまり知らないけど、隣のクラスの男子が”今日は勝ったからおごってやる”と言って、イカ串をケースごと買おうとして、おばあちゃんに怒られてたの覚えてるわ」
「じゃやっぱり”お楽しみ会”を再開してたってこと?」
「しかもかなりのハイレートだ」
勝ったからといって、イカ串をケースごと買おうなんて、僕らの”お楽しみ会”ではとうてい考えられない額だ。おそらく掛け金自体が、一桁か二桁は違ったのだろう。それだけ勝ったやつがいるということは、それだけ負けたやつがいるということに他ならない。小学生の財力などたかが知れているから、かなり逼迫した状況になる事は容易に想像ができる。
’オノケンショック”から”セカンドインパクト”までおよそ一ヶ月、お楽しみ会を再開し、借金で首が回らなくなるには十分な時間だ。
「ニセモノのノートは、そこで使われていたノートなのね」
「その可能性は無くはないが、俺は低いと思っている」
「え?でもノートはニセモノだってさっき言ってたわよ」
「結果から考えてみてくれ。刑事ドラマなんかによくある”事件が起きたことによって誰が一番得したか”ってやつだ」
「えと……この場合”お楽しみ会”が無くなって、得したヤツ?」
「そうか!借金してたヤツが、”セカンドインパクト”でお金のやり取りが禁止されたから、結果として借金帳消しになって、得したのか」
「その通りだ。恐らく犯人は俺が転校したことよりも、持っていたノートが無くなったことにより一度借金が消えたことに注目した。そして再び借金を作ってしまい、同じように借金を消そうとした。が、そもそもお金のやり取りをノートで管理していなかった」
「だから……」
「だから、何よ」
「俺のノートのニセモノを作り”お楽しみ会”の全てを告発する事で、大人達に借金を帳消しにさせた……といったところだろう」
「流石だわ賢章!その場にいなかったのに伝聞だけで全部わかっちゃうなんてアンタ探偵とかやんなさいよ、マンガとか映画みたいな」
そう言って桜井はその場でスカートを広げ、くるくると回ってみせた。
はっきりと何かコレという理由があったわけではない。ただ少し違和感を感じた。
一寸の先も見えない暗闇の中で、手を伸ばしても伸ばしても、空を切る虚しさ。助けを求める声は誰の耳にも届かず、手を差し伸べてくれる者は誰もいない。
そんな中、暗闇に一筋の光が射したとしよう。僕を含めたほとんどの人が希望を求め走りだすに違いない。足元に転がっている石も穴も罠も、顧みる事なく。
オノケンは何かを焦っている。
よく考えると、ニセモノのノートの存在。ノートである必要は無いのではないか。大人達を動かし、“お楽しみ会”の存在を暴露する目的なら、密告や手紙でもいいのではないか。事がコトだけに僅かな疑いさえあれば、調査に乗り出す十分な動機になる。
それに犯人の行動。借金のために場をひっくり返すなんてのは、天才オノケンならではの発想ではないか。僕ならまず、姉か杉屋のばーさんあたりに泣きつくと思うが。
「リョータ!聞いてる?」
「え?……何なに?なんだって?」
「小学校に行くわよ」
「学校?なんで?」
「本来なら、クラスのみんなの前で、俺の無実を証明したいとこなんだが、もう全員が集まる機会なんてほぼ無い。だが、山崎先生を含めた大勢が集まる予定の日が1日だけある」
「……成人式!それで僕と桜井なのか」
僕と桜井は、5年のクラスのタイムカプセル係だった。
タイムカプセルとは、もはや説明不要のアレである。僕らのクラスでは、未来の自分へ向けた手紙や思い出の写真を入れ、成人式の日に掘り起こす事になっていた。イタズラで勝手に掘り起こされないように、埋めた場所については、タイムカプセル係である僕と桜井、それに担任の山崎先生しか知らない。一応は三人の同意のもと、掘り起こす事になっているが、成人式にここに来れない可能性も考えて、最低一人は立ち合いが必要なルールになっていた。
僕ら三人は、学校の裏手にある垣根の切れ目から、敷地内に入った。ここからなら、校舎から見られる心配は無いはずだ。そしてそこには丁度目印になるような大きな桜の木が生えているし、宝物を埋めるにはうってつけの場所だ。
「ところで何でわざわざここに埋めるワケ?リョータに預かって貰えばいいじゃないの」
そこは、自分が預かるじゃないのか。
シャベルを使っているとはいえ、意外に堅い土に苦戦を強いられる。こんな所にデカイ穴を掘るなんてやった事がない上に、帰宅部軟弱男子には辛い作業だ。
「成人の日。つまりクラスの皆んなが出来るだけ揃う日に、遺産がここにある事が重要なんだ。タイムカプセル係のお前達がいれば、俺の無実を証明できる」
「なに他人事みたいに言ってんのよ。アンタが成人の日にここに来ればいいだけの話じゃない」
「俺、実は……遠く……外国へ行くんだ。しばらくは帰ってこれない」
「外国って留学とか?」
「そうだな……そんな感じだ」
「そう……」
ウソだ。オノケンはウソを言っている。
桜井はオノケンから視線を外して遠くを見ている。ザクザクと土を掻く音が、暗闇迫る校舎の壁に反響して寂しさを増していく。
僕らにも言えない事情があるのかも知れないが、それならせめてウソをつかないで欲しかった。これでは5年生のあの日、何も言わず転校してしまった時と同じじゃないか。
突然の別れから8年ほどの月日が流れ、その間何があったかはお互い知る由もない。今回オノケンが突然現れて、図らずも昔の記憶を思い起こすことになり、小学生に戻ったような感覚になった。しかし、本当の自分はあれから成長し、多少の苦いも甘いも経験して大きくなったつもりだ。
「……やっぱりこんなことはやめよう」
僕は大きく息を吐いて、シャベルを動かす手を止めた。
「リョータ?」
「今さら昔の事をほじくり出すべきじゃないよ。山崎先生には僕から話しておく。成人式の日に先生の口からオノケンの無実を語ってもらう。それでいいだろ」
「ダメだ。大人は信用できない」
「成人の日には大人の仲間入りをしている!僕だってその日にハイどうぞと大人になるものじゃないことは知ってるさ。でも、ゆっくりと確実にその信用できない大人になって行く。僕も桜井もそしてオノケンキミもだ!」
思わず放り出したシャベルが、穴の縁に置いてあった小包に当たり、甲高い音を立てた。僕は構わず、オノケンへの追求を続ける。
「外国へ行く……なんてウソだろ?本当の事を言えない事情があるならそう言えばいいのに……僕ら……友達じゃなかったのかよ……それとも君はもう信用できない大人になってしまったのか」
僕は悔しかった。
スポーツも勉強も恋愛も友情も、熱を持って挑まずにいた自分が。
どこかに冷めた目で見ている自分がいて、そうする事が恥ずかしく、周りの友達と違うところに立っている自分が。
そして羨ましかった。
嫌いなものを嫌いと、好きなのもを好きと言える強さを持ったオノケンを。
それだけに、彼から信頼されていない自分を、同じ熱を持てなかった自分を、後悔した。
だからせめて、今は同じ温度で悔しさをぶつける。もうすぐそれさえも出来なくなるのだから。
「リョータ……残念だが俺は…………!」
深く、重苦しい沈黙。
見るとオノケンは、僕でもなく桜井でもなく、シャベルがぶつかって一部新聞紙が剥がれている小包に視線を送っていた。
「どういう事だ……アレは俺の預けた箱じゃない……」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
拝啓 小野賢至様
まずは貴方から預かった箱を勝手に開けてしまった事をお詫び致します。
最初、ノートの中身を見て驚きました。いたずら好きで、近所の子供達のリーダーだった貴方が、犯罪者まがいの真似をして非常に残念な思いがしました。ですが、貴方が私を信頼し、ノートとお金を預けてくれた心に応えるためにも、他言するつもりはありませんでした。しかし、私のもとへ一人の小学生が訪れ、涙ながらに相談されました。その子は軽い気持ちから、賭けトランプに参加し、そのうち子供ではなかなか返せないほどの借金を作ってしまったという事でした。
同じ時期、私の店では駄菓子を大量に買おうとする子供が、時々現れるようになり、疑問に思っていました。
私は、子供は子供らしく、みんな笑顔で遊んで欲しい。誰かが泣くような遊びは止めるべきだと思い立ち、小学校の先生に相談しました。
貴方から預かったノートは、誰か特定の個人が責められる事の無いよう条件を出し、使っていただきました。
叱られた子供達は、辛い思いをして大変だったでしょうが、これも大切な経験のひとつとして大きく成長し、また先生や親御さんたちも、陰で大変な努力をされていた事も理解してほしいと思います。
ほとぼりが冷めた頃、先生からノートを返却して頂きましたので、いずれ貴方の手に戻る事を願い、手紙をしたためました。
一緒に入っていたお金は、貴方の欲しがっていた物と交換しました。恋の悩みを打ち明けてくれたお嬢さんへ、是非貴方の手で渡してあげてください。私のせめてもの罪滅ぼしです。
杉屋のばーさん 杉野 すず
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
箱の中には、オノケンのノート、おもちゃの宝石、そして一通の手紙が入っていた。
僕の読む手紙は、昔の真実を語り、想いを語った。
それは思ったより単純で純粋だった。
「オノケンこれは……」
動揺し、動けずにいるオノケンに代わり、手紙を読み終わった。そして振り返ってみるとそこに僕の友人の姿は無かった。
僕は隣にいる桜井と顔を見合わせ、オノケンは?と聞いてみたが、彼女もまた僕と同様にオノケンの姿を見失っていた。
現れた時と同じように、突然消えてしまった。
次の日、僕は桜井に誘われ、オノケンの父親のいるマンションを訪ねる事にした。
あの後、いくら探してもオノケンの姿は見当たらなかった。死者が帰るお盆の日に突然現れて、突然消えた。
最初に再開した印象といい、暑い日のパーカーといい、どうも普通じゃない。
一応は、お盆に合わせてオノケンが帰ってきたのではないかという事で落ち着いた。
「賢至の推理、半分は外れていたわね」
「頭が良すぎたのさ。どうにか白黒つけたくて、自分と他人が同じ考えを持つと思い込んでしまった。皆んなが皆んなオノケンほど頭は良くない」
「リョータはさ、自分が大人だと思う?」
「途中、としか。ゴールがあるならって話だけどね」
僕らが一緒に過ごした数時間は、あまりにも現実的すぎて、未だにオノケンが霊的な何かだったとは信じがたい。
夏場の怪談として、何百キロも離れたゆかりのある場所に現れて、別れの挨拶を言ったなんて話は聞くが、実際に体験した後でも本当だったのかどうか自信がない。
良く思い出すと、桜井はオノケンを叩こうとして空振りしていたし、僕ら以外に会話をした者もいない。
「結局、お楽しみ会の事が心残りで化けて出たのかしら」
「化けて出たってか、丁度お盆だったから、帰って来た。でいいんじゃない?」
「そうだアイツまた、宝石くれないでどこか行きやがったわ。代わりにアンタ貢ぎなさいよ」
「“行きやがった”と“代わりに”の間にどういう理論があったのか、僕に説明しろよ。話はそれからだ」
照りつける陽光が降り注ぎ、容赦なく肌を焼く。彼岸は過ぎても残暑がおさまるのはまだまだ先になりそうだ。桜井のかぶるつばの大きな帽子は、それをものともせず、濃い影を落とす。緩やかに波打つロングスカートを押さえる仕草は、映画のヒロインのようだ。
不覚にも、中身が桜井れいなだということを一瞬忘れそうなってしまった。
「そういえばさ」
少し前を歩く桜井は、くるりと振り返る。
「賢至が“お楽しみ会”をやり始めた理由、聞いたことある?」
僕は無言で首を振る。あまりそこに疑問を持ったことはないが、特別な理由とかあったのか?
「杉屋の駄菓子クジを買い占めて、特賞のおもちゃの宝石を手に入れる為だってさ。笑っちゃうわ」
ばーさんの手紙にあった、恋の悩みを相談したお嬢さんというのが、桜井だったかどうかは分からない。箱に入っていたおもちゃの宝石は、実は僕が持っているのだが、コレを桜井に渡すべきかどうか正直迷っている。オノケンの心残りはお楽しみ会の事じゃなくて、コレを桜井に渡せなかった事だろうから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
酒井リョータが小野賢至と再開する数時間前に遡る。
「よっ、桜井。久しぶり」
「アンタ……賢至じゃん。何しに来たのよ」
「冷たい反応だなあ。何年かぶりに友達が訪ねてきたんだぜ、もっと歓迎してくれよ」
「いきなり転校しといて無責任ね。あの後私たちがどんな目になったか」
「おうそれそれ。今日はそれもあってわざわざ九州から来たんだ」
「話が見えないわ。もっと手短に分かりやすく言いなさいよ」
「じゃ、手短に。まだリョータのこと好きなのか?」
「なっ!……なんでアンタがそんな事知ってんのよ。むむむ昔の話よ」
「まだ好きなんだな?」
「…………ぐぐっ……だだだだから何よ!いいでしょ別に!違うクラスだから接点が無いだけだし、文化祭とか超誘うつもりだし!」
「リョータはアホだから、桜井の態度から気づいてくれるなんて思うなよ。あいつはお前のこと女だと思っちゃいねよ」
「うるさいわね!アンタわざわざ九州から喧嘩売りに来たの!」
「んなわけあるか。お節介&罪滅ぼし&イタズラさ。お前とリョータの仲を取り持ってやるよ、めかし込んで後で小学校に来いよ」
「ええっ!?わわ私ジャージしか持ってないんだけど……」
「借りればいいだろう?リョータは意外にギャップに弱い。乱暴者の桜井が、女性らしい格好をするなんて思ってもみないはずだから、きっと意識するはずさ」
「何よ何をするつもり!?ちゃんと教えなさいよ!」
「お前はプレッシャーに弱いから、詳しく知らない方がいい。俺は幽霊になって戻ってきたという設定でよろしく。後はなんとなく話を合わせればいい」
「無理ムリむり!絶対ムリ!出来ないって!」
「俺はなあ桜井、お前のその過激なスキンシップに耐えられるのは、あの怪獣姉をもつリョータしかいないと思ってるんだ。知ってるだろ?」
「うん。酒井こいとさんでしょ、お兄ちゃんと同級生だし、道場で一緒だし」
「頑張れ桜井、お前の魅力でリョータをメロメロにするんだ!」
「メロメロに……わわわ分かった、ややってみる」
「うまく行ったら、明日にでも俺の住んでたマンションに来いよ。ネタばらしするから」
「えっ、ばらしちゃうの?」
「当たり前だ。イタズラはバレるからイタズラなんだ。じゃ待ってるからすぐ来いよ」
冒頭へと続く。