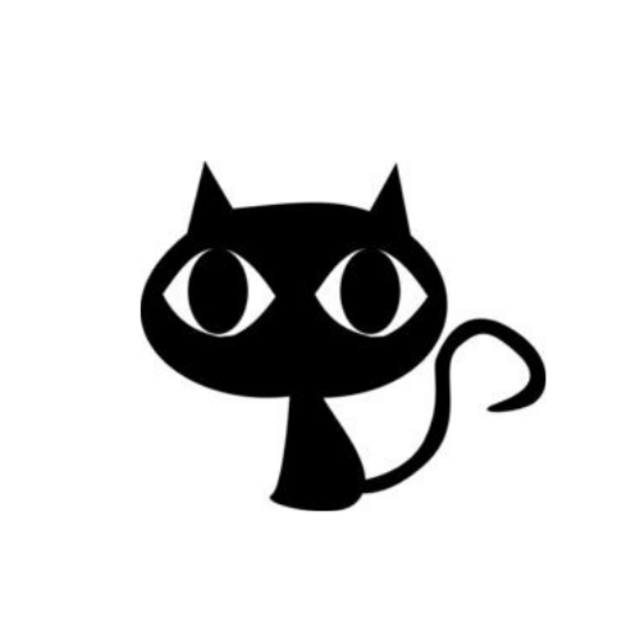毛虫
文字数 6,539文字
比喩や例えではなく、生まれたときから私は毛虫だった。緑色の葉の上、薄黄色い卵から孵った、一匹の小さな毛虫。殻の欠片を尻につけて見回した周囲では、すでにたくさんの兄弟たちが緑色の葉を齧っていた。その音があたりに満ちていた。カリカリカリカリ、音に促されるように、私も葉の表を齧った。なぜなのか、そうするべきだと私は初めから知っているようだった。カリカリカリカリ、透明だった体は、瞬く間に葉の緑色に染まっていった。その色がお尻の先っぽまでくると、私は同じ色の糞を出した。私の乗っている葉の根元には、私より大きな兄弟がいて、その兄弟は私より大きくて四角い糞をごろごろとお尻からひりだしていた。
「よお、兄弟」
大きな兄弟が私に呼びかけた。
「一つだけ言っておくことがある。頭の上には気をつけな。あの青くて広い空ってところからは、大いなる翼の持ち主や、強靭な翅の主、二つの目玉がやってくる。そいつらに見つかったらおしまいだ。見つからずに、なんとか生き延びてくれよな」
そう言うと、あたりで一番大きなカリカリという音を響かせながら、その空の方へと登っていく。
「ああ、忠告をありがとう。……兄弟」
その兄弟に私の声は届いたかどうか、返事の代わりに四角く大きな糞がごろごろと落ちてきて、それは私の乗る葉を大きく揺らして、さらに下へと落ちていった。
「ったく、あぶねえじゃねえか」
端っこにいたらしい兄弟が驚いたような声で叫んだ。
「気をつけろって言っといて、てめえのほうが気をつけろってんだ」
その私よりも少し大きな兄弟は、体中の毛を逆立てて怒った。と、その三角の目が私に向けられた。
「何だい。こちとら見せもんじゃねえぞ」
そんなつもりはないと言いたかったが、私は黙って目を伏せた。そうしている間にも、口は葉を齧っている。忠告に耳は傾けても、言い合いなどしている暇はない。私は早くあの兄弟のように大きくならなければいけないのだ。音を立てて葉を齧り、この新鮮な葉がなくなれば、どこか新しい葉のある場所へ移動し、そこで葉を齧らなければならない。あの兄弟が言ったように、十分「空」に気をつけながら。そうしなければ、大きくなれない。大きくなれなければ、もっと大きくなれない。もっと大きくなれなければ、もっと大きくなれなければ、そのときは——。
私の中には、ある鮮明な像があった。こうして葉を齧り続けていれば、私はこの目に浮かぶ想像の一部となれる。もちろん、そのときになったなら、それは想像ではなく、現実になっているのだから、想像の一部になるという表現はおかしいかもしれない。けれど、いまの私にとって、まだ小さな私にとって、それは確固たる目標でありながら、どこか夢のような想像だった。私はその夢に向かって、葉を齧り続けるのだ。
私が生まれてから一日経ち、二日経ち、一週間が経った。忠告通り、「空」に気をつけた甲斐あって、私は葉の上をほんの十歩で進めるほどに大きくなった。体の毛はより濃く、長くなり、糞も中くらいではあるが四角くなった。生まれた葉からはすでに離れ、何枚もの葉を齧り尽くしてきたのだが、ここへきてある問題に直面した。私の頭上に空が見えるようになったのだ。否、いままでも見えていた空が、より一層、恐ろしいほど広く私の頭上に広がっていることに気づいたのだ。
それはつまり、以前はそこに茂っていた葉が齧り尽くされてしまったということだった。私によって、私の兄弟たちによってか細い葉脈のみになってしまった葉は、最早私たちを隠す力も、養う力も失ってしまったのだ。
それでも私たちは粘り強く、葉脈に残ったわずかな葉の部分を齧り続けた。けれど、そんなことをしても限界がある。眩しい光は燦々と降り注いで私たちの体をしぼませ、その体を再び膨らまそうにも食料となる葉がそこにはない。また、問題はそれだけではなかった。「空」だ。このままではその恐ろしい場所から大いなる翼が、翅が、目玉がやってきてしまう。このままでは、まずい。そう考えるのは当然だった。生まれたこの場所を捨て、どこか別の場所——緑茂る場所へ移らなければ。
追い込まれた私はようやく移動を決意したが、それは私の兄弟たちも同じであったようだった。その日の朝、私たちは打ち合わせたかのように、同時に故郷を出発した。向かうは、未知なる地面——空とは反対にある場所。黙々と列を作る兄弟たちに倣って、私はその列の最後尾に着いた。垂直に茎を降りていく黒い筋が、地面に着くなり空と平行に動いていく。
「先頭の兄弟は、どの方向へ行くべきか知っているのだろうか」
前を行く兄弟が不安そうに呟いた。
「このまま地面を行くつもりが、いつのまにか『空』へ向かうことになりはしないだろうか」
「お前はまだ『空』が怖いのか」
すると、その前の前を行く兄弟がにやりと笑った。前を行く兄弟はむっとして答えた。
「ああ、怖いさ。それとも、君は怖くないのかい、兄弟?」
問いかけに、前の前を行く兄弟はさもおかしそうに高笑いした。
「弱虫め。そんなんでお前はこの先どうするつもりなんだ、兄弟? 俺たちはいつまでも『空』を怖がってるわけにはいかないってのに——」
前の前の兄弟が笑いながら振り向いたときだった。その兄弟の姿が消えた。黒い筋は、その兄弟のいた場所をぽっかり開けたまま、先へ進んで行く。どうしたことか、私は思わず歩を緩めた。前を行く兄弟が叫んだ。
「目玉だ、目玉が兄弟を食っちまったぞ!」
その叫びは、先頭の兄弟まで届いたようだった。目玉が出たぞ、兄弟たちの列が恐怖で乱れた。あるものは右へ、あるものは左へ、またあるものは方向転換して最後尾の私の方へまっすぐに戻ってくる。
「こっちはだめだ、こっちにきたらやられる——」
そう叫んだ兄弟が、再び目の前から消えた。同時に、地の底から響くような音。そちらを見ると、目玉があった。手足も体さえもない、その宙に浮いた二つの目玉がぎらぎらと光り、私たちの方を見ている。と、目玉の下からピンク色の何かが飛びてて、瞬く間に別の兄弟の姿が飲み込まれて消えた。うわああ、それを見た兄弟たちの混乱に拍車がかかる。恐ろしい目玉から逃れようと、私も懸命に足を動かしたが、やたらめったら動き回る兄弟たちに押されて思うように進めない。すると今度は先頭の方で、「翼だ!」と叫ぶ声がした。
「翼だ、翼が来たぞ!」
その瞬間、激しい風が吹いた。どしん、地面が揺れ、ごつんごつんと、そのくちばしが地面を穴だらけにしていく。跳ね飛ばされた泥土が、私の体を容赦なく汚す。小石に当たった兄弟から緑色の汁が出て、動かなくなる。「兄弟!」
悲痛な声がそこかしこから聞こえる。しかし翼は止まらない。ごつんとごつんと、再び何匹かの兄弟の命を奪いながら進んで行く。そして、とうとう私たちのすぐ近くへやってくると、すべてを覆うほどの大きな影を落として、その黄色い足を止めた。寄り添い、震える私たちを見下ろし、くちばしを振り上げる。地面に巨大な穴をあけるほどのその一撃を喰らって、私たちが無事でいられるはずもない。もうおしまいだ——私は体を小さく丸めた。ごつん、いままで以上に激しい衝撃を受け、地面が揺れる。あまりの恐怖に私は体中の汁が飛び散る思いがする。それは兄弟たちも同じだったろう。けれど、いつまでたっても、兄弟の悲鳴は聞こえてこなかった。もぞり、隣の兄弟が身じろぎし、もぞり、私も丸めた体を元へ戻す。恐る恐るあたりを見回す。兄弟たちも次々とその顔を上げる。
「……目玉が」
そのとき、誰かが呟いた。
「目玉が翼に喰われてる」
驚きのざわめきが体の毛を伝って届き、私も兄弟たちの見上げる方を、同じように見上げた。すると、そこには聞こえた通りの光景が広がっていた。
翼のくちばしが、目玉を軽々と挟んで持ち上げている。目玉はすでに事切れているのか、そこにぎらぎらとした輝きはない。翼がその死を飲み込む瞬間、私は目玉にも体と手足があることに気づいた。それは地面と全く同じ色をしていたため、私たちにはその目玉しか見えなかったのだ。
私や兄弟たちが固唾を飲んで見守る中、翼はゆうゆうと風を捉え、再び空へと戻っていった。
「助かったのか」
兄弟の誰かが呟いた。
「助かったんだ」
また別の兄弟が呟いた。
「俺たちは助かった」
さざなみのようなつぶやきの中、助かった、私も小さく呟いた。目玉は死に、翼は去った。とりあえずの恐怖はもうそこにない。
けれど、私はいつまでもぼうっとしているつもりはなかった。危機は完全に去ったわけではない。いつ新しい目玉が、翼がやってくるかもしれない。それとも今度は強靭な翅が、あの鮮やかな黄色を見せつけるようにやってくるかもしれない。いますぐに、皆で次の緑を目指さなければ。
けれど、一度崩れてしまった列は元には戻らず、私たちはてんでばらばらの方向へと動き出した。あるものは明るい方へ、あるものは暗い方へ、そしてあるものは馴染みのない緑の方へ。
ともあれ、私も己の足を動かすことに専念した。私はつるつるの地面を進み、湿った緑を進み、やかましい光の流れに架かった橋を懸命に進んだ。一日中、何も食べずに歩き続けたため、体の緑は失われ、糞を出すごとにしぼんでいくようだった。このままここに立ち止まり、目玉か翼か、それとも翅に食われた方がましだと何度も思った。その通りに立ち止まってもみた。けれど、風が体の毛を揺らすたび、ブウンという翅の音が聞こえるたび、私は自分の意思とは裏腹に足を動かしてしまうのだった。懐かしい緑を探して。齧る葉の感触を求めて。
一体そこまで私を駆り立てるものは何なのだろう——歩きながら、私は考えた。それは兄弟の死を目の前で見たあのときから、頭の隅でずっと考えていたことだった。そう考えたとき、一番に思い浮かぶのは、やはりあの想像の風景の一部になりたいということだった。葉を齧り、大きくなった先に待っているあの夢のような風景。その夢を目指して、私は歩いている。
けれど、よくよく考えるとそれは奇妙なことでもあった。なぜなら、私はその風景を見たことがない。兄弟たちから聞いたことがあるわけでもない。だというのに、どうして私はそれを知っているのだろう? どうしてそれを目指しているのだろう?
その答えが出ないままに、私はもっと不思議なことに気づく。
私はその風景を目指して歩いている、それはいい。しかし、他の兄弟たちはどうだろうかと考えたときに、私は確信を持ってこう思っていた——兄弟たちも、私と同じ風景を目指して、いまも歩いているのだろうということに。
なぜそう思うのか、思うばかりではなく、なぜ確信を持っているのか、考えれば考えるほどそれは不思議なことだった。できれば、兄弟に確かめてみたいとも思った。けれど、そんな問いが届かないほど、彼らと私は遠く離れてしまった。いまから誰かを見つけ出して聞くだなんて、そんなことができるはずがない。
私はとうとう考えることをやめた。けれど、そうしたのは答えが出ないことに飽いたからだけではなかった。長い旅を終え、私はようやく懐かしい緑にたどり着いていた。その緑を前にして、私は早くそれに齧りつきたい欲求に耐えられなくなっていたのだ。
経験から知っているように、ふもとの葉の緑は濃く、硬かった。けれど、大きく成長していた私はその緑さえ齧ることができた。私は味わうようにゆっくりと齧った。そうしていると、時折、上からぽろぽろと砂つぶのような糞が降って来て、そこには以前、生まれたてだった頃の私のような、小さな兄弟たちがいることが知れた。
幼い彼らは知らないだろうな、ゴリゴリと葉を齧りながら私は思った。いまは小さなこの空が、大きく大きくなることを。そうして、そのときが来れば、翼や、翅や、目玉に襲われてしまうだろうことを。
いずれ、私は上へ行く——久しぶりに食事にありついたせいか、ぼんやりしてきた思考で私は思う。この太い茎を登り、高い場所で夢を見る。その行きすがら、小さな兄弟たちに忠告してやろう。恐ろしい目玉のことを。その目玉さえ喰らった翼のことを。会うことのなかった翅のことを。
そのとき、私は再び不思議な感覚に襲われた。小さな卵から孵ったあの日、いまは遠いあの日に、私は大きな兄弟から忠告を受けた。『空に気をつけろ』とそう聞いた。けれど、そのときすでに私は知っていたのではなかったか? 空の恐ろしさを。待ち受ける翼や目玉のことを。
それはなぜか——私は考えようとしたが、どうやらそんな時間は残されていないようだった。私の足は、以前よりゆったりとした動きで、自然に上へ向かった。その途中、やはり小さな兄弟たちはそこにいた。驚くほど小さなその兄弟は、葉の表面を舐めるように、懸命に齧っていた。
「よお、兄弟」
歩きながら、私はその小さな兄弟に呼びかけた。兄弟は顔を上げた。その眼差しには驚きと、尊敬が浮かんでいる。私はそれを堪能しながら、ゆっくりと言った。
「一つだけ言っておくことがある。頭の上には気をつけな。あの青くて広い空ってところからは、大いなる翼の持ち主や、強靭な翅の主、二つの目玉がやってくる。そいつらに見つかったらおしまいだ。見つからずに、なんとか生き延びてくれよな」
「……ああ」
小さな兄弟は答えた。
「忠告をありがとう、兄弟」
その目に未だ尊敬がこもっていることを確認し、私は上へと進んだ。さっき食べた葉が大きく四角い糞となり、小さな兄弟たちの乗った葉を揺らす。「何しやがんだ!」——威勢のいい声が下から聞こえる。あのとき叫んだ兄弟は無事だったか、そんなことを考えながら、私は十分に高い場所へと上り詰めた。体を葉の裏に隠すように密着させる。ゆっくりと息を吐く。最後の糞が尻からぼとりと落ちていく。それから私は葉を透かすようにして空を見た。
ここまで来られたことは奇跡だ、私は思う。生き延びた他の兄弟たちもきっと、そう思っているに違いない。こうして葉の裏から空を見ながら、同じ思いでいるに違いない。きっと、ではなく、絶対に私たちは同じ思いを共有しているのだ——私は確信を持って、そう思った。いや、思ったのではない。理解した。私たちは別の存在でありながら、同時に一つの存在であることを。同じことを思い、同じ夢を見る、意識の共同体であることを。
見えなくなっていく空を、それでも必死に見つめながら、私は兄弟の言葉を思い出していた。故郷の葉から地面に降り、目玉に食べられる直前のことだ。空を怖がる兄弟に、別の兄弟が言ったのだった。『そんなんでお前はこの先どうするつもりなんだ、兄弟? 俺たちはいつまでも『空』を怖がってるわけにはいかないってのに』と。
空。やはり、あの場所は私たちの意識の底にずっとあったのだ。恐ろしい場所でありながら、いつか飛び立つ場所として。私たち兄弟全員が、目指すべき場所として。
空の光が薄れていく。そのときがやってきたのだと、私たちの共有する意識が、私に教える。怖がることはない、そのまま身を任せればいいのだ、と。
わかっている、その声に私は頷いた。準備はすでにできている。伝えなければならないことも、小さな兄弟たちに伝えて来た。そうして誰にも見つからないこの場所へ、覚悟を持ってやって来た。先へ進むために。空へ還るために。
とうとう光が視界から消えた。体が溶けるような感覚に、私は素直に身を任せた。
いまから私は夢を見る。他の兄弟たちと同じ、光溢れる夢を見る。そして、その夢から目覚めたとき、私は空の一部となる。光へ舞い上がるひとひらになる。
たくさんの兄弟たちと一斉に飛び立つその日を待ちわびて、私の意識は静かに消えた。私が再び目覚めたとき、私は私という意識を持つのだろうか——寂しさを伴う不安もやがて、兄弟たちの意識に溶け込み、個を失くしていったのだった。
「よお、兄弟」
大きな兄弟が私に呼びかけた。
「一つだけ言っておくことがある。頭の上には気をつけな。あの青くて広い空ってところからは、大いなる翼の持ち主や、強靭な翅の主、二つの目玉がやってくる。そいつらに見つかったらおしまいだ。見つからずに、なんとか生き延びてくれよな」
そう言うと、あたりで一番大きなカリカリという音を響かせながら、その空の方へと登っていく。
「ああ、忠告をありがとう。……兄弟」
その兄弟に私の声は届いたかどうか、返事の代わりに四角く大きな糞がごろごろと落ちてきて、それは私の乗る葉を大きく揺らして、さらに下へと落ちていった。
「ったく、あぶねえじゃねえか」
端っこにいたらしい兄弟が驚いたような声で叫んだ。
「気をつけろって言っといて、てめえのほうが気をつけろってんだ」
その私よりも少し大きな兄弟は、体中の毛を逆立てて怒った。と、その三角の目が私に向けられた。
「何だい。こちとら見せもんじゃねえぞ」
そんなつもりはないと言いたかったが、私は黙って目を伏せた。そうしている間にも、口は葉を齧っている。忠告に耳は傾けても、言い合いなどしている暇はない。私は早くあの兄弟のように大きくならなければいけないのだ。音を立てて葉を齧り、この新鮮な葉がなくなれば、どこか新しい葉のある場所へ移動し、そこで葉を齧らなければならない。あの兄弟が言ったように、十分「空」に気をつけながら。そうしなければ、大きくなれない。大きくなれなければ、もっと大きくなれない。もっと大きくなれなければ、もっと大きくなれなければ、そのときは——。
私の中には、ある鮮明な像があった。こうして葉を齧り続けていれば、私はこの目に浮かぶ想像の一部となれる。もちろん、そのときになったなら、それは想像ではなく、現実になっているのだから、想像の一部になるという表現はおかしいかもしれない。けれど、いまの私にとって、まだ小さな私にとって、それは確固たる目標でありながら、どこか夢のような想像だった。私はその夢に向かって、葉を齧り続けるのだ。
私が生まれてから一日経ち、二日経ち、一週間が経った。忠告通り、「空」に気をつけた甲斐あって、私は葉の上をほんの十歩で進めるほどに大きくなった。体の毛はより濃く、長くなり、糞も中くらいではあるが四角くなった。生まれた葉からはすでに離れ、何枚もの葉を齧り尽くしてきたのだが、ここへきてある問題に直面した。私の頭上に空が見えるようになったのだ。否、いままでも見えていた空が、より一層、恐ろしいほど広く私の頭上に広がっていることに気づいたのだ。
それはつまり、以前はそこに茂っていた葉が齧り尽くされてしまったということだった。私によって、私の兄弟たちによってか細い葉脈のみになってしまった葉は、最早私たちを隠す力も、養う力も失ってしまったのだ。
それでも私たちは粘り強く、葉脈に残ったわずかな葉の部分を齧り続けた。けれど、そんなことをしても限界がある。眩しい光は燦々と降り注いで私たちの体をしぼませ、その体を再び膨らまそうにも食料となる葉がそこにはない。また、問題はそれだけではなかった。「空」だ。このままではその恐ろしい場所から大いなる翼が、翅が、目玉がやってきてしまう。このままでは、まずい。そう考えるのは当然だった。生まれたこの場所を捨て、どこか別の場所——緑茂る場所へ移らなければ。
追い込まれた私はようやく移動を決意したが、それは私の兄弟たちも同じであったようだった。その日の朝、私たちは打ち合わせたかのように、同時に故郷を出発した。向かうは、未知なる地面——空とは反対にある場所。黙々と列を作る兄弟たちに倣って、私はその列の最後尾に着いた。垂直に茎を降りていく黒い筋が、地面に着くなり空と平行に動いていく。
「先頭の兄弟は、どの方向へ行くべきか知っているのだろうか」
前を行く兄弟が不安そうに呟いた。
「このまま地面を行くつもりが、いつのまにか『空』へ向かうことになりはしないだろうか」
「お前はまだ『空』が怖いのか」
すると、その前の前を行く兄弟がにやりと笑った。前を行く兄弟はむっとして答えた。
「ああ、怖いさ。それとも、君は怖くないのかい、兄弟?」
問いかけに、前の前を行く兄弟はさもおかしそうに高笑いした。
「弱虫め。そんなんでお前はこの先どうするつもりなんだ、兄弟? 俺たちはいつまでも『空』を怖がってるわけにはいかないってのに——」
前の前の兄弟が笑いながら振り向いたときだった。その兄弟の姿が消えた。黒い筋は、その兄弟のいた場所をぽっかり開けたまま、先へ進んで行く。どうしたことか、私は思わず歩を緩めた。前を行く兄弟が叫んだ。
「目玉だ、目玉が兄弟を食っちまったぞ!」
その叫びは、先頭の兄弟まで届いたようだった。目玉が出たぞ、兄弟たちの列が恐怖で乱れた。あるものは右へ、あるものは左へ、またあるものは方向転換して最後尾の私の方へまっすぐに戻ってくる。
「こっちはだめだ、こっちにきたらやられる——」
そう叫んだ兄弟が、再び目の前から消えた。同時に、地の底から響くような音。そちらを見ると、目玉があった。手足も体さえもない、その宙に浮いた二つの目玉がぎらぎらと光り、私たちの方を見ている。と、目玉の下からピンク色の何かが飛びてて、瞬く間に別の兄弟の姿が飲み込まれて消えた。うわああ、それを見た兄弟たちの混乱に拍車がかかる。恐ろしい目玉から逃れようと、私も懸命に足を動かしたが、やたらめったら動き回る兄弟たちに押されて思うように進めない。すると今度は先頭の方で、「翼だ!」と叫ぶ声がした。
「翼だ、翼が来たぞ!」
その瞬間、激しい風が吹いた。どしん、地面が揺れ、ごつんごつんと、そのくちばしが地面を穴だらけにしていく。跳ね飛ばされた泥土が、私の体を容赦なく汚す。小石に当たった兄弟から緑色の汁が出て、動かなくなる。「兄弟!」
悲痛な声がそこかしこから聞こえる。しかし翼は止まらない。ごつんとごつんと、再び何匹かの兄弟の命を奪いながら進んで行く。そして、とうとう私たちのすぐ近くへやってくると、すべてを覆うほどの大きな影を落として、その黄色い足を止めた。寄り添い、震える私たちを見下ろし、くちばしを振り上げる。地面に巨大な穴をあけるほどのその一撃を喰らって、私たちが無事でいられるはずもない。もうおしまいだ——私は体を小さく丸めた。ごつん、いままで以上に激しい衝撃を受け、地面が揺れる。あまりの恐怖に私は体中の汁が飛び散る思いがする。それは兄弟たちも同じだったろう。けれど、いつまでたっても、兄弟の悲鳴は聞こえてこなかった。もぞり、隣の兄弟が身じろぎし、もぞり、私も丸めた体を元へ戻す。恐る恐るあたりを見回す。兄弟たちも次々とその顔を上げる。
「……目玉が」
そのとき、誰かが呟いた。
「目玉が翼に喰われてる」
驚きのざわめきが体の毛を伝って届き、私も兄弟たちの見上げる方を、同じように見上げた。すると、そこには聞こえた通りの光景が広がっていた。
翼のくちばしが、目玉を軽々と挟んで持ち上げている。目玉はすでに事切れているのか、そこにぎらぎらとした輝きはない。翼がその死を飲み込む瞬間、私は目玉にも体と手足があることに気づいた。それは地面と全く同じ色をしていたため、私たちにはその目玉しか見えなかったのだ。
私や兄弟たちが固唾を飲んで見守る中、翼はゆうゆうと風を捉え、再び空へと戻っていった。
「助かったのか」
兄弟の誰かが呟いた。
「助かったんだ」
また別の兄弟が呟いた。
「俺たちは助かった」
さざなみのようなつぶやきの中、助かった、私も小さく呟いた。目玉は死に、翼は去った。とりあえずの恐怖はもうそこにない。
けれど、私はいつまでもぼうっとしているつもりはなかった。危機は完全に去ったわけではない。いつ新しい目玉が、翼がやってくるかもしれない。それとも今度は強靭な翅が、あの鮮やかな黄色を見せつけるようにやってくるかもしれない。いますぐに、皆で次の緑を目指さなければ。
けれど、一度崩れてしまった列は元には戻らず、私たちはてんでばらばらの方向へと動き出した。あるものは明るい方へ、あるものは暗い方へ、そしてあるものは馴染みのない緑の方へ。
ともあれ、私も己の足を動かすことに専念した。私はつるつるの地面を進み、湿った緑を進み、やかましい光の流れに架かった橋を懸命に進んだ。一日中、何も食べずに歩き続けたため、体の緑は失われ、糞を出すごとにしぼんでいくようだった。このままここに立ち止まり、目玉か翼か、それとも翅に食われた方がましだと何度も思った。その通りに立ち止まってもみた。けれど、風が体の毛を揺らすたび、ブウンという翅の音が聞こえるたび、私は自分の意思とは裏腹に足を動かしてしまうのだった。懐かしい緑を探して。齧る葉の感触を求めて。
一体そこまで私を駆り立てるものは何なのだろう——歩きながら、私は考えた。それは兄弟の死を目の前で見たあのときから、頭の隅でずっと考えていたことだった。そう考えたとき、一番に思い浮かぶのは、やはりあの想像の風景の一部になりたいということだった。葉を齧り、大きくなった先に待っているあの夢のような風景。その夢を目指して、私は歩いている。
けれど、よくよく考えるとそれは奇妙なことでもあった。なぜなら、私はその風景を見たことがない。兄弟たちから聞いたことがあるわけでもない。だというのに、どうして私はそれを知っているのだろう? どうしてそれを目指しているのだろう?
その答えが出ないままに、私はもっと不思議なことに気づく。
私はその風景を目指して歩いている、それはいい。しかし、他の兄弟たちはどうだろうかと考えたときに、私は確信を持ってこう思っていた——兄弟たちも、私と同じ風景を目指して、いまも歩いているのだろうということに。
なぜそう思うのか、思うばかりではなく、なぜ確信を持っているのか、考えれば考えるほどそれは不思議なことだった。できれば、兄弟に確かめてみたいとも思った。けれど、そんな問いが届かないほど、彼らと私は遠く離れてしまった。いまから誰かを見つけ出して聞くだなんて、そんなことができるはずがない。
私はとうとう考えることをやめた。けれど、そうしたのは答えが出ないことに飽いたからだけではなかった。長い旅を終え、私はようやく懐かしい緑にたどり着いていた。その緑を前にして、私は早くそれに齧りつきたい欲求に耐えられなくなっていたのだ。
経験から知っているように、ふもとの葉の緑は濃く、硬かった。けれど、大きく成長していた私はその緑さえ齧ることができた。私は味わうようにゆっくりと齧った。そうしていると、時折、上からぽろぽろと砂つぶのような糞が降って来て、そこには以前、生まれたてだった頃の私のような、小さな兄弟たちがいることが知れた。
幼い彼らは知らないだろうな、ゴリゴリと葉を齧りながら私は思った。いまは小さなこの空が、大きく大きくなることを。そうして、そのときが来れば、翼や、翅や、目玉に襲われてしまうだろうことを。
いずれ、私は上へ行く——久しぶりに食事にありついたせいか、ぼんやりしてきた思考で私は思う。この太い茎を登り、高い場所で夢を見る。その行きすがら、小さな兄弟たちに忠告してやろう。恐ろしい目玉のことを。その目玉さえ喰らった翼のことを。会うことのなかった翅のことを。
そのとき、私は再び不思議な感覚に襲われた。小さな卵から孵ったあの日、いまは遠いあの日に、私は大きな兄弟から忠告を受けた。『空に気をつけろ』とそう聞いた。けれど、そのときすでに私は知っていたのではなかったか? 空の恐ろしさを。待ち受ける翼や目玉のことを。
それはなぜか——私は考えようとしたが、どうやらそんな時間は残されていないようだった。私の足は、以前よりゆったりとした動きで、自然に上へ向かった。その途中、やはり小さな兄弟たちはそこにいた。驚くほど小さなその兄弟は、葉の表面を舐めるように、懸命に齧っていた。
「よお、兄弟」
歩きながら、私はその小さな兄弟に呼びかけた。兄弟は顔を上げた。その眼差しには驚きと、尊敬が浮かんでいる。私はそれを堪能しながら、ゆっくりと言った。
「一つだけ言っておくことがある。頭の上には気をつけな。あの青くて広い空ってところからは、大いなる翼の持ち主や、強靭な翅の主、二つの目玉がやってくる。そいつらに見つかったらおしまいだ。見つからずに、なんとか生き延びてくれよな」
「……ああ」
小さな兄弟は答えた。
「忠告をありがとう、兄弟」
その目に未だ尊敬がこもっていることを確認し、私は上へと進んだ。さっき食べた葉が大きく四角い糞となり、小さな兄弟たちの乗った葉を揺らす。「何しやがんだ!」——威勢のいい声が下から聞こえる。あのとき叫んだ兄弟は無事だったか、そんなことを考えながら、私は十分に高い場所へと上り詰めた。体を葉の裏に隠すように密着させる。ゆっくりと息を吐く。最後の糞が尻からぼとりと落ちていく。それから私は葉を透かすようにして空を見た。
ここまで来られたことは奇跡だ、私は思う。生き延びた他の兄弟たちもきっと、そう思っているに違いない。こうして葉の裏から空を見ながら、同じ思いでいるに違いない。きっと、ではなく、絶対に私たちは同じ思いを共有しているのだ——私は確信を持って、そう思った。いや、思ったのではない。理解した。私たちは別の存在でありながら、同時に一つの存在であることを。同じことを思い、同じ夢を見る、意識の共同体であることを。
見えなくなっていく空を、それでも必死に見つめながら、私は兄弟の言葉を思い出していた。故郷の葉から地面に降り、目玉に食べられる直前のことだ。空を怖がる兄弟に、別の兄弟が言ったのだった。『そんなんでお前はこの先どうするつもりなんだ、兄弟? 俺たちはいつまでも『空』を怖がってるわけにはいかないってのに』と。
空。やはり、あの場所は私たちの意識の底にずっとあったのだ。恐ろしい場所でありながら、いつか飛び立つ場所として。私たち兄弟全員が、目指すべき場所として。
空の光が薄れていく。そのときがやってきたのだと、私たちの共有する意識が、私に教える。怖がることはない、そのまま身を任せればいいのだ、と。
わかっている、その声に私は頷いた。準備はすでにできている。伝えなければならないことも、小さな兄弟たちに伝えて来た。そうして誰にも見つからないこの場所へ、覚悟を持ってやって来た。先へ進むために。空へ還るために。
とうとう光が視界から消えた。体が溶けるような感覚に、私は素直に身を任せた。
いまから私は夢を見る。他の兄弟たちと同じ、光溢れる夢を見る。そして、その夢から目覚めたとき、私は空の一部となる。光へ舞い上がるひとひらになる。
たくさんの兄弟たちと一斉に飛び立つその日を待ちわびて、私の意識は静かに消えた。私が再び目覚めたとき、私は私という意識を持つのだろうか——寂しさを伴う不安もやがて、兄弟たちの意識に溶け込み、個を失くしていったのだった。