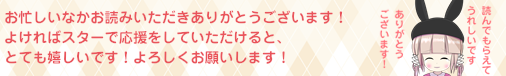1話:隻眼のカリスマ
文字数 3,637文字

虎太郎が扉を開けると、壁全面に魔法陣が書きこまれていた。
机が無造作に集められた教室には西日が射し、人影がのびやかに自己主張している。
既に取壊しが決まった旧校舎が無法地帯と化しているのは、この最上階教室に限ったことではない。かと言って虎太郎は、壁はおろか床にまで魔法陣が書かれていることに、法の概念を飛び越えた道徳的な危うさと禍々しさがあるように感じていた。
「なんだこれ……?」
次に虎太郎が思ったのはその空気感だった。これまで彼の人生で味わったことのない不気味な雰囲気が、この部屋にはあそびなく張り詰めている。そこにいたすべての人物が虎太郎の熱意を冷然と受け流しているのが、彼の不安を更に駆り立てた。
教室ではその魔法陣をいまもなお壁へ床へと書き続けている長髪の男に、虎太郎を含め五人の視線が向いている。しかし視線の中央にいる男は特段ひるむことなく、その奇怪な記述を続けていた。
「遅い」
目線を床から離すことなく、男は虎太郎へ向けて放つ。
虎太郎にとっては見覚えのある顔だった。
「遅いじゃねぇよ。訳わかんねぇよ説明しろ」
「お前を此処に呼び出したのは俺だ。そこに突っ立ってる四人を呼び出したのも俺だ。俺はいま此処で魔法陣を書いている。お前は、あとの四人に比べて十五分も来るのが遅かった」
「いや……そうじゃねぇだろ」
この奇怪な振る舞いの男、
「お前、どこで知ったんだよ」
虎太郎が感じるなによりのすごみは、彼の葛藤が聡に握られていたことから来るものが大きかった。
数時間前に虎太郎のスマートフォンに着た匿名からの通知は、彼をこの部屋に呼び出すと同時に、赤裸々と言うほど遠慮なく彼の抱える葛藤を言い当てていた。
「髪も伸び放題で、眼帯なんかしやがって、気持ち悪いんだよお前。なにが言いたいんだよ」
「お前の彼女、
「……っ」
明日葉希來と見附虎太郎は、付き合い始めてまだ数週間だった。まだ手も繋いだことのない、始まったばかりの関係性。虎太郎は自分に初めて彼女ができたことが嬉しかった。
ただ虎太郎は、おちょくられてはたまらないと言う気持ちで、誰にもその関係性を打ち明けてはいなかった。
「明日葉希來が行方不明になって今日でちょうど半年だ。金髪頭にピアスまでして、とっかえひっかえ違う女に手を出すかと思いきや、案外モテないんだな」
とは言え虎太郎は、それをこの一匹狼に言われるなどと夢にも思いはしなかった。日向聡はこの藤原西高校ではカリスマ的な存在だが、誰もこの男の笑顔を見たことがない。
交友関係が狭く、校内では聡がどのような人物と知り合いなのかすらあまり知られていない。それほど無口とも言える。
「日向、お前……」
「虎太郎くん、やめて。日向くんの話を聞いて」
虎太郎の視線は希来の妹、明日葉みるへと動いた。足が悪く車椅子の彼女は、この素行の悪そうな男に全くひるまない。みるの姉を探したい気持ちは強い。
「みる、お前がコイツに教えたのか」
「違う。いいから聞いて」
虎太郎の逆上がちっぽけなものに見えるほど、いつもの彼女の丸く澄んだ瞳がいまは信念に染まっている。それを見た虎太郎は自分の無神経さを鼻をならして汲み取り、大人しく聡の話を聞くことにした。
「フン……クソ野郎。早く話せ」
「人の所為にするな。お前が早く来い」
散々な言いようだが、これ以上場を荒らしたくないと言う理由で、虎太郎は反発しなかった。
聡は立ち上がり、強い口調で言う。
「此処に呼びつけた全員の葛藤を俺は知っている。明日葉希來が行方不明になったこともそうだが、到底このままでは報われないような連中だ。顔なじみの奴もいるな」
「特段、明日葉希來が行方不明になっていることについては各自知っての通りだが、それも踏まえて俺からお前らにひとつ提案させて貰えればと思う」
左目に眼帯をした聡は、なにかを見透かしているような口ぶりだった。
そして、その次に放たれる言葉には、最早悪魔の囁きのような含みがあった。
「もし、お前たちがいま抱えている葛藤を俺が解消できるなら」
「仮にそこに危険が伴うとしても、命を掛けることでその原因を解き明かすことができるなら」
「お前たちはどうしたい」
雰囲気が更に悪くなってもなお、聡は怯むどころか更に突き付けて来た。
「一分待ってやる」
「もし俺の言っていることが信用出来ない奴、危険を伴うことが怖い奴は」
「一分以内にこの部屋を出ていけ」
聡の開き切った隻眼は威圧的ですらあったものの、判断力を削ぐほどのものではなかった。
つまり、それはあくまで提案であって、強制するものではなかった。
この瞬間各自が聡を咎めようとすれば、そのようにも出来ただろう。虎太郎を含めこの場に呼び出された全員が、聡に自らの葛藤を、悩みを、ジレンマを握られている。何のために? どうやって? 各自この教室に来るまでに考えてきたことだ。不満など、あって然るべきものとも言える。
「五十、四十九、四十八、四十七」
しかし、この空気はひりついたまま。聡を咎めるようにはならなかった。
「三十五、三十四、三十三」
また、この部屋を出ようとする者も誰もいなかった。
「十三、十二、十一」
聡の予想通りと言うべきか、それとも各人の鬱屈とした感情があまりに大き過ぎたと言うべきか、五人それぞれがいまはなにが起きているかわかっていなくとも、自分に掛かった脆い橋を臆さず渡り切る気概を見せていた。
それは彼らを待ち受ける、異世界戦争の幕開けでもあった。
「零」
カウントダウンを終えた聡は、良いだろう、と床に書き上げた魔法陣へ右手を着いた。
「お前たちの活路だ、お前たちが掴み取れ」
あぁ、魔法を使うのか、などと思えたものではない。魔法などと言うものが実際にあるかどうか、少なくとも現実の理として知られてはいない。
とは言え聡がその魔法陣の中心にいると言うことは、なにかしらの魔法を使おうとしていると各自が推察し得るところである。
また、特に聡に魔法を説明しろと言う者もいない。そもそもこの男に説明を求めたところで応じてくれるような人物ではないと言うこともそうだが、彼がそれほどくだらない男ではないと言うことが公然の事実だからだ。
誰かが「信じられない」などと述べたところで、最早「ある」か「ない」かと言う次元はとうに過ぎている。聡が投げかけているのは「あったらどうする」と言う例え話ではなく「あるからどうする」と言う選択肢。つまり聡はそれだけのものを持っているのだ。
「
精々自分の葛藤にしがみつけ
」聡の右手がテスラコイルのように青い稲光を放った。
回転数を上げるエンジンのような激しい音が鳴り響き、魔法陣それぞれが噛み合った歯車として速度の異なる回転を重ね合う。
その光景を目の当たりにしてもなお、聡はおろか、虎太郎を含めた全員が全く臆していなかった。
最早魔法と言う言葉を抜きにしては表現することが出来ない状況。命の危険を促されるほどの事態。
それでも彼らが抱えた、痛みは、怒りは、彼らの決断をよどませないのだ。
「人は、それぞれが自分の世界に生きている」
「目の前、同じ空間に存在する人物ですら、誰一人として同じ世界を生きてはいない」
「ただ、各自の世界線が、バタフライエフェクトで結びつき、認識を補完している」
「だからこそ、誰の所為かもわからない、あからさまな理不尽が起きる」
「そうやって互いに引っ張り合いながら、七十七億もの並列世界が走っている」
「これは比喩ではない」
ただ、次に聡が放つ言葉は、聡以外の各人が想定できないほど大きな規模と勢いで、彼らをまだ見たことのない未知の受難へと手招いた。
「だったら異世界七十七億を支配しろ。権利は与えてやる」
「
七十七億人のお前たちを統合する
」