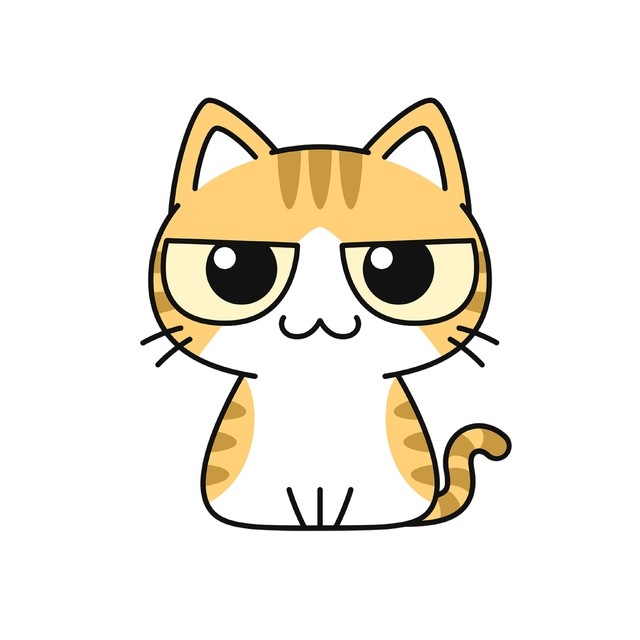最終話 somewhere,again (1)
文字数 1,398文字
「もう10年になりますか……」
気品を纏う老婦人が、ティーカップを片手に呟く。
レトロながらも清潔感漂う喫茶店のカウンター席には、老婦人の他には埃もなにもない。
「そうさなぁ、10年が経つか」
カウンターの中から、穏やかな人柄がうかがえる声がする。
おしゃれな意匠が施されたティーポットで湯を沸かす年老いたマスターは、カウンターの中で優美な手つきでドリッパーを準備している。
「そろそろ潮時ですかねぇ」
そう言うと、老婦人はレモンティーを一口含み、音を立てずにソーサーにカップを戻した。
ふぅと、深い息を漏らす。
その中には、どうしてやることもできなかった自分への不甲斐なさと、不憫な状況へのやるせなさが混在していた。
「ふむ。じゃが、わしらももう充分に待った。残念じゃが、ここまでじゃろう」
年老いたマスターは目を伏せ、悲愁の思いでそう呟く。
湯が沸き、準備していたドリッパーにゆっくりと円を描くように注ぐ。
熟練されたその動きは、長年この場所で培われた技そのもので、一切の無駄がなく、見るものをうっとりとさせる。
「あなたが珈琲を淹れるのを見るのも、もうすぐ終わりね。優雅に湯を注ぐわたくしが好きな仕草も、もう見れなくなるのね」
「ふむ。あの子も同じようなことを言ってくれたわい」
年老いたマスターは顎髭に手を添え、感慨深い遠い目をしてそう話す。
ティーポットを定位置に戻し、ドリップが終わると、ふわりと湯気を漂わせる珈琲をティースプーンでくるっと一周させた。
まるで執事のような紳士的な所作で、スプーンをシンクの脇にコトっと置くと、自ら淹れた珈琲を一口含み味を見る。
今日も満足がいく出来だ。
年老いたマスターは自らを褒め称えるようにそう思う。
それと同時に、あの子はココアばかりだったと思うと、懐かしさに口元が緩んだ。
このレトロな喫茶店のカウンター内には客の忘れ物を収納しておく、特別な引き出しがある。
煙草、財布、携帯電話、ハンカチなど忘れ物は多岐に渡る。貴重品の類いは、本人からの連絡がない場合、三日程で近所の派出所に届ける。
自分の判断で、貴重品でないものや、直接返した方がよいと思うものは、客が再度訪れた際にそっと返している。
中には忘れたことすら、忘れている客もいるのだが。
この年老いたマスターは、一度来店した客は必ず記憶しているので、再度来店してもらえれば必ず忘れ物を返すよう心掛けている。
そして、それが客の心を掴み、また再来店にも繋がるわけだ。
年老いたマスターは、その特別な引き出しをゆっくりと引く。
中には数個の100円ライターと、一枚の男性用ハンカチ、そして一通の手紙がある。
ほとんどの忘れ物は客に返却している。
ここに残されているものは、一度きり来店の客のものと、過去にこの店の常連だった、ある少女のものだ。
そしてそれは、もう10年間、届けるべき主のもとへ届いておらず、ここに眠り続けている。
年老いたマスターは手紙をそっと取り出し、老婦人の座るカウンター席へゆっくりと置いた。
「だいぶ傷みましたね……」
老婦人は眉を寄せ、哀切な声音で口にする。
「うむ、わしの心残りも、もうこれだけじゃ」
そう呟くと、年老いたマスターは手紙の宛名に目を落とす。
そこには、今年の夏に開催される大阪五輪の陸上の代表選手と同姓同名の名が、愛らしい少女が書いたような字体で記されていた。
気品を纏う老婦人が、ティーカップを片手に呟く。
レトロながらも清潔感漂う喫茶店のカウンター席には、老婦人の他には埃もなにもない。
「そうさなぁ、10年が経つか」
カウンターの中から、穏やかな人柄がうかがえる声がする。
おしゃれな意匠が施されたティーポットで湯を沸かす年老いたマスターは、カウンターの中で優美な手つきでドリッパーを準備している。
「そろそろ潮時ですかねぇ」
そう言うと、老婦人はレモンティーを一口含み、音を立てずにソーサーにカップを戻した。
ふぅと、深い息を漏らす。
その中には、どうしてやることもできなかった自分への不甲斐なさと、不憫な状況へのやるせなさが混在していた。
「ふむ。じゃが、わしらももう充分に待った。残念じゃが、ここまでじゃろう」
年老いたマスターは目を伏せ、悲愁の思いでそう呟く。
湯が沸き、準備していたドリッパーにゆっくりと円を描くように注ぐ。
熟練されたその動きは、長年この場所で培われた技そのもので、一切の無駄がなく、見るものをうっとりとさせる。
「あなたが珈琲を淹れるのを見るのも、もうすぐ終わりね。優雅に湯を注ぐわたくしが好きな仕草も、もう見れなくなるのね」
「ふむ。あの子も同じようなことを言ってくれたわい」
年老いたマスターは顎髭に手を添え、感慨深い遠い目をしてそう話す。
ティーポットを定位置に戻し、ドリップが終わると、ふわりと湯気を漂わせる珈琲をティースプーンでくるっと一周させた。
まるで執事のような紳士的な所作で、スプーンをシンクの脇にコトっと置くと、自ら淹れた珈琲を一口含み味を見る。
今日も満足がいく出来だ。
年老いたマスターは自らを褒め称えるようにそう思う。
それと同時に、あの子はココアばかりだったと思うと、懐かしさに口元が緩んだ。
このレトロな喫茶店のカウンター内には客の忘れ物を収納しておく、特別な引き出しがある。
煙草、財布、携帯電話、ハンカチなど忘れ物は多岐に渡る。貴重品の類いは、本人からの連絡がない場合、三日程で近所の派出所に届ける。
自分の判断で、貴重品でないものや、直接返した方がよいと思うものは、客が再度訪れた際にそっと返している。
中には忘れたことすら、忘れている客もいるのだが。
この年老いたマスターは、一度来店した客は必ず記憶しているので、再度来店してもらえれば必ず忘れ物を返すよう心掛けている。
そして、それが客の心を掴み、また再来店にも繋がるわけだ。
年老いたマスターは、その特別な引き出しをゆっくりと引く。
中には数個の100円ライターと、一枚の男性用ハンカチ、そして一通の手紙がある。
ほとんどの忘れ物は客に返却している。
ここに残されているものは、一度きり来店の客のものと、過去にこの店の常連だった、ある少女のものだ。
そしてそれは、もう10年間、届けるべき主のもとへ届いておらず、ここに眠り続けている。
年老いたマスターは手紙をそっと取り出し、老婦人の座るカウンター席へゆっくりと置いた。
「だいぶ傷みましたね……」
老婦人は眉を寄せ、哀切な声音で口にする。
「うむ、わしの心残りも、もうこれだけじゃ」
そう呟くと、年老いたマスターは手紙の宛名に目を落とす。
そこには、今年の夏に開催される大阪五輪の陸上の代表選手と同姓同名の名が、愛らしい少女が書いたような字体で記されていた。