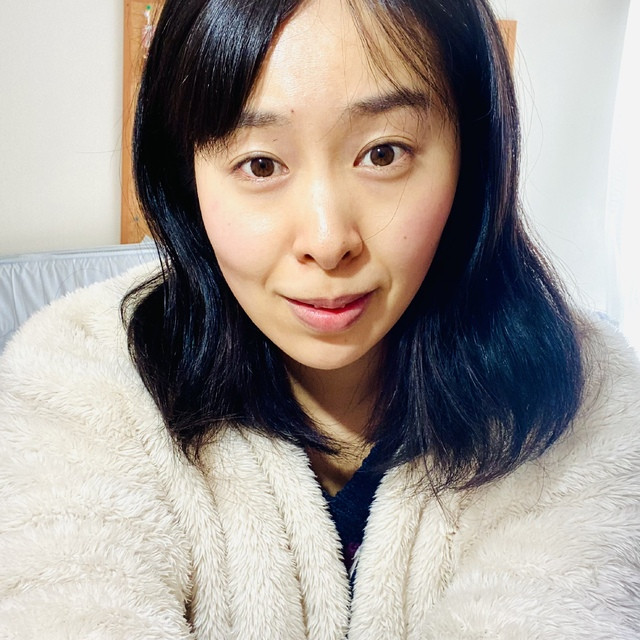第1話
文字数 23,579文字
The Monster
アメリカの海辺の街。
夜、バスケットゴールの下に後ろを向いた黒人が立っていた。
「話ってなんだよ、カイル。」
日系と白人のハーフ、レックスが声をかけると、黒人カイル・バートレットは、悲しげに振り向いた。
カイルは歩き出した。
「どこに行くの?」
レックスは聞いた。
「どこでもない。」
「話ってなに?」
「お前には大切な話だ。」
カイルはベンチに置いてあったコカ・コーラを持った。
そしてまた歩く。
「そっちは駐車場だよ。」
レックスは言った。
「まぁ、これでも飲め。」
カイルはレックスにコーラを渡した。
「ありがとう、気が利く。」
レックスはコーラを飲んだ。
カイルも少し飲んだ。
「うっ‥。」
レックスは苦しみ始めた。
カイルは冷めた目でそれを見守る。
やがて、レックスは動かなくなった。
カイルは何事もなかったかのように、マウンテンバイクに乗って、帰る。
ペットボトルは、指紋を拭き、海に投げた。
ここらへんには、防犯カメラがない事は分かっていた。
「ただいま。」
「おかえり。遅かったわね、何かあった?」
お母さんと、猫を抱いた可愛い妹が玄関に来た。
「いや、何もないよ。」
カイルはケラケラと笑った。
場所はアフリカ。
陽気な音楽にのるように、黒人の陸上選手は、スタブロに乗る。
自分の頭の中には、いつでも陽気な音楽が流れているので、とても楽しいが、
他の者はそうでもないみたいだ。
スタートの前はみんな、苦悩に満ちた表情をしている。
なんで?すぐに終わるのに。人生を60年に例えたとしても、10秒なんてあっという間だ。
パン
スタートは難しいという者は多いが、なんてことない。
ピスの音とともに、駆け出せばいいだけだ。
最初から全速力で走れるわけない。だから徐々に加速していく。
5,60メートルでマッハが出せればいいが、大体、マッハが出るのは70メートルくらいになる。80でも遅くはない。何事もあきらめないことが肝心だ。
「ふぅ~もう終わったぜ。」
今日もバルトが一番である。
「バルトさん、お疲れ様です。」
「今日のレース、いかがでしたか?」
インタビュアーたちが駆け寄ってくる。
本当に華やかな世界だ。
「最高だぜ。みんな、俺は元気だ。」
バルトはカメラに向かって言った。
韓国のカフェ‥。22歳の長身の男が働いている。
高校もろくに卒業できなかった、出来損ないだ。
店長のオバタリアンはとても厳しい。
長身の男ミンジェが、オバタリアンのソナさんに言った。
「今日、客、全然来ないっすね。」
「そうね。近くにパンケーキ屋ができたから仕方ないわ。それが終わったら、床に掃除機をかけてちょうだい。」
「分かりました。」
ソナさんは答えなかった。その代わり、入口の近くから窓を見て、つぶやいた。
「変わってる。」
ミンジェは掃除機の準備をしながら、ソナさんをちらりと見たが、気にしなかった。
ソナさんの方こそ、変わっている。30歳でバツ4らしい。
本人はバツ1と嘘をついている。
線路を作る仕事をしている白人のジェレミーと黒人のアレクシス。
バラストと呼ばれる線路に敷く石を運びながら、ジェレミーは言った。
「こうして石を運んでいると、鉱山で働いているみたいだ。」
「ああ、そうだな。」
「本当は鉱山で働いてみたかったけど、近所にはないから仕方ない。」
「アメリカンドリームにはほど遠いな。というか、現代には鉱山はもうあまりない。」
「うん。さっさと終わらせて帰りたいよ。」
仕事を終え、事務所に戻ると、休憩室でテレビを見ながら、カイルが休んでいた。
カイルは現在24歳で、ジェレミーとアレクシスと同い年である。
「カイル。お疲れ様。」
「おお。お疲れ。」
カイルはニコリと笑った。
「もう帰る?」
「そうだな。」
ジェレミーは聞き、アレクシスは答えた。カイルもこちらに来た。
3人は、駅まで歩く。
3人は電車に乗るが、カイルは仕方なく一緒に来たというかのように、反対側に座って、窓から外を眺めている。
アレクシスがジェレミーにささやいた。
「あいつ、冷めてる。」
「そうだね。そっとしておこう。」
アレクシスの背は200センチくらいあるが、ジェレミーは170センチないくらいだ。
力をつける努力はしている。
カイルの身長は195センチくらい。
ジェレミーはアレクシスに聞いた。
「アレクシスは、どこか行ってみたい場所はある?」
「行ってみたい場所?」
「うん。僕たち、ボーナスが出ただろう。」
「そうだな。5万‥。」
2人は笑った。
そして、小声で言った。
「本当は15万な。」
その声はカイルにも聞こえ、カイルもクスリと笑った。
ジェレミーは話し続けた。
「もちろん一緒に行きたいわけじゃないけど、もしも行くならどこに行く?」
「ジェレミーはどこなんだよ?」
「韓国。」
「あはは、偶然だな。俺もだ。」
「でも旅費はかなり高いだろうな。15万じゃ足りないよ。150万あったってすぐに使ってしまう。」
ジェレミーは言い、電車は止まった。
カイルは降りようとしている。
ジェレミーは言った。
「カイル、また明日。」
「あばよ。」
アレクシスは、カイルに黒人風の英語で何か言った。
カイルも何か言い、電車を降りた。
「今、何て言ったの?僕、英語が苦手なんだ。」
「どうして?いつも普通に話しているじゃないか。」
「いや、全然うまく話せないんだ。さっきのも聞こえなかったし。」
「たわいのないことさ。」
アレクシスはニヤニヤと笑った。
「適当にしか、返事が出来ない時がある。」
「気にするな。」
アレクシスは言った。
「カイルのヤツ、大丈夫かな。わからない、何も話してくれないから。」
ジェレミーは言った。
「大丈夫さ、ヤツのことは心配するな。恋人と一緒に住んでいる。
きっと、もうすぐ結婚だよ。」
アレクシスは言い、ジェレミーは安心した。
2人は会社の関係のアパートに住んでいるが、別の部屋である。
「ただいま。」
カイルは家に帰った。
「おかえり。」
玄関にイーデンが来て、カイルをハグした。
「ご飯が出来ているわ。その前にシャワーを浴びる?」
「うん。」
2人は毎晩幸せな時間を過ごす。
2人でご飯を食べて、テレビを見る。
2人で一緒に眠る時もあるし、寝ない時もある。
今日は一緒に寝なかった。
そんな時は、カイルは冷めた目をして、自分の部屋から小さなテラスに出る。
ここは田舎なので、星がとても綺麗に見える。
星を観ていると、昔、レックスを殺した事を思い出して、涙が出てしまう。
この事は、イーデンには話していない。
高校時代は、時間を無駄にしてしまった。
彼女を作り、甘い時間を過ごしたせいだ。
勉強もスポーツもろくにせず、みんなから遅れてしまった。
可愛い妹は、ボーイフレンドを作っていたし、むしゃくしゃしていた。
レックスの両親は、不正入国をしたと聞いていたし、レックス自体、あまり好きじゃないのでいいと思った。
昔、母親から、絵本を読んでもらったことを思い出す。
もっと読んでもらえばよかった。そうしたら、もっと良い心を持っていたかもしれない。
少し寒くなってきたし、イーデンが気づいている気がしたので、カイルは部屋に入った。
アフリカ。
バルトは有名になった今でも、地元の教会のミサには参加する。
そうすると、みんながバルト君と呼んでくる。
まるで、自分がまだ、ほんの小さな子供みたいだ。
そこまで気にされないので、地元は楽だった。
バルトは同い年の知り合い、メリエムを見つけたので、話しかけた。
「メリエム、久しぶりだな。」
「ええ。」
メリエムの髪の毛は、坊主だ。1センチくらいしかない。
バルトは聞いた。
「どうした、その髪の毛。」
「ちょっと‥。」
メリエムはうつむいた。
「おいおい、シスターにでもなる気か?」
バルトは両手を広げ、オーバーに聞いた。
メリエムはうつむいている。
前の席に座っていた男が言った。
「メリエム、元彼との裁判は終わったか?」
ついにメリエムは泣きだした。
ミサが終わり、バルトはメリエムを心配して追いかけたが、メリエムは泣いて行ってしまった。さきほどの男、ブラハムがバルトを止めた。
「あのな、メリエムは、元彼とケンカした時に、脱毛器具で彼の頭を脱毛しちまったんだよ。それで、彼の髪の毛がもう生えてこなくなってしまったんだ。だからきっと、メリエムも自分の髪の毛を脱毛したんだよ。」
「ちょ、ちょっと待てよ。それマジか?」
「マジだ。大変な騒ぎだった。」
はあ‥バルトは訳が分からなかった。
男には脱毛は関係ないからだ。
「じゃあ、俺は何をすればいいかな?」
「さぁ。お金で解決できれば、まだマシかもな。」
ブラハムは言った。
韓国ソウル。
ソナさんのカフェ、レインボーはまた盛ってきた。
『変わってる』という言葉は、ソナさんの口癖みたいだ。
接客をした後に、笑顔でつぶやいている。
つぶやいているが、声には出さないので、お客にはバレていない。
大学生のテナちゃんが入ってきた。
ソナさんはお客と話しながら、テナをちらりと見て、「ありがとう。」とつぶやいた。
夜のバイトは、テナ以外にも何人かいる。
「いい男。」
ソナさんはカフェの外で、傘を開きながらつぶやいた。
ミンジェは、ソナさんを見た。
「お疲れ様です。」
「お疲れ様です。」
ソナさんは30代の余裕さがある。
ソナさんを見ていると、胃が痛くなる時もあるし、胸が重くなる時がある。
これは恋かもしれない。
ミンジェは、ソナさんの後ろ姿を心配そうに見守った。
ソナさんとなら、静かでお洒落なとても良い暮らしができるだろう。
でも、年齢があまりにも離れすぎている事は心のどこかで分かっていた。
ミンジェはバッティングセンターに行く。
高校では野球部だったが、うまく行かなくなって、辞めた。
高校も行けなくなってしまった。それは、ミンジェがうますぎたからだ。
先輩からの嫉妬がすごかった。
上履きを隠されたり、上からゴミを落とされたり。
私立高校の授業料を前払いしてもらったのに、授業に出られなくて、親に申し訳なかった。
一度は怒られたが、ミンジェが泣いたので、二度目はなかった。
ミンジェが学校を辞めると、みんなが心配してきて、いじめてきた先輩も心配して家に来た。
「先輩のせいじゃないですよ。」
「じゃあ、なんのせいだよ。」
「弟の看病があるので。」
風邪をよく引く、弟のビナのせいにした。
「ただいま。」
ミンジェが帰ると、ビナが来た。
ビナは18歳だ。
「野球やってるよ。」
「あ~。そう。」
和室のテレビで、おじいちゃんも中継を見ている。
野球はみんな見る。
ミンジェは心の片隅で野球選手になれると信じているから見る。
ビナはそれを知っているから、わくわくして見る。
おじいちゃんはどういうつもりで、笑って見ているのだろう?
野球選手の親戚は、家族は、どんな感じだろう?
『あ~、いいなぁ。』
そう思ってミンジェは笑う。
ミンジェはビナに言った。
「今日、バッティングセンターに行ってきた。」
「そうなんだ。どうだった?誰かいた?」
「知り合いはいないよ。○○(野球選手)の球で、2回ホームラン打った。」
「すごいじゃん。でも、それって、機械だろ?」
「そうだよ。」
「いつか本物と対戦できればいいね。」
ビナはミンジェの手を握って言った。
「ただいま~。」
お母さんが帰ってきた。
ビナが玄関に行った。
「おかえり。おふくろ、今日の晩飯なに?」
「今日はねぇ、デパートで押し寿司買ってきたのよ。好きでしょう、アンタたち。」
「ふーん、わかった。」
ビナは和室に来た。
「今日、押し寿司だって。」
「押し寿司?え~またぁ?」
ミンジェは立ち上がった。
「お父さん、今日も遅いって。」
食卓で、お母さんは言い、ミンジェは言った。
「どうせ、キャバクラだろ。」
「ちがうわよ~。お父さんは仕事。今、大変な時期だからねぇ。」
ミンジェとビナは目を見合わせた。
「ソナさん、付き合ってください。」
ミンジェはビナの前で、告白の練習をした。
「そんなんじゃダメ。」
ビナは手本を見せた。
「ソナさんって年いくつ?」
「30歳。」
「うわー、おばさんだ。」
「まぁ、お前にとってはな。俺は8つしか離れていないから、別に普通だよ。」
レックスを殺した19歳のあの日、恐ろしくてカイルは布団の中で泣いてしまった。
警察に捕まったらどうしよう。
もしも俺に弟がいたなら、なんて無様な兄貴だろう。
もしも弟がいれば、殺さなかったかもしれない。
カイルは自分の状況を、客観的に見た。
今は自分に弟がいなくて、本当によかった。
犯罪者は、犯罪をしなければエリートに向いている。
次の日は、車修理の専門学校だった。
全然勉強をしていないので、当然分からないことだらけだ。
まわりは本気で勉強していた。こんな自分が本当にうざかった。
「ええ、レックス君が?あらぁ、かわいそうに。」
レックスの訃報を、母親が電話で受け取った。
もしも自分が電話に出ることになったら、腹が痛いからと断ろうと決めた。
「カイル?すみません、今、出かけているんです。」
母親はカイルがした事を知っているかのようだ。
母親は電話を切り、こちらを見た。
赤い目をしている。
「レックス君が亡くなったって。」
「知ってる。かわいそうだよね。」
「本当にね‥。体育館の近くで倒れていたらしいわ。心臓発作かしらねぇ‥。」
「母さん。」
カイルは母親をなぐさめた。
母親は、カイルがしたことを知らないようだ。
次の日も学校だった。
意味が分からない勉強を終え、自宅に戻る。
中学2年の妹は勉強をしている。
キッチンで、両親が座って、話していた。
カイルはつばを飲んだ。
「カイル。」
「何?」
「お父さんと話したんだけど、学校が合わないなら、もう辞めて働きなさい。それから夢を見つけてもいいから。」
「うん。」
カイルはゲーセンに置いてあるジョブ雑誌で仕事を見つけた。
ガソリンスタンドだ。
「母さん、僕はガソリンスタンドで働くよ。」
カイルが言うと、母親は笑った。
「また車?それじゃ、あんたが辞めた学校の人から笑われるねぇ。」
「でも、働きたいから。」
カイルは言い、外に出た。
外に出たものの、交通安全のために見張っている警察官を見ると、今はまだ実家を出られないと感じる。
「おーい、カイル。」
レックスを殺す三か月前に、中学時代の友達から誘いがあり、バスケをすることになった。
中学時代はバスケ部だったが、高校に入って、恋愛をして、部活を休んでしまった。
休んでもまた参加することは可能だったが、もう無理な気がした。
優しい先輩はカイルに何度も声をかけてくれたが、辞めてしまった。
クラスマッチでバスケットボールに触ると、とても楽しいと感じたが、
クラスマッチの最中にトラベリングをしてしまったと感じた。
審判はそれを見逃していたし、まわりも見逃していたが、もう遅れたと思った。
高校で3年間バスケをした奴らは強い。プロになったヤツもいる。
カイルは卒業後にゴールしたが、ボールのコントロールがうまくできなかった。
少し泣きそうになったが我慢して、もう一度、もう一度と何度も打って、
なんとか綺麗に入るようになった。
でも、速い動きができない。
難しいレイアップも決められない。
レックスを殺したのは、その3カ月後だ。
その後もレックスを殺したゴールの前でバスケを続けた。昔の仲間達とのバスケは楽しかった。
みんな笑いながらプレーして、カイルもレイアップを決めたりした。
高校で3年間プレーしていたヤツが来た。
それが、19歳のアレクシスだ。
アレクシスはまず、遠い場所からゴールを決め、次に、試合の中で、難しいシュートを見せてくれた。
カイルは聞いた。
「プロは、目指さないの?」
「目指すさ。でもまだ無理だ。」
「どうして?かなりに上手いのに。」
「まだみんなと一緒にいたいからさ。」
「そうこうしているうちに、遅れてしまうぜ。俺みたいに。」
「俺は、高校でプレーしてない。中学ではやってたんだけど。」
「はああ。でも君、うまかったよ。これからはバスケをやるといい。」
アレクシスは満面の笑みを見せた。
カイルはみんながいない日に、難しいレイアップの練習をした。
アレクシスが来た。ボールを持っている。
「コレでやってみろ。」
アレクシスが速くて良いパスをくれた。
「うん。」
カイルはトライした。
「こうだ。」
アレクシスは手本を見せてくれた。
2人はそれを何度か繰り返し、カイルは出来るようになった。
「はああ、うまくなった。」
アレクシスは言った。
「ボール、ありがとう。」
「いいんだ。お前も買った方がいい。」
カイルは体を鍛え、アレクシスと1対1をできるまでになった。
この場所でレックスを殺した事が信じられない。
頭はぼんやりとして、逆にまわりが暗くなり、集中できた。
「俺に嘘はあるか?」
バスケをしながら、アレクシスは聞いた。
「そんなものはない。」
カイルはシュートしようとしたが、アレクシスは止めてしまった。
「まだまだだな。」
アレクシスは笑った。
ガソリンスタンドは1年勤めてやめた。
鉄道関連の会社の求人があったので、応募した。
カイルが会社に入って、1カ月たった頃、アレクシスがその会社に入社した。
「アレクシス。」
「カイル。ごめん、同じ会社に入ってしまった。」
「いや、いいよ。でも、君はバスケでプロを目指すと思っていたから。」
「やっぱり俺には無理だ。みんなから離れたくない。」
「そうか。残念だな。」
「そんなことない。」
アレクシスは満面の笑みを見せた。
カイルは残念に思った。
アレクシスのような良いヤツと働けることはありがたいが、友達から有名人が出てくれれば、嬉しかったからだ。
ブラハムは建設現場で働いているが、休みの日は、バルトの仕事についてくる。
ブラハムの給料がいいのかはわからないが、ブラハムからお金をせびられることはない。
でも、ブラハムは突然言った。
「バルト、お金をめぐんでくれ。」
「やめてくれ。君は今まで、僕にお金をせびってこなかった。だから友達だったんだぞ。」
「はは、冗談だ。でも給料はいくらだい?」
「うーん‥くだらない金額だよ。」
「印税?雑誌とかの?」
「そう。ああ‥。僕が有名になったとたん、みんなが金をくれと言ってきたんだ。だから泣けてきたよ。」
「それはみんなの冗談だ。」
ブラハムは笑った。
「冗談じゃないさ。」
バルトは本当に困った感じだ。
「今日の仕事は?」
「今日は、テレビのインタビューだ。」
バルトは少し良い服に着替えた。
「それってもらえる?」
「もらえるとしても、有料だ。だから、汚さないようにして、返してる。」
「そうだな。あまり高い服は、着ない方がいい。」
ブラハムは言い、バルトは何も言わなかった。
「なんだ?高い服の方がいいのか?」
「いいとは言えないが、悪くはない。」
「まぁ、値段に合った着心地なら、許せるかもな。」
ブラハムは言った。
インタビュアーは言った。
「バルトさんは、マラソンに興味はありますか?」
「マラソン?」
「うーん‥あまりやったことがないんだ。」
帰り道、ブラハムは聞いた。
「マラソンは本当にしないのか?」
「うん。マラソンって、100キロじゃないだろう。100キロじゃないと、力の出し加減がつかめなそうだ。」
「そうか。でも、陸上の王様って、マラソンだと思うぜ。」
「ええ‥。」
バルトは一着で、白いテープを切ってゴールするのが好きだ。
いや、それでなければ、意味はない。
苦しい道をたどって、ビリでゴールすることなど、地獄と同じである。
それに、ファンの子供たちに、そんな姿は見せたくない。
バルトはもうすぐ、建設会社に戻らないといけない。
韓国。
ミンジェはついていた。野球選手になれると確信していたのも、お母さんのはとこに、メジャーリーガーがいたからだ。
「ねぇ、ウルソンさん、紹介してくれよ。」
ミンジェは母親に頼んだ。
「ダーメ。ウルソンさんはアメリカにいるのよ。それに、帰ってきたって、忙しくて会えないんだからね。」
ミンジェは仕方なく、何度も手紙を書き、ようやく会えることになった。
ミンジェはスターになって、ソナさんを驚かしたかったし、養いたいのもあった。
そうでないと、ソナさんは一生男で失敗を続けてしまう。
「それじゃダメだ。」
ウルソンさんは、腕組みをして、ミンジェのフォームを見た。
ミンジェはバッティングセンターで打つ所を見てもらいたかったが、
ウルソンさんは、まずフォームを見せてもらうと言ってきた。
これになんの意味があるかわからないし、ちょっと恥ずかしい。
「おい、なんだ、それは!」
ウルソンさんはでかい声を出した。
「お前、女みたいだぞ!」
ビナも見に来て、驚いた顔をしている。
ミンジェは言った。
「だってこんなの恥ずかしいんだもん。おじさん、おかしいよ。」
「ばかたれ!!俺に向かっておかしいとはなんだ!」
「うるさい‥。」
ビナもつぶやいた。
「あのな、プロになったらこんなの普通だぞ。」
ウルソンさんは少しミンジェの尻をさわったりした。
「やだぁ‥。やめてくださいよ。」
「俺はなぁ、たくさん苦労してきた。
男からセクハラをされたこともある。嫌なら、そうやって断れよ!!」
ウルソンさんはまた大声を出した。
夜、子供の頃にしてくれたように、ウルソンさんはデパートのレストランに連れて行ってくれた。
2人はハンバーグとラーメンを食べた後に、パフェを注文した。
ウルソンさんは揚げ物を食べ、コーヒーを飲んでいる。
ミンジェは聞いた。
「また連れてきてくれるでしょ?」
「今日で終わりだよ、バカタレ!」
「ええ‥なんで‥。」
ビナも残念そうにした。
「ミンジェ、ビナ、お前たち、プロになりたいか?」
「いや‥俺は‥。」
「はい!!」
ミンジェは真剣な目をした。
「じゃあ‥、頑張れ。」
「でも、どうやったらプロになれますか?俺は大統領杯には出てないけど、打てるのは間違いないんだよ?」
「うーん。じゃあお前、入団テスト受けてみろ。」
「へー、それいつ?俺、仕事辞めなきゃいけないから。」
「ソナさん。」
「やっぱり、今日で終わり。」
ソナさんは小さな声でつぶやいた。
「終わりってわけじゃないですよ。」
「いいえ、いいのよ。」
ソナさんは笑った。
「もうすぐ辞めます。野球選手になるので。」
「あら、そう。すごいのねぇ。」
「いえ。まだカフェ、続けますか。」
「はい。」
ソナさんは即答をした。
「また会いに来ます。」
「あそう‥。」
ソナさんは大人なので、余裕そうだ。
多分、ミンジェが野球選手になれると信じていない。
アメリカ。
仕事の帰りはいつもと変わりない。
カイルは反対側に座って、景色を見ている。
ジェレミーはアレクシスに聞いた。
「休みの日って何してる?」
「何って、俺はいつもバスケだ。」
アレクシスは笑った。
どんなにイラついても、まわりへの笑顔を忘れないのは、アレクシスのポリシーだった。
アレクシスはカイルに声をかけた。
「明日の練習行くだろ?」
「ああ。」
カイルの降りる駅には、マジシャンのポスターが貼ってある。
とてもお洒落な感じだ。
ジェレミーは言った。
「素敵だ。」
「そうだな。」
アレクシスは答えた。
『でも、本当はどうでもいい。
イカサマカジノも、上手いバイオリンも、舌を噛みそうなラップも、銃撃戦も、
政治家になりたての若造も、社長も、そんなことは関係ない。
どんな脅しにも屈することなく、自分のやるべきことをやるまでだ。
いつか日か、その意味が分かる日がくる。
どんな脅しにも屈するな。
自分がやるべきことを見定め、実行をしろ。』
アレクシスは言った。
「俺はバスケをやる。」
ジェレミーは見て、ニコリと笑った。
ジェレミーの休日は、朝ランニングをして、コンビニで朝食を買い、海が見えるベンチで食べる。
そして、クロスワードをする。
雨の日は、家で映画を観る。あと、カフェにランチを食べに行く。
言っておこう、ジェレミーはチャーミングな方だ。
でも、恋愛が下手である。
電車から降りた後、アレクシスは聞いた。
「ジェレミーは、仕事以外で何かやりたいことはないのかよ?」
「まだわからない。見つからないし、あまり出来ない方がいいかもしれない。」
「はぁ‥。かわいそうだな。」
帰りはいつも一緒だが、行きは別だ。
お互いに干渉しあわないので、関係は良好だった。
もしも仕事が別になっても、友達でいたいと思っている。
「アレクシスは、バスケで、プロを目指すでしょ?」
「ああ。そのつもりだ。まだ24だから、大丈夫だろう。あんまり若いと、いじめられる。」
「そうだね。」
「結婚していなければ、なれるよな。女はみんなそう言う。勝手な物だ。」
アレクシスは言った。
アパートの部屋に入りながら、アレクシスは思い出したように言った。
「ジェレミー、明日の練習、見に来い。」
「うん‥。」
「バッシュあるか?」
「ないけど、室内履きがある。」
「なら、それでいい。」
次の日、カイルも来ていた。
カイルのバスケはプロ並みになった。
練習はプロよりは劣るが、かなりキツいものだ。
アレクシスは言った。
「ジェレミーも入ってみろ。」
「ええ、でも、ほとんどやったことないんだ。」
「大丈夫だ。軽めに投げてくれ。」
アレクシスが言うと、メンバーはうなずいた。
ジェレミーは中1並みのドリブルでレイアップをしたりした。
練習の後、みんなでコーラを飲む。
アレクシスはカイルのした事を気づいていたが、何も言わなかった。
『もう帰るだろう?』
『この後、カイルと会う。』
アレクシスは、あの日のレックスの優しげな困り顔をよく覚えている。
アレクシスはレックスを好きではなかった。
レックスはとても可愛い子と付き合っていたからだ。
だけど、なにも殺すなんて。ゾッとする。
カイルに初めてコーラを渡したのは、あの日から1年ほどたった時だ。
アレクシスは毒入りコーラだと見抜いていた。
見ていないが、見えていた。
カイルは受け取って、美味そうに飲んだ。
アレクシスは同情深い男だった。
黒人には情というものがあるが、アレクシスは特に情が深いので、自分の心を傷つけた。
帰り、カイルの恋人のイーデンが迎えに来ていた。
アレクシスは持っていた袋を落としてしまった。
「おっと、いけない。」
ジェレミーに笑顔で言った。
「大丈夫かい?」
「ああ。あの人は、カイルの奥さんだよ。」
「もう結婚したの?」
「まだだけど、きっともうすぐ奥さんになる。」
「綺麗な人だね。」
ジェレミーは言った。
『初めて見た時は驚いたものだ。
イーデンは、俺の女だと思った。
なぜ神はこんなことをする?』
『カイルこそ、死ねばいいかもしれない。』
アレクシスは想像した。
カイルの墓の前で泣き崩れるイーデンを支える、自分がいた。
次の日の休憩時間、ジェレミーは浮かない顔をしていた。
ジェレミーの見た目はチャーミングだが、冴えない。
アレクシスは聞いた。
「どうしたんだよ。」
「僕は特技がない。」
「好きなことは?」
「クロスワードパズル。」
「それじゃ仕事にできないだろう?」
「そうなんだよ。だから、この仕事をしっかりやるつもりだ。
君は、バスケを頑張ってくれ。」
ジェレミーが言うと、アレクシスはアゴでうなずいた。
「恋人は‥いないのか?」
アレクシスは聞いたが、途中でまちがえたと思った。
「いない。いないというか、できないんだ。僕が奥手だから。」
「かわいそうに。いいか、気に入った子がいたらな、すぐにデートに誘え。」
「君はいつもそうしてるの?」
「まあ‥そうだよ。」
アレクシスには、弟が1人と妹が2人いる。
姉貴はいないはずだが、従姉のニコアが家によく来ている。
ニコアはコギャルで、まだ実家に住んでいた頃は、アレクシスが帰ってくる頃に、
アレクシスのベッドで寝ていたものだ。
『もしものことがあれば、俺はニコアと付き合えばいいだろう。
だから安心している。カイルのことも、イーデンのことも。
おバカなニコアがいてくれて、本当に助かっている。ありがとう。』
アレクシスはニヤニヤと笑った。
休憩室のテレビは、NBAのニュースになった。
NBAのニュースが出ると、アレクシスの目は本気になる。
他の仲間たちと、めずらしくゲラゲラ笑って話していたカイルも、テレビを見た。
アナウンサーは、NBAでそこそこ活躍した選手が日本に行くことを伝えた。
アレクシスは笑って、ジェレミーに言った。
「爺さんだ。」
「そうだね。日本って、弱いだろ?」
「まぁ、そこそこだろうな。ダンクシュートが出来りゃ、ガキでも呼ばれる。」
「でも、馴染めるのかな?」
「馴染めるわけない。」
アレクシスとジェレミーは笑った。
バルトは建設現場にいた。
今はビルを建てているので、上階だ。
1度、目の前で仲間が落ちて死んだ。
だから、本当はすごく怖い。
命綱があるので大丈夫だが、若い女が通ると、わざわざ落ちそうな所に行くヤツがいるので、心配だ。
バルトは結構この仕事を理解しているので、難しい箇所を任せられる。
ベテランの親父と話した。
バルトは紙を持った親父さんの話を真剣に聞いた。
そして、少し考えた。
ふと隣を見ると、まるで自分のような男が立っている。
まだ、若いみたいだ。
そいつはこちらを見て、白い歯を見せた。
「ボビーです、よろしく。」
「おお、よろしく。」
バルトは握手をした。
白人のチビ助が来て、バルトの隣にしゃがんだ。
「リッキー君。」
「リックウェルだ。バルト、大丈夫か?」
「大丈夫だ。俺はしっかり勉強している。」
「そうだな。」
リックウェルは立ち上がって、ボビーを見た。
「なぜ、君はここにいる?」
「バルトさんに挨拶を。」
「さっさと持ち場に戻れ。」
「はい。」
2人は持ち場に戻って行った。
韓国ソウル。
ミンジェの入団テストが行われていた。
入団テストの会場に行く際、テストを受ける数名の男子達と一緒にワゴン車に乗せられた。
運転手はサングラスがかった眼鏡をして、球団の帽子をかぶっている。
大丈夫だ、間違いではない。
男子の一人が聞いた。
「どんなことをするか知っている?」
「さぁ~。平手打ち、とかじゃない?」
ミンジェは愛想笑いをした。
野球選手は芸能人と同じだと思うので、面白いことも言えないといけないと思った。
バラエティー番組に出演する機会はあまりないと思うけど‥。
聞いた男子は、メモ帳に何かメモした。
『この子は大丈夫そう。』
ミンジェは思った。
プロ野球選手に、ふつうの男みたいな人が多かったので、ミンジェは心配していた。
もしも自分がなれなくても、ソナさんと結婚すればいいし、こういう最初から芸能人っぽい男を選んでほしいと思った。
不安そうな色白の男子が乗っている。
「お母さんは?」
ミンジェは聞いた。
「いるよ。」
「入団テストのこと、知ってる?」
「知ってる。」
色白の男はニコリと笑った。
ミンジェは、男は18を超えたら、野放しにしてほしいと思った。
ミンジェにも親はいるが、ビナもいるので、安心だ。
ミンジェは深呼吸をした。
古着屋で勝ったスタジャンを着ている。
こんなジェケットは着てこなければよかった。
なんだか不良みたいだ。
冴えない男とも仲良くやらなければいけない。
野球も人生も同じだが、何が起こるかは、分からないからだ。
今までの経験上、自分が苦しい時は、冴えないヤツから助けられる。
まずは、野球界のお爺さんたちと話をした。
その後はテストがある。
走らされると聞かされたので、少し走り込んだが、野球に持久力なんて必要ない。
大切なのは、瞬発力だ。
やっぱり走らされるは短距離の話だった。
短距離走は弱い。さきほど話したメモ帳の男子は超速かった。
「ああ、どうしよう。」
「ほれ、次はミンジェだ。」
お爺さんは指示した。
ふぅ‥
ミンジェは陸上のスターティングポーズをしてしまった。
そして走り出した。
『大丈夫だ。いつもより速く走れた。』
お爺さんは何も言わず、こちらを見て、そして、笑顔で手招きした。
次はバッティングテストがあった。
ピッチャーは、よくテレビで見る人気選手だ。
ミンジェは、思わず声をかけた。
「ジュレン選手ですよね。僕、ジュレン選手とここでお会いできると思ってなかったので、光栄です。」
「ああ‥どうも。」
ジュレン選手は帽子をとって、挨拶をした。
ミンジェは思わず、ジュレン選手と握手してしまった。
そして、自分の番を待った。
ジュレン選手は投げる前に、何度かボールを右手で少し投げて、グローブにぶつけたりした。
『ああ‥。握手をしなければよかった。ジュレン選手はこれからテストがあるのに。』
最初はメモの男子からだ。
ミンジェは結構打てるので、最初見ているのは、不公平かなと感じた。
メモの男は2回見逃し、最後にヒットした。
『ジュレン選手は手加減したかもしれない。だって、全部同じ球だ。』
色白の男は、三振してしまった。
『ああ、なぜバットを振る。1度目も2度目は、ボールなのに。』
他にも何人か打った。
最後にミンジェの番だ。
『ジュレン選手はきっと、本気を出すだろう。』
1度目はボールで、2度目はストレート。3度目はボールだった。
お爺さんは言った。
「ほら、あと1球だぞ。」
「でも、2回ボールだったんです。」
「まぁ、いい。」
ジュレン選手もニヤリと笑った。
ミンジェは首をかしげた。
『ジュレン選手は変化球をするかな‥。』
ジュレン選手は変化球を投げた。
ミンジェには才能が有り、投げた瞬間に変化球かそうでないか判断できる。
そして、瞬時にボールがどこにくるか判断し、打てるのだ。
そうだな、その瞬間だけは、アニメの世界に入った感じになる。
ミンジェはホームランを打った。
お爺さんは言った。
「ジュレン、ストレートが打たれたぞ!」
『いや、ちがう。今のは変化球だ。』
『このお爺さんのこと好きだったけど、もう終わりなのかな。』
「おめでとう。」
ジュレンは握手を求めてきた。
「ありがとうございます。」
「今の変化球ですか?」
「変化球にしたかったけど、できなかった。」
「ああ、そうなんですか。」
この時のミンジェは分からなかった。
自分が思った事と、視聴者が思う事はちがうということを‥。
お爺さんは言った。
「ね、視聴者に合わせよう。野球解説者が、あれこれと言っていたら、みんなうるさくて、集中して試合を見られない。」
「分かりました。」
「みんな、今日どうだった?正直言って、ダメだった人もいる。
でも、本気でやりたいなら、また出直せばいい。」
ミンジェは採用された。メモ帳男子と白肌君も採用されたらしい。
ミンジェは、もし会えたなら、白肌君とも仲良くするつもりだが、野球選手としては、あまりはよくない。
メモ帳男子は、大丈夫だと思う。
ミンジェは、球団の人達と話す事になった。
試験の時のお爺さんと、監督、コーチ、それとミンジェが知らなかった年上の選手が入ってきた。
お爺さんと監督は険しい顔をしていて、コーチはヘラヘラと笑っている。
お爺さんは言った。
「あ~、どうもどうも。実はね、イ・ミンジェ君には、野球選手として、ウ・ミンシンと名乗ってほしいんだ。」
「え‥?僕、イ・ミンジェですよ。」
「それは分かっている。でもこれは、我々からの頼みなんだ‥。」
「ええ‥。でも‥。」
ミンジェは少し顔をふくらせた。
「せめて、ウ・ミンジェがいいんですけど。」
「わかった。そうしよう。」
お爺さんは安心した感じだ。
「それからね。年齢のことなんだけど‥。」
「えっ‥。」
「高校から出直してほしいんだ。」
「えーそれは無理。」
「もちろん、試合だけでいい。私立のボンシン高校なんだけどさ、去年ドラフトでとった子が自殺したんだよ。頼む、金は払う。」
監督は言った。
「うーん‥。仕方ない、分かりました。」
ミンジェは4才もサバを読むことになってしまった。
「これは誓約書だよ。」
お爺さんは誓約書を出した。
普通の誓約書と同じだ。
ただ、球団に無関係者を連れて来ないとかは書かれていた。
あとは、秘密をもらさないとかだ。
「あの、弟が練習を見たいと言っていて。」
「いいよ。事前に教えて、そう言う事は。」
「わかりました。僕、彼女はいません。」
「そうか。」
「はい。週刊誌に嘘を書かれたらどうしましょう?」
「週刊誌に書かれるような事はしたらダメだぞ。でもな、うちにもスポンサーがちゃんとついているので、大丈夫です。」
ミンジェはうなずいた。
「また遊んでよ。」
ビナは家の前で、ミンジェの腕をつかんで言った。
ミンジェは少し変わってしまった。
冷たい目で言ってしまった。
「ごめん。今は練習があるから。」
「はぁ?」
ビナはでかい声を出した。
「お前、なんでそんなに変わっちゃったんだよぉ!」
「ちがうって。今はって言ったでしょ。」
「きもい。」
「ビナにもそういう日が、ちゃんと来るから。」
ミンジェが言うと、お母さんが家から出てきた。
「ミンジェ、ビナちゃんにあまりキツイ事を言うのやめてあげて。」
「母さん。」
「ビナちゃんはね、病院で受けたテストで、子供を作るための遺伝子がない事が判明したばかりなの。」
「はぁ?病院でのテストって何?」
ミンジェは大声を出した。
ビナは涙を拭きながら、言った。
「病院で検査をうけて、僕に精子がないことが判明したんだ。」
「ええ。」
ミンジェは後退りした。
「仕方ないじゃんか!!」
ビナは大声を出した。
「もうお互いにして。こんな意味がないことは辞めてちょうだい。」
お母さんは泣いた。
夜。2人は仲直りの証に、ウルソンさんと言ったファミレスに行く事にした。
アメリカ。
休日、ランニングと朝食を終えたジェレミーは、アパートの部屋のドアの前で、ため息をついた。
アレクシスが引っ越しの準備をしている。
ニコアや弟、両親が来て、手伝っていた。
「1人で充分なのにな。」
アレクシスは段ボールを持って、ニヤリと笑った。
ジェレミーは家に入り、涙をぬぐった。
ポストに入っていた封筒を見る。
「なにかな‥。」
夜、2人はマクドナルドで夕食をとることにした。
「ようやく片付いたよ。」
アレクシスは言った。
「そうか。これでようやく、NBAに行けるね‥。」
「離れ離れになるけど、ジェレミーとはずっと友達でいたいと思ってる。」
「うん‥。」
「どうした?元気がないぞ。」
「実は‥、クロスワードパズルの抽選で、韓国ペア旅行が当たったんだ。
よければ一緒に行かないか?」
「ええ?いいのか?!」
「うん。君と一緒に行きたいんだ。」
アメリカの国際空港。
ついに2人は飛行機のエコノミークラスに乗り込んだ。
「ハハハ、本物の飛行機だぜ。」
アレクシスは笑った。
「飛行機は初めてかい?」
「二度目さ。でもよかった。代表に入ったら、海外にも行くことになる。
あまり騒ぎ立てたら、まわりに迷惑になるだろう?旅行するために、バスケをするわけじゃない。」
「でも、感動するぜ。」
アレクシスはヘッドホンをつけたり、椅子を倒したりして楽しんだ。
ジェレミーは言った。
「窓際の席じゃなくて残念だ。」
「でもいい席だよ。目の前に、こんなに大きなモニターがある。」
飛行機は離陸した。
アレクシスは怖そうだったが、楽しんでいた。
アレクシスは言った。
「ああ、このモニターで、飛行機がどこにいるか分かるわけだ。」
「そうだね。」
アレクシスはアイマスクをして、音楽を聴き、家族のことを思い出した。
「NBAから、誘いがあった。ついにプロになる。」
みんなに打ち明けた時の、喜んだ顔は忘れられない。
父親は聞いた。
「誘われたのは、お前だけか?」
「いや、友人のカイルも一緒だ。俺が頼んだ。仲間も喜んでくれたよ。」
家族は少しだけ目を合わした。
「ニコア、君に待っていてくれとは言わない。でも‥ずっと、君は俺の支えだ。」
「ええ‥。」
ニコアは胸に手を当てた。
「お兄ちゃん、それってプロポーズ?」
「言っとくけど、ニコアは従姉なのよ。」
「別にプロポーズじゃない。でも、ニコアは俺にとって大切な人だということを、伝えたかっただけだよ。」
アレクシスは言った。
「ありがとう、嬉しいわ。」
ニコアはアレクシスに抱きついた。
機内食を食べながら、ジェレミーは聞いた。
「意外と悪くない。」
「そうだな。ジャムをもう少しつけてくれれば‥。」
「甘い物が欲しければ、リンゴジュースを頼めば?」
2人はしばらくの間、エコノミーの機内食を食べ、その後は寝ることにした。
窓際の席でなかったことは良い事もある。
外に気がいかないので、よく休む事ができる。
韓国についた2人はひと通りの手続きを済ませ、タクシーでロッテホテルに向かい、
ホテルのツインに荷物を置いて、街に繰り出した。
「すごいな‥。とてもお洒落だ。」
NBA選手になるアレクシスは、まだ有名ではないが、笑顔を心がけることにした。
2人はサムスン美術館に行き、いろいろな所を見て回った。
夜は、韓国のおばちゃんが教えてくれた食堂で食べることにした。
韓国はそこまで値段も高くないし、騙されることもあまりなかったのでよかった。
ミンジェは素振りをしていた。
素振りが撮られることには抵抗があったが、今はもう慣れた。
ビナは勝手に見に来たが、ミンジェの実の弟だと気づいた球団のお爺さんが入れてくれた。
この後、試合がある。
ベンチへと向かう廊下でビナは待つことにした。
お爺さんは聞いた。
「おい、控えまで、会いに行くか?」
「いい。僕、ここで待ちたい。」
「そうか。」
お爺さんはあきらめた感じだ。
いよいよ選手たちが来た。
ビナは自信に満ちた表情で、ミンジェを待った。
ミンジェは真剣な顔で歩き、ビナの顔をちらりと見たが行ってしまった。
最後の選手は、ちらりと振り返ってビナを見て、何か言った。
そして、ミンジェが小走りで来て、ビナの前髪をつかんで言った。
「お前なんで来たんだよ。」
「やめてよ!会いにきてあげたんじゃん。」
「勝手に来るなって言っただろう。メイちゃんか?お前は。」
「来てほしいって言ったから、来てあげたんじゃないか。」
「来てほしいだなんて、誰も言ってない。」
ミンジェはベンチに戻ってしまった。
「うう‥。」
ビナは泣き、知り合いの選手が来て、ビナをなぐさめた。
試合が終わり、選手が帰る時間まで、ビナは待っていた。
気のいい先輩選手が、ミンジェに声をかけた。
「あのチビ、まだいるぞ。」
「ああ‥。」
「ビナ、待っていてくれたんだね。」
ミンジェが言うと、ビナはうなずいた。
「わかった、一緒に帰ろう。どこか寄って、何か食べようか?」
ミンジェは作り笑いをすると、ビナも元気になって笑った。
次の日、野球の仕事に行くため、ミンジェは歩いた。
ビナを家に泊めたせいで、少しペースが乱された。
ビナはポエマーで、夜には変な事を言いだすので、困っている。
2人の白人と黒人が、道に迷っている。
英語を勉強しているので、話しかけてみることにした。
どうせ相手は観光客だし、二度と会うことはない。
「どうかしましたか?」
「ありがとう、○○に行きたいんだけど、わからなくて。」
「それなら、こうですよ。」
ミンジェは英語で説明をし、ニッコリと笑った。
「あれ、野球選手のウ・ミンジェさんですか?」
ジェレミーは聞いた。
「はい。なぜ‥?」
「韓国について、調べたんです。あなたはとても有名だ。」
「ありがとうございます。」
「今度、アレクシスも、NBAにいくんですよ。」
「そうでしたか。頑張ってください。」
「ありがとう。君も頑張ってくれ。」
3人はお別れした。
有名になると、いちいち連絡先を交換せずにすむので、ありがたい。
アフリカ。バルトは、ブラハムとメリエムと共にカフェにいた。
「今日は首都までわざわざ来てくれてありがとう。ここは俺のおごりだ。なんでも好きな物を注文してくれ。」
3人は、料理を注文し、食べた。
最後に、アイスティーが運ばれてきた。
「だけど、なぜ来たんだい?」
バルトは聞き、ブラハムが答えた。
「バルト。メリエムが金に困っている。少し貸してくれ。」
「嘘だろう?メリエム、お前が脱毛をしてしまった男のことか?」
メリエムは泣きながらうなずいた。
「ああ、そんな‥。」
バルトは目頭をおさえ、ブラハムも渋い顔をした。
「一体いくらなんだい?」
「100万円。」
メリエムは答えた。
「ええ!そんなにか!」
バルトは立ち上がって、大きな声を出した。
「あのな、俺はスポーツ選手だぞ!セレブじゃない!だから、そんな大金を渡せるはずがないんだ。」
ブラハムは言った。
「頼む、バルト。なんとか金を出してくれ。」
「断る。アフリカには飢餓で苦しむ子供がたくさんいるのに、そんなお金を出せるわけない。」
メリエムは泣いている。
ブラハムも大きなため息をついて、うなだれてしまった。
カフェの客たちもちらちらとこちらを見た。
バルトが大金持ちだということは分かっていた。
「仕方ない。お金を出そう。ただ、お金を出すのはもうしたくない。いいな?」
「はい。分かりました、バルトさん。ありがとうございます。」
メリエムは涙目で言い、
「バルトさん、ありがとうございます。」
ブラハムも続けて言った。
カフェから出て、ブラハムは言った。
「よければ君の、靴をなめようか?」
「やめてくれ!そんなことはしてほしくない。」
バルトは笑った。
カイルの恋人、イーデンは迷っていた。
カイルはたまに怯えていて、小心者の時がある。でも、離れたくはなかった。
ちょうど、アレクシスからNBAに誘われたので、お別れの機会ができた。
「引っ越すことになる。」
カイルはイーデンを抱きしめた。
「ええ。私も、実家に戻るわ。」
「この家は‥思い出だらけだ。」
イーデンはカイルから離れた。
「悲しいけど、売る事にしましょう。」
「そうだな。」
引っ越しの朝、カイルはイーデンに声をかけた。
「最後にコーヒーを飲まないか?」
「だけど‥。」
「僕の荷物から出してきた。」
カイルはヤカンとマグカップを見せた。
2人は置いて行くテーブルと椅子に座って、コーヒーを飲んだ。
この静けさは、2人が大人になったという証だろう。
カイルの叔父が来て、荷物を車に乗せた。
カイルは言った。
「必ずまた会おう。」
「ええ。」
「イーデンと別れたくはない。」
「私もよ。」
2人はハグし、カイルはイーデンの頭をなでた。
カイルは行ってしまい、イーデンは家の前で座って少しぼんやりした。
韓国、ソウル。
新聞はミンジェのメジャーリーグ進出を知らせた。
それはアメリカでも、ニュースで報道され、アレクシスとジェレミーもそれぞれミンジェの姿を確認し、にやりと笑った。
「行ってくる。」
報道陣の前で、ミンジェはビナと握手を交わした。
ウルソンさんは、ミンジェを相手にしないと思ったが、心配してくれたので、ミンジェは嬉しかった。
ミンジェは礼儀正しくするように心がけた。アメリカでの一番の頼りは、ウルソンさんなのだ。
2人きりで食事をした時は、なんとなく、スターになった気がして、ミンジェは食べた後、紙でよく口を拭いた。
ミンジェはメジャーリーグでも素振りをした。
ファンが見に来ている。その中に、見覚えがある黒人と白人がいたので、ミンジェは駆け寄った。
「あの‥、前にソウルでお会いしましたよね?」
「うん。アレクシスとジェレミーだ。」
「ああ、すみません。忘れてしまっていて‥。」
「いいんだ。実は頼みがある。」
アレクシスは言った。
「何ですか?」
「君の試合のチケットをくれ。」
ジェレミーは答えた。
「でも、僕、持っていなくて。」
「これと交換しよう。」
アレクシスは、NBAの試合のチケットを2枚くれた。
「ああ‥。ちょっと待っていてください、すみません。」
ミンジェは走って、小太りの黒人コーチにかけよって、何か話した。
コーチはNBAのチケットを見て、中でスタッフと話し、チケットを2枚持ってきてくれた。
ミンジェがまた戻ると、2人は消えていたが、すぐに戻ってきた。
「どうだった?」
アレクシスは聞いた。
「チケット2枚もらえました。はい。」
ミンジェがヒアユーアーと言うと、アレクシスは少し笑った。
「ありがとう。」
「どういたしまして。」
2人はニヤニヤとした。
「またな。」
「さよなら。」
ついに、2人は吹き出してしまった。
コーチはチケットを1枚、ミンジェに渡そうとした。
「いいんですか?」
コーチは2枚ほしいか、確認した。
「いいえ、僕、1枚で結構です。」
ミンジェが言うと、コーチは神妙な顔でミンジェを見た。
このコーチは、アメリカ人選手の前では結構笑うのに、ミンジェの前だと、表情が硬いままだ。ミンジェはそういうのが原因で、暗くなってしまう。
あとは、韓国の家族からメールが一通もない日は、悲しくなる。
ビナは病気だから仕方ないけど、親が僕を見捨てるなんて、酷すぎる。
家はマンションみたいな感じだ。
同僚が同じ階にいる。
昔はおばさんと同じアパートにも住んでいた。
でも、自分を嫌いな人と一緒に住むのは苦痛だ‥。
部屋は少し広いが、荷物を置きたいので便利だ。
野球選手だがバスケットゴールを置いてみた。
前に同僚の部屋を見たら、いろいろと改造してあったので、いいと思った。
こんなにお金がもらえると思っていなかったし、遊びやプレステにくらい贅沢してもいいだろう。
時々、幻覚が見えてしまう。
一人ではでかすぎる冷蔵庫の隅に、ネズミが置かれていると思って二度見した。
よく見たら、自分がいれておいたタオルだ。
『この色のタオルは買わない方がいいかもしれない‥。』
日用品で、特別欲しい物なんてなかったのに、同僚がホームセンターに連れて行った。
いろいろとカゴに入れられて、大変だった。
あとは、大きなデスクトップパソコンも買った。
ソリティアをしているだけなのに、仕事をしている気分になってくる。
『これは仕事じゃないのに。』
ミンジェはPCメガネをかけ、ソリティアをよくやっている。
マンションには、乾燥機がある。
この前行ったら、いっぱいで、女性用のブラジャーがあったので、やっぱりベランダに干すことにした。
ベッドはキングサイズで、部屋が広すぎるので散らかしても、綺麗に見える。
起きる時は、ジリリと鳴る目覚まし時計だ。
昔、ビナにもらった物とよく似ている。あれは、喧嘩をした時に捨ててしまった。
アラームが鳴ったとたん、布団を蹴飛ばして、起きるのがほとんどだ。
一度、ビナがベッドの目の前に腕組みして立っていた気がして、二度寝してしまった。
夜はよく泣いてしまう。
一番の気がかりは、ソナさんの部屋がどんな部屋か、見なかったことだ。
『ソナさん‥。』
『俺のメールや通信は全て見られていることを知っている。
だから、グラビアも見ることは出来ない。』
『見られているのは、いつからの物だろう?
俺だって、変な子と付き合った事もあるし、ソナさんとのやり取りもあるから、見られたくない内容だってある。』
『大体、何が楽しいの?』
「まぁ、調べたいのは当然だよな。俺は〇億円もいただいている。」
鳩の壁掛け時計が鳴ったので後ろを見た。
これは、昔の友達からの贈り物だ。
「あ、そうだ。」
財布にいれておいたチケットを見た。
財布はルイヴィトンを使っている。
「えっ。」
Googleで、NBAの試合会場を検索した。
前に、Google社から、本社を見学に来ないかと誘われたが、まだ行っていない。
もしもGoogleで働くことになったら、困るからだ。
とりあえず、英語が分からないという顔をしておいた。
「飛行機になるのかな‥。えー、だったら‥無理なんだけど。」
「ほっ。」
検索結果が出て、会場まではバスや電車を使って、3時間くらいで行ける。
「でも、この日‥。」
スケジュールを確認した。
スケジュール表を落としたり、外部に見せたりして、停職になった選手がいるので、
全て手帳に記入している。
大事な物は全て金庫だ。
パスポートも‥。
手帳を確認して、この日は空いていることが判明した。
「どうしよう‥、一人で長旅なんて。」
アフリカ。
バルトは子供達とレースすることになった。
子供達は先に走り出し、バルトが後から追いかける。
カメラマンが2名ほどいて、写真を撮った。
バルトは最初の方は手加減していたが、最後に本気を見せてやろうと思った。
最後は立候補した男の子と一騎打ちをすることになった。
男の子は走り出す。
バルトは本気になった。
バルトは男の子を追い抜き、男の子は転んでしまった。
男の子は風で起きられない。
バルトは走り終わると、両手をあげた。
「あれ?」
ふりむくと、男の子の下には、みんなが駆け寄っていた。
アメリカ。
アレクシスとカイルが所属するNBAチームでは、練習が行われていた。
コーチのキムは、アレクシスはもう年だからと不安に思ったが、そんなことはなかった。
充分に若いし、手足が長く、動きに固さがなかった。
「キムコーチ。」
「タリスタン。東京への準備はバッチリか?」
「はい。日本には友達がいるので、絶対に出場したいです。」
「努力を続けろ。東京で彼にきっと会える。」
「はい、分かりました。」
タリスタンはベテランの黒人選手だ。
タリスタンは、日本人で初めてNBA選手になった山田純太郎を思い出した。
「ハイ!!」
山田は、NBAの練習中も大きな声を出して、パスを受け取った。
黒人選手は何も言わない。
目で合図をする。あまり、声を出してはいけないし、みんなクールに見せたい。
タリスタンは山田にそのことを伝えてみると、山田は言った。
「だって、そうじゃなきゃ、分からないじゃんよぉ!」
「ああ‥。でも、試合中は話せない。」
「えっ‥。」
「まずいだろ?どこにパスをまわすか、敵にバレたら。」
「オー、アイシー。」
山田は言い、タリスタンは笑った。
「あんた、名前は?」
「ああ、僕は、タリスタンだよ。」
「タリズタン。」
山田はメモした。
山田は初めての試合で、なかなかパスを回してもらえなかった。
山田はチームとうまくいっていないと言ったが、まだ仲良くなれていなかった。
山田はあちこちと動き回った。
山田のような人種と出会うのは初めてなので、よく分からなかった。
山田にようやくパスがいき、山田は3ポイントを狙ったが、外した。
山田はコートで泣いた。
コートで泣くなと、何度後輩に言ったか分からないのに、泣いてしまった。
最後にコーチがなんと言ったかわからないが、労いの言葉をかけ、チームメイトは山田を見た。
コーチは山田について何かを話し、チームメイトたちは、握手を求めてきたので、
山田はまた泣いた。
山田は、親友に泣きながら、国際電話をした。
「だけどさ、会ってから10日しかたっていないのに、試合に出されたんだぜ。」
「ああ‥。でも、山田君さ、行ってから1カ月くらいたつんじゃない?」
「でも、生活に慣れるのに精一杯だったから。」
「そうか。そうだ、国際電話は高いから、切るね。」
「だって、そっち持ちだろ?」
「でも、俺もそんなには金ないからさ。」
「わかった。」
山田はしぶしぶ電話を切り、また泣いた。
「おい、何か作ってくれよぉ!俺は腹が減っちゃったんだから。」
「あれぇ?誰もいない。」
山田は、アメリカの食事に慣れてきた。
でも、バイキングで料理を選んでいると、まだ夢を見ている気分になる。
プルルル
山田は唇でその音を出した。
黒人はじろりとこちらを見て、ニヤリと笑ってくる。
山田は持ち前の根性で、NBAの速さに慣れた。
山田はゾーンに入ると、一人一人がしっかりと見えなくなる。
自分だけがしっかりとした人間で、まわりがみんな影のような感覚に陥る。
「山田、大丈夫か。」
「山田、そんなんでシュートできるか。」
「山田、お願いだ、他の者にパスを回してくれ。」
山田はつぶやいた。
「大丈夫。みんな影だから。」
山田はシュートした。
山田は誰にパスをまわすかは、輪郭で決める。
よく見えている仲間の輪郭で判断する。
山田は栄光をつかんだ試合の後でも、ベッドで涙した。
「はー、ゲームしたいよ。」
山田は涙をぬぐった。
山田は、中学の同級生が作ってくれた寄せ書きや写真を見て、
「こんな物、いらねっ!!」
山田はそれを投げ捨てた。
ぼんやりとした物ではあったが、山田には戦争に行っていたという記憶があった。
その記憶だけを頼りに、ここまで強くなった。
高校時代に仲良くバスケをしてあげた長身も、そこまでは強くなっていない。
山田が強くなれたのは、みんな運だと言う。
「運なわけねぇだろうがぁ!!」
山田は部屋で、一人でよく怒鳴っていたので、隣の部屋の黒人から、壁を叩かれた。
一度、黒人も怒っていたが、それきりだ。いや、その三日後にも怒鳴っていた。
今日の試合はこちらが負けて、終了した。
今日は少ししか出番がなかったが、大丈夫かな‥。
まぁいいか。日本に戻ることになっても、きっと居場所はある。
結構楽しいし、どこも近いし、自分の身の丈に合っていると思う。
「タリズタン、俺、荷物持とうか?」
「いいよ、大丈夫。」
ついに、日本代表が、アメリカに来ることになる。
山田はタリスタンに言った。
「日本、超強いんだけど、大丈夫かな‥。」
「強いっ?ワオ!」
「あっ、ごめん、間違えた。結構強いだった。」
「ええ?本当?」
「これはマジ。ちょっと手加減してくんない?」
「うーん。それは無理だな。」
タリスタンは首をかしげた。
「みんな、今までありがとうね。」
NBAを去る日、山田は、仲間に漢字ドリルを配った。
「全然、いられなかった、けど。」
山田は涙をぬぐった。
「タリズタン、大好きだよ。」
山田はタリスタンに抱きつき、頬にキスをしたので、タリスタンは顔をしかめた。
アフリカ。
バルトは、フルマラソンに出る事になってしまった。
これにはアマチュアランナーも出られるので、ブラハムも出る。
顔をこわばらせているスタート前のブラハムに、バルトは話しかけた。
「緊張する?」
「うん。そうだな。」
「大丈夫だ。俺もマラソンじゃ素人同然だから。」
「ああ。」
ブラハムは少しでも良いタイムを残したかった。
いい男になりたかったし、これからもバルトと仲良くするためだ。
「もっと前の方に行く?」
バルトは聞いた。
「いや、俺はここで。」
「そうかい。俺はちょっと、行ってもいいかな。」
バルトは前を指した。
「いいぞ。」
ブラハムは、前や後ろは関係ないと思った。
パン
みんな一斉に走り出した。
これはプロの試合じゃないので、ふざけて転ぶヤツもいる。
バルトはいつもの調子で走ったので、一番前の組に入ってしまった。
でも、だんだんと遅れていく‥。
バルトは本当に胸が苦しくなってしまった。
スタッフのテントの近くで立ち止まり、手を上げ、棄権した。
スタッフ達は、これが誰か最初分からなかったが、女性がテントに入れてくれた。
「大丈夫?あなた、名前は?」
「バルトです。」
女性は息を飲んだ。
「バルトさん、どうかされましたか?」
女性は口調を変えた。
「いえ、何も。急に胸が苦しくなったものですから。」
「すぐに、お医者様を呼びますからねぇ。」
女性はにこやかに言った。
ブラハムが遅れて通りすぎた時、テントの中で診察を受けるバルトと目が合って、ブラハムはガン見してしまった。
ミンジェは一泊二日でNBAの試合を見に行くことにした。
バスに乗る。
一応、Googleで調べたことを、メモをしてきた。
『元気?』
ビナからメールが届いている。
『これから旅行だよ(^^)』
『お友達と?うらやましい((>_
アメリカの海辺の街。
夜、バスケットゴールの下に後ろを向いた黒人が立っていた。
「話ってなんだよ、カイル。」
日系と白人のハーフ、レックスが声をかけると、黒人カイル・バートレットは、悲しげに振り向いた。
カイルは歩き出した。
「どこに行くの?」
レックスは聞いた。
「どこでもない。」
「話ってなに?」
「お前には大切な話だ。」
カイルはベンチに置いてあったコカ・コーラを持った。
そしてまた歩く。
「そっちは駐車場だよ。」
レックスは言った。
「まぁ、これでも飲め。」
カイルはレックスにコーラを渡した。
「ありがとう、気が利く。」
レックスはコーラを飲んだ。
カイルも少し飲んだ。
「うっ‥。」
レックスは苦しみ始めた。
カイルは冷めた目でそれを見守る。
やがて、レックスは動かなくなった。
カイルは何事もなかったかのように、マウンテンバイクに乗って、帰る。
ペットボトルは、指紋を拭き、海に投げた。
ここらへんには、防犯カメラがない事は分かっていた。
「ただいま。」
「おかえり。遅かったわね、何かあった?」
お母さんと、猫を抱いた可愛い妹が玄関に来た。
「いや、何もないよ。」
カイルはケラケラと笑った。
場所はアフリカ。
陽気な音楽にのるように、黒人の陸上選手は、スタブロに乗る。
自分の頭の中には、いつでも陽気な音楽が流れているので、とても楽しいが、
他の者はそうでもないみたいだ。
スタートの前はみんな、苦悩に満ちた表情をしている。
なんで?すぐに終わるのに。人生を60年に例えたとしても、10秒なんてあっという間だ。
パン
スタートは難しいという者は多いが、なんてことない。
ピスの音とともに、駆け出せばいいだけだ。
最初から全速力で走れるわけない。だから徐々に加速していく。
5,60メートルでマッハが出せればいいが、大体、マッハが出るのは70メートルくらいになる。80でも遅くはない。何事もあきらめないことが肝心だ。
「ふぅ~もう終わったぜ。」
今日もバルトが一番である。
「バルトさん、お疲れ様です。」
「今日のレース、いかがでしたか?」
インタビュアーたちが駆け寄ってくる。
本当に華やかな世界だ。
「最高だぜ。みんな、俺は元気だ。」
バルトはカメラに向かって言った。
韓国のカフェ‥。22歳の長身の男が働いている。
高校もろくに卒業できなかった、出来損ないだ。
店長のオバタリアンはとても厳しい。
長身の男ミンジェが、オバタリアンのソナさんに言った。
「今日、客、全然来ないっすね。」
「そうね。近くにパンケーキ屋ができたから仕方ないわ。それが終わったら、床に掃除機をかけてちょうだい。」
「分かりました。」
ソナさんは答えなかった。その代わり、入口の近くから窓を見て、つぶやいた。
「変わってる。」
ミンジェは掃除機の準備をしながら、ソナさんをちらりと見たが、気にしなかった。
ソナさんの方こそ、変わっている。30歳でバツ4らしい。
本人はバツ1と嘘をついている。
線路を作る仕事をしている白人のジェレミーと黒人のアレクシス。
バラストと呼ばれる線路に敷く石を運びながら、ジェレミーは言った。
「こうして石を運んでいると、鉱山で働いているみたいだ。」
「ああ、そうだな。」
「本当は鉱山で働いてみたかったけど、近所にはないから仕方ない。」
「アメリカンドリームにはほど遠いな。というか、現代には鉱山はもうあまりない。」
「うん。さっさと終わらせて帰りたいよ。」
仕事を終え、事務所に戻ると、休憩室でテレビを見ながら、カイルが休んでいた。
カイルは現在24歳で、ジェレミーとアレクシスと同い年である。
「カイル。お疲れ様。」
「おお。お疲れ。」
カイルはニコリと笑った。
「もう帰る?」
「そうだな。」
ジェレミーは聞き、アレクシスは答えた。カイルもこちらに来た。
3人は、駅まで歩く。
3人は電車に乗るが、カイルは仕方なく一緒に来たというかのように、反対側に座って、窓から外を眺めている。
アレクシスがジェレミーにささやいた。
「あいつ、冷めてる。」
「そうだね。そっとしておこう。」
アレクシスの背は200センチくらいあるが、ジェレミーは170センチないくらいだ。
力をつける努力はしている。
カイルの身長は195センチくらい。
ジェレミーはアレクシスに聞いた。
「アレクシスは、どこか行ってみたい場所はある?」
「行ってみたい場所?」
「うん。僕たち、ボーナスが出ただろう。」
「そうだな。5万‥。」
2人は笑った。
そして、小声で言った。
「本当は15万な。」
その声はカイルにも聞こえ、カイルもクスリと笑った。
ジェレミーは話し続けた。
「もちろん一緒に行きたいわけじゃないけど、もしも行くならどこに行く?」
「ジェレミーはどこなんだよ?」
「韓国。」
「あはは、偶然だな。俺もだ。」
「でも旅費はかなり高いだろうな。15万じゃ足りないよ。150万あったってすぐに使ってしまう。」
ジェレミーは言い、電車は止まった。
カイルは降りようとしている。
ジェレミーは言った。
「カイル、また明日。」
「あばよ。」
アレクシスは、カイルに黒人風の英語で何か言った。
カイルも何か言い、電車を降りた。
「今、何て言ったの?僕、英語が苦手なんだ。」
「どうして?いつも普通に話しているじゃないか。」
「いや、全然うまく話せないんだ。さっきのも聞こえなかったし。」
「たわいのないことさ。」
アレクシスはニヤニヤと笑った。
「適当にしか、返事が出来ない時がある。」
「気にするな。」
アレクシスは言った。
「カイルのヤツ、大丈夫かな。わからない、何も話してくれないから。」
ジェレミーは言った。
「大丈夫さ、ヤツのことは心配するな。恋人と一緒に住んでいる。
きっと、もうすぐ結婚だよ。」
アレクシスは言い、ジェレミーは安心した。
2人は会社の関係のアパートに住んでいるが、別の部屋である。
「ただいま。」
カイルは家に帰った。
「おかえり。」
玄関にイーデンが来て、カイルをハグした。
「ご飯が出来ているわ。その前にシャワーを浴びる?」
「うん。」
2人は毎晩幸せな時間を過ごす。
2人でご飯を食べて、テレビを見る。
2人で一緒に眠る時もあるし、寝ない時もある。
今日は一緒に寝なかった。
そんな時は、カイルは冷めた目をして、自分の部屋から小さなテラスに出る。
ここは田舎なので、星がとても綺麗に見える。
星を観ていると、昔、レックスを殺した事を思い出して、涙が出てしまう。
この事は、イーデンには話していない。
高校時代は、時間を無駄にしてしまった。
彼女を作り、甘い時間を過ごしたせいだ。
勉強もスポーツもろくにせず、みんなから遅れてしまった。
可愛い妹は、ボーイフレンドを作っていたし、むしゃくしゃしていた。
レックスの両親は、不正入国をしたと聞いていたし、レックス自体、あまり好きじゃないのでいいと思った。
昔、母親から、絵本を読んでもらったことを思い出す。
もっと読んでもらえばよかった。そうしたら、もっと良い心を持っていたかもしれない。
少し寒くなってきたし、イーデンが気づいている気がしたので、カイルは部屋に入った。
アフリカ。
バルトは有名になった今でも、地元の教会のミサには参加する。
そうすると、みんながバルト君と呼んでくる。
まるで、自分がまだ、ほんの小さな子供みたいだ。
そこまで気にされないので、地元は楽だった。
バルトは同い年の知り合い、メリエムを見つけたので、話しかけた。
「メリエム、久しぶりだな。」
「ええ。」
メリエムの髪の毛は、坊主だ。1センチくらいしかない。
バルトは聞いた。
「どうした、その髪の毛。」
「ちょっと‥。」
メリエムはうつむいた。
「おいおい、シスターにでもなる気か?」
バルトは両手を広げ、オーバーに聞いた。
メリエムはうつむいている。
前の席に座っていた男が言った。
「メリエム、元彼との裁判は終わったか?」
ついにメリエムは泣きだした。
ミサが終わり、バルトはメリエムを心配して追いかけたが、メリエムは泣いて行ってしまった。さきほどの男、ブラハムがバルトを止めた。
「あのな、メリエムは、元彼とケンカした時に、脱毛器具で彼の頭を脱毛しちまったんだよ。それで、彼の髪の毛がもう生えてこなくなってしまったんだ。だからきっと、メリエムも自分の髪の毛を脱毛したんだよ。」
「ちょ、ちょっと待てよ。それマジか?」
「マジだ。大変な騒ぎだった。」
はあ‥バルトは訳が分からなかった。
男には脱毛は関係ないからだ。
「じゃあ、俺は何をすればいいかな?」
「さぁ。お金で解決できれば、まだマシかもな。」
ブラハムは言った。
韓国ソウル。
ソナさんのカフェ、レインボーはまた盛ってきた。
『変わってる』という言葉は、ソナさんの口癖みたいだ。
接客をした後に、笑顔でつぶやいている。
つぶやいているが、声には出さないので、お客にはバレていない。
大学生のテナちゃんが入ってきた。
ソナさんはお客と話しながら、テナをちらりと見て、「ありがとう。」とつぶやいた。
夜のバイトは、テナ以外にも何人かいる。
「いい男。」
ソナさんはカフェの外で、傘を開きながらつぶやいた。
ミンジェは、ソナさんを見た。
「お疲れ様です。」
「お疲れ様です。」
ソナさんは30代の余裕さがある。
ソナさんを見ていると、胃が痛くなる時もあるし、胸が重くなる時がある。
これは恋かもしれない。
ミンジェは、ソナさんの後ろ姿を心配そうに見守った。
ソナさんとなら、静かでお洒落なとても良い暮らしができるだろう。
でも、年齢があまりにも離れすぎている事は心のどこかで分かっていた。
ミンジェはバッティングセンターに行く。
高校では野球部だったが、うまく行かなくなって、辞めた。
高校も行けなくなってしまった。それは、ミンジェがうますぎたからだ。
先輩からの嫉妬がすごかった。
上履きを隠されたり、上からゴミを落とされたり。
私立高校の授業料を前払いしてもらったのに、授業に出られなくて、親に申し訳なかった。
一度は怒られたが、ミンジェが泣いたので、二度目はなかった。
ミンジェが学校を辞めると、みんなが心配してきて、いじめてきた先輩も心配して家に来た。
「先輩のせいじゃないですよ。」
「じゃあ、なんのせいだよ。」
「弟の看病があるので。」
風邪をよく引く、弟のビナのせいにした。
「ただいま。」
ミンジェが帰ると、ビナが来た。
ビナは18歳だ。
「野球やってるよ。」
「あ~。そう。」
和室のテレビで、おじいちゃんも中継を見ている。
野球はみんな見る。
ミンジェは心の片隅で野球選手になれると信じているから見る。
ビナはそれを知っているから、わくわくして見る。
おじいちゃんはどういうつもりで、笑って見ているのだろう?
野球選手の親戚は、家族は、どんな感じだろう?
『あ~、いいなぁ。』
そう思ってミンジェは笑う。
ミンジェはビナに言った。
「今日、バッティングセンターに行ってきた。」
「そうなんだ。どうだった?誰かいた?」
「知り合いはいないよ。○○(野球選手)の球で、2回ホームラン打った。」
「すごいじゃん。でも、それって、機械だろ?」
「そうだよ。」
「いつか本物と対戦できればいいね。」
ビナはミンジェの手を握って言った。
「ただいま~。」
お母さんが帰ってきた。
ビナが玄関に行った。
「おかえり。おふくろ、今日の晩飯なに?」
「今日はねぇ、デパートで押し寿司買ってきたのよ。好きでしょう、アンタたち。」
「ふーん、わかった。」
ビナは和室に来た。
「今日、押し寿司だって。」
「押し寿司?え~またぁ?」
ミンジェは立ち上がった。
「お父さん、今日も遅いって。」
食卓で、お母さんは言い、ミンジェは言った。
「どうせ、キャバクラだろ。」
「ちがうわよ~。お父さんは仕事。今、大変な時期だからねぇ。」
ミンジェとビナは目を見合わせた。
「ソナさん、付き合ってください。」
ミンジェはビナの前で、告白の練習をした。
「そんなんじゃダメ。」
ビナは手本を見せた。
「ソナさんって年いくつ?」
「30歳。」
「うわー、おばさんだ。」
「まぁ、お前にとってはな。俺は8つしか離れていないから、別に普通だよ。」
レックスを殺した19歳のあの日、恐ろしくてカイルは布団の中で泣いてしまった。
警察に捕まったらどうしよう。
もしも俺に弟がいたなら、なんて無様な兄貴だろう。
もしも弟がいれば、殺さなかったかもしれない。
カイルは自分の状況を、客観的に見た。
今は自分に弟がいなくて、本当によかった。
犯罪者は、犯罪をしなければエリートに向いている。
次の日は、車修理の専門学校だった。
全然勉強をしていないので、当然分からないことだらけだ。
まわりは本気で勉強していた。こんな自分が本当にうざかった。
「ええ、レックス君が?あらぁ、かわいそうに。」
レックスの訃報を、母親が電話で受け取った。
もしも自分が電話に出ることになったら、腹が痛いからと断ろうと決めた。
「カイル?すみません、今、出かけているんです。」
母親はカイルがした事を知っているかのようだ。
母親は電話を切り、こちらを見た。
赤い目をしている。
「レックス君が亡くなったって。」
「知ってる。かわいそうだよね。」
「本当にね‥。体育館の近くで倒れていたらしいわ。心臓発作かしらねぇ‥。」
「母さん。」
カイルは母親をなぐさめた。
母親は、カイルがしたことを知らないようだ。
次の日も学校だった。
意味が分からない勉強を終え、自宅に戻る。
中学2年の妹は勉強をしている。
キッチンで、両親が座って、話していた。
カイルはつばを飲んだ。
「カイル。」
「何?」
「お父さんと話したんだけど、学校が合わないなら、もう辞めて働きなさい。それから夢を見つけてもいいから。」
「うん。」
カイルはゲーセンに置いてあるジョブ雑誌で仕事を見つけた。
ガソリンスタンドだ。
「母さん、僕はガソリンスタンドで働くよ。」
カイルが言うと、母親は笑った。
「また車?それじゃ、あんたが辞めた学校の人から笑われるねぇ。」
「でも、働きたいから。」
カイルは言い、外に出た。
外に出たものの、交通安全のために見張っている警察官を見ると、今はまだ実家を出られないと感じる。
「おーい、カイル。」
レックスを殺す三か月前に、中学時代の友達から誘いがあり、バスケをすることになった。
中学時代はバスケ部だったが、高校に入って、恋愛をして、部活を休んでしまった。
休んでもまた参加することは可能だったが、もう無理な気がした。
優しい先輩はカイルに何度も声をかけてくれたが、辞めてしまった。
クラスマッチでバスケットボールに触ると、とても楽しいと感じたが、
クラスマッチの最中にトラベリングをしてしまったと感じた。
審判はそれを見逃していたし、まわりも見逃していたが、もう遅れたと思った。
高校で3年間バスケをした奴らは強い。プロになったヤツもいる。
カイルは卒業後にゴールしたが、ボールのコントロールがうまくできなかった。
少し泣きそうになったが我慢して、もう一度、もう一度と何度も打って、
なんとか綺麗に入るようになった。
でも、速い動きができない。
難しいレイアップも決められない。
レックスを殺したのは、その3カ月後だ。
その後もレックスを殺したゴールの前でバスケを続けた。昔の仲間達とのバスケは楽しかった。
みんな笑いながらプレーして、カイルもレイアップを決めたりした。
高校で3年間プレーしていたヤツが来た。
それが、19歳のアレクシスだ。
アレクシスはまず、遠い場所からゴールを決め、次に、試合の中で、難しいシュートを見せてくれた。
カイルは聞いた。
「プロは、目指さないの?」
「目指すさ。でもまだ無理だ。」
「どうして?かなりに上手いのに。」
「まだみんなと一緒にいたいからさ。」
「そうこうしているうちに、遅れてしまうぜ。俺みたいに。」
「俺は、高校でプレーしてない。中学ではやってたんだけど。」
「はああ。でも君、うまかったよ。これからはバスケをやるといい。」
アレクシスは満面の笑みを見せた。
カイルはみんながいない日に、難しいレイアップの練習をした。
アレクシスが来た。ボールを持っている。
「コレでやってみろ。」
アレクシスが速くて良いパスをくれた。
「うん。」
カイルはトライした。
「こうだ。」
アレクシスは手本を見せてくれた。
2人はそれを何度か繰り返し、カイルは出来るようになった。
「はああ、うまくなった。」
アレクシスは言った。
「ボール、ありがとう。」
「いいんだ。お前も買った方がいい。」
カイルは体を鍛え、アレクシスと1対1をできるまでになった。
この場所でレックスを殺した事が信じられない。
頭はぼんやりとして、逆にまわりが暗くなり、集中できた。
「俺に嘘はあるか?」
バスケをしながら、アレクシスは聞いた。
「そんなものはない。」
カイルはシュートしようとしたが、アレクシスは止めてしまった。
「まだまだだな。」
アレクシスは笑った。
ガソリンスタンドは1年勤めてやめた。
鉄道関連の会社の求人があったので、応募した。
カイルが会社に入って、1カ月たった頃、アレクシスがその会社に入社した。
「アレクシス。」
「カイル。ごめん、同じ会社に入ってしまった。」
「いや、いいよ。でも、君はバスケでプロを目指すと思っていたから。」
「やっぱり俺には無理だ。みんなから離れたくない。」
「そうか。残念だな。」
「そんなことない。」
アレクシスは満面の笑みを見せた。
カイルは残念に思った。
アレクシスのような良いヤツと働けることはありがたいが、友達から有名人が出てくれれば、嬉しかったからだ。
ブラハムは建設現場で働いているが、休みの日は、バルトの仕事についてくる。
ブラハムの給料がいいのかはわからないが、ブラハムからお金をせびられることはない。
でも、ブラハムは突然言った。
「バルト、お金をめぐんでくれ。」
「やめてくれ。君は今まで、僕にお金をせびってこなかった。だから友達だったんだぞ。」
「はは、冗談だ。でも給料はいくらだい?」
「うーん‥くだらない金額だよ。」
「印税?雑誌とかの?」
「そう。ああ‥。僕が有名になったとたん、みんなが金をくれと言ってきたんだ。だから泣けてきたよ。」
「それはみんなの冗談だ。」
ブラハムは笑った。
「冗談じゃないさ。」
バルトは本当に困った感じだ。
「今日の仕事は?」
「今日は、テレビのインタビューだ。」
バルトは少し良い服に着替えた。
「それってもらえる?」
「もらえるとしても、有料だ。だから、汚さないようにして、返してる。」
「そうだな。あまり高い服は、着ない方がいい。」
ブラハムは言い、バルトは何も言わなかった。
「なんだ?高い服の方がいいのか?」
「いいとは言えないが、悪くはない。」
「まぁ、値段に合った着心地なら、許せるかもな。」
ブラハムは言った。
インタビュアーは言った。
「バルトさんは、マラソンに興味はありますか?」
「マラソン?」
「うーん‥あまりやったことがないんだ。」
帰り道、ブラハムは聞いた。
「マラソンは本当にしないのか?」
「うん。マラソンって、100キロじゃないだろう。100キロじゃないと、力の出し加減がつかめなそうだ。」
「そうか。でも、陸上の王様って、マラソンだと思うぜ。」
「ええ‥。」
バルトは一着で、白いテープを切ってゴールするのが好きだ。
いや、それでなければ、意味はない。
苦しい道をたどって、ビリでゴールすることなど、地獄と同じである。
それに、ファンの子供たちに、そんな姿は見せたくない。
バルトはもうすぐ、建設会社に戻らないといけない。
韓国。
ミンジェはついていた。野球選手になれると確信していたのも、お母さんのはとこに、メジャーリーガーがいたからだ。
「ねぇ、ウルソンさん、紹介してくれよ。」
ミンジェは母親に頼んだ。
「ダーメ。ウルソンさんはアメリカにいるのよ。それに、帰ってきたって、忙しくて会えないんだからね。」
ミンジェは仕方なく、何度も手紙を書き、ようやく会えることになった。
ミンジェはスターになって、ソナさんを驚かしたかったし、養いたいのもあった。
そうでないと、ソナさんは一生男で失敗を続けてしまう。
「それじゃダメだ。」
ウルソンさんは、腕組みをして、ミンジェのフォームを見た。
ミンジェはバッティングセンターで打つ所を見てもらいたかったが、
ウルソンさんは、まずフォームを見せてもらうと言ってきた。
これになんの意味があるかわからないし、ちょっと恥ずかしい。
「おい、なんだ、それは!」
ウルソンさんはでかい声を出した。
「お前、女みたいだぞ!」
ビナも見に来て、驚いた顔をしている。
ミンジェは言った。
「だってこんなの恥ずかしいんだもん。おじさん、おかしいよ。」
「ばかたれ!!俺に向かっておかしいとはなんだ!」
「うるさい‥。」
ビナもつぶやいた。
「あのな、プロになったらこんなの普通だぞ。」
ウルソンさんは少しミンジェの尻をさわったりした。
「やだぁ‥。やめてくださいよ。」
「俺はなぁ、たくさん苦労してきた。
男からセクハラをされたこともある。嫌なら、そうやって断れよ!!」
ウルソンさんはまた大声を出した。
夜、子供の頃にしてくれたように、ウルソンさんはデパートのレストランに連れて行ってくれた。
2人はハンバーグとラーメンを食べた後に、パフェを注文した。
ウルソンさんは揚げ物を食べ、コーヒーを飲んでいる。
ミンジェは聞いた。
「また連れてきてくれるでしょ?」
「今日で終わりだよ、バカタレ!」
「ええ‥なんで‥。」
ビナも残念そうにした。
「ミンジェ、ビナ、お前たち、プロになりたいか?」
「いや‥俺は‥。」
「はい!!」
ミンジェは真剣な目をした。
「じゃあ‥、頑張れ。」
「でも、どうやったらプロになれますか?俺は大統領杯には出てないけど、打てるのは間違いないんだよ?」
「うーん。じゃあお前、入団テスト受けてみろ。」
「へー、それいつ?俺、仕事辞めなきゃいけないから。」
「ソナさん。」
「やっぱり、今日で終わり。」
ソナさんは小さな声でつぶやいた。
「終わりってわけじゃないですよ。」
「いいえ、いいのよ。」
ソナさんは笑った。
「もうすぐ辞めます。野球選手になるので。」
「あら、そう。すごいのねぇ。」
「いえ。まだカフェ、続けますか。」
「はい。」
ソナさんは即答をした。
「また会いに来ます。」
「あそう‥。」
ソナさんは大人なので、余裕そうだ。
多分、ミンジェが野球選手になれると信じていない。
アメリカ。
仕事の帰りはいつもと変わりない。
カイルは反対側に座って、景色を見ている。
ジェレミーはアレクシスに聞いた。
「休みの日って何してる?」
「何って、俺はいつもバスケだ。」
アレクシスは笑った。
どんなにイラついても、まわりへの笑顔を忘れないのは、アレクシスのポリシーだった。
アレクシスはカイルに声をかけた。
「明日の練習行くだろ?」
「ああ。」
カイルの降りる駅には、マジシャンのポスターが貼ってある。
とてもお洒落な感じだ。
ジェレミーは言った。
「素敵だ。」
「そうだな。」
アレクシスは答えた。
『でも、本当はどうでもいい。
イカサマカジノも、上手いバイオリンも、舌を噛みそうなラップも、銃撃戦も、
政治家になりたての若造も、社長も、そんなことは関係ない。
どんな脅しにも屈することなく、自分のやるべきことをやるまでだ。
いつか日か、その意味が分かる日がくる。
どんな脅しにも屈するな。
自分がやるべきことを見定め、実行をしろ。』
アレクシスは言った。
「俺はバスケをやる。」
ジェレミーは見て、ニコリと笑った。
ジェレミーの休日は、朝ランニングをして、コンビニで朝食を買い、海が見えるベンチで食べる。
そして、クロスワードをする。
雨の日は、家で映画を観る。あと、カフェにランチを食べに行く。
言っておこう、ジェレミーはチャーミングな方だ。
でも、恋愛が下手である。
電車から降りた後、アレクシスは聞いた。
「ジェレミーは、仕事以外で何かやりたいことはないのかよ?」
「まだわからない。見つからないし、あまり出来ない方がいいかもしれない。」
「はぁ‥。かわいそうだな。」
帰りはいつも一緒だが、行きは別だ。
お互いに干渉しあわないので、関係は良好だった。
もしも仕事が別になっても、友達でいたいと思っている。
「アレクシスは、バスケで、プロを目指すでしょ?」
「ああ。そのつもりだ。まだ24だから、大丈夫だろう。あんまり若いと、いじめられる。」
「そうだね。」
「結婚していなければ、なれるよな。女はみんなそう言う。勝手な物だ。」
アレクシスは言った。
アパートの部屋に入りながら、アレクシスは思い出したように言った。
「ジェレミー、明日の練習、見に来い。」
「うん‥。」
「バッシュあるか?」
「ないけど、室内履きがある。」
「なら、それでいい。」
次の日、カイルも来ていた。
カイルのバスケはプロ並みになった。
練習はプロよりは劣るが、かなりキツいものだ。
アレクシスは言った。
「ジェレミーも入ってみろ。」
「ええ、でも、ほとんどやったことないんだ。」
「大丈夫だ。軽めに投げてくれ。」
アレクシスが言うと、メンバーはうなずいた。
ジェレミーは中1並みのドリブルでレイアップをしたりした。
練習の後、みんなでコーラを飲む。
アレクシスはカイルのした事を気づいていたが、何も言わなかった。
『もう帰るだろう?』
『この後、カイルと会う。』
アレクシスは、あの日のレックスの優しげな困り顔をよく覚えている。
アレクシスはレックスを好きではなかった。
レックスはとても可愛い子と付き合っていたからだ。
だけど、なにも殺すなんて。ゾッとする。
カイルに初めてコーラを渡したのは、あの日から1年ほどたった時だ。
アレクシスは毒入りコーラだと見抜いていた。
見ていないが、見えていた。
カイルは受け取って、美味そうに飲んだ。
アレクシスは同情深い男だった。
黒人には情というものがあるが、アレクシスは特に情が深いので、自分の心を傷つけた。
帰り、カイルの恋人のイーデンが迎えに来ていた。
アレクシスは持っていた袋を落としてしまった。
「おっと、いけない。」
ジェレミーに笑顔で言った。
「大丈夫かい?」
「ああ。あの人は、カイルの奥さんだよ。」
「もう結婚したの?」
「まだだけど、きっともうすぐ奥さんになる。」
「綺麗な人だね。」
ジェレミーは言った。
『初めて見た時は驚いたものだ。
イーデンは、俺の女だと思った。
なぜ神はこんなことをする?』
『カイルこそ、死ねばいいかもしれない。』
アレクシスは想像した。
カイルの墓の前で泣き崩れるイーデンを支える、自分がいた。
次の日の休憩時間、ジェレミーは浮かない顔をしていた。
ジェレミーの見た目はチャーミングだが、冴えない。
アレクシスは聞いた。
「どうしたんだよ。」
「僕は特技がない。」
「好きなことは?」
「クロスワードパズル。」
「それじゃ仕事にできないだろう?」
「そうなんだよ。だから、この仕事をしっかりやるつもりだ。
君は、バスケを頑張ってくれ。」
ジェレミーが言うと、アレクシスはアゴでうなずいた。
「恋人は‥いないのか?」
アレクシスは聞いたが、途中でまちがえたと思った。
「いない。いないというか、できないんだ。僕が奥手だから。」
「かわいそうに。いいか、気に入った子がいたらな、すぐにデートに誘え。」
「君はいつもそうしてるの?」
「まあ‥そうだよ。」
アレクシスには、弟が1人と妹が2人いる。
姉貴はいないはずだが、従姉のニコアが家によく来ている。
ニコアはコギャルで、まだ実家に住んでいた頃は、アレクシスが帰ってくる頃に、
アレクシスのベッドで寝ていたものだ。
『もしものことがあれば、俺はニコアと付き合えばいいだろう。
だから安心している。カイルのことも、イーデンのことも。
おバカなニコアがいてくれて、本当に助かっている。ありがとう。』
アレクシスはニヤニヤと笑った。
休憩室のテレビは、NBAのニュースになった。
NBAのニュースが出ると、アレクシスの目は本気になる。
他の仲間たちと、めずらしくゲラゲラ笑って話していたカイルも、テレビを見た。
アナウンサーは、NBAでそこそこ活躍した選手が日本に行くことを伝えた。
アレクシスは笑って、ジェレミーに言った。
「爺さんだ。」
「そうだね。日本って、弱いだろ?」
「まぁ、そこそこだろうな。ダンクシュートが出来りゃ、ガキでも呼ばれる。」
「でも、馴染めるのかな?」
「馴染めるわけない。」
アレクシスとジェレミーは笑った。
バルトは建設現場にいた。
今はビルを建てているので、上階だ。
1度、目の前で仲間が落ちて死んだ。
だから、本当はすごく怖い。
命綱があるので大丈夫だが、若い女が通ると、わざわざ落ちそうな所に行くヤツがいるので、心配だ。
バルトは結構この仕事を理解しているので、難しい箇所を任せられる。
ベテランの親父と話した。
バルトは紙を持った親父さんの話を真剣に聞いた。
そして、少し考えた。
ふと隣を見ると、まるで自分のような男が立っている。
まだ、若いみたいだ。
そいつはこちらを見て、白い歯を見せた。
「ボビーです、よろしく。」
「おお、よろしく。」
バルトは握手をした。
白人のチビ助が来て、バルトの隣にしゃがんだ。
「リッキー君。」
「リックウェルだ。バルト、大丈夫か?」
「大丈夫だ。俺はしっかり勉強している。」
「そうだな。」
リックウェルは立ち上がって、ボビーを見た。
「なぜ、君はここにいる?」
「バルトさんに挨拶を。」
「さっさと持ち場に戻れ。」
「はい。」
2人は持ち場に戻って行った。
韓国ソウル。
ミンジェの入団テストが行われていた。
入団テストの会場に行く際、テストを受ける数名の男子達と一緒にワゴン車に乗せられた。
運転手はサングラスがかった眼鏡をして、球団の帽子をかぶっている。
大丈夫だ、間違いではない。
男子の一人が聞いた。
「どんなことをするか知っている?」
「さぁ~。平手打ち、とかじゃない?」
ミンジェは愛想笑いをした。
野球選手は芸能人と同じだと思うので、面白いことも言えないといけないと思った。
バラエティー番組に出演する機会はあまりないと思うけど‥。
聞いた男子は、メモ帳に何かメモした。
『この子は大丈夫そう。』
ミンジェは思った。
プロ野球選手に、ふつうの男みたいな人が多かったので、ミンジェは心配していた。
もしも自分がなれなくても、ソナさんと結婚すればいいし、こういう最初から芸能人っぽい男を選んでほしいと思った。
不安そうな色白の男子が乗っている。
「お母さんは?」
ミンジェは聞いた。
「いるよ。」
「入団テストのこと、知ってる?」
「知ってる。」
色白の男はニコリと笑った。
ミンジェは、男は18を超えたら、野放しにしてほしいと思った。
ミンジェにも親はいるが、ビナもいるので、安心だ。
ミンジェは深呼吸をした。
古着屋で勝ったスタジャンを着ている。
こんなジェケットは着てこなければよかった。
なんだか不良みたいだ。
冴えない男とも仲良くやらなければいけない。
野球も人生も同じだが、何が起こるかは、分からないからだ。
今までの経験上、自分が苦しい時は、冴えないヤツから助けられる。
まずは、野球界のお爺さんたちと話をした。
その後はテストがある。
走らされると聞かされたので、少し走り込んだが、野球に持久力なんて必要ない。
大切なのは、瞬発力だ。
やっぱり走らされるは短距離の話だった。
短距離走は弱い。さきほど話したメモ帳の男子は超速かった。
「ああ、どうしよう。」
「ほれ、次はミンジェだ。」
お爺さんは指示した。
ふぅ‥
ミンジェは陸上のスターティングポーズをしてしまった。
そして走り出した。
『大丈夫だ。いつもより速く走れた。』
お爺さんは何も言わず、こちらを見て、そして、笑顔で手招きした。
次はバッティングテストがあった。
ピッチャーは、よくテレビで見る人気選手だ。
ミンジェは、思わず声をかけた。
「ジュレン選手ですよね。僕、ジュレン選手とここでお会いできると思ってなかったので、光栄です。」
「ああ‥どうも。」
ジュレン選手は帽子をとって、挨拶をした。
ミンジェは思わず、ジュレン選手と握手してしまった。
そして、自分の番を待った。
ジュレン選手は投げる前に、何度かボールを右手で少し投げて、グローブにぶつけたりした。
『ああ‥。握手をしなければよかった。ジュレン選手はこれからテストがあるのに。』
最初はメモの男子からだ。
ミンジェは結構打てるので、最初見ているのは、不公平かなと感じた。
メモの男は2回見逃し、最後にヒットした。
『ジュレン選手は手加減したかもしれない。だって、全部同じ球だ。』
色白の男は、三振してしまった。
『ああ、なぜバットを振る。1度目も2度目は、ボールなのに。』
他にも何人か打った。
最後にミンジェの番だ。
『ジュレン選手はきっと、本気を出すだろう。』
1度目はボールで、2度目はストレート。3度目はボールだった。
お爺さんは言った。
「ほら、あと1球だぞ。」
「でも、2回ボールだったんです。」
「まぁ、いい。」
ジュレン選手もニヤリと笑った。
ミンジェは首をかしげた。
『ジュレン選手は変化球をするかな‥。』
ジュレン選手は変化球を投げた。
ミンジェには才能が有り、投げた瞬間に変化球かそうでないか判断できる。
そして、瞬時にボールがどこにくるか判断し、打てるのだ。
そうだな、その瞬間だけは、アニメの世界に入った感じになる。
ミンジェはホームランを打った。
お爺さんは言った。
「ジュレン、ストレートが打たれたぞ!」
『いや、ちがう。今のは変化球だ。』
『このお爺さんのこと好きだったけど、もう終わりなのかな。』
「おめでとう。」
ジュレンは握手を求めてきた。
「ありがとうございます。」
「今の変化球ですか?」
「変化球にしたかったけど、できなかった。」
「ああ、そうなんですか。」
この時のミンジェは分からなかった。
自分が思った事と、視聴者が思う事はちがうということを‥。
お爺さんは言った。
「ね、視聴者に合わせよう。野球解説者が、あれこれと言っていたら、みんなうるさくて、集中して試合を見られない。」
「分かりました。」
「みんな、今日どうだった?正直言って、ダメだった人もいる。
でも、本気でやりたいなら、また出直せばいい。」
ミンジェは採用された。メモ帳男子と白肌君も採用されたらしい。
ミンジェは、もし会えたなら、白肌君とも仲良くするつもりだが、野球選手としては、あまりはよくない。
メモ帳男子は、大丈夫だと思う。
ミンジェは、球団の人達と話す事になった。
試験の時のお爺さんと、監督、コーチ、それとミンジェが知らなかった年上の選手が入ってきた。
お爺さんと監督は険しい顔をしていて、コーチはヘラヘラと笑っている。
お爺さんは言った。
「あ~、どうもどうも。実はね、イ・ミンジェ君には、野球選手として、ウ・ミンシンと名乗ってほしいんだ。」
「え‥?僕、イ・ミンジェですよ。」
「それは分かっている。でもこれは、我々からの頼みなんだ‥。」
「ええ‥。でも‥。」
ミンジェは少し顔をふくらせた。
「せめて、ウ・ミンジェがいいんですけど。」
「わかった。そうしよう。」
お爺さんは安心した感じだ。
「それからね。年齢のことなんだけど‥。」
「えっ‥。」
「高校から出直してほしいんだ。」
「えーそれは無理。」
「もちろん、試合だけでいい。私立のボンシン高校なんだけどさ、去年ドラフトでとった子が自殺したんだよ。頼む、金は払う。」
監督は言った。
「うーん‥。仕方ない、分かりました。」
ミンジェは4才もサバを読むことになってしまった。
「これは誓約書だよ。」
お爺さんは誓約書を出した。
普通の誓約書と同じだ。
ただ、球団に無関係者を連れて来ないとかは書かれていた。
あとは、秘密をもらさないとかだ。
「あの、弟が練習を見たいと言っていて。」
「いいよ。事前に教えて、そう言う事は。」
「わかりました。僕、彼女はいません。」
「そうか。」
「はい。週刊誌に嘘を書かれたらどうしましょう?」
「週刊誌に書かれるような事はしたらダメだぞ。でもな、うちにもスポンサーがちゃんとついているので、大丈夫です。」
ミンジェはうなずいた。
「また遊んでよ。」
ビナは家の前で、ミンジェの腕をつかんで言った。
ミンジェは少し変わってしまった。
冷たい目で言ってしまった。
「ごめん。今は練習があるから。」
「はぁ?」
ビナはでかい声を出した。
「お前、なんでそんなに変わっちゃったんだよぉ!」
「ちがうって。今はって言ったでしょ。」
「きもい。」
「ビナにもそういう日が、ちゃんと来るから。」
ミンジェが言うと、お母さんが家から出てきた。
「ミンジェ、ビナちゃんにあまりキツイ事を言うのやめてあげて。」
「母さん。」
「ビナちゃんはね、病院で受けたテストで、子供を作るための遺伝子がない事が判明したばかりなの。」
「はぁ?病院でのテストって何?」
ミンジェは大声を出した。
ビナは涙を拭きながら、言った。
「病院で検査をうけて、僕に精子がないことが判明したんだ。」
「ええ。」
ミンジェは後退りした。
「仕方ないじゃんか!!」
ビナは大声を出した。
「もうお互いにして。こんな意味がないことは辞めてちょうだい。」
お母さんは泣いた。
夜。2人は仲直りの証に、ウルソンさんと言ったファミレスに行く事にした。
アメリカ。
休日、ランニングと朝食を終えたジェレミーは、アパートの部屋のドアの前で、ため息をついた。
アレクシスが引っ越しの準備をしている。
ニコアや弟、両親が来て、手伝っていた。
「1人で充分なのにな。」
アレクシスは段ボールを持って、ニヤリと笑った。
ジェレミーは家に入り、涙をぬぐった。
ポストに入っていた封筒を見る。
「なにかな‥。」
夜、2人はマクドナルドで夕食をとることにした。
「ようやく片付いたよ。」
アレクシスは言った。
「そうか。これでようやく、NBAに行けるね‥。」
「離れ離れになるけど、ジェレミーとはずっと友達でいたいと思ってる。」
「うん‥。」
「どうした?元気がないぞ。」
「実は‥、クロスワードパズルの抽選で、韓国ペア旅行が当たったんだ。
よければ一緒に行かないか?」
「ええ?いいのか?!」
「うん。君と一緒に行きたいんだ。」
アメリカの国際空港。
ついに2人は飛行機のエコノミークラスに乗り込んだ。
「ハハハ、本物の飛行機だぜ。」
アレクシスは笑った。
「飛行機は初めてかい?」
「二度目さ。でもよかった。代表に入ったら、海外にも行くことになる。
あまり騒ぎ立てたら、まわりに迷惑になるだろう?旅行するために、バスケをするわけじゃない。」
「でも、感動するぜ。」
アレクシスはヘッドホンをつけたり、椅子を倒したりして楽しんだ。
ジェレミーは言った。
「窓際の席じゃなくて残念だ。」
「でもいい席だよ。目の前に、こんなに大きなモニターがある。」
飛行機は離陸した。
アレクシスは怖そうだったが、楽しんでいた。
アレクシスは言った。
「ああ、このモニターで、飛行機がどこにいるか分かるわけだ。」
「そうだね。」
アレクシスはアイマスクをして、音楽を聴き、家族のことを思い出した。
「NBAから、誘いがあった。ついにプロになる。」
みんなに打ち明けた時の、喜んだ顔は忘れられない。
父親は聞いた。
「誘われたのは、お前だけか?」
「いや、友人のカイルも一緒だ。俺が頼んだ。仲間も喜んでくれたよ。」
家族は少しだけ目を合わした。
「ニコア、君に待っていてくれとは言わない。でも‥ずっと、君は俺の支えだ。」
「ええ‥。」
ニコアは胸に手を当てた。
「お兄ちゃん、それってプロポーズ?」
「言っとくけど、ニコアは従姉なのよ。」
「別にプロポーズじゃない。でも、ニコアは俺にとって大切な人だということを、伝えたかっただけだよ。」
アレクシスは言った。
「ありがとう、嬉しいわ。」
ニコアはアレクシスに抱きついた。
機内食を食べながら、ジェレミーは聞いた。
「意外と悪くない。」
「そうだな。ジャムをもう少しつけてくれれば‥。」
「甘い物が欲しければ、リンゴジュースを頼めば?」
2人はしばらくの間、エコノミーの機内食を食べ、その後は寝ることにした。
窓際の席でなかったことは良い事もある。
外に気がいかないので、よく休む事ができる。
韓国についた2人はひと通りの手続きを済ませ、タクシーでロッテホテルに向かい、
ホテルのツインに荷物を置いて、街に繰り出した。
「すごいな‥。とてもお洒落だ。」
NBA選手になるアレクシスは、まだ有名ではないが、笑顔を心がけることにした。
2人はサムスン美術館に行き、いろいろな所を見て回った。
夜は、韓国のおばちゃんが教えてくれた食堂で食べることにした。
韓国はそこまで値段も高くないし、騙されることもあまりなかったのでよかった。
ミンジェは素振りをしていた。
素振りが撮られることには抵抗があったが、今はもう慣れた。
ビナは勝手に見に来たが、ミンジェの実の弟だと気づいた球団のお爺さんが入れてくれた。
この後、試合がある。
ベンチへと向かう廊下でビナは待つことにした。
お爺さんは聞いた。
「おい、控えまで、会いに行くか?」
「いい。僕、ここで待ちたい。」
「そうか。」
お爺さんはあきらめた感じだ。
いよいよ選手たちが来た。
ビナは自信に満ちた表情で、ミンジェを待った。
ミンジェは真剣な顔で歩き、ビナの顔をちらりと見たが行ってしまった。
最後の選手は、ちらりと振り返ってビナを見て、何か言った。
そして、ミンジェが小走りで来て、ビナの前髪をつかんで言った。
「お前なんで来たんだよ。」
「やめてよ!会いにきてあげたんじゃん。」
「勝手に来るなって言っただろう。メイちゃんか?お前は。」
「来てほしいって言ったから、来てあげたんじゃないか。」
「来てほしいだなんて、誰も言ってない。」
ミンジェはベンチに戻ってしまった。
「うう‥。」
ビナは泣き、知り合いの選手が来て、ビナをなぐさめた。
試合が終わり、選手が帰る時間まで、ビナは待っていた。
気のいい先輩選手が、ミンジェに声をかけた。
「あのチビ、まだいるぞ。」
「ああ‥。」
「ビナ、待っていてくれたんだね。」
ミンジェが言うと、ビナはうなずいた。
「わかった、一緒に帰ろう。どこか寄って、何か食べようか?」
ミンジェは作り笑いをすると、ビナも元気になって笑った。
次の日、野球の仕事に行くため、ミンジェは歩いた。
ビナを家に泊めたせいで、少しペースが乱された。
ビナはポエマーで、夜には変な事を言いだすので、困っている。
2人の白人と黒人が、道に迷っている。
英語を勉強しているので、話しかけてみることにした。
どうせ相手は観光客だし、二度と会うことはない。
「どうかしましたか?」
「ありがとう、○○に行きたいんだけど、わからなくて。」
「それなら、こうですよ。」
ミンジェは英語で説明をし、ニッコリと笑った。
「あれ、野球選手のウ・ミンジェさんですか?」
ジェレミーは聞いた。
「はい。なぜ‥?」
「韓国について、調べたんです。あなたはとても有名だ。」
「ありがとうございます。」
「今度、アレクシスも、NBAにいくんですよ。」
「そうでしたか。頑張ってください。」
「ありがとう。君も頑張ってくれ。」
3人はお別れした。
有名になると、いちいち連絡先を交換せずにすむので、ありがたい。
アフリカ。バルトは、ブラハムとメリエムと共にカフェにいた。
「今日は首都までわざわざ来てくれてありがとう。ここは俺のおごりだ。なんでも好きな物を注文してくれ。」
3人は、料理を注文し、食べた。
最後に、アイスティーが運ばれてきた。
「だけど、なぜ来たんだい?」
バルトは聞き、ブラハムが答えた。
「バルト。メリエムが金に困っている。少し貸してくれ。」
「嘘だろう?メリエム、お前が脱毛をしてしまった男のことか?」
メリエムは泣きながらうなずいた。
「ああ、そんな‥。」
バルトは目頭をおさえ、ブラハムも渋い顔をした。
「一体いくらなんだい?」
「100万円。」
メリエムは答えた。
「ええ!そんなにか!」
バルトは立ち上がって、大きな声を出した。
「あのな、俺はスポーツ選手だぞ!セレブじゃない!だから、そんな大金を渡せるはずがないんだ。」
ブラハムは言った。
「頼む、バルト。なんとか金を出してくれ。」
「断る。アフリカには飢餓で苦しむ子供がたくさんいるのに、そんなお金を出せるわけない。」
メリエムは泣いている。
ブラハムも大きなため息をついて、うなだれてしまった。
カフェの客たちもちらちらとこちらを見た。
バルトが大金持ちだということは分かっていた。
「仕方ない。お金を出そう。ただ、お金を出すのはもうしたくない。いいな?」
「はい。分かりました、バルトさん。ありがとうございます。」
メリエムは涙目で言い、
「バルトさん、ありがとうございます。」
ブラハムも続けて言った。
カフェから出て、ブラハムは言った。
「よければ君の、靴をなめようか?」
「やめてくれ!そんなことはしてほしくない。」
バルトは笑った。
カイルの恋人、イーデンは迷っていた。
カイルはたまに怯えていて、小心者の時がある。でも、離れたくはなかった。
ちょうど、アレクシスからNBAに誘われたので、お別れの機会ができた。
「引っ越すことになる。」
カイルはイーデンを抱きしめた。
「ええ。私も、実家に戻るわ。」
「この家は‥思い出だらけだ。」
イーデンはカイルから離れた。
「悲しいけど、売る事にしましょう。」
「そうだな。」
引っ越しの朝、カイルはイーデンに声をかけた。
「最後にコーヒーを飲まないか?」
「だけど‥。」
「僕の荷物から出してきた。」
カイルはヤカンとマグカップを見せた。
2人は置いて行くテーブルと椅子に座って、コーヒーを飲んだ。
この静けさは、2人が大人になったという証だろう。
カイルの叔父が来て、荷物を車に乗せた。
カイルは言った。
「必ずまた会おう。」
「ええ。」
「イーデンと別れたくはない。」
「私もよ。」
2人はハグし、カイルはイーデンの頭をなでた。
カイルは行ってしまい、イーデンは家の前で座って少しぼんやりした。
韓国、ソウル。
新聞はミンジェのメジャーリーグ進出を知らせた。
それはアメリカでも、ニュースで報道され、アレクシスとジェレミーもそれぞれミンジェの姿を確認し、にやりと笑った。
「行ってくる。」
報道陣の前で、ミンジェはビナと握手を交わした。
ウルソンさんは、ミンジェを相手にしないと思ったが、心配してくれたので、ミンジェは嬉しかった。
ミンジェは礼儀正しくするように心がけた。アメリカでの一番の頼りは、ウルソンさんなのだ。
2人きりで食事をした時は、なんとなく、スターになった気がして、ミンジェは食べた後、紙でよく口を拭いた。
ミンジェはメジャーリーグでも素振りをした。
ファンが見に来ている。その中に、見覚えがある黒人と白人がいたので、ミンジェは駆け寄った。
「あの‥、前にソウルでお会いしましたよね?」
「うん。アレクシスとジェレミーだ。」
「ああ、すみません。忘れてしまっていて‥。」
「いいんだ。実は頼みがある。」
アレクシスは言った。
「何ですか?」
「君の試合のチケットをくれ。」
ジェレミーは答えた。
「でも、僕、持っていなくて。」
「これと交換しよう。」
アレクシスは、NBAの試合のチケットを2枚くれた。
「ああ‥。ちょっと待っていてください、すみません。」
ミンジェは走って、小太りの黒人コーチにかけよって、何か話した。
コーチはNBAのチケットを見て、中でスタッフと話し、チケットを2枚持ってきてくれた。
ミンジェがまた戻ると、2人は消えていたが、すぐに戻ってきた。
「どうだった?」
アレクシスは聞いた。
「チケット2枚もらえました。はい。」
ミンジェがヒアユーアーと言うと、アレクシスは少し笑った。
「ありがとう。」
「どういたしまして。」
2人はニヤニヤとした。
「またな。」
「さよなら。」
ついに、2人は吹き出してしまった。
コーチはチケットを1枚、ミンジェに渡そうとした。
「いいんですか?」
コーチは2枚ほしいか、確認した。
「いいえ、僕、1枚で結構です。」
ミンジェが言うと、コーチは神妙な顔でミンジェを見た。
このコーチは、アメリカ人選手の前では結構笑うのに、ミンジェの前だと、表情が硬いままだ。ミンジェはそういうのが原因で、暗くなってしまう。
あとは、韓国の家族からメールが一通もない日は、悲しくなる。
ビナは病気だから仕方ないけど、親が僕を見捨てるなんて、酷すぎる。
家はマンションみたいな感じだ。
同僚が同じ階にいる。
昔はおばさんと同じアパートにも住んでいた。
でも、自分を嫌いな人と一緒に住むのは苦痛だ‥。
部屋は少し広いが、荷物を置きたいので便利だ。
野球選手だがバスケットゴールを置いてみた。
前に同僚の部屋を見たら、いろいろと改造してあったので、いいと思った。
こんなにお金がもらえると思っていなかったし、遊びやプレステにくらい贅沢してもいいだろう。
時々、幻覚が見えてしまう。
一人ではでかすぎる冷蔵庫の隅に、ネズミが置かれていると思って二度見した。
よく見たら、自分がいれておいたタオルだ。
『この色のタオルは買わない方がいいかもしれない‥。』
日用品で、特別欲しい物なんてなかったのに、同僚がホームセンターに連れて行った。
いろいろとカゴに入れられて、大変だった。
あとは、大きなデスクトップパソコンも買った。
ソリティアをしているだけなのに、仕事をしている気分になってくる。
『これは仕事じゃないのに。』
ミンジェはPCメガネをかけ、ソリティアをよくやっている。
マンションには、乾燥機がある。
この前行ったら、いっぱいで、女性用のブラジャーがあったので、やっぱりベランダに干すことにした。
ベッドはキングサイズで、部屋が広すぎるので散らかしても、綺麗に見える。
起きる時は、ジリリと鳴る目覚まし時計だ。
昔、ビナにもらった物とよく似ている。あれは、喧嘩をした時に捨ててしまった。
アラームが鳴ったとたん、布団を蹴飛ばして、起きるのがほとんどだ。
一度、ビナがベッドの目の前に腕組みして立っていた気がして、二度寝してしまった。
夜はよく泣いてしまう。
一番の気がかりは、ソナさんの部屋がどんな部屋か、見なかったことだ。
『ソナさん‥。』
『俺のメールや通信は全て見られていることを知っている。
だから、グラビアも見ることは出来ない。』
『見られているのは、いつからの物だろう?
俺だって、変な子と付き合った事もあるし、ソナさんとのやり取りもあるから、見られたくない内容だってある。』
『大体、何が楽しいの?』
「まぁ、調べたいのは当然だよな。俺は〇億円もいただいている。」
鳩の壁掛け時計が鳴ったので後ろを見た。
これは、昔の友達からの贈り物だ。
「あ、そうだ。」
財布にいれておいたチケットを見た。
財布はルイヴィトンを使っている。
「えっ。」
Googleで、NBAの試合会場を検索した。
前に、Google社から、本社を見学に来ないかと誘われたが、まだ行っていない。
もしもGoogleで働くことになったら、困るからだ。
とりあえず、英語が分からないという顔をしておいた。
「飛行機になるのかな‥。えー、だったら‥無理なんだけど。」
「ほっ。」
検索結果が出て、会場まではバスや電車を使って、3時間くらいで行ける。
「でも、この日‥。」
スケジュールを確認した。
スケジュール表を落としたり、外部に見せたりして、停職になった選手がいるので、
全て手帳に記入している。
大事な物は全て金庫だ。
パスポートも‥。
手帳を確認して、この日は空いていることが判明した。
「どうしよう‥、一人で長旅なんて。」
アフリカ。
バルトは子供達とレースすることになった。
子供達は先に走り出し、バルトが後から追いかける。
カメラマンが2名ほどいて、写真を撮った。
バルトは最初の方は手加減していたが、最後に本気を見せてやろうと思った。
最後は立候補した男の子と一騎打ちをすることになった。
男の子は走り出す。
バルトは本気になった。
バルトは男の子を追い抜き、男の子は転んでしまった。
男の子は風で起きられない。
バルトは走り終わると、両手をあげた。
「あれ?」
ふりむくと、男の子の下には、みんなが駆け寄っていた。
アメリカ。
アレクシスとカイルが所属するNBAチームでは、練習が行われていた。
コーチのキムは、アレクシスはもう年だからと不安に思ったが、そんなことはなかった。
充分に若いし、手足が長く、動きに固さがなかった。
「キムコーチ。」
「タリスタン。東京への準備はバッチリか?」
「はい。日本には友達がいるので、絶対に出場したいです。」
「努力を続けろ。東京で彼にきっと会える。」
「はい、分かりました。」
タリスタンはベテランの黒人選手だ。
タリスタンは、日本人で初めてNBA選手になった山田純太郎を思い出した。
「ハイ!!」
山田は、NBAの練習中も大きな声を出して、パスを受け取った。
黒人選手は何も言わない。
目で合図をする。あまり、声を出してはいけないし、みんなクールに見せたい。
タリスタンは山田にそのことを伝えてみると、山田は言った。
「だって、そうじゃなきゃ、分からないじゃんよぉ!」
「ああ‥。でも、試合中は話せない。」
「えっ‥。」
「まずいだろ?どこにパスをまわすか、敵にバレたら。」
「オー、アイシー。」
山田は言い、タリスタンは笑った。
「あんた、名前は?」
「ああ、僕は、タリスタンだよ。」
「タリズタン。」
山田はメモした。
山田は初めての試合で、なかなかパスを回してもらえなかった。
山田はチームとうまくいっていないと言ったが、まだ仲良くなれていなかった。
山田はあちこちと動き回った。
山田のような人種と出会うのは初めてなので、よく分からなかった。
山田にようやくパスがいき、山田は3ポイントを狙ったが、外した。
山田はコートで泣いた。
コートで泣くなと、何度後輩に言ったか分からないのに、泣いてしまった。
最後にコーチがなんと言ったかわからないが、労いの言葉をかけ、チームメイトは山田を見た。
コーチは山田について何かを話し、チームメイトたちは、握手を求めてきたので、
山田はまた泣いた。
山田は、親友に泣きながら、国際電話をした。
「だけどさ、会ってから10日しかたっていないのに、試合に出されたんだぜ。」
「ああ‥。でも、山田君さ、行ってから1カ月くらいたつんじゃない?」
「でも、生活に慣れるのに精一杯だったから。」
「そうか。そうだ、国際電話は高いから、切るね。」
「だって、そっち持ちだろ?」
「でも、俺もそんなには金ないからさ。」
「わかった。」
山田はしぶしぶ電話を切り、また泣いた。
「おい、何か作ってくれよぉ!俺は腹が減っちゃったんだから。」
「あれぇ?誰もいない。」
山田は、アメリカの食事に慣れてきた。
でも、バイキングで料理を選んでいると、まだ夢を見ている気分になる。
プルルル
山田は唇でその音を出した。
黒人はじろりとこちらを見て、ニヤリと笑ってくる。
山田は持ち前の根性で、NBAの速さに慣れた。
山田はゾーンに入ると、一人一人がしっかりと見えなくなる。
自分だけがしっかりとした人間で、まわりがみんな影のような感覚に陥る。
「山田、大丈夫か。」
「山田、そんなんでシュートできるか。」
「山田、お願いだ、他の者にパスを回してくれ。」
山田はつぶやいた。
「大丈夫。みんな影だから。」
山田はシュートした。
山田は誰にパスをまわすかは、輪郭で決める。
よく見えている仲間の輪郭で判断する。
山田は栄光をつかんだ試合の後でも、ベッドで涙した。
「はー、ゲームしたいよ。」
山田は涙をぬぐった。
山田は、中学の同級生が作ってくれた寄せ書きや写真を見て、
「こんな物、いらねっ!!」
山田はそれを投げ捨てた。
ぼんやりとした物ではあったが、山田には戦争に行っていたという記憶があった。
その記憶だけを頼りに、ここまで強くなった。
高校時代に仲良くバスケをしてあげた長身も、そこまでは強くなっていない。
山田が強くなれたのは、みんな運だと言う。
「運なわけねぇだろうがぁ!!」
山田は部屋で、一人でよく怒鳴っていたので、隣の部屋の黒人から、壁を叩かれた。
一度、黒人も怒っていたが、それきりだ。いや、その三日後にも怒鳴っていた。
今日の試合はこちらが負けて、終了した。
今日は少ししか出番がなかったが、大丈夫かな‥。
まぁいいか。日本に戻ることになっても、きっと居場所はある。
結構楽しいし、どこも近いし、自分の身の丈に合っていると思う。
「タリズタン、俺、荷物持とうか?」
「いいよ、大丈夫。」
ついに、日本代表が、アメリカに来ることになる。
山田はタリスタンに言った。
「日本、超強いんだけど、大丈夫かな‥。」
「強いっ?ワオ!」
「あっ、ごめん、間違えた。結構強いだった。」
「ええ?本当?」
「これはマジ。ちょっと手加減してくんない?」
「うーん。それは無理だな。」
タリスタンは首をかしげた。
「みんな、今までありがとうね。」
NBAを去る日、山田は、仲間に漢字ドリルを配った。
「全然、いられなかった、けど。」
山田は涙をぬぐった。
「タリズタン、大好きだよ。」
山田はタリスタンに抱きつき、頬にキスをしたので、タリスタンは顔をしかめた。
アフリカ。
バルトは、フルマラソンに出る事になってしまった。
これにはアマチュアランナーも出られるので、ブラハムも出る。
顔をこわばらせているスタート前のブラハムに、バルトは話しかけた。
「緊張する?」
「うん。そうだな。」
「大丈夫だ。俺もマラソンじゃ素人同然だから。」
「ああ。」
ブラハムは少しでも良いタイムを残したかった。
いい男になりたかったし、これからもバルトと仲良くするためだ。
「もっと前の方に行く?」
バルトは聞いた。
「いや、俺はここで。」
「そうかい。俺はちょっと、行ってもいいかな。」
バルトは前を指した。
「いいぞ。」
ブラハムは、前や後ろは関係ないと思った。
パン
みんな一斉に走り出した。
これはプロの試合じゃないので、ふざけて転ぶヤツもいる。
バルトはいつもの調子で走ったので、一番前の組に入ってしまった。
でも、だんだんと遅れていく‥。
バルトは本当に胸が苦しくなってしまった。
スタッフのテントの近くで立ち止まり、手を上げ、棄権した。
スタッフ達は、これが誰か最初分からなかったが、女性がテントに入れてくれた。
「大丈夫?あなた、名前は?」
「バルトです。」
女性は息を飲んだ。
「バルトさん、どうかされましたか?」
女性は口調を変えた。
「いえ、何も。急に胸が苦しくなったものですから。」
「すぐに、お医者様を呼びますからねぇ。」
女性はにこやかに言った。
ブラハムが遅れて通りすぎた時、テントの中で診察を受けるバルトと目が合って、ブラハムはガン見してしまった。
ミンジェは一泊二日でNBAの試合を見に行くことにした。
バスに乗る。
一応、Googleで調べたことを、メモをしてきた。
『元気?』
ビナからメールが届いている。
『これから旅行だよ(^^)』
『お友達と?うらやましい((>_
ワンクリックで応援できます。
(ログインが必要です)
(ログインが必要です)