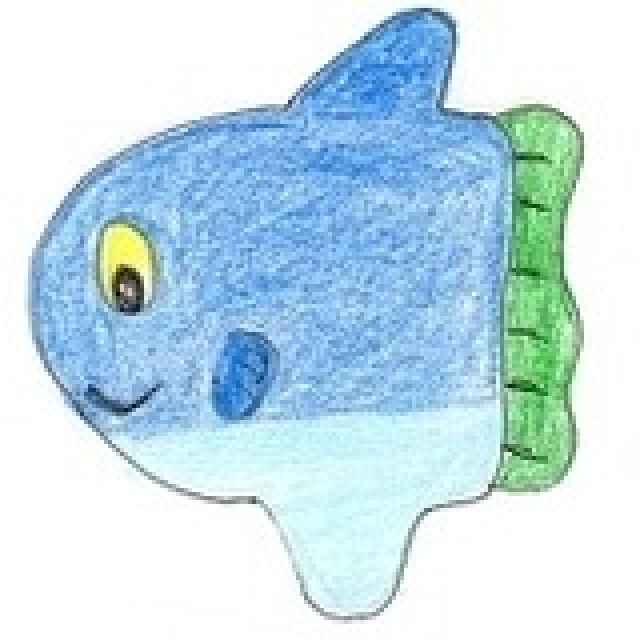第15話 幻の噺家 1
文字数 3,940文字
春という季節は良いものだとこの歳になって気がついた。
薫のお腹の子供は順調に育って俺たち夫婦に楽しみを与えてくれていた。五月は両協会とも真打披露の興行があるのだが、今年は噺家協会が三月に披露興行をやってしまったので、GW明けの時期に噺家芸術協会だけが真打披露を行っていた。
一門に昇進者がいる柳生も芝居に出ていたが、今や彼は協会でも抜きんでた人気者となっており、師匠ともども忙しくしていた。
俺も春の芸人年鑑の仕事が終わり一息入れていたことろだった。のんびりと編集部でしていたら、盛喬が顔色を変えてやってきた。見ると手にはこの前ウチが出した芸人年鑑を手にしている。
「どうしたんだ? 顔色を変えて……」
息を弾ませている盛喬は、やっとのことで俺に向かって
「神山さん。この年鑑なんですが……」
およそ出版関係者なら聞きたくないことを言った。
「いや、ちゃんと協会の事務方に見て監修して貰ったぞ。その上で出したんだ。印刷ミスも今回は無かったはずだしな」
俺の答えが余りにもちゃんとしていたのと、自分の言葉が足らなかったのを理解した盛喬は
「ああ、そうじゃないんです。記録的にはちゃんとしてるんですが、協会に加盟していても噺家として活動してない人も載ってるんです」
盛喬の言う事は編集部でも確認していたことで、協会の事務方の言うことでも「そのまま載せて構わない」という事だったのだ。
「確認ずみだぞ」
短く答えると盛喬は
「いや、また言葉が足りませんでした。今まではあの人に仕事を頼むなんてことが無かったので問題が起きなかったんです。それが、あの年鑑を見た師匠の古い贔屓が、この次の師匠の独演会にどうか? って言ってきたんですよ。正直困りますよね。もう何年も高座に上がってないと思いますから……」
やっと普通に話せるようになった盛喬に椅子を進めて
「確か、圓盛師匠の兄弟子だったよな? 俺も高座を見たのは学生の頃だったな……あれから何年だ?」
盛喬は俺の言葉を待っていたように
「十年じゃ利かないですよね?」
おどけて言うので俺も悪のりして
「ついこの前だ」
そう言ったら編集部の皆があきれて笑った。
「圓海師匠のことだろう? 生きてはいるんだよな。年鑑に載せてしまったからな」
「ええ、達者です。但し、つい最近まで長く病気で臥せってらしたんです。そんな状態で独演会のゲストになんて無理だと言ったんです。でも贔屓が『訊いてみるだけでもいいい。何なら顔だけでも見たい』って言うんですよ。それで師匠も困ってしまって……」
「で、年鑑を作った俺に責任を取れと乗り込んで来た訳か?」
「そういう訳じゃないですけど、相談には乗って貰おうかと思いまして」
大体のところは理解できた。要するに俺に圓海師匠との交渉役になって欲しいということだと判った。
だが、俺だって圓海師匠とは面会したことも無ければ、話を伺ったことも無い。
「だから、私について来てください。それだけでいいんです」
全く、こういうところは盛喬はちゃっかりしている。
「師匠の家は判ってるのか?」
俺は盛喬に確認をして、青いアルファに盛喬を載せると編集部のあるビルを後にした。
アルファの助手席の盛喬に一番大事なことを尋ねる
「圓盛師匠は自分の独演会に兄弟子でもある圓海師匠が出てくれる事を望んでいるんだろうな?」
それが一番大事だと思う。師匠がそんな事露とも思っていなかったら、こんな行動は余計なお節介になるのだから。
「それは大丈夫です。師匠も『アニさんに一度は出て欲しかったんだ』と言っていましたから。それに師匠が望まない事を惣領の自分がする訳無いじゃありませんか」
確かにそうなのだが、こいつの事を百%信用していない自分が居るのに気がついた。全くおかしなモノだと苦笑してしまった。
圓海師の自宅は東京の東の端とも言うべき江戸川沿いにあった。江戸川の土手の道から師匠の家の二階の窓が見える。脇を通る時に盛喬が指を指して教えてくれた。
ここに来る途中で師匠の好きな吾妻橋のたもとの店で佃煮を買って来ていた。
「この店の佃煮が好きだって師匠が言ってましたから」
まあ、正直、そんなものだけで話が上手く運ぶとは思えないが、何も無いよりは遥かにマシだと俺も思った。
土手沿いの道を離れて路地に入り車を駐める。やや古風とも思える佇まいを持った昭和の家がそこに立っていた。盛喬が佃煮の折を手に玄関の引き戸の脇の呼び鈴を押す。やや間があって中から「どなたですかな?」記憶の彼方から覚えのある声がした。
「師匠、圓盛の一番弟子の盛喬と申します。本日はお話がありまして参上致しました」
先ほど車の中で盛喬に圓海師匠に会ったことあるのかと尋ねたら二三度あると語っていた。圓海師匠が覚えておいてくれれば良いと思った。
「圓盛のところの……ああ、思い出した。今開けるから」
引き戸が開かれると俺の記憶よりも小柄な老人が立っていた。温かい日だというのに綿入れみたいなのを羽織っていた。それなのに素足と言ったところが妙におかしかった。
「圓海師匠お久しぶりでございます。これはご挨拶代わりでございます、どうぞお納め下さい」
盛喬の差し出した折を見て僅かに目を細めて
「ま、そこの人も一緒に上がんなさい。茶でも出そう」
そう言って手招きをした。そして、
「そこの人は『よみうり版』の記者さんじゃろ。色々なパーティーで見た顔だ。盛喬の付き添いで来たのかい。ご苦労さまなこった」
正直驚いた。外見からするに少々ボケでも入ってるのか? と思わせられたが、とんでも無かった。しっかりしてる。これなら期待出来そうだと腹の中で考えた。
六畳の茶の間には昔ながらの長火鉢が置いてあった。この季節だというのに炭が熾きていた。
「歳取ると寒がりになるものでな。梅雨になるまではこいつは放せんよ」
そう言って灰をかき回した。掛かっていた薬缶から急須に湯を注ぎお茶を入れてくれた。
「なんせ婆さんに先立たれてからは不自由しててのう」
僅かに笑ったのは照れ隠しだと感じた。
「それで、ワシに何の用だね。まさか噺の用ではあるまいな」
言葉とは裏腹にその目は死んでは無いと感じた。
「圓海師匠、師匠圓盛の独演会にどうか出演して戴けませんか? 師匠も一度一緒に出たいと常々語っていたのです。圓海師匠のご病気が良くなったとお聞きしてそれならと伺いました」
盛喬も噺家ならもう少し粋な言い方があるだろうと思ったが、それだけ緊張しているのだと思い直した。
圓海師匠は自分で入れたお茶を一口飲むと息を吐いてから
「ワシで良かったら何時でも出る。幸い病も心配無くなった。だが、ワシの事を知ってるお客が居るかな。それでお客が集まるかい」
「それは大丈夫です。ここにいる神山さんが『よみうり版』で紹介してくれますから」
圓海師匠は俺をひと睨みすると
「まあ、その点では大丈夫だとは思うが、せいぜい宣伝してください」
そう言ってから盛喬に振り向き
「圓盛にも良いように言っておいておくれ」
そう言って答えた表情に先ほどとは打って変わって生気がみなぎって来たのを感じた。
その後、圓海師匠から演題の注文で「青菜」がやりたいと言って来たので、それに合わせて調整をすることになった。
出演者は、圓海師匠のゲストに開口一番が盛喬だ。真打を開口一番に使うとは贅沢な独演会だと思った。圓盛師匠の演目は「転宅」と「唐茄子屋政談」となった。
盛喬は「あくび指南」を演じるという。これらをプログラム的に記すと
開口一番 三遊亭盛喬 「あくび指南」
三遊亭圓盛 「転宅」
三遊亭圓海 「青菜」
仲入り
兄弟弟子対談 圓海、圓盛、司会盛喬
トリ 三遊亭圓盛 「唐茄子屋政談」
とこんな感じになる。場所は都内の落語が良く開かれている某ホールを押さえた。大体500人前後を収容出来るホールだが、そこに400人ほど入れる。満員にしないのは師匠圓盛師の方針だそうだ。満員よりも若干余裕がある方が演じやすいそうだ。
兎に角公演の日まで時間がないので、「よみうり版」にも差し替えで独演会に圓海師が出演する記事を入れて月末の発売に間に合わせたのだった。
幻と言われた噺家、三遊亭圓海師が高座に上がるという事が落語ファンの間で結構な話題になり。前売りが始まると結構な売れ行きを示した。
独演会の準備が一息ついて、後は当日を待つばかりとなった。俺はこの頃仕事をセーブして家に居ることが多くなった薫と色々な事を話していた。
「圓海師匠って、わたしは聴いたこと無いけど、どんな噺をするの?」
薫の疑問は尤もだ。噺家として恐らく一番大事な時期に病を患ってしまい、棒に振ってしまった。俺が何度か聴いたのは病を患い始めた頃で、その前よりも精彩が無かったことを思い出した。
「そうだな、圓盛師が人の心に入り込むような高座だとすると当時の圓海師は噺全体でお客を包み込んでしまう感じだった。小手先の話芸では無い感じだったな。器用さで言えば圓盛師の方が上だな」
俺のそんな感想を聴いて薫は当日自分も連れて行って欲しいとねだった。無論駄目なはずが無いので了解する。
「その二人の師匠の違いを肌で感じて自分に活かせればいいなと思ってるの。わたしも、もうヒロインなんかは来ないだろうし、演技で採用される役者にならないとね」
そんなことを言って俺にしなだれかかって来た。それを優しく抱きめた……
薫のお腹の子供は順調に育って俺たち夫婦に楽しみを与えてくれていた。五月は両協会とも真打披露の興行があるのだが、今年は噺家協会が三月に披露興行をやってしまったので、GW明けの時期に噺家芸術協会だけが真打披露を行っていた。
一門に昇進者がいる柳生も芝居に出ていたが、今や彼は協会でも抜きんでた人気者となっており、師匠ともども忙しくしていた。
俺も春の芸人年鑑の仕事が終わり一息入れていたことろだった。のんびりと編集部でしていたら、盛喬が顔色を変えてやってきた。見ると手にはこの前ウチが出した芸人年鑑を手にしている。
「どうしたんだ? 顔色を変えて……」
息を弾ませている盛喬は、やっとのことで俺に向かって
「神山さん。この年鑑なんですが……」
およそ出版関係者なら聞きたくないことを言った。
「いや、ちゃんと協会の事務方に見て監修して貰ったぞ。その上で出したんだ。印刷ミスも今回は無かったはずだしな」
俺の答えが余りにもちゃんとしていたのと、自分の言葉が足らなかったのを理解した盛喬は
「ああ、そうじゃないんです。記録的にはちゃんとしてるんですが、協会に加盟していても噺家として活動してない人も載ってるんです」
盛喬の言う事は編集部でも確認していたことで、協会の事務方の言うことでも「そのまま載せて構わない」という事だったのだ。
「確認ずみだぞ」
短く答えると盛喬は
「いや、また言葉が足りませんでした。今まではあの人に仕事を頼むなんてことが無かったので問題が起きなかったんです。それが、あの年鑑を見た師匠の古い贔屓が、この次の師匠の独演会にどうか? って言ってきたんですよ。正直困りますよね。もう何年も高座に上がってないと思いますから……」
やっと普通に話せるようになった盛喬に椅子を進めて
「確か、圓盛師匠の兄弟子だったよな? 俺も高座を見たのは学生の頃だったな……あれから何年だ?」
盛喬は俺の言葉を待っていたように
「十年じゃ利かないですよね?」
おどけて言うので俺も悪のりして
「ついこの前だ」
そう言ったら編集部の皆があきれて笑った。
「圓海師匠のことだろう? 生きてはいるんだよな。年鑑に載せてしまったからな」
「ええ、達者です。但し、つい最近まで長く病気で臥せってらしたんです。そんな状態で独演会のゲストになんて無理だと言ったんです。でも贔屓が『訊いてみるだけでもいいい。何なら顔だけでも見たい』って言うんですよ。それで師匠も困ってしまって……」
「で、年鑑を作った俺に責任を取れと乗り込んで来た訳か?」
「そういう訳じゃないですけど、相談には乗って貰おうかと思いまして」
大体のところは理解できた。要するに俺に圓海師匠との交渉役になって欲しいということだと判った。
だが、俺だって圓海師匠とは面会したことも無ければ、話を伺ったことも無い。
「だから、私について来てください。それだけでいいんです」
全く、こういうところは盛喬はちゃっかりしている。
「師匠の家は判ってるのか?」
俺は盛喬に確認をして、青いアルファに盛喬を載せると編集部のあるビルを後にした。
アルファの助手席の盛喬に一番大事なことを尋ねる
「圓盛師匠は自分の独演会に兄弟子でもある圓海師匠が出てくれる事を望んでいるんだろうな?」
それが一番大事だと思う。師匠がそんな事露とも思っていなかったら、こんな行動は余計なお節介になるのだから。
「それは大丈夫です。師匠も『アニさんに一度は出て欲しかったんだ』と言っていましたから。それに師匠が望まない事を惣領の自分がする訳無いじゃありませんか」
確かにそうなのだが、こいつの事を百%信用していない自分が居るのに気がついた。全くおかしなモノだと苦笑してしまった。
圓海師の自宅は東京の東の端とも言うべき江戸川沿いにあった。江戸川の土手の道から師匠の家の二階の窓が見える。脇を通る時に盛喬が指を指して教えてくれた。
ここに来る途中で師匠の好きな吾妻橋のたもとの店で佃煮を買って来ていた。
「この店の佃煮が好きだって師匠が言ってましたから」
まあ、正直、そんなものだけで話が上手く運ぶとは思えないが、何も無いよりは遥かにマシだと俺も思った。
土手沿いの道を離れて路地に入り車を駐める。やや古風とも思える佇まいを持った昭和の家がそこに立っていた。盛喬が佃煮の折を手に玄関の引き戸の脇の呼び鈴を押す。やや間があって中から「どなたですかな?」記憶の彼方から覚えのある声がした。
「師匠、圓盛の一番弟子の盛喬と申します。本日はお話がありまして参上致しました」
先ほど車の中で盛喬に圓海師匠に会ったことあるのかと尋ねたら二三度あると語っていた。圓海師匠が覚えておいてくれれば良いと思った。
「圓盛のところの……ああ、思い出した。今開けるから」
引き戸が開かれると俺の記憶よりも小柄な老人が立っていた。温かい日だというのに綿入れみたいなのを羽織っていた。それなのに素足と言ったところが妙におかしかった。
「圓海師匠お久しぶりでございます。これはご挨拶代わりでございます、どうぞお納め下さい」
盛喬の差し出した折を見て僅かに目を細めて
「ま、そこの人も一緒に上がんなさい。茶でも出そう」
そう言って手招きをした。そして、
「そこの人は『よみうり版』の記者さんじゃろ。色々なパーティーで見た顔だ。盛喬の付き添いで来たのかい。ご苦労さまなこった」
正直驚いた。外見からするに少々ボケでも入ってるのか? と思わせられたが、とんでも無かった。しっかりしてる。これなら期待出来そうだと腹の中で考えた。
六畳の茶の間には昔ながらの長火鉢が置いてあった。この季節だというのに炭が熾きていた。
「歳取ると寒がりになるものでな。梅雨になるまではこいつは放せんよ」
そう言って灰をかき回した。掛かっていた薬缶から急須に湯を注ぎお茶を入れてくれた。
「なんせ婆さんに先立たれてからは不自由しててのう」
僅かに笑ったのは照れ隠しだと感じた。
「それで、ワシに何の用だね。まさか噺の用ではあるまいな」
言葉とは裏腹にその目は死んでは無いと感じた。
「圓海師匠、師匠圓盛の独演会にどうか出演して戴けませんか? 師匠も一度一緒に出たいと常々語っていたのです。圓海師匠のご病気が良くなったとお聞きしてそれならと伺いました」
盛喬も噺家ならもう少し粋な言い方があるだろうと思ったが、それだけ緊張しているのだと思い直した。
圓海師匠は自分で入れたお茶を一口飲むと息を吐いてから
「ワシで良かったら何時でも出る。幸い病も心配無くなった。だが、ワシの事を知ってるお客が居るかな。それでお客が集まるかい」
「それは大丈夫です。ここにいる神山さんが『よみうり版』で紹介してくれますから」
圓海師匠は俺をひと睨みすると
「まあ、その点では大丈夫だとは思うが、せいぜい宣伝してください」
そう言ってから盛喬に振り向き
「圓盛にも良いように言っておいておくれ」
そう言って答えた表情に先ほどとは打って変わって生気がみなぎって来たのを感じた。
その後、圓海師匠から演題の注文で「青菜」がやりたいと言って来たので、それに合わせて調整をすることになった。
出演者は、圓海師匠のゲストに開口一番が盛喬だ。真打を開口一番に使うとは贅沢な独演会だと思った。圓盛師匠の演目は「転宅」と「唐茄子屋政談」となった。
盛喬は「あくび指南」を演じるという。これらをプログラム的に記すと
開口一番 三遊亭盛喬 「あくび指南」
三遊亭圓盛 「転宅」
三遊亭圓海 「青菜」
仲入り
兄弟弟子対談 圓海、圓盛、司会盛喬
トリ 三遊亭圓盛 「唐茄子屋政談」
とこんな感じになる。場所は都内の落語が良く開かれている某ホールを押さえた。大体500人前後を収容出来るホールだが、そこに400人ほど入れる。満員にしないのは師匠圓盛師の方針だそうだ。満員よりも若干余裕がある方が演じやすいそうだ。
兎に角公演の日まで時間がないので、「よみうり版」にも差し替えで独演会に圓海師が出演する記事を入れて月末の発売に間に合わせたのだった。
幻と言われた噺家、三遊亭圓海師が高座に上がるという事が落語ファンの間で結構な話題になり。前売りが始まると結構な売れ行きを示した。
独演会の準備が一息ついて、後は当日を待つばかりとなった。俺はこの頃仕事をセーブして家に居ることが多くなった薫と色々な事を話していた。
「圓海師匠って、わたしは聴いたこと無いけど、どんな噺をするの?」
薫の疑問は尤もだ。噺家として恐らく一番大事な時期に病を患ってしまい、棒に振ってしまった。俺が何度か聴いたのは病を患い始めた頃で、その前よりも精彩が無かったことを思い出した。
「そうだな、圓盛師が人の心に入り込むような高座だとすると当時の圓海師は噺全体でお客を包み込んでしまう感じだった。小手先の話芸では無い感じだったな。器用さで言えば圓盛師の方が上だな」
俺のそんな感想を聴いて薫は当日自分も連れて行って欲しいとねだった。無論駄目なはずが無いので了解する。
「その二人の師匠の違いを肌で感じて自分に活かせればいいなと思ってるの。わたしも、もうヒロインなんかは来ないだろうし、演技で採用される役者にならないとね」
そんなことを言って俺にしなだれかかって来た。それを優しく抱きめた……