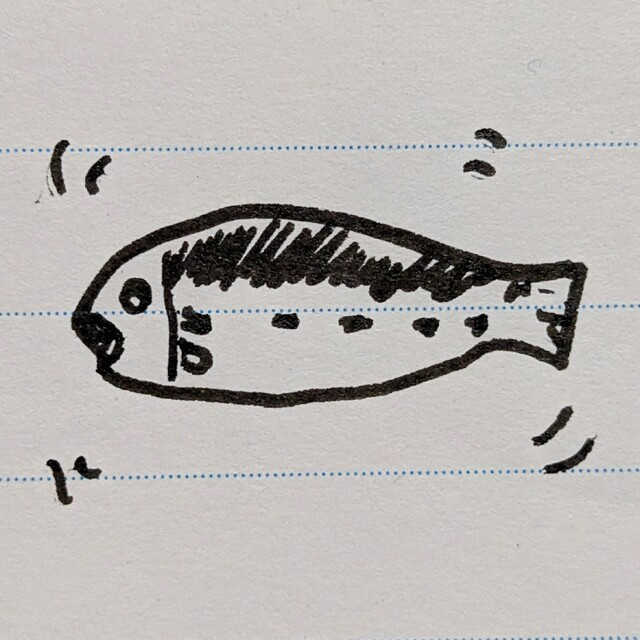7月中旬
文字数 2,765文字
宵宮を貸し切ってみたいと思っていた。
いや、貸し切るという言葉では弱すぎて、屋台はあるけど店員はいないし、華やいだ雰囲気なのに喧騒はないし、灯りはあるけど、どこか悲し気で――とにかく僕しかいない宵宮を夢見ていた事があった。その方が、宵宮と言う幻想的な世界をより幻想的に感じられる気がしていたからだ。でも実際、そんな状況に僕がいたとしたら、望んでいた幻想的な世界を楽しむ余裕なんてきっとまるでなくて、活気がありそうでない儚げな空間を孤独だと感じるのだろう。
7月中旬のあの日、夏希と共に来た宵宮は、正直、夏希の見慣れない浴衣姿や高い位置で纏めた髪型が印象的過ぎたせいで曖昧な部分が多いものの、やっぱり当たり前の宵宮だった。むしろ活気があり過ぎて、僕の願望が濃くなった事を思い出す。
とはいえ現実には僕が夢見る空間など自明な通り存在はせず、宵宮というものは、人で溢れているのが当たり前だった。だのにその当たり前な世界は、切り取り方一つでまるで変わるのだ。
あの日、僕たちは屋台でりんご飴を買い、群衆を避けるように境内を進めば、徐々にそんな空間に近い世界が広がり始めて、御社の近くにあるベンチに腰を下ろした時には既に、想像していた世界によく似た光景の中にいる事を知った。
ただ違ったのは、儚くはなかった事だ。静かではあったものの、道中人が入り乱れる光景を目撃したからか、店員と言葉を交わしてりんご飴を購入したからか、あるいは2人だったからか、とても儚いとは思えなかった。だからこそ孤独は感じなかったし、幻想的かと問われても、そこまでではないと言ってしまいそうだったし、ただただ、夏らしい風が通り過ぎていくばかりで、求めているものとは違った。それに、りんご飴なんて言う、宵宮とか夏祭りにありふれた食事が共存している時点で、儚いとも孤独だとも思えそうにない。
飴を齧る時に鳴る独特な粉砕する音を喧騒と錯覚してしまいそうになった事を思い出して、それに引っ張られるようにその日が目の前に広がった。
「夏が終わる確率って知ってる?」
「いや、100パーセントでしょ。四季って言葉があるんだし」
もう2ヵ月も前の事だから明確ではないけど、そんな意味不明な会話ですら、まさか進学希望者向けの説明会で知り合って1年ばかりの異性とこんなにも意気投合し、こんな風に宵宮に訪れる事ができるとは想像できていなかった当時の僕からしてみたら、さぞ高鳴っていたに違いない。
「じゃあ、夏が終わる確率が100パーセントである場合、夏が始まる確率は?」
「……いや、100パーセントでしょ。以下同文」
「と思うじゃん? 問題と公式は前提によって景色が変わるんだよ」
「いやわからん。それで、答えはなんなの?」
「んー、答えなんてないんだけど、何か興味深い答えが返ってくるかなと思って」
「その言動に答えが欲しいわ」
そうだった。度々、夏希のはにかむような笑いや、りんご飴を粉砕する音が会話の間に鳴っていたのだ。それに似た感覚が、まるで耳を欹てているかのように脳裏で反響すると、気温が上がり初めの時期の熱気が、身近に感じた。
「でも考えてみてよ。答えのないものに答えを出してなんて意味わかんないと思うけど、夏休み最終日まででいいからさ」
「なんで夏休み最終日まで? 夏の終わりみたいだから?」
「お、なんかかっこいいねそれ。でも残念な事に違うんだよ。9月1日なれば、私はここにいないから、それまでに答えが欲しいだけでさ」
「……転校すんの?」
「転校はしないよ。ただちょっと、会えなくなるってだけ」
りんご飴を落としそうになり、なんとかそれを耐えると、突発的に、いなくなるのであれば想いを告げておくべきだと過った。でも結局、それが声になる事はなかったが、今となってはその事実が、自他ともに好ましい。
「それも少し、長くなるかも」
「なんで?」
「……私さ、父親を殺したの」
夏希は、捕まるから、拘禁されるから、会えなくなると言っていたのだ。……正直、その事実を聞くまでは、驕っていた。当たり前のように卒業し同じ大学に受験すると勘違いしていたと知ると、空気とか会話とか、とにかく沢山の物が当たり前じゃない事を知って、景色が変わった。とはいえ実際には、その場限りの感覚的な錯覚でしかなく、次の日になれば感覚的にも、視覚的にも、当たり前に生きていた世界が広がっていたのだ。もし、絶えず景色が変わっていたのであれば、変わったと根っから錯覚できていれば、僕の言動はもう少しばかり理知的なものになっていたのかもしれない。いや、それらを俯瞰できなかった僕は、そもそも理知とは縁がなかったのだろう。
「父親と言っても、親権を持っている訳でもないし、私が物心ついた時には詐欺まがいの手法でお金を奪って、そのお金をギャンブルに注ぎ込んで、ギャンブルに負ければ暴力。何があってそうなったのかなんて知らないけど、そんな人を今も今までも父親だと思った事なんてなくて、なんだったらなんであんな悪人が生きてるんだろうって、ずっと死んで当然だって思ってた。そしたら3日前にアイツはまた同じ事をしようとして、衝動的に私は……。それでもね、誰一人として悲しむ人はいなかったし、未だにその事実が気づかれる事すらないんだから、その程度の人間なんだって安心したんだ。でも、気分が晴れる事はなくて、それどころか日に日に苛まれるの。鑑みればアイツより私の方が善行だと思うのに、ね。もし私があんな父親似でクズ人間だったらこんなに苛まれる事なんてないんだろうなって思う。でも私は幸か不幸か似なかったから――とまあそんな感じだから、自首しようと思うんだ。だけど、せめて夏休みくらいは猶予期間にしたいなって」
「夏休み……」
「なんか劇的だね。悲劇のヒロインに見える事あるくない?」
痩せ我慢してるみたいに笑った顔が不愉快だった。せっかく生まれた小気味いい関係を失う事がどうしようもなく嫌だった。夏希が悪人になるのが許せなかった。その思いが、どうしようもなく肥大する。
「でも、正当防衛じゃん」
「んー、詳しくないからわからないし、本当に正当防衛なんだとしても、私は罪を償わなきゃいけないって思うの。なんたって、人殺しだからね」
「……自首させないようにするには、どうしたらいい?」
「まって、私をクズ乙女にさせたいの?」
「割と本気なんだけど」
この時にはっきりと一言――いや二言三言、自首に否定的な言葉を、夏希は善人である説明をぶつけていたのならば、幾分か結果は変わっていたのかもしれない。
「じゃあ、夏休みが終わるまでに、私の行為を社会的に善行だと認めさせる事ができたなら、いいよ。自首しない」
いや、貸し切るという言葉では弱すぎて、屋台はあるけど店員はいないし、華やいだ雰囲気なのに喧騒はないし、灯りはあるけど、どこか悲し気で――とにかく僕しかいない宵宮を夢見ていた事があった。その方が、宵宮と言う幻想的な世界をより幻想的に感じられる気がしていたからだ。でも実際、そんな状況に僕がいたとしたら、望んでいた幻想的な世界を楽しむ余裕なんてきっとまるでなくて、活気がありそうでない儚げな空間を孤独だと感じるのだろう。
7月中旬のあの日、夏希と共に来た宵宮は、正直、夏希の見慣れない浴衣姿や高い位置で纏めた髪型が印象的過ぎたせいで曖昧な部分が多いものの、やっぱり当たり前の宵宮だった。むしろ活気があり過ぎて、僕の願望が濃くなった事を思い出す。
とはいえ現実には僕が夢見る空間など自明な通り存在はせず、宵宮というものは、人で溢れているのが当たり前だった。だのにその当たり前な世界は、切り取り方一つでまるで変わるのだ。
あの日、僕たちは屋台でりんご飴を買い、群衆を避けるように境内を進めば、徐々にそんな空間に近い世界が広がり始めて、御社の近くにあるベンチに腰を下ろした時には既に、想像していた世界によく似た光景の中にいる事を知った。
ただ違ったのは、儚くはなかった事だ。静かではあったものの、道中人が入り乱れる光景を目撃したからか、店員と言葉を交わしてりんご飴を購入したからか、あるいは2人だったからか、とても儚いとは思えなかった。だからこそ孤独は感じなかったし、幻想的かと問われても、そこまでではないと言ってしまいそうだったし、ただただ、夏らしい風が通り過ぎていくばかりで、求めているものとは違った。それに、りんご飴なんて言う、宵宮とか夏祭りにありふれた食事が共存している時点で、儚いとも孤独だとも思えそうにない。
飴を齧る時に鳴る独特な粉砕する音を喧騒と錯覚してしまいそうになった事を思い出して、それに引っ張られるようにその日が目の前に広がった。
「夏が終わる確率って知ってる?」
「いや、100パーセントでしょ。四季って言葉があるんだし」
もう2ヵ月も前の事だから明確ではないけど、そんな意味不明な会話ですら、まさか進学希望者向けの説明会で知り合って1年ばかりの異性とこんなにも意気投合し、こんな風に宵宮に訪れる事ができるとは想像できていなかった当時の僕からしてみたら、さぞ高鳴っていたに違いない。
「じゃあ、夏が終わる確率が100パーセントである場合、夏が始まる確率は?」
「……いや、100パーセントでしょ。以下同文」
「と思うじゃん? 問題と公式は前提によって景色が変わるんだよ」
「いやわからん。それで、答えはなんなの?」
「んー、答えなんてないんだけど、何か興味深い答えが返ってくるかなと思って」
「その言動に答えが欲しいわ」
そうだった。度々、夏希のはにかむような笑いや、りんご飴を粉砕する音が会話の間に鳴っていたのだ。それに似た感覚が、まるで耳を欹てているかのように脳裏で反響すると、気温が上がり初めの時期の熱気が、身近に感じた。
「でも考えてみてよ。答えのないものに答えを出してなんて意味わかんないと思うけど、夏休み最終日まででいいからさ」
「なんで夏休み最終日まで? 夏の終わりみたいだから?」
「お、なんかかっこいいねそれ。でも残念な事に違うんだよ。9月1日なれば、私はここにいないから、それまでに答えが欲しいだけでさ」
「……転校すんの?」
「転校はしないよ。ただちょっと、会えなくなるってだけ」
りんご飴を落としそうになり、なんとかそれを耐えると、突発的に、いなくなるのであれば想いを告げておくべきだと過った。でも結局、それが声になる事はなかったが、今となってはその事実が、自他ともに好ましい。
「それも少し、長くなるかも」
「なんで?」
「……私さ、父親を殺したの」
夏希は、捕まるから、拘禁されるから、会えなくなると言っていたのだ。……正直、その事実を聞くまでは、驕っていた。当たり前のように卒業し同じ大学に受験すると勘違いしていたと知ると、空気とか会話とか、とにかく沢山の物が当たり前じゃない事を知って、景色が変わった。とはいえ実際には、その場限りの感覚的な錯覚でしかなく、次の日になれば感覚的にも、視覚的にも、当たり前に生きていた世界が広がっていたのだ。もし、絶えず景色が変わっていたのであれば、変わったと根っから錯覚できていれば、僕の言動はもう少しばかり理知的なものになっていたのかもしれない。いや、それらを俯瞰できなかった僕は、そもそも理知とは縁がなかったのだろう。
「父親と言っても、親権を持っている訳でもないし、私が物心ついた時には詐欺まがいの手法でお金を奪って、そのお金をギャンブルに注ぎ込んで、ギャンブルに負ければ暴力。何があってそうなったのかなんて知らないけど、そんな人を今も今までも父親だと思った事なんてなくて、なんだったらなんであんな悪人が生きてるんだろうって、ずっと死んで当然だって思ってた。そしたら3日前にアイツはまた同じ事をしようとして、衝動的に私は……。それでもね、誰一人として悲しむ人はいなかったし、未だにその事実が気づかれる事すらないんだから、その程度の人間なんだって安心したんだ。でも、気分が晴れる事はなくて、それどころか日に日に苛まれるの。鑑みればアイツより私の方が善行だと思うのに、ね。もし私があんな父親似でクズ人間だったらこんなに苛まれる事なんてないんだろうなって思う。でも私は幸か不幸か似なかったから――とまあそんな感じだから、自首しようと思うんだ。だけど、せめて夏休みくらいは猶予期間にしたいなって」
「夏休み……」
「なんか劇的だね。悲劇のヒロインに見える事あるくない?」
痩せ我慢してるみたいに笑った顔が不愉快だった。せっかく生まれた小気味いい関係を失う事がどうしようもなく嫌だった。夏希が悪人になるのが許せなかった。その思いが、どうしようもなく肥大する。
「でも、正当防衛じゃん」
「んー、詳しくないからわからないし、本当に正当防衛なんだとしても、私は罪を償わなきゃいけないって思うの。なんたって、人殺しだからね」
「……自首させないようにするには、どうしたらいい?」
「まって、私をクズ乙女にさせたいの?」
「割と本気なんだけど」
この時にはっきりと一言――いや二言三言、自首に否定的な言葉を、夏希は善人である説明をぶつけていたのならば、幾分か結果は変わっていたのかもしれない。
「じゃあ、夏休みが終わるまでに、私の行為を社会的に善行だと認めさせる事ができたなら、いいよ。自首しない」