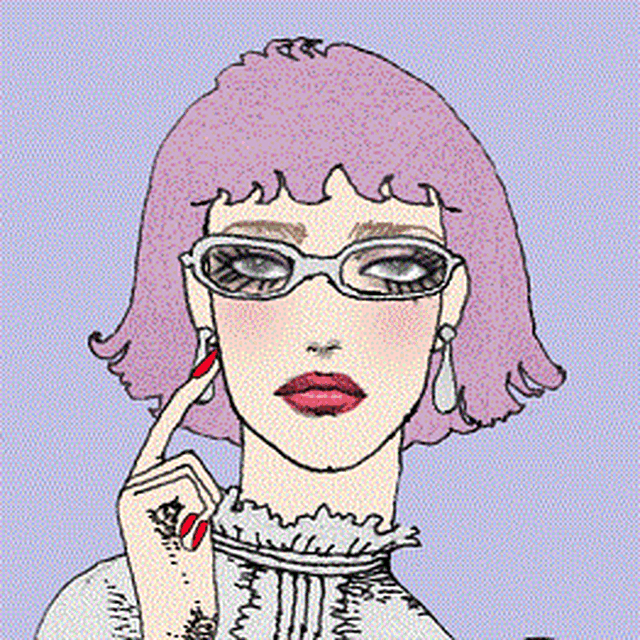第3話
文字数 3,093文字
「白河殿!」
とっさに背後から抱きとめた基通に、盛子は途切れそうな意識のまま抗おうとしたが、それを許さない力の強さにひどく動揺した。
それは、幼くして未亡人となった盛子がはじめて知る感情的な抱擁で、このままではいけないと、理性が激しく警鐘を鳴らしていた。
しかしそれをかき消すほど近く、基通は盛子の耳もとへ唇を寄せてささやいた。
「あなたも、わたしを息子などとは、思っておいでにならなかったはずです。──ちがいますか」
基通が盛子の艷やかな髪に口づけてゆくたびに、頭の中が真っ白になっていく。
胸の鼓動は沸騰したかのように激しく高鳴り、いまにも基通にも伝わるのではないかと思うと、恥ずかしさでふたたび意識が薄れそうになる。
(──流されてはだめよ。すぐそこに、たくさんの人がいる)
おそらく聞き耳を立てているであろう女房たちの顔をひとりずつ思い浮かべて、盛子は大きく息を吸いこんだ。そして乾いた唇を湿すと、諭すようにゆっくりと言った。
「基通どの……あなたには、約束された将来があります。いっときの気の迷いで、道を踏みはずすことはなりません」
このまま、勢いに乗る平家を外戚として後ろ盾にしていれば、基通はいずれ摂政の地位につき、氏の長者にもなることができるはずだった。
けれどいま、義理の母であり、正室の姉でもある盛子と過ちを犯してしまえば、それは基通だけでなく、近衛家そのものに大きな打撃を与えることになるだろう。
つかの間、基通は腕の力をゆるめたが、すぐさま癇癪を起したように強く盛子を抱き寄せた。
「わたしは正気です、誓って気の迷いなどではありません。はじめてお会いしたときから……少年だったあの日からずっと、あなたはひとりの女性として、わたしの心の奥深くにおいでだった」
盛子の首筋に鼻先を押しつけるようにして、基通は熱い吐息とともに言葉を吐き出した。絡みあう吐息にこもった熱が盛子の肌へ伝わり、身体の芯から震えるほどの衝動が駆け抜けていく。
盛子はうわずりそうになる声を懸命に抑えて言った。
「わたしたちは、母と子です。血がつながっていなくても、それは変わらない。変えてはいけないのです」
「……本心から、そう言っておいでなのですか。燠火をかかえているのは、わたしだけだと?」
基通はほとんど触れそうなまでに唇を寄せて、盛子を責めるように言った。しっとりとした基通の息づかいと、甘く立ちのぼる薫物の香りが、どうしようもなく盛子の心をかき乱していく。
(もう、何もおっしゃらないで。わたしは、ずっと心に蓋をしてきたのに──!)
幼かったあの日々、ふたりのあいだにはごく自然に小さな小さな火が灯っていた。しかし、それを恋だと理解するころには、あきらめる以外にどうしようもないことなのだと受けいれるしかなかった。
盛子も基通も、ちろちろと燃える小さな炎を抱いたまま、そのことには気づかないふりをして、そのくせそれが消えてしまわぬように、ひっそりと心の奥底に隠してきたはずだった。
それなのに──
「白河殿、あなたの真実の心を知りたい。わたしは、あなたが欲しい」
ふたりが守りつづけていた燠火は、にわかに息を吹き返しつつあった。
基通だけではない。盛子自身も、身体の奥ではじけそうになる情動をやっとのことで抑え込んでいた。
もし、ふたりの恋が公けになれば、それは燎原の火のごとく周囲をも焼き尽くしてしまうだろう。
(いけない。それだけは、ぜったいに──。わたしは、平家も近衛家も、守っていかなければいけない)
盛子は奥歯を噛みしめると、ふたたび己の心を厳重に閉じた。そして強い口調で基通へ問いかけた。
「基通どの。あなたは近衛家を、たった二代で潰えさせてしまうおつもりですか。あなたには、守るべきものがあるはずです」
父の基実が亡くなったあと、幼少だった基通に代わって叔父が暫定的に摂政を務めている。しかもそれは、すでに十年に及んでいた。叔父は有職故実にも通じ、若年の基通よりもずっと周囲から重んじられている。
「平家の後ろ盾があったとしても、あなたの足もとは盤石ではないのですよ。このような世迷言にかまけている場合ですか?」
さっと、基通から熱が引いていくのがわかった。
「母上……」
「そうです。わたしはあなたの母です。あなたと近衛家を守るために、わたしは母となったのです」
だらりと、基通の腕が落ちた。
それを合図とするかのように、六波羅からの迎えを告げる声が聞こえてくる。
「あなたの責務を忘れないで。──ただひたすらに、近衛家を守ることだけを考えなさい」
うなだれる基通を残して、盛子は牛車を降りた。
◇ ◇ ◇
脇息にもたれたままうたた寝をしていた盛子は、自分を呼ぶ女房の声で目を覚ました。断片的に見た夢の名残が、生々しく身体に残っている。妙なことを口走っていなければいいけれど、と思いながら声に応えた。
「──どうしたの」
「冷泉局でございます。お目覚めでいらっしゃいますか」
「ええ、大丈夫よ」
「基通さまが、桜の枝をお目にかけたいとの仰せでございます」
「そう……。通して」
花見のあと、維盛たちは盛子の姉である中宮徳子のもとへ向かったらしく、簀子には基通ひとりが座っていた。
燭に照らされた細面の顔には疲れも見えず、いくぶん酔っているのか目もとがやわらかい。
冷泉局の手を通して桜の枝を寄越した基通は、そこかしこで桜が咲き誇り、ふくよかに匂い立つ様子は夢のようだったと弁舌さわやかに話して聞かせた。
「つぎはぜひ、母上もいらしてください。みな、よろこびます」
「そうね。ありがとう」
盛子は贈られた桜の枝にほころぶ淡い花弁を愛でながら、これでよかったのだ──と、夢に見たばかりのあの夜を反芻した。
(わたしはきっと、女のしあわせも、悦びも、なにも知らずに朽ちてゆく──)
妹のように子を産むことも、姉のように夫と睦まじく過ごすことも、盛子には叶わなかった。おなじ平家の姉妹として生まれたのに、なぜ自分だけが、と妬ましく思うこともある。
そうして梁の奥に広がる闇に囚われそうになるとき、盛子はいつも、近衛家が末永く受け継がれてゆく未来に思いを馳せる。
昔もいまも、近衛家の存在だけが、盛子と基通をつないでいた。だれ憚ることなく、ふたりで手を携えて守り育てることができる、たったひとつのもの。
(──夫も、子も持たないわたしには、近衛家がつづいてゆくことだけが生涯のしあわせで、唯一の悦びになる)
願わくば、彼もそうでありますように──と思う。
家を守り、存続させていくことが、あきらめるしかなかったふたりの恋を、未来永劫守りつづけることになる。盛子はそう信じていた。
「基通どの。これからも、近衛家をよくよく守ってください」
「もちろんです。母上のお気持ちは承知しております」
「……あなたなら、きっと応えてくれると信じていますよ」
それは、会うたびにくりかえされる会話。互いの心に燠火が消えずにあることを確かめるように、慎重に言葉を重ねる。女房の口を介していても、盛子の気持ちは伝わっているはずだった。
わずかにくれた視線の端に、名残惜しさを忍ばせながら基通が退出すると、盛子は御簾を巻きあげるように言いつけた。
春の庭は、やがて来る梅雨の気配を含んで湿り気を帯びている。母屋の奥まで流れこむ夜半 の風のなかに、盛子は基通の残り香を探った。
(わたしたちは、燠火の舟でさまよいつづける。けして煽らず、燃えあがることのないように、ひそやかに──)
たったひとつの恋を抱きしめるように、盛子は桜の枝をそっと胸に押しあてた。
了
とっさに背後から抱きとめた基通に、盛子は途切れそうな意識のまま抗おうとしたが、それを許さない力の強さにひどく動揺した。
それは、幼くして未亡人となった盛子がはじめて知る感情的な抱擁で、このままではいけないと、理性が激しく警鐘を鳴らしていた。
しかしそれをかき消すほど近く、基通は盛子の耳もとへ唇を寄せてささやいた。
「あなたも、わたしを息子などとは、思っておいでにならなかったはずです。──ちがいますか」
基通が盛子の艷やかな髪に口づけてゆくたびに、頭の中が真っ白になっていく。
胸の鼓動は沸騰したかのように激しく高鳴り、いまにも基通にも伝わるのではないかと思うと、恥ずかしさでふたたび意識が薄れそうになる。
(──流されてはだめよ。すぐそこに、たくさんの人がいる)
おそらく聞き耳を立てているであろう女房たちの顔をひとりずつ思い浮かべて、盛子は大きく息を吸いこんだ。そして乾いた唇を湿すと、諭すようにゆっくりと言った。
「基通どの……あなたには、約束された将来があります。いっときの気の迷いで、道を踏みはずすことはなりません」
このまま、勢いに乗る平家を外戚として後ろ盾にしていれば、基通はいずれ摂政の地位につき、氏の長者にもなることができるはずだった。
けれどいま、義理の母であり、正室の姉でもある盛子と過ちを犯してしまえば、それは基通だけでなく、近衛家そのものに大きな打撃を与えることになるだろう。
つかの間、基通は腕の力をゆるめたが、すぐさま癇癪を起したように強く盛子を抱き寄せた。
「わたしは正気です、誓って気の迷いなどではありません。はじめてお会いしたときから……少年だったあの日からずっと、あなたはひとりの女性として、わたしの心の奥深くにおいでだった」
盛子の首筋に鼻先を押しつけるようにして、基通は熱い吐息とともに言葉を吐き出した。絡みあう吐息にこもった熱が盛子の肌へ伝わり、身体の芯から震えるほどの衝動が駆け抜けていく。
盛子はうわずりそうになる声を懸命に抑えて言った。
「わたしたちは、母と子です。血がつながっていなくても、それは変わらない。変えてはいけないのです」
「……本心から、そう言っておいでなのですか。燠火をかかえているのは、わたしだけだと?」
基通はほとんど触れそうなまでに唇を寄せて、盛子を責めるように言った。しっとりとした基通の息づかいと、甘く立ちのぼる薫物の香りが、どうしようもなく盛子の心をかき乱していく。
(もう、何もおっしゃらないで。わたしは、ずっと心に蓋をしてきたのに──!)
幼かったあの日々、ふたりのあいだにはごく自然に小さな小さな火が灯っていた。しかし、それを恋だと理解するころには、あきらめる以外にどうしようもないことなのだと受けいれるしかなかった。
盛子も基通も、ちろちろと燃える小さな炎を抱いたまま、そのことには気づかないふりをして、そのくせそれが消えてしまわぬように、ひっそりと心の奥底に隠してきたはずだった。
それなのに──
「白河殿、あなたの真実の心を知りたい。わたしは、あなたが欲しい」
ふたりが守りつづけていた燠火は、にわかに息を吹き返しつつあった。
基通だけではない。盛子自身も、身体の奥ではじけそうになる情動をやっとのことで抑え込んでいた。
もし、ふたりの恋が公けになれば、それは燎原の火のごとく周囲をも焼き尽くしてしまうだろう。
(いけない。それだけは、ぜったいに──。わたしは、平家も近衛家も、守っていかなければいけない)
盛子は奥歯を噛みしめると、ふたたび己の心を厳重に閉じた。そして強い口調で基通へ問いかけた。
「基通どの。あなたは近衛家を、たった二代で潰えさせてしまうおつもりですか。あなたには、守るべきものがあるはずです」
父の基実が亡くなったあと、幼少だった基通に代わって叔父が暫定的に摂政を務めている。しかもそれは、すでに十年に及んでいた。叔父は有職故実にも通じ、若年の基通よりもずっと周囲から重んじられている。
「平家の後ろ盾があったとしても、あなたの足もとは盤石ではないのですよ。このような世迷言にかまけている場合ですか?」
さっと、基通から熱が引いていくのがわかった。
「母上……」
「そうです。わたしはあなたの母です。あなたと近衛家を守るために、わたしは母となったのです」
だらりと、基通の腕が落ちた。
それを合図とするかのように、六波羅からの迎えを告げる声が聞こえてくる。
「あなたの責務を忘れないで。──ただひたすらに、近衛家を守ることだけを考えなさい」
うなだれる基通を残して、盛子は牛車を降りた。
◇ ◇ ◇
脇息にもたれたままうたた寝をしていた盛子は、自分を呼ぶ女房の声で目を覚ました。断片的に見た夢の名残が、生々しく身体に残っている。妙なことを口走っていなければいいけれど、と思いながら声に応えた。
「──どうしたの」
「冷泉局でございます。お目覚めでいらっしゃいますか」
「ええ、大丈夫よ」
「基通さまが、桜の枝をお目にかけたいとの仰せでございます」
「そう……。通して」
花見のあと、維盛たちは盛子の姉である中宮徳子のもとへ向かったらしく、簀子には基通ひとりが座っていた。
燭に照らされた細面の顔には疲れも見えず、いくぶん酔っているのか目もとがやわらかい。
冷泉局の手を通して桜の枝を寄越した基通は、そこかしこで桜が咲き誇り、ふくよかに匂い立つ様子は夢のようだったと弁舌さわやかに話して聞かせた。
「つぎはぜひ、母上もいらしてください。みな、よろこびます」
「そうね。ありがとう」
盛子は贈られた桜の枝にほころぶ淡い花弁を愛でながら、これでよかったのだ──と、夢に見たばかりのあの夜を反芻した。
(わたしはきっと、女のしあわせも、悦びも、なにも知らずに朽ちてゆく──)
妹のように子を産むことも、姉のように夫と睦まじく過ごすことも、盛子には叶わなかった。おなじ平家の姉妹として生まれたのに、なぜ自分だけが、と妬ましく思うこともある。
そうして梁の奥に広がる闇に囚われそうになるとき、盛子はいつも、近衛家が末永く受け継がれてゆく未来に思いを馳せる。
昔もいまも、近衛家の存在だけが、盛子と基通をつないでいた。だれ憚ることなく、ふたりで手を携えて守り育てることができる、たったひとつのもの。
(──夫も、子も持たないわたしには、近衛家がつづいてゆくことだけが生涯のしあわせで、唯一の悦びになる)
願わくば、彼もそうでありますように──と思う。
家を守り、存続させていくことが、あきらめるしかなかったふたりの恋を、未来永劫守りつづけることになる。盛子はそう信じていた。
「基通どの。これからも、近衛家をよくよく守ってください」
「もちろんです。母上のお気持ちは承知しております」
「……あなたなら、きっと応えてくれると信じていますよ」
それは、会うたびにくりかえされる会話。互いの心に燠火が消えずにあることを確かめるように、慎重に言葉を重ねる。女房の口を介していても、盛子の気持ちは伝わっているはずだった。
わずかにくれた視線の端に、名残惜しさを忍ばせながら基通が退出すると、盛子は御簾を巻きあげるように言いつけた。
春の庭は、やがて来る梅雨の気配を含んで湿り気を帯びている。母屋の奥まで流れこむ
(わたしたちは、燠火の舟でさまよいつづける。けして煽らず、燃えあがることのないように、ひそやかに──)
たったひとつの恋を抱きしめるように、盛子は桜の枝をそっと胸に押しあてた。
了