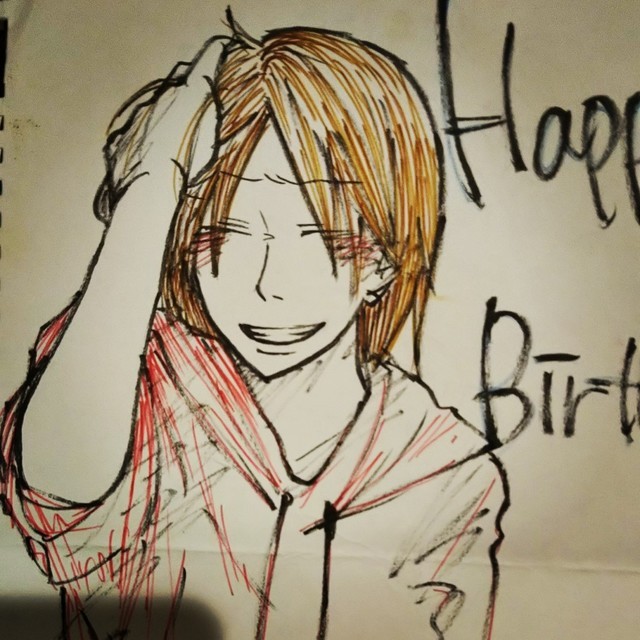うたうたい、1
文字数 1,525文字
うたうたい
一
耳の奥にこびりついたメロディー。
いくつかの音が複雑に組み合わさってできたというよりは、一音一音確かめるようにきちんと発音する音の集まり。丁度幼子が歩いた道筋のような。けれどもそれは、しっかりと踏みしめて進む一歩。単純に聞きやすく、まっすぐな音。
頭が痛い。雨音で目が覚めると、鈍くうずくこめかみを押さえる。例え陽性でなかったとしても光であることに変わりはなく、一度覚醒してしまえば容赦なくまぶたを叩く。布団をかぶりなおすと、波が過ぎ去るのを待つ。
以前に比べてだいぶ減ったが、時々まだ夢を見る。こうして弱っている時は特にそう。家族三人で暮らしている夢だ。父がいて、母がいて、まだ幼い自分がいる。鼻歌を歌う母の足元を、お気に入りの絵本を抱えて行ったり来たりしていると、コーヒーのお代わりを取りに来た父に頭をなでられる。力強く、大きな手。自分にとっての絶対の庇護者。その万能の安心感、を奪われる日が来るなんて、いったい誰が想像できただろう。この時初めて知る。自分にとっての絶対は、世の中にとっての絶対ではないのだ。
深い谷底から浮上する。意識が輪郭を取り戻す頃、懐かしいメロディーが聞こえた。頭痛を忘れて飛び起きると、のんきな声が僕を迎えた。
「やっと起きた」
あごまでの長さの内巻きの髪。細い肩がくるりと回る。同時に感じ取ったのはカレーのにおいだった。
「……勝手に入るなって言ったよね」
「ちょっとすごい汗! 今着替え持ってくるから待ってて」
相も変わらず人の話を聞きやしない。
「いいから勝手に触らないで」
ベッドを下りると同時に視界がぐらりと回る。あわててサイドテーブルに手をつくが、しばらく動けそうにない。大きく息をついた。
どうせ言ったところであいつが聞くと思えない。このやりとり自体、体力の無駄使いだ。
「はい。また体調崩したの? 運動しないからだよ」
下着は自分で用意して、と持って来た着替えを押し付ける。
確かにひどい汗だった。冷えた汗が体温を奪う。仕方なく着替えることにした。
「ごはん食べる?」
「……ん。カレー以外なら食べる」
「何言ってるの。カレー以外食べないくせに」
「病人だよ」
「病人だから間違いなく食べる物をつくったの」
キッチンからコンロの電源を入れる音がした。少しして沸騰する音が聞こえてくる。僕は布団に入りなおすと、蹴とばすようにしてシーツをはがした。しっとりと人一人分の汗を吸い込んだそれは、丸めて押しやるとつんのめるようにして頭から床に落ちた。
両親共に失った僕は、幼いころから特別扱いされていた。
そんな世間の期待通り「人と違って特別な存在」である自分をまっすぐ演じた。生まれ持った性質もあったのかもしれない。よどみない傲慢は、けれども無神経な同情や哀れみをはねのける上で必要なものでもあった。自分の存在を腫れ物だなんて、絶対に思わなかった。そんな特別な存在である僕を唯一特別扱いしなかったのが幼馴染のあいつだった。
「いけないんだ」
ことあるごとに指をさす。
通学用の黄色い帽子をかぶらなかった時。横断歩道で手を上げなかった時。先生に敬語を使わなかった時。体育をさぼった時。下校中に買い食いをした時。まるで専用の学級委員であるかのようなしつこさでどこにでも現れた。
「うっとおしいんだけど」
だから僕も決まってそう返した。人のすることなすことに目くじらを立てて、常にストレスを抱えて生活して何が楽しいのか分からない。それでもあいつは僕を指さし続けた。
「いけないんだ」
誰も口にしなかった「正しい事」を抱きかかえて。