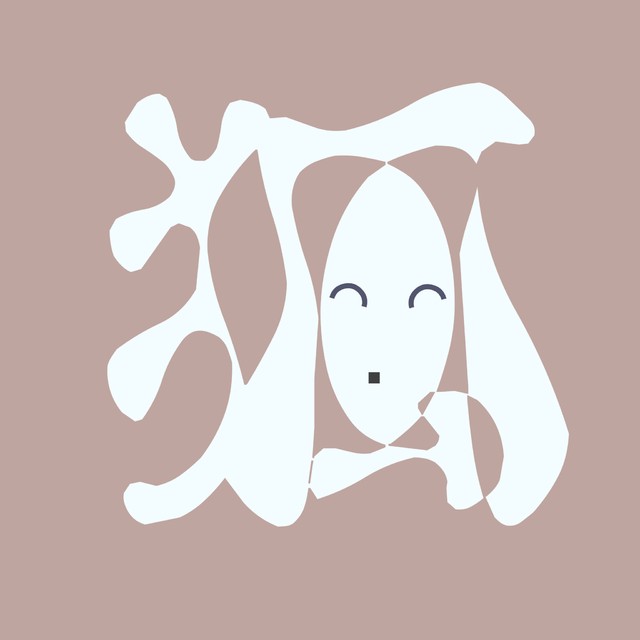片想いの賞味期限
文字数 2,016文字
ママは、とても身なりにうるさい。
遅くまで深夜ラジオを聴いていた。日の出が近づいた頃に、お風呂に入った。昼過ぎまで寝て起きた。朝昼兼用のごはんを食べた。部屋でぐだぐだしてた。ずっと同じジャージのまんまだ。
Tシャツは、体育祭で作ったクラスT。ジャージの上着のファスナーをあげれば、見えはしない。ぼさぼさの髪はキャップで隠した。マスクはマストだ。そもそも誰に会うわけでもない。
「玉葱買うだけだし、大丈夫だよ」
「だめ。今日に限って、イケメンが街に繰り出してるかもしれないでしょ」
抵抗をやめて着替えに戻ったのは、イケメンに目が眩んだわけじゃない。彼の顔が頭に浮かんだからだ。
もし、彼に会ってしまったら——。
そんな可能性は、二階からの目薬が命中するくらいゼロに近い。分かってはいても、一度思ってしまったら無視は出来ない。
無駄だ無駄だと一人ごちつつ、五着目に手にしたワンピースに着替えた。諸々整え、再び玄関に向かうまで、なんと四十分。我ながら論評に窮する。
でも、そこからさらに二十分後、わたしはママに感謝することになった。
商店街の八百屋で玉葱を買って、本屋の店先で雑誌を立ち読みしていた。そこに、彼が通りかかったからだ。
「久しぶりだね。元気?」
先に声を掛けたのは、彼の方だ。
持っていた雑誌を胸の前に抱き、ソーシャルディスタンスと言われる程度の距離をとって、彼と向かい合った。
二人きりで話すなんて、いつ以来か。他のことなら、記憶の保存期限が切れてしまっているところだ。
最後に見かけた時と比べて、彼の背がまた伸びている気がした。中一の時は同じくらいだったのに。
「うん。久しぶり。元気?」
「元気だよ」
「ジョギング?」
「そう。ずっと家の中にいるのもあれだから」
「だよね」
「そっちは?」
手に下げたエコバッグを、ちょっと上げて見せる。
「お遣い頼まれちゃって。玉葱」
「そっか」
「うん」
東京の大学に進学した彼は、本来ならもうこの町にはいない筈だった。東京で借りた部屋を整理して、従兄弟の結婚式のために帰省していたらしい。そこに新型ウイルス感染拡大に伴う県外移動規制が始まった。大学のキャンパスも立入禁止のままだから、急いで戻る理由がないらしい。
「そうなんだ……」
ここで会話が途切れてしまうのが、わたしの駄目なところ。彼じゃなければ男子相手でもへっちゃらなのに。彼を前にした途端に言葉が出なくなる。きっと、本来は脳に送られる筈のエネルギーまで、心臓が消費してしまうせいだ。
無理もない。もう会えないと思ってた人。六年間の片想いを、片想いのまま終わらせてしまった彼だ。
——じゃあね。
そう言って彼が走り去ってしまう。そんな光景が脳裏を掠める。
中一の春、同じクラスの彼を好きになった。運良く同じ高校に進学した。その間ずっと、視界の片隅で彼を探し続けた六年間だった。
高校最後のバレンタインも不戦敗。よし、卒業式までには告白するぞと意気込んではみたものの、ウイルスのせいで休校となり、卒業式もなくなった。
大学に入ったら彼のことなんか忘れて、キャンパスライフを謳歌するんだ。素敵な彼氏を見つけるんだ。そう思っていた出端 も、ウイルスのせいでくじかれた。思い出にしてしまうはずだったものが、思い出になりきらない。
ここでこのまま別れたら、何も変わらない。最後にちょっとおまけのような再会が得られただけ。彼の中に残る最後のわたしの記憶が、くたびれたジャージ姿じゃなくてよかった。
——それだけで終わる。
ここで言わなきゃ。
でも。
しゃがみこんで靴紐を結び直した彼が、立ち上がった。
「じゃあ、行くよ」
「え、あ、う、うん。……ばいばい」
膨らみかけていた風船は、一瞬で萎んだ。
走り去る彼を見送る。
そりゃそうだ。六年間できなかったことが、今日できるはずがない。
とっくに賞味期限が切れたような片想いを、いつまでも大事にしているわたしが馬鹿なんだ。
——帰ろう。
彼とは反対方向に歩き始めた。
会えてよかったじゃん。考えようによっては、ふられて終わるよりもハッピーエンドだし。ウイルスとママに感謝だ。うん。よかったよかった。めでたしめでたし。
自分に言い聞かせる自己防衛モードを発動。外部をシャットダウンしながら、早足で歩いていた。
不意に、後ろから手首を掴まれた。
「きゃ」
驚いて振り向くと彼だったので、また驚いた。
「ごめん、名前、呼んだんだけど」
「え、あ、ううん。何、どうしたの?」
彼は見るからに挙動不審だった。目が泳ぎ、手首を握られた手は冷たく汗をかいていて、何となく震えてすらいる。そんな彼は見たことがなかった。
まだ私の手首を握ったままの手をじっと見ていると、彼は慌てて離して謝った。
「ご、ごめん」
それはつまり、六年間言おうとして言えなかったことを、ついに今から言うぞっていう極度の緊張のせいだったのだと、少し後になって理解した。
遅くまで深夜ラジオを聴いていた。日の出が近づいた頃に、お風呂に入った。昼過ぎまで寝て起きた。朝昼兼用のごはんを食べた。部屋でぐだぐだしてた。ずっと同じジャージのまんまだ。
Tシャツは、体育祭で作ったクラスT。ジャージの上着のファスナーをあげれば、見えはしない。ぼさぼさの髪はキャップで隠した。マスクはマストだ。そもそも誰に会うわけでもない。
「玉葱買うだけだし、大丈夫だよ」
「だめ。今日に限って、イケメンが街に繰り出してるかもしれないでしょ」
抵抗をやめて着替えに戻ったのは、イケメンに目が眩んだわけじゃない。彼の顔が頭に浮かんだからだ。
もし、彼に会ってしまったら——。
そんな可能性は、二階からの目薬が命中するくらいゼロに近い。分かってはいても、一度思ってしまったら無視は出来ない。
無駄だ無駄だと一人ごちつつ、五着目に手にしたワンピースに着替えた。諸々整え、再び玄関に向かうまで、なんと四十分。我ながら論評に窮する。
でも、そこからさらに二十分後、わたしはママに感謝することになった。
商店街の八百屋で玉葱を買って、本屋の店先で雑誌を立ち読みしていた。そこに、彼が通りかかったからだ。
「久しぶりだね。元気?」
先に声を掛けたのは、彼の方だ。
持っていた雑誌を胸の前に抱き、ソーシャルディスタンスと言われる程度の距離をとって、彼と向かい合った。
二人きりで話すなんて、いつ以来か。他のことなら、記憶の保存期限が切れてしまっているところだ。
最後に見かけた時と比べて、彼の背がまた伸びている気がした。中一の時は同じくらいだったのに。
「うん。久しぶり。元気?」
「元気だよ」
「ジョギング?」
「そう。ずっと家の中にいるのもあれだから」
「だよね」
「そっちは?」
手に下げたエコバッグを、ちょっと上げて見せる。
「お遣い頼まれちゃって。玉葱」
「そっか」
「うん」
東京の大学に進学した彼は、本来ならもうこの町にはいない筈だった。東京で借りた部屋を整理して、従兄弟の結婚式のために帰省していたらしい。そこに新型ウイルス感染拡大に伴う県外移動規制が始まった。大学のキャンパスも立入禁止のままだから、急いで戻る理由がないらしい。
「そうなんだ……」
ここで会話が途切れてしまうのが、わたしの駄目なところ。彼じゃなければ男子相手でもへっちゃらなのに。彼を前にした途端に言葉が出なくなる。きっと、本来は脳に送られる筈のエネルギーまで、心臓が消費してしまうせいだ。
無理もない。もう会えないと思ってた人。六年間の片想いを、片想いのまま終わらせてしまった彼だ。
——じゃあね。
そう言って彼が走り去ってしまう。そんな光景が脳裏を掠める。
中一の春、同じクラスの彼を好きになった。運良く同じ高校に進学した。その間ずっと、視界の片隅で彼を探し続けた六年間だった。
高校最後のバレンタインも不戦敗。よし、卒業式までには告白するぞと意気込んではみたものの、ウイルスのせいで休校となり、卒業式もなくなった。
大学に入ったら彼のことなんか忘れて、キャンパスライフを謳歌するんだ。素敵な彼氏を見つけるんだ。そう思っていた
ここでこのまま別れたら、何も変わらない。最後にちょっとおまけのような再会が得られただけ。彼の中に残る最後のわたしの記憶が、くたびれたジャージ姿じゃなくてよかった。
——それだけで終わる。
ここで言わなきゃ。
でも。
しゃがみこんで靴紐を結び直した彼が、立ち上がった。
「じゃあ、行くよ」
「え、あ、う、うん。……ばいばい」
膨らみかけていた風船は、一瞬で萎んだ。
走り去る彼を見送る。
そりゃそうだ。六年間できなかったことが、今日できるはずがない。
とっくに賞味期限が切れたような片想いを、いつまでも大事にしているわたしが馬鹿なんだ。
——帰ろう。
彼とは反対方向に歩き始めた。
会えてよかったじゃん。考えようによっては、ふられて終わるよりもハッピーエンドだし。ウイルスとママに感謝だ。うん。よかったよかった。めでたしめでたし。
自分に言い聞かせる自己防衛モードを発動。外部をシャットダウンしながら、早足で歩いていた。
不意に、後ろから手首を掴まれた。
「きゃ」
驚いて振り向くと彼だったので、また驚いた。
「ごめん、名前、呼んだんだけど」
「え、あ、ううん。何、どうしたの?」
彼は見るからに挙動不審だった。目が泳ぎ、手首を握られた手は冷たく汗をかいていて、何となく震えてすらいる。そんな彼は見たことがなかった。
まだ私の手首を握ったままの手をじっと見ていると、彼は慌てて離して謝った。
「ご、ごめん」
それはつまり、六年間言おうとして言えなかったことを、ついに今から言うぞっていう極度の緊張のせいだったのだと、少し後になって理解した。