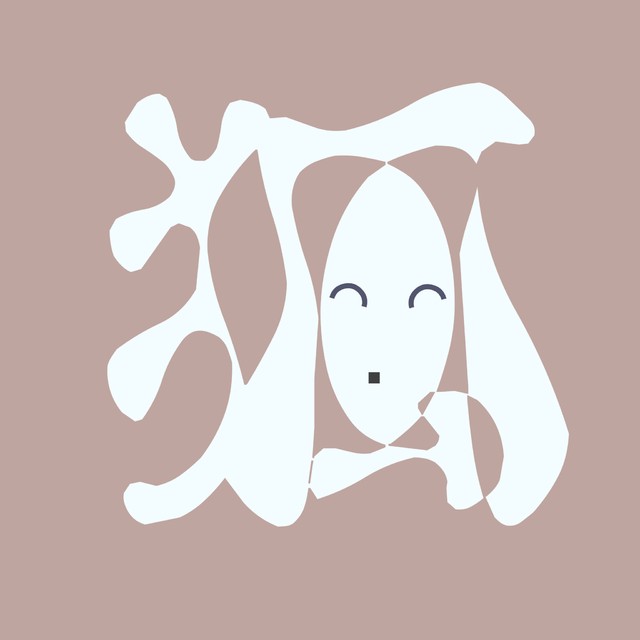(4) 七転び八起きか七転八倒か
文字数 1,399文字
一人の女性に何度も告白してふられまくった。そんな大学時代を過ごした。
相手は同じテニスサークルで、小柄で華奢な体格ながら、コート内を縦横無尽に駆け回る、小気味のよい人だった。似つかわしくない強烈なショットを決めると、全身で喜びを表現する。ポイントを取られたときにも同じく全身で悔しさを表現するが、それでも楽しそうだ。そんな姿や人柄に魅了された。
彼女の方が一つ先輩だったので、ほんの少しだけ躊躇 もしたが、どうやらつき合っている男はいないらしいと情報を得てから強気になった。
ただ、アルバイトが忙しいとかで、コートに姿を見せることが少ない人だった。たまに見せても、いつの間にか早退して姿を消してしまうので、最初はなかなか距離を詰められず苦労したものだ。のちにキャバクラで夜遅くまで働いているのだと知っても、彼女を想う気持ちに変わりはなかった。
自分自身が貧乏学生で、奨学金を借りた上にバイトをしてかつかつの生活だったせいもあって、キャバ嬢に対しては割のいいバイトができていいなという羨望以外の思いは湧かなかった。
店を突き止めて何度かは客として行ってみたけれど、金のない学生には続かない。肝心の彼女本人から喜ばれていないことも明らかだった。
告白してはふられを繰り返し、いつしか七転び八起きどころではなくなった。
最初は応援してくれていた友人の各務 も、途中からは呆れた様子で、ふられたことを報告しても大して慰めも励ましもしてくれなくなった。
今から思えば、各務自身、自分の恋のことで精いっぱいだったのかもしれない。人のことは七転び八起きというより七転八倒 だななどと笑いながら、自分は告白するかしないかでうじうじと悩み続けていた。やっと告白してつき合い始めたかと思えば、すぐにふられて、萎んだ風船のように落ち込んでいた。結局その恋に関して、各務は一回転んだだけで起き上がるのをやめてしまったようだった。
相手のことを想う気持ちには大差なかっただろうに、現れる行動は人によってかくも違うんだなあと、変なところで感心したりもした。
ふられた回数をカウントしていればギネスに認定されたかもしれない。芸人時代にそんな自虐ネタとして使ったほどふられにふられ、いつの間にか二年半以上の月日が流れた。
先輩にとっては大学で迎える最後のクリスマス、そのイブの深夜のことだ。もう日付は変わっていただろうと思う。
彼女の住むマンション近くの公園で待ち伏せをした。もはやほぼストーカーだ。
雪こそ降ってはいないものの、季節相応に冷え込んだ夜だった。
洒落 た衣類など持っていないくせに、多少なりとも見栄えを良くしようと見栄を張ったがために、防寒が疎 かになっていた。止まらない鼻水に、五つあったポケットティッシュを使い果たした頃、歩いて来る彼女の姿が外灯に照らし出された。
暖かそうで軽そうで柔らかそうで、そして、とても高そうな真っ白なコートと真っ赤なマフラーに身を包み、派手な化粧の彼女は、肘からたくさんの紙袋をぶら下げていた。
「どうしたの、こんな時間に?」
「先輩を待ってたんです」
言葉は白い息になって冬の空に溶けるようで、彼女の耳まで届いているのか心配になった。
「またふられに来たの? しかもクリスマスに? 馬鹿じゃない」
ずいぶんな言われようだが、慣れていた。
黙って白い息だけを漏らしながら、小さな紙袋を差し出した。
相手は同じテニスサークルで、小柄で華奢な体格ながら、コート内を縦横無尽に駆け回る、小気味のよい人だった。似つかわしくない強烈なショットを決めると、全身で喜びを表現する。ポイントを取られたときにも同じく全身で悔しさを表現するが、それでも楽しそうだ。そんな姿や人柄に魅了された。
彼女の方が一つ先輩だったので、ほんの少しだけ
ただ、アルバイトが忙しいとかで、コートに姿を見せることが少ない人だった。たまに見せても、いつの間にか早退して姿を消してしまうので、最初はなかなか距離を詰められず苦労したものだ。のちにキャバクラで夜遅くまで働いているのだと知っても、彼女を想う気持ちに変わりはなかった。
自分自身が貧乏学生で、奨学金を借りた上にバイトをしてかつかつの生活だったせいもあって、キャバ嬢に対しては割のいいバイトができていいなという羨望以外の思いは湧かなかった。
店を突き止めて何度かは客として行ってみたけれど、金のない学生には続かない。肝心の彼女本人から喜ばれていないことも明らかだった。
告白してはふられを繰り返し、いつしか七転び八起きどころではなくなった。
最初は応援してくれていた友人の
今から思えば、各務自身、自分の恋のことで精いっぱいだったのかもしれない。人のことは七転び八起きというより
相手のことを想う気持ちには大差なかっただろうに、現れる行動は人によってかくも違うんだなあと、変なところで感心したりもした。
ふられた回数をカウントしていればギネスに認定されたかもしれない。芸人時代にそんな自虐ネタとして使ったほどふられにふられ、いつの間にか二年半以上の月日が流れた。
先輩にとっては大学で迎える最後のクリスマス、そのイブの深夜のことだ。もう日付は変わっていただろうと思う。
彼女の住むマンション近くの公園で待ち伏せをした。もはやほぼストーカーだ。
雪こそ降ってはいないものの、季節相応に冷え込んだ夜だった。
暖かそうで軽そうで柔らかそうで、そして、とても高そうな真っ白なコートと真っ赤なマフラーに身を包み、派手な化粧の彼女は、肘からたくさんの紙袋をぶら下げていた。
「どうしたの、こんな時間に?」
「先輩を待ってたんです」
言葉は白い息になって冬の空に溶けるようで、彼女の耳まで届いているのか心配になった。
「またふられに来たの? しかもクリスマスに? 馬鹿じゃない」
ずいぶんな言われようだが、慣れていた。
黙って白い息だけを漏らしながら、小さな紙袋を差し出した。