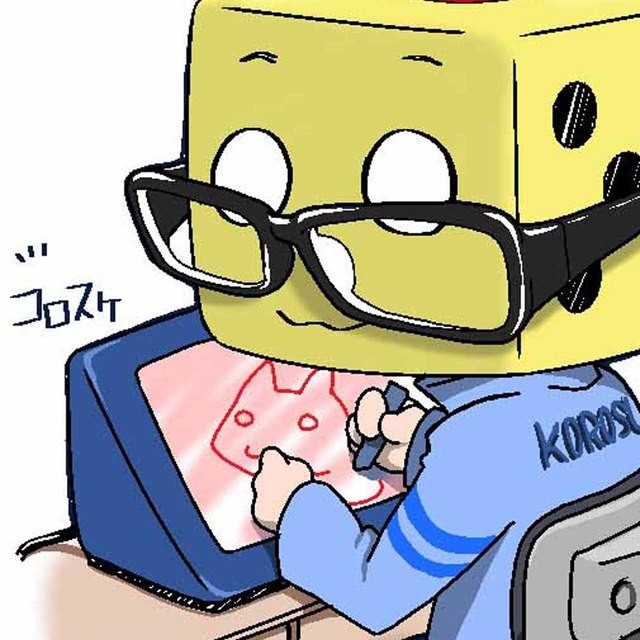鬼河原凛々の名推理
文字数 4,996文字
その日は、間違いなく記念すべき日でした。
少なくとも鬼河原家執事、山田はそのように記憶しておりました。
事の起こりは鬼河原家のご息女、凛々(りり)様が、つぶやいた一言からです。その言葉に思い悩んだ山田は、“あなたのお悩み、出来るだけ解決いたします”という奇妙な謳い文句の探偵事務所に連絡を取ることにいたしました。
「ようこそ、鬼河原家へ。私は鬼河原家執事、山田と申します」
「こんにちは。いやあ広い敷地ですねえ。田舎のコンビニの駐車場ぐらい広いですね」
「……貴方が名探偵様でございますか?」
山田はくっきりとした眉毛を片方だけ、クイっとあげました。
「違います、僕は助手の小林、喜多川と申します」
そう答えた学生服の少年は、軽く会釈をしました。そう言われてみますと、確かに助手っぽい顔つきをしております。彼の職業は何でしょうとクイズを出せば、十人が十人とも『助手』と答えるでしょう。
「助手の……小林様と喜多川様ですか?」
「いえ、昨年度の全日本助手選手権で準グランプリに贈られる「小林」の称号を獲得しました“助手の中の助手”喜多川です」
「助手の中の……助手……」
「はい!助手界では、二番目の位置を重んじます。トップに立ってしまっては真の助手とは言えません。一番ではダメなのです」
助手の中の助手とは何とも不可解な、と山田は思いましたが、はっと我にかえり、
背後の椅子に座るお嬢様を肩越しに見ました。
山田の背後には、細かい装飾の施された、高い背もたれの付いた椅子が置いてありました。
その椅子には、たおやかに座る美少女の姿がございました。
名門鬼河原家息女、鬼河原凛々様は、陽光に煌めく黒髪を揺らし、微笑んでおいでです。伏せ目がちに潤んだ瞳は憂いを帯び、長い睫毛を一層優美に際立たせておりました。その麗しさは、まさにお嬢様オブお嬢様、お嬢様オブザイヤー三年連続受賞級でした。
そのお嬢様の中のお嬢様、凛々様は、ルビーのように輝く唇を、優雅に扇子で隠され、山田と喜多川氏を眺めながら何事もなかったかのように、椅子にお掛けでした。
山田はお嬢様に悟られぬよう、わずかにホッとした表情を浮かべました。そして助手の喜多川氏を睨みつけ、視線だけで何かしらの合図を送りました。
「そっそれで、名探偵様はどちらですか?」
「そうでした。出番ですよ、先生!せんせーい!」
そう言うと、助手の小林、喜多川少年は左手に持っていた手綱を引っ張りました。
のそり、と毛長の絨毯を踏みしめ、牛のような大きな……もとい、牛そのものが室内へと歩み入ったのでございます。
「よ……うこそお越しくださいました。この度は依頼をお受けくださり、誠にありがとうございます」
山田は笑顔を引きつらせながらも丁寧に挨拶をしましたが、名探偵の牛はモウとも鳴かず、フンフンと辺りの匂いを嗅ぐばかりです。
すかさず山田は振り返り、凛々お嬢様の表情を注視しました。しかしお嬢様様は、牛に軽く会釈されただけで、デフォルトの笑顔が崩れる事はございません。
山田は、明らかに落胆した表情で、額に汗をにじませました。そして、つかつかと喜多川少年に歩み寄り、小声で話しかけました。
「どういうことですか!お嬢様はまったく理解されておられないではないですか!」
「おや?お気に召しませんでしたか。ウチの先生の鉄板ボケなのですが」
「ボケではなく、謎をとお願いしたはずですよ!そもそも鬼河原家のご息女とあろうお方が、『探偵になりたい』などとは、お戯れがすぎることなのです。兎に角、分かり易い謎を解いて、名探偵に“さすがはお嬢様の名推理だ!すばらしい!”と言っていただければ、満足されます。なんでもイイからお願いしますよ!」
「僕は出オチのつもりだったのになあ……でも」
そこで助手の小林、喜多川少年は、お嬢様に聞こえるようにわざと声のボリュームを上げました。
「必ずご期待のお答えしますよ!じっちゃんの名にかけて!……ま、祖父は農家ですけどね」
そこで二人は同時に振り返り、お嬢様の反応を伺いました。
お嬢様は最初、不思議そうな顔をされておりましたが、やがて、トンと膝を叩かれます。
山田・喜多川両名は、身を乗り出して次のお嬢様の反応を待ちました。お嬢様は、右手で力強く拳を作り、ビシッと小指を立て、ポーズをお決めになったのでございます。
「なんですか、アレ……」
「応援なさっておいでです。なぜ小指なのかは分かりかねますが」
二人は深く深くため息をつきました。
「山田」
か細く可憐な声と共に、執事山田の頭部へ、すけん、とまぬけな音を立てて、投げた扇子が当たります。お嬢様は、山田を呼ぶときに必ずこうされるのですが、山田がいつどこでなにをしていようとも、必ず扇子が当たるので、特技というより自然現象の一種ではないか、というのが学者の意見でした。
すぐさま山田はお嬢様の元へと駆け寄り、そのか細き声を聞き逃さんと耳をすませました。
「山田、あの牛……私が思うに……」
山田の胸は高まり、心の中で叫びます。
そう!そうなのですお嬢様!名探偵と言われて牛が来た事が、おかしい所なのです。さあ今こそお嬢様の名推理をこの山田にお聞かせ下さいませ!
「ホルスタイン……ではないでしょうか」
山田の心はへし折れそうでした。その場で転がってしまいそうでした。
「お嬢様、誠に僭越ながら申し上げますと、あの牛はジャージー牛でございます」
「まあ……モーモー泣いてますから、私てっきりホルスタインかと思いましたわ」
もしも、悔しさで血の涙が流せるなら、とうの昔に大瀑布級の血涙を流している!と山田は思いました。
お嬢様……牛は皆もーと鳴きます……
「あのーそろそろ現場へ案内してもらってもいいですか?先生は意外に忙しいもので」
「失礼致しました。こちらへどうぞ」
三人と一頭は、お嬢様の部屋のひとつと思われる、部屋へ移動しました。
その部屋は、壁際に棚がぐるりと置かれていて、その上には、大小ヌイグルミが所狭しとひしめきあっておりました。
部屋の真ん中には、赤い服を着た白兎のヌイグルミが寝かされていて、その頭部には深々とナイフが突き刺さっていたのです。
「私が今朝、この部屋に訪れた時には、すでにこのような状態でした」
「○ッフィーですか」
「ただのミッ○ィーではありません。お嬢様が非常に大切にされていた、心の支えにございます。それが……このような無残なお姿に……」
山田はハンカチを取り出し、お嬢様もまた在りし日の親友の姿を思い出し涙するのでした。
「まあここは、先生にお任せしましょう」
牛は部屋の中をのんびりと歩き回り、尻尾をふりふり臭いを嗅いでいます。
その間、お嬢様は喜多川少年にしずしずと近寄り、そよ風に揺れる風鈴のように涼やかな声で話しかけられたのでございます。
「ジャージー喜多川様。ひとつよろしいでしょうか?」
「ジャニー喜多川みたいに言わないで下さい。僕は“助手の小林”こと、喜多川です」
「私、考えますに」
喜多川少年は、ついに来たか、と身構えた。
もはやどんな些細な考えでも、むりやり絶賛してやる。こんな面倒な依頼はサクッと終わらせて、僕は週末のデートに備えたいのだ。数ヶ月のアプローチのすえ、やっと先輩(20歳♂)からルーブル美術館展に誘われたのだ。先輩の僕を見る目の熱っぽさは、間違いなく愛を感じる。先輩探偵、僕助手のBL探偵!ふふ……待っていてください。先輩のダメなところもダメダメなところも全部僕が愛してあげます!
喜多川少年が、妄想を暴走させている間に、お嬢様はその考えを口にされました。
「『ナニ』とは、ふりかけでしょうか?」
「は?」
「先ほど、“じっちゃんのナニかけて”と言っておられましたので、“ナニ”とは何かを考えておりました。熟慮しました結果、ナニとは“ふりかけ”なのでは……」
「違います」
「えっ……?」
お嬢様は明らかにショックを受けたご様子で、二、三歩後ろへよろめかれましたが、すかさず山田が助けに入ります。
「百歩譲って、ナニがふりかけだったとして、あの状況で突然“じいちゃんのふりかけかけて!”なんて絶叫しないでしょ。どんな変人奇人なんですか。アレはあのセリフを決め台詞にしている探偵がいましてですね、それは漫画なんですけども……」
地獄。
喜多川少年にとっては、まさに地獄。
たいしてウケもしなかったボケを天然のボケで返され、それを解説しなければならないのです。
「喜多川様、どうかそのあたりでご容赦下さい。それより見てください。名探偵様がこれを私にお渡し下さいました」
「これは……オモチャのナイフ?」
まったく進展が見られないことに業を煮やした山田は、強硬手段に出ました。自作自演で事件を捏造してお嬢様に解決していただくという0.2秒で考えた作戦を諦め、牛の名探偵が起こした偶然をこじ付けて、無理矢理解決しようとしているのです。
「お嬢さまご安心ください。○ッフィー様に刺さっていたと思われておりましたナイフは、実はオモチャだったのでございます。あの通りミッ○ィー様は無事に……」
「きゃああっ⁉︎」
悲鳴をあげたお嬢様の視線の先には、名探偵の牛のお尻からモリモリとわき出る茶色の物体に押しつぶされる、哀れな白兎の姿でございました。
「申し訳ありませんでした」
正門へと通じる道の途中、鬼の形相で立つ山田に、喜多川少年は深々と頭を下げました。
ベタなボケに対してお嬢様をツッこませる。もとい、難解な謎をお嬢様に解決していただくという、史上まれに見るどうでもいい依頼をこなせず、名探偵とその助手は屋敷を去ることにしました。
「先生の落し物のせいで、○ッフィーをメラニンにしちゃったんですから、ちゃんと謝ってください」
「余計なことは言わないでよろしい!クリーニング代は後ほど請求いたしますので、覚悟していたください」
山田は眉毛をつり上げて、牛を睨みつけました。
流石に牛といえど、非難の視線を感じずにはいられなかったのか、地面に鼻をこすりつけ、申し訳なさそうに……してはいませんでした。
ただ地面の草をもむもむしているだけでした。しょせん奇蹄目に、ヒト科に興味を持てというのは無理があります。
喜多川少年は手綱を引っ張りますが、なぜか牛はその場から動こうとしません。いくら引っ張っても、もーもー鳴くばかりです。
「もうこれ以上、名探偵の名を汚すことは出来ませんって、帰りましょう先生」
山田の後ろに隠れ、大切な友達をウ○コまみれにされた悲しみに打ちひしがれていたお嬢様は、喜多川少年のその言葉を聞き、よろよろと前へ歩み出られました。
「お嬢様?」
山田の声も耳に入らず、ただ喜多川少年の言葉が、頭の中をぐるぐると回ります。
やがてそれは一点へと収束して行き、やがて稲光のようにその身を打ったのでございます。
(もうこれ以上、名探偵の名を……
もうこれいじょう、めいたんていの……
モーこれいじょう、メーたんていの……!)
「山田」
「あはっ痛あっ⁉︎」
いつものように、お嬢様は扇子で山田を呼びました。しかし、たった今発見した事実に、あまりにも興奮し、それを抑えきれず、横に立つ山田の顔めがけて扇子で突きを入れてしましました。扇子は、まるで秋田新幹線こまちがこまちトンネルに突入するが如く、山田の左鼻の穴に高速で吸い込まれ、見事にぶっ刺さりました。
「私、気がつきました」
「お、お嬢様」
山田は痛すぎて感覚の無くなった鼻を抑えながら、確信に満ちたお嬢様の目を見ました。
「名探偵が来るはずが、牛が来る……これではメー探偵じゃなくてモー探偵になってしまいます!そうですね!山田!」
「お嬢様あああっ!!」
鬼河原凛々の名推理。
この偉業を讃えるかのように、庭の木々からは小鳥たちの歌声が流れ、赤青様々な花が次々と咲き始めます。天の雲が割れ、陽光がお嬢様の周りを照らしました。そこからは光り輝く天使が、楽器を手に舞い降り、口々に賞賛の言葉をあびせました。
そしてこの日は「名探偵の日」として広く国民に認知され、史上初の三連休になったのでした。
少なくとも鬼河原家執事、山田はそのように記憶しておりました。
事の起こりは鬼河原家のご息女、凛々(りり)様が、つぶやいた一言からです。その言葉に思い悩んだ山田は、“あなたのお悩み、出来るだけ解決いたします”という奇妙な謳い文句の探偵事務所に連絡を取ることにいたしました。
「ようこそ、鬼河原家へ。私は鬼河原家執事、山田と申します」
「こんにちは。いやあ広い敷地ですねえ。田舎のコンビニの駐車場ぐらい広いですね」
「……貴方が名探偵様でございますか?」
山田はくっきりとした眉毛を片方だけ、クイっとあげました。
「違います、僕は助手の小林、喜多川と申します」
そう答えた学生服の少年は、軽く会釈をしました。そう言われてみますと、確かに助手っぽい顔つきをしております。彼の職業は何でしょうとクイズを出せば、十人が十人とも『助手』と答えるでしょう。
「助手の……小林様と喜多川様ですか?」
「いえ、昨年度の全日本助手選手権で準グランプリに贈られる「小林」の称号を獲得しました“助手の中の助手”喜多川です」
「助手の中の……助手……」
「はい!助手界では、二番目の位置を重んじます。トップに立ってしまっては真の助手とは言えません。一番ではダメなのです」
助手の中の助手とは何とも不可解な、と山田は思いましたが、はっと我にかえり、
背後の椅子に座るお嬢様を肩越しに見ました。
山田の背後には、細かい装飾の施された、高い背もたれの付いた椅子が置いてありました。
その椅子には、たおやかに座る美少女の姿がございました。
名門鬼河原家息女、鬼河原凛々様は、陽光に煌めく黒髪を揺らし、微笑んでおいでです。伏せ目がちに潤んだ瞳は憂いを帯び、長い睫毛を一層優美に際立たせておりました。その麗しさは、まさにお嬢様オブお嬢様、お嬢様オブザイヤー三年連続受賞級でした。
そのお嬢様の中のお嬢様、凛々様は、ルビーのように輝く唇を、優雅に扇子で隠され、山田と喜多川氏を眺めながら何事もなかったかのように、椅子にお掛けでした。
山田はお嬢様に悟られぬよう、わずかにホッとした表情を浮かべました。そして助手の喜多川氏を睨みつけ、視線だけで何かしらの合図を送りました。
「そっそれで、名探偵様はどちらですか?」
「そうでした。出番ですよ、先生!せんせーい!」
そう言うと、助手の小林、喜多川少年は左手に持っていた手綱を引っ張りました。
のそり、と毛長の絨毯を踏みしめ、牛のような大きな……もとい、牛そのものが室内へと歩み入ったのでございます。
「よ……うこそお越しくださいました。この度は依頼をお受けくださり、誠にありがとうございます」
山田は笑顔を引きつらせながらも丁寧に挨拶をしましたが、名探偵の牛はモウとも鳴かず、フンフンと辺りの匂いを嗅ぐばかりです。
すかさず山田は振り返り、凛々お嬢様の表情を注視しました。しかしお嬢様様は、牛に軽く会釈されただけで、デフォルトの笑顔が崩れる事はございません。
山田は、明らかに落胆した表情で、額に汗をにじませました。そして、つかつかと喜多川少年に歩み寄り、小声で話しかけました。
「どういうことですか!お嬢様はまったく理解されておられないではないですか!」
「おや?お気に召しませんでしたか。ウチの先生の鉄板ボケなのですが」
「ボケではなく、謎をとお願いしたはずですよ!そもそも鬼河原家のご息女とあろうお方が、『探偵になりたい』などとは、お戯れがすぎることなのです。兎に角、分かり易い謎を解いて、名探偵に“さすがはお嬢様の名推理だ!すばらしい!”と言っていただければ、満足されます。なんでもイイからお願いしますよ!」
「僕は出オチのつもりだったのになあ……でも」
そこで助手の小林、喜多川少年は、お嬢様に聞こえるようにわざと声のボリュームを上げました。
「必ずご期待のお答えしますよ!じっちゃんの名にかけて!……ま、祖父は農家ですけどね」
そこで二人は同時に振り返り、お嬢様の反応を伺いました。
お嬢様は最初、不思議そうな顔をされておりましたが、やがて、トンと膝を叩かれます。
山田・喜多川両名は、身を乗り出して次のお嬢様の反応を待ちました。お嬢様は、右手で力強く拳を作り、ビシッと小指を立て、ポーズをお決めになったのでございます。
「なんですか、アレ……」
「応援なさっておいでです。なぜ小指なのかは分かりかねますが」
二人は深く深くため息をつきました。
「山田」
か細く可憐な声と共に、執事山田の頭部へ、すけん、とまぬけな音を立てて、投げた扇子が当たります。お嬢様は、山田を呼ぶときに必ずこうされるのですが、山田がいつどこでなにをしていようとも、必ず扇子が当たるので、特技というより自然現象の一種ではないか、というのが学者の意見でした。
すぐさま山田はお嬢様の元へと駆け寄り、そのか細き声を聞き逃さんと耳をすませました。
「山田、あの牛……私が思うに……」
山田の胸は高まり、心の中で叫びます。
そう!そうなのですお嬢様!名探偵と言われて牛が来た事が、おかしい所なのです。さあ今こそお嬢様の名推理をこの山田にお聞かせ下さいませ!
「ホルスタイン……ではないでしょうか」
山田の心はへし折れそうでした。その場で転がってしまいそうでした。
「お嬢様、誠に僭越ながら申し上げますと、あの牛はジャージー牛でございます」
「まあ……モーモー泣いてますから、私てっきりホルスタインかと思いましたわ」
もしも、悔しさで血の涙が流せるなら、とうの昔に大瀑布級の血涙を流している!と山田は思いました。
お嬢様……牛は皆もーと鳴きます……
「あのーそろそろ現場へ案内してもらってもいいですか?先生は意外に忙しいもので」
「失礼致しました。こちらへどうぞ」
三人と一頭は、お嬢様の部屋のひとつと思われる、部屋へ移動しました。
その部屋は、壁際に棚がぐるりと置かれていて、その上には、大小ヌイグルミが所狭しとひしめきあっておりました。
部屋の真ん中には、赤い服を着た白兎のヌイグルミが寝かされていて、その頭部には深々とナイフが突き刺さっていたのです。
「私が今朝、この部屋に訪れた時には、すでにこのような状態でした」
「○ッフィーですか」
「ただのミッ○ィーではありません。お嬢様が非常に大切にされていた、心の支えにございます。それが……このような無残なお姿に……」
山田はハンカチを取り出し、お嬢様もまた在りし日の親友の姿を思い出し涙するのでした。
「まあここは、先生にお任せしましょう」
牛は部屋の中をのんびりと歩き回り、尻尾をふりふり臭いを嗅いでいます。
その間、お嬢様は喜多川少年にしずしずと近寄り、そよ風に揺れる風鈴のように涼やかな声で話しかけられたのでございます。
「ジャージー喜多川様。ひとつよろしいでしょうか?」
「ジャニー喜多川みたいに言わないで下さい。僕は“助手の小林”こと、喜多川です」
「私、考えますに」
喜多川少年は、ついに来たか、と身構えた。
もはやどんな些細な考えでも、むりやり絶賛してやる。こんな面倒な依頼はサクッと終わらせて、僕は週末のデートに備えたいのだ。数ヶ月のアプローチのすえ、やっと先輩(20歳♂)からルーブル美術館展に誘われたのだ。先輩の僕を見る目の熱っぽさは、間違いなく愛を感じる。先輩探偵、僕助手のBL探偵!ふふ……待っていてください。先輩のダメなところもダメダメなところも全部僕が愛してあげます!
喜多川少年が、妄想を暴走させている間に、お嬢様はその考えを口にされました。
「『ナニ』とは、ふりかけでしょうか?」
「は?」
「先ほど、“じっちゃんのナニかけて”と言っておられましたので、“ナニ”とは何かを考えておりました。熟慮しました結果、ナニとは“ふりかけ”なのでは……」
「違います」
「えっ……?」
お嬢様は明らかにショックを受けたご様子で、二、三歩後ろへよろめかれましたが、すかさず山田が助けに入ります。
「百歩譲って、ナニがふりかけだったとして、あの状況で突然“じいちゃんのふりかけかけて!”なんて絶叫しないでしょ。どんな変人奇人なんですか。アレはあのセリフを決め台詞にしている探偵がいましてですね、それは漫画なんですけども……」
地獄。
喜多川少年にとっては、まさに地獄。
たいしてウケもしなかったボケを天然のボケで返され、それを解説しなければならないのです。
「喜多川様、どうかそのあたりでご容赦下さい。それより見てください。名探偵様がこれを私にお渡し下さいました」
「これは……オモチャのナイフ?」
まったく進展が見られないことに業を煮やした山田は、強硬手段に出ました。自作自演で事件を捏造してお嬢様に解決していただくという0.2秒で考えた作戦を諦め、牛の名探偵が起こした偶然をこじ付けて、無理矢理解決しようとしているのです。
「お嬢さまご安心ください。○ッフィー様に刺さっていたと思われておりましたナイフは、実はオモチャだったのでございます。あの通りミッ○ィー様は無事に……」
「きゃああっ⁉︎」
悲鳴をあげたお嬢様の視線の先には、名探偵の牛のお尻からモリモリとわき出る茶色の物体に押しつぶされる、哀れな白兎の姿でございました。
「申し訳ありませんでした」
正門へと通じる道の途中、鬼の形相で立つ山田に、喜多川少年は深々と頭を下げました。
ベタなボケに対してお嬢様をツッこませる。もとい、難解な謎をお嬢様に解決していただくという、史上まれに見るどうでもいい依頼をこなせず、名探偵とその助手は屋敷を去ることにしました。
「先生の落し物のせいで、○ッフィーをメラニンにしちゃったんですから、ちゃんと謝ってください」
「余計なことは言わないでよろしい!クリーニング代は後ほど請求いたしますので、覚悟していたください」
山田は眉毛をつり上げて、牛を睨みつけました。
流石に牛といえど、非難の視線を感じずにはいられなかったのか、地面に鼻をこすりつけ、申し訳なさそうに……してはいませんでした。
ただ地面の草をもむもむしているだけでした。しょせん奇蹄目に、ヒト科に興味を持てというのは無理があります。
喜多川少年は手綱を引っ張りますが、なぜか牛はその場から動こうとしません。いくら引っ張っても、もーもー鳴くばかりです。
「もうこれ以上、名探偵の名を汚すことは出来ませんって、帰りましょう先生」
山田の後ろに隠れ、大切な友達をウ○コまみれにされた悲しみに打ちひしがれていたお嬢様は、喜多川少年のその言葉を聞き、よろよろと前へ歩み出られました。
「お嬢様?」
山田の声も耳に入らず、ただ喜多川少年の言葉が、頭の中をぐるぐると回ります。
やがてそれは一点へと収束して行き、やがて稲光のようにその身を打ったのでございます。
(もうこれ以上、名探偵の名を……
もうこれいじょう、めいたんていの……
モーこれいじょう、メーたんていの……!)
「山田」
「あはっ痛あっ⁉︎」
いつものように、お嬢様は扇子で山田を呼びました。しかし、たった今発見した事実に、あまりにも興奮し、それを抑えきれず、横に立つ山田の顔めがけて扇子で突きを入れてしましました。扇子は、まるで秋田新幹線こまちがこまちトンネルに突入するが如く、山田の左鼻の穴に高速で吸い込まれ、見事にぶっ刺さりました。
「私、気がつきました」
「お、お嬢様」
山田は痛すぎて感覚の無くなった鼻を抑えながら、確信に満ちたお嬢様の目を見ました。
「名探偵が来るはずが、牛が来る……これではメー探偵じゃなくてモー探偵になってしまいます!そうですね!山田!」
「お嬢様あああっ!!」
鬼河原凛々の名推理。
この偉業を讃えるかのように、庭の木々からは小鳥たちの歌声が流れ、赤青様々な花が次々と咲き始めます。天の雲が割れ、陽光がお嬢様の周りを照らしました。そこからは光り輝く天使が、楽器を手に舞い降り、口々に賞賛の言葉をあびせました。
そしてこの日は「名探偵の日」として広く国民に認知され、史上初の三連休になったのでした。