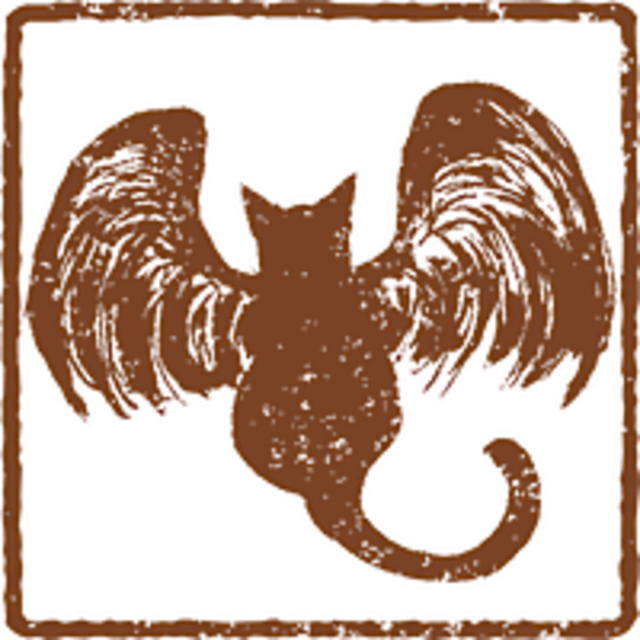その3黒犬小道
文字数 3,286文字
サーリス教授と黒い犬
灰色の雲の向こうからぼんやりと白い太陽が照らし、からりと乾いた風が吹く。こんな日をイギリスでは「よく晴れた冬の日」と呼ぶ。さらに青い空が見えた場合は「奇跡」と。
ともあれ。
サーリス教授は歩く。上質のウールのコートを着てカシミヤのマフラーを巻き、ほどよく固まった雪道を踏みしめて。すぐ隣をのっしのっしと、黒いダウンジャケットを着込んだ背の高い青年が歩いている。安くて丈夫な実用本位の製品で、学生に人気のアウトドア量販店の定番商品。実際彼は学生だった。
「さすが水際、冷えますね。って言うか湖もかっちかちだ」
「ああ、ここは毎年そうだよ」
「鎧に身を固めた騎士を乗せ、馬が駆け抜けるってのはこう言う湖なんですね」
「きっとそうだ」
葉を落とした広葉樹林は黒々と立ち尽くす骨の群れ。囲まれた湖は十月の終わりから氷が張り、十二月にはさざ波の形のまま凍結する。分厚い氷に根元をとらえられ、干からびた葦は朽ち倒れることもできずただカラカラと風に鳴る。
「今日は晴れてるから、湖まで歩こうか」
「はい!」
教授の一声で、ルドルフ・フォン・ベーレンドルフは尻尾を振りそうな勢いで立ち上がった。
「冷えるからあたたかくするんだよ」
「はい!」
そんな誘いで始まった散歩が続くこと30分。
湖岸を縁取る小道は一旦水辺を離れ、落ち葉で埋まった広葉樹の林の中へと分け入る。途中で渡った反り橋の下、湖に注ぐ小川もまた完全に凍りついている。
「鴨や白鳥はどうしているんだろう」
「この先にもっと大きな川がある。そっちにいるのだろう。たまに、家の裏庭まで餌を求めてやって来るよ」
「わぉ! 鴨が? 勇気あるなあ、そのままオーブンの中に案内されてもおかしくないのに」
「君の発想は、実に意外性に満ちているね」
「鴨美味しいですよ?」
「うん、美味しいね」
教授は笑う。マフラーに顏をうずめ、軽やかな声を立てて。それを見ているだけで、ルドルフは幸せな気持ちになる。
きぃ、きぃ、きぃ。
通り抜ける風に、青銅の道しるべがゆれる。歳月とともに表面は黒ずみ、すり減っていたがそれでも刻印された優美な書体は読めた。
「黒犬通り……」
白い息を吐き、ルドルフは読み上げる。
「いるんですか、ブラックドッグ」
「いたよ。昔はね」
「うれしそうですね」
「ああ。ここの黒犬は大人しくて、優しいんだ」
不意に林が開ける。広がるのは平らな空き地と、凍てついた湖。曲がりくねった小道はいつの間にか、水辺に戻っていた。それも正面から向き合う形で。
「うわあ、すっごい! 湖が、目の前に!」
「少し休もうか」
「……はい」
ルドルフは背負っていたリュックを下ろした。
「ここ、火を炊いてもOKですよね」
「うん、夏はキャンプでにぎわうよ」
「良かった」
リュックから出したのはキャンプ用の小型コンロ、小さな鍋、紙パックに入った牛乳にマグカップが二つ、そして小さな袋に入った粉末のココア。
「まるで手品だね」
「前は缶ごと持ち歩いてたんですけど、最近は一回分ずつ小分けになってるココアがありますから。こうやって必要な分だけ持ってくればいい」
スノーブーツを履いた足でザクザクと雪を踏み固めると、手際よくコンロを設置する。安定性を確かめてから点火、火力を調節。
カップではかって二杯分、小鍋に牛乳をそそぎ、あたため始める。慣れた手つきだ。
「聞かせてくださいな。黒犬のこと」
「わかったよ」
※
自分でも、最初は夢かと思ったんだ。子供の頃からまずは理屈で物事を考える性質だったからね。
ここを歩くたびに、誰かに見られているような気がした。見回しても誰もいない。不思議と怖いとは思わなかった……恐ろしい黒妖犬の伝説を知っていたはずなのにね。
何となく。(私の性質とは相反するが、にもかかわらず私は直感を信じた)
何となく、感じていたのだ。視線の主に害意は無い。むし見守っているのだと。
5歳の冬、迷子になった。軽い気持ちで散歩に出かけたら、急に天候が変わってね。羽毛のような雪がひとひら、ふたひら。気づけばあっと言う間に吹雪だ。右を向いても、左を向いても雪と風の壁。歩くことはできても、一向に家に近づけない。手探りで、泣きながら歩いた。顏に雪がぴしぴしと吹きつけて痛かった。父も母も、みんな探してるんだろうな。だけど牧草地はあまりに広く、曲がりくねった小道がそこ、ここに口を開けている。
そんな時、あの音を聞いたんだ。風に紛れてキィ、キィと道しるべの看板が軋む音が。
そうだ、ここに居たんだ。
君と今歩いてきた、『黒犬通り』に。
不意に風が遮られた。
あたたかく、大きな生き物の体を感じた。すぐそばに、居た。ずっと私を見守っていた『誰か』が。
それは、大きな黒い犬だった。
優しい銀色の瞳が見つめていた。『子牛ほど』と伝承にはある。だが幼い私には、それこそ山のように大きく感じられた。
ゆっくりと黒い犬はうずくまった。
『乗りなさい』
そう言われた気がした。大きな背中にしがみつく。毛皮の表面は雪に濡れていたが、内側はあたたかかった。
雪の中を、飛んだ。
実際には走っていたのだろうけど、そう感じた。まったく、あの黒い大きな犬ときたら! 飛ぶ合間に、気まぐれに地面に足をつけていたんだ。それだけ早く走っているのに、少しも恐怖を感じない。振り落とされたらどうする?
あり得ない。彼は決して私を傷つけない。何も恐れることは無い。ただ私は、あたたかな黒い毛並にうずもれていればいい……。
ふっと、夢は終わった。
炎に溶ける雪片のようにはかなく。
私は踏み固められた雪の上に立っていた。
目の前には懐かしいわが家の明かり。黒犬は私に寄り添い、風と雪から守っていた。鼻面を空に向け、長々と吠えた。
雷のとどろくような音。
扉が開き、両親が駆けて来る。警察官、消防士、近所の人たち。
母に抱きしめられた時には、黒犬の姿はもう、どこにもなかった。
家の中に連れて行かれて、父と母のキスとハグにもみくちゃにされ、乾いた服に着替えさせられ、暖炉の前の寝椅子に寝かされて。かけつけた医師から『申し分の無い健康状態だ』と診断がおりてから、ようやく聞かれた。
「今までどこに?」
「……犬といたの。大きな犬」
当時は今よりずっと犬の飼育がおおらかでね。特にここのような田舎には、縄張りを好き勝手に散歩する飼い犬はいくらでもいた。雪の夜にも牧草地を歩き回る仕事熱心な牧羊犬の一匹が、本能にもとづき迷子を助けたのだろう。
大人たちはそう結論づけた。
しかし、翌朝私は確かに見たんだ。
疲れ切って眠る両親の間から抜け出して、色鮮やかな手編みのブランケットを羽織って外に飛び出した時。
奇跡のような青空の下、輝く日差しに照されて、植え込みの陰に残った一つの足跡を……。
どんな牧羊犬も遠く及ばない、大きな大きな犬の足跡を。
※
「そりゃあもう大きな足跡だった。母のお気に入りのケーキ皿くらいはあったかな」
「黒犬の中には、道に迷った子供を助けるのもいるそうですね」
サーリス教授はうなずいた。湯気の立つカップを受け取りながら。
「大人になってから知ったよ」
そうして二人は肩を寄せ合い、ココアを飲んだ。キャンプ用の折り畳み式の持ち手のマグカップで。
「金属製だから、もっと熱いかと思ったよ」
「チタン製ですから。飲み口は熱くならないんですよ」
刹那、雲が吹き払われた。灰色の空が切り取られ、まばゆい青空が現れる。
凍った湖が輝きに満たされる。
「まぶしいなあ……」
「きれいだね」
「はい……」
奇跡の一瞬の中、ルドルフは愛しい人を見つめる。
「きれいです」
湖のきらめきを宿し、その瞳は銀色に輝いていた。
「ああ」
サーリス教授は知っている。
黒犬は今、ここにいる。
灰色の雲の向こうからぼんやりと白い太陽が照らし、からりと乾いた風が吹く。こんな日をイギリスでは「よく晴れた冬の日」と呼ぶ。さらに青い空が見えた場合は「奇跡」と。
ともあれ。
サーリス教授は歩く。上質のウールのコートを着てカシミヤのマフラーを巻き、ほどよく固まった雪道を踏みしめて。すぐ隣をのっしのっしと、黒いダウンジャケットを着込んだ背の高い青年が歩いている。安くて丈夫な実用本位の製品で、学生に人気のアウトドア量販店の定番商品。実際彼は学生だった。
「さすが水際、冷えますね。って言うか湖もかっちかちだ」
「ああ、ここは毎年そうだよ」
「鎧に身を固めた騎士を乗せ、馬が駆け抜けるってのはこう言う湖なんですね」
「きっとそうだ」
葉を落とした広葉樹林は黒々と立ち尽くす骨の群れ。囲まれた湖は十月の終わりから氷が張り、十二月にはさざ波の形のまま凍結する。分厚い氷に根元をとらえられ、干からびた葦は朽ち倒れることもできずただカラカラと風に鳴る。
「今日は晴れてるから、湖まで歩こうか」
「はい!」
教授の一声で、ルドルフ・フォン・ベーレンドルフは尻尾を振りそうな勢いで立ち上がった。
「冷えるからあたたかくするんだよ」
「はい!」
そんな誘いで始まった散歩が続くこと30分。
湖岸を縁取る小道は一旦水辺を離れ、落ち葉で埋まった広葉樹の林の中へと分け入る。途中で渡った反り橋の下、湖に注ぐ小川もまた完全に凍りついている。
「鴨や白鳥はどうしているんだろう」
「この先にもっと大きな川がある。そっちにいるのだろう。たまに、家の裏庭まで餌を求めてやって来るよ」
「わぉ! 鴨が? 勇気あるなあ、そのままオーブンの中に案内されてもおかしくないのに」
「君の発想は、実に意外性に満ちているね」
「鴨美味しいですよ?」
「うん、美味しいね」
教授は笑う。マフラーに顏をうずめ、軽やかな声を立てて。それを見ているだけで、ルドルフは幸せな気持ちになる。
きぃ、きぃ、きぃ。
通り抜ける風に、青銅の道しるべがゆれる。歳月とともに表面は黒ずみ、すり減っていたがそれでも刻印された優美な書体は読めた。
「黒犬通り……」
白い息を吐き、ルドルフは読み上げる。
「いるんですか、ブラックドッグ」
「いたよ。昔はね」
「うれしそうですね」
「ああ。ここの黒犬は大人しくて、優しいんだ」
不意に林が開ける。広がるのは平らな空き地と、凍てついた湖。曲がりくねった小道はいつの間にか、水辺に戻っていた。それも正面から向き合う形で。
「うわあ、すっごい! 湖が、目の前に!」
「少し休もうか」
「……はい」
ルドルフは背負っていたリュックを下ろした。
「ここ、火を炊いてもOKですよね」
「うん、夏はキャンプでにぎわうよ」
「良かった」
リュックから出したのはキャンプ用の小型コンロ、小さな鍋、紙パックに入った牛乳にマグカップが二つ、そして小さな袋に入った粉末のココア。
「まるで手品だね」
「前は缶ごと持ち歩いてたんですけど、最近は一回分ずつ小分けになってるココアがありますから。こうやって必要な分だけ持ってくればいい」
スノーブーツを履いた足でザクザクと雪を踏み固めると、手際よくコンロを設置する。安定性を確かめてから点火、火力を調節。
カップではかって二杯分、小鍋に牛乳をそそぎ、あたため始める。慣れた手つきだ。
「聞かせてくださいな。黒犬のこと」
「わかったよ」
※
自分でも、最初は夢かと思ったんだ。子供の頃からまずは理屈で物事を考える性質だったからね。
ここを歩くたびに、誰かに見られているような気がした。見回しても誰もいない。不思議と怖いとは思わなかった……恐ろしい黒妖犬の伝説を知っていたはずなのにね。
何となく。(私の性質とは相反するが、にもかかわらず私は直感を信じた)
何となく、感じていたのだ。視線の主に害意は無い。むし見守っているのだと。
5歳の冬、迷子になった。軽い気持ちで散歩に出かけたら、急に天候が変わってね。羽毛のような雪がひとひら、ふたひら。気づけばあっと言う間に吹雪だ。右を向いても、左を向いても雪と風の壁。歩くことはできても、一向に家に近づけない。手探りで、泣きながら歩いた。顏に雪がぴしぴしと吹きつけて痛かった。父も母も、みんな探してるんだろうな。だけど牧草地はあまりに広く、曲がりくねった小道がそこ、ここに口を開けている。
そんな時、あの音を聞いたんだ。風に紛れてキィ、キィと道しるべの看板が軋む音が。
そうだ、ここに居たんだ。
君と今歩いてきた、『黒犬通り』に。
不意に風が遮られた。
あたたかく、大きな生き物の体を感じた。すぐそばに、居た。ずっと私を見守っていた『誰か』が。
それは、大きな黒い犬だった。
優しい銀色の瞳が見つめていた。『子牛ほど』と伝承にはある。だが幼い私には、それこそ山のように大きく感じられた。
ゆっくりと黒い犬はうずくまった。
『乗りなさい』
そう言われた気がした。大きな背中にしがみつく。毛皮の表面は雪に濡れていたが、内側はあたたかかった。
雪の中を、飛んだ。
実際には走っていたのだろうけど、そう感じた。まったく、あの黒い大きな犬ときたら! 飛ぶ合間に、気まぐれに地面に足をつけていたんだ。それだけ早く走っているのに、少しも恐怖を感じない。振り落とされたらどうする?
あり得ない。彼は決して私を傷つけない。何も恐れることは無い。ただ私は、あたたかな黒い毛並にうずもれていればいい……。
ふっと、夢は終わった。
炎に溶ける雪片のようにはかなく。
私は踏み固められた雪の上に立っていた。
目の前には懐かしいわが家の明かり。黒犬は私に寄り添い、風と雪から守っていた。鼻面を空に向け、長々と吠えた。
雷のとどろくような音。
扉が開き、両親が駆けて来る。警察官、消防士、近所の人たち。
母に抱きしめられた時には、黒犬の姿はもう、どこにもなかった。
家の中に連れて行かれて、父と母のキスとハグにもみくちゃにされ、乾いた服に着替えさせられ、暖炉の前の寝椅子に寝かされて。かけつけた医師から『申し分の無い健康状態だ』と診断がおりてから、ようやく聞かれた。
「今までどこに?」
「……犬といたの。大きな犬」
当時は今よりずっと犬の飼育がおおらかでね。特にここのような田舎には、縄張りを好き勝手に散歩する飼い犬はいくらでもいた。雪の夜にも牧草地を歩き回る仕事熱心な牧羊犬の一匹が、本能にもとづき迷子を助けたのだろう。
大人たちはそう結論づけた。
しかし、翌朝私は確かに見たんだ。
疲れ切って眠る両親の間から抜け出して、色鮮やかな手編みのブランケットを羽織って外に飛び出した時。
奇跡のような青空の下、輝く日差しに照されて、植え込みの陰に残った一つの足跡を……。
どんな牧羊犬も遠く及ばない、大きな大きな犬の足跡を。
※
「そりゃあもう大きな足跡だった。母のお気に入りのケーキ皿くらいはあったかな」
「黒犬の中には、道に迷った子供を助けるのもいるそうですね」
サーリス教授はうなずいた。湯気の立つカップを受け取りながら。
「大人になってから知ったよ」
そうして二人は肩を寄せ合い、ココアを飲んだ。キャンプ用の折り畳み式の持ち手のマグカップで。
「金属製だから、もっと熱いかと思ったよ」
「チタン製ですから。飲み口は熱くならないんですよ」
刹那、雲が吹き払われた。灰色の空が切り取られ、まばゆい青空が現れる。
凍った湖が輝きに満たされる。
「まぶしいなあ……」
「きれいだね」
「はい……」
奇跡の一瞬の中、ルドルフは愛しい人を見つめる。
「きれいです」
湖のきらめきを宿し、その瞳は銀色に輝いていた。
「ああ」
サーリス教授は知っている。
黒犬は今、ここにいる。