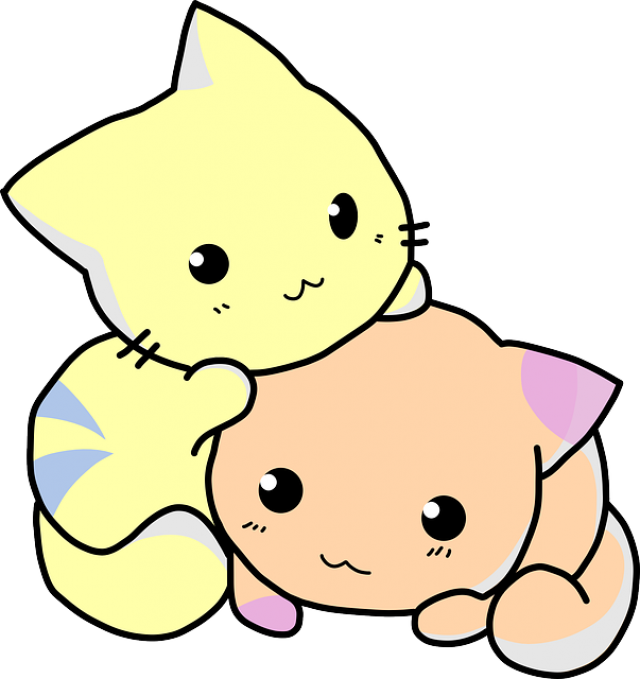流れ落ちる水のように
文字数 5,341文字

ある『ろくでなし』の話をしよう。
その男は、ごく普通の、ありふれた一人に過ぎなかった。それでも敢えて言うなら、多少、正義感が強かったとも言えるだろう。そんな男が『ろくでなし』と呼びたくなるような人生を歩んだのは、そもそもそんな素質を元来持ち合わせていたからではないかと考える。それが、あることを切っ掛けにして表面に出てきただけなのかもしれない。
男は職場で小さな不正を見つけた。それは偶然目にしたものだったが、見てしまった以上、男の性格上、黙って見過ごすことは出来なかった。それに、本当に小さく些細な出来事であったため、告発をためらう程ではないと、即座に注意したものだ。
「おい! なにやってんだよ」
言い方は悪いが、いたって普通の調子で声を掛けたつもりだ。男の表情も怒った風ではなく普段のそれである。そんな男に相手は、
「あっ、すまん。どうやら間違えたようだ」と即座に非を認めたため、この件はすぐに収まり、男の記憶にも残らないくらい些細な出来事になるはずだった。もしここで相手が反発していれば、それなりに揉めていたかもしれないが、かえってその方が良かったかもしれなかったと、男はだいぶ後で思ったようだ。
これ以降、不思議なことに男は職場で他の者から距離を置かれているような感じを覚えるようになった。それが具体的に何かを指すものではなかったが、漠然とそう思えたようだ。それはただの勘違いか、気のせいか。それを強いて言えば、同僚との会話が短く切り上げられるようになった、誰かとすれ違うと必要以上に距離を置かれているような気がする、と言った類のものである。
しかしそれらが顕著化した時には、言葉の通り『時すでに遅し』の状態であった。それでも身に覚えのない男にとっては不思議でならない。そこで男は雇い主に相談をしたが、それが
その甲斐あって、なんとか事を収めることは出来たが、それは飽くまで表面的で一時的なものでしかなかったようだ。徐々にではあるが男の仕事量は減り続け、職場でも孤立するようになった。
そしてとうとう、我慢の限界を迎えた男は捨て台詞を吐いて、その職場を去ったが、次の職場は割と容易に探すことが出来たようだ。それで心機一転、新しい職場では寡黙に働き、子供も生まれたことにより、男にとっては順風満帆な人生を歩んだ、と言いたいところだが、どこでも不正は大なり小なり付き物である。それを無視するか自らの正義を押し通すのか。その選択に迫らた時、先例を省みり、男は無視すると決めていたようだ。
しかしそれは男にとっては不満であったらしい。己の正義を殺してまで不正を見て見ぬ振りをすることで、嫌悪感と怒りが同時に蓄積されていくのを感じていたようだ。ただしこの男の正義感は、特に厳しく育てられたとか宗教上の理念なのではなく、ただ自然と湧き上がってくる感情であったらしい。そのこと自体、男も自分のことであっても不思議に思えたらしく、『こんな事くらい』と思うような些細な事柄であっても気になってしまうのは『おかしい』のではないかと認識くらいはしていたようだ。
平穏な日々が続いていたかのように見えた男だったが、日々積もる不満を溜め込む一方であったため、肥大していくだけだったようだ。それは次第に『怒る』ことで発散するようになった男であるが、それでも不満は積み上げる一方だった。
物に強く当たるようになった男は、それが壊れるまで当たり散らし、そしてその後に後悔する、ということを繰り返したが、それは強い自己嫌悪となって跳ね返るばかりであり、それが物から人に対象が広がったのは、流れ落ちる水のごとく、どうしようもない流れだったのかもしれない。
男はつまらない喧嘩の末、後先も考えずに職場を去ってしまった。正確には、ある日を境にぷっつりと仕事に行かなくなったのである。それでも男にとっては、それが正義であり、正しい行いだと自負していたようだ。職場が、世間が、果ては社会全体が無知で不法であり、そんな世界の方が『おかしい』のだと男は考えるようになった。
そんな男に唯一理解を示した、というよりも、ただ寄り添っていたのが男の妻である。男の収入が途絶え生活が苦しくなったとしても不平を零さず、男に好きなように言わせていた。それが妻なりの男への愛だったのかどうかは定かではないが、大いなる慈悲の心で男を許していた、という心の持ち主ではなく、妻なりの考えが他にあったのだろう。それは子供がまだ生まれて間もないというのを差し引いても、ただ男に従うだけの女性ではなかったことだけは確かだ、と言えるかどうかは分からないが、男を見捨てようとはしなかった事だけは確かである。
そうして悪化の一途を辿るばかりの男と、それに引きずられていく妻と子供であったが、何事にも終わりというものがある。別の言い方をすれば限界を迎えたと言ってもいいだろう。それはある夜に訪れたが、全ては悪い方向に一気に振り切れ、その時を迎えるべくして迎えた、分岐点ではなく分岐しただけの運命に流されただけかもしれない。
その夜、男は特に不機嫌だった。理由の分からないまま泣き続ける子供に、疲れ果てた妻、そして底を見せた酒と空の財布。これら今すぐに解決できない事柄を全て妻のせいにして罵る男である。それもこれも男には非は無く、この世の全てが無責任だと繰り返すだけの男に、初めてではないだろうか、妻が言い返したのだ。それは独り言のようにも聞こえたが、一度開いた口は閉じることが出来なかったのだろう。それに、余計に
小さな家で家族全員が声を張り上げている場面は、想像するだけでも賑やか、いやいや、悲惨なものだろう。そんな中、怒鳴り散らしている男の頭の中は意外に冷静な部分もあったようで、この状況から逃れたいと考えていたようである。それにはまず、この状況から消えてしまうこと、そしてまだ理性が残っている部分を酒で追いやってしまうことである。
そこで男は、捨て台詞を吐きながら駆け出すように修羅場から逃走。その際、この家に一つしかないランタンを手にし、街の酒場までの
男が居なくなったことで明かりの無い家では、今までの喧騒が嘘だったかのように静かさを取り戻し、ランタンの代わりに窓から差し込む月明かりが照明となった。その暗闇と静寂は妻にとって
勢いよく家を飛び出し、用意周到にランタンまで持ち出した男ではあるが、生憎と靴を履き忘れたようで、暫く走った後に感じた足の痛みでそれに気が付いた次第だ。しかし、靴のために戻るという気にはなれない男であり、問題はそれだけではなかった。街の酒場に向かってはいたものの、無銭では話にならない。さりとて家に戻ったところで無いものは無いのだ。それが有れば男がこの場に立っているはずはなかっただろう。
それでも、とにかく歩くと決めた男である。それはこの状況を打破するような明暗が浮かんだ訳ではないが、何がしらの偶然が起きるかもしれない、と暗闇の世界が男に夢のような淡い期待の妄想を抱かせたのかもしれない。
そのような偶然が起きるのなら、それは奇跡と言っても良いだろう。だから奇跡というやつは——、いやいや、それが起きたようだ。ただしそれが本物の奇跡であるかどうかは見方や立ち位置によるはずだ。
殆ど放心状態で歩いていた男の前に、身なりの良さそうな男女が歩いていた。それは夜の散歩のつもりなのかもしれないが、時と場所を考えれば不用心にも程があるだろう。何故ならその心の隙に付け込もうと男が良からぬことを考えていたからだ。
男女が時折あげる笑い声が、貧相で軽薄な、まるで男を嘲笑うかのように聞こえてしまったのは、今の男にとっては自然なことだ。ましてその貴族のような出で立ちは、この男の状況を作り出した諸悪の根源なのだ、と伏せっていた男の怒りを倍増させた。すると、全ての責任は相手方にあり、俺の行為は必然で仕方のないことなのだという思いが正義へと変わる。それが男の
男はなるべく音を立てずに男女に近づき、男性に狙いを定めた。しかしここで誤算があり、不用心と思われた男性の腰に剣があったのだ。それで
そうして男性が動かなくなった頃、震える手で金目のものを奪い、靴も脱がせた。そして怯えているだけの女性をチラリと確認すると、
これで、男に巡ってきた奇跡は終わり、男女にとっては不運が突然襲ってきた訳だが、まだ幕は降り切ってはいなかった。その幕は、何も出来ないと男が思い込んでいた女性によって降ろされる。男性の生死は不明だが、その男性から剣を引き抜いた女性は男の背中に真っ直ぐ、そして体重をかけて剣を突き立てた。女性に剣術の心得は無かったが、無防備に立つ男を背後から刺すことは容易であり、手加減など知る由もない。剣は男に深く突き刺さり、そのままの状態で男から離れた女性である。
男は自分に何が起こったのか把握できず、ただ全身の力が急に抜けていくのを感じただけだ。そしてその場に倒れたが、自身の生命がそれで終わるとは思わなかったようだ。なぜ体の力が抜けたのか、なぜ倒れたのか、それら全てが分からないまま、男の人生はロウソクの火を吹き消すかのに終わった。
これで男の人生は終わりを告げたが、それで男の罪が無くなった訳ではない。男は罪と共に『次』の段階に誘われる。男が暗闇から光を見出した時、そこは荒れ果てた大地と曇り空が広がるばかりの世界が見えるだけだった。そしてその光景は、目を逸らしたり閉じたりすることの出来ない永遠の光景となる。何故なら、見えてはいるが男には『眼』というものが無かったからだ。それどころか、頭や手足といった『体』というべきものが無い。それでは意識だけの存在かと言われれば、そうでもない。それに近いようなものかもしれないが、男はランタンの姿をしていた。強いて言えば、そのランタンの中で燃えている炎が男自身と言えるかもしれない。
「わああああああああああぁぁぁあああぁぁぁあああぁぁぁあああぁぁぁ」
男は訳も分からず叫んだが、それを発することが出来、かつそれが聞こえるということは、口や耳に相当する『何か』があるのだあろう。しかし、それがどうなっているのかなど、今の男にはそれを考える余裕は無かった。まして、ここがどこで、自分がどうなっているのか全く分からず、殆ど狂ってしまったような男である。それで、嘆き、苦しみの声を上げるが、それはまだまだ、これから先の『時』を考えれば楽な方なのかもしれない。
その『時』を刻むためなのか、荒れ果てた大地の向こうに時計塔がポツンと建っている。それはまるで男の時間を計るために在るかのようだ。そして時折吹く風は、とても優雅とは言えず、不規則に何かを削っていくような風である。
恐らくここは永遠に続く世界、それは終わりが訪れることのない、ずっと『時』だけが過ぎて行く世界のようだ。多分それを『地獄』と呼んでも良いだろう。
◇