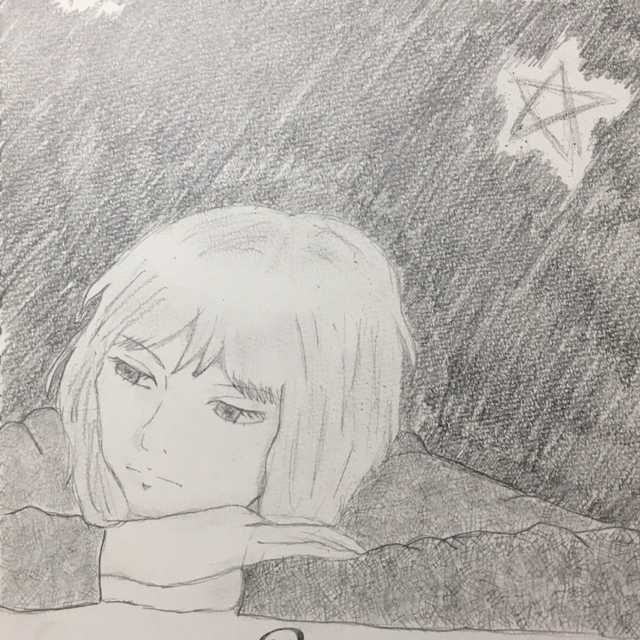14
文字数 1,843文字
「お父様、あなた確かに言いましたよね。家族だからって贔屓はしないと。それなのに、自分が過去に関わった人の関係者を対象にするのはまだしも、事前に対象者に接触して事前に情報伝達するなんてあんまりじゃないですか。一体どういうおつもりなんですか、流石に説明していただかないと納得できません」
ずっと前に自分が接触していた人をターゲットにして、それを実の息子に回して、しかも死神が来ることを予め伝えておいた。これほどに死ぬ気でいる人に、敢えて。正式な試験のはずだったのに、俺は最初からこの人の手のひらの上だったということか。そんなものの上で成り立つ合格なんて、全く俺の力じゃない。今まで自分自身の力でここまで突破してきたんだ、嬉しくもなんともない。
叫ぶように吐き出してようやく、びくともしなかった彼の口が開いた。
『たまたまだ』
「は……? たまたま?」
『そう、本当に偶然だったのだよ。ずっと前に接触した人が、たまたまこの時期にリストとして挙がってきた。ただ、例外的に相手は死神の存在を知っている。だから軽く挨拶をしに行っただけだ。如何せん、今回手を下すのは私ではないからな』
彼の発言は嘘か誠か、いつも本当に分からない。表情にも声色にも、感情というものがまるでない。それがまた、軽くあしらわれているような気がして悔しかった。握り締めた拳の中の爪が、自らの柔い手のひらに刺さる。しかし、それを痛いと構っていられるほどの余裕もなかった。
「この期に及んでしらばっくれる気ですか。それで納得するとお思いですか」
『それに私は、試験に関しては一切贔屓したつもりはない』
「そんなことをしてまで、まだ――」
『それならタツヤ、お前はどうして未だに彼女を殺さないのだ』
「それは……」
どう答えよう、と考える間もなく、彼は続きを発する。
『確かに試験期間は一週間設けている。しかし、必ず最終日に答えを出せというわけではない。答えが決まった時点で実行すれば良いのだ。それが正しいかどうかはこちらが判断することだ』
「分かっていますよ、そのルールは」
『分かっているなら、何故だ?』
「何故って、それは……」
言葉に詰まった俺を見てか、彼は小さく息を吐いた。
『タツヤ、お前は殺すべきか否か迷っているのではないか』
「ッ……!」
そして、思わぬ反撃の矢が勢いよく刺さってきた。やはり、様子を全て見られているから、自分の心境でさえも容易く見抜かれてしまうというのか。「殺すための理由を探しているだけだ」と言い返したかった。しかし、それすら口にできないほど、動揺していた。
何が正解か、とは思っていた。だが、実際に他人から言い当てられてしまったことで、俺は自分自身が迷っていることを自覚せざるを得なくなってしまった。
『今日の会話で、彼女を殺すための理由の材料は揃ったはずだ。それなのにどうして迷う。これが贔屓されたハンデ試合だと主張するのであれば、お前ならすぐ答えを出せたはずだ』
「そう、です……けど……」
『あとはお前自身の問題だ。あと二日で答えを出し、私に示しなさい。健闘を祈る』
「あっ、ちょっと待っ――」
俺の最後の言葉も虚しく、通信は一方的に切られてしまった。横にいたオハラはフッと息を吹きかけ、スクリーンの存在を一瞬で消してしまった。
「……なぁ、オハラ」
「何でしょう、タツヤ様」
「オハラは……このこと、最初から知っていたのか」
ようやく刺さった爪が痛いと思えても、拳を解けずにいた。俯いた目線は河原の石を映していたため、彼の姿は見えていなかった。
「いえ、私も今、タツヤ様からのお言葉で初めて知りました。恐らく、知っていても、旦那様の最側近の秘書までかと。私はただ、『タツヤに何かあった際は動いてくれ』というお言葉をいただいたのみでして」
「……そうか」
その言葉を聞き、もう何をどうしようもないと悟った俺は、やっとのことで固まってしまった足を動かす。足元の砂利が乾いた音を立てる。
「……俺、帰るよ。悪かったな、わざわざこんなことで呼び出して」
そして元来た道を辿ろうとした時、「タツヤ様」と、落ち着いているが確かな声で呼び止められた。振り向けなかったが、足は止めた。
「これはタツヤ様の試験なので、答えを出すのはタツヤ様ご自身です。ただ、もし私の言葉が届くのであれば……。
ご自身で納得いく答えが出せるなら、それで良いのだと思います。どうか、ベストを尽くされますよう」
そんな彼の言葉に何も反応できないまま、俺は再び静かに歩き出した。
ずっと前に自分が接触していた人をターゲットにして、それを実の息子に回して、しかも死神が来ることを予め伝えておいた。これほどに死ぬ気でいる人に、敢えて。正式な試験のはずだったのに、俺は最初からこの人の手のひらの上だったということか。そんなものの上で成り立つ合格なんて、全く俺の力じゃない。今まで自分自身の力でここまで突破してきたんだ、嬉しくもなんともない。
叫ぶように吐き出してようやく、びくともしなかった彼の口が開いた。
『たまたまだ』
「は……? たまたま?」
『そう、本当に偶然だったのだよ。ずっと前に接触した人が、たまたまこの時期にリストとして挙がってきた。ただ、例外的に相手は死神の存在を知っている。だから軽く挨拶をしに行っただけだ。如何せん、今回手を下すのは私ではないからな』
彼の発言は嘘か誠か、いつも本当に分からない。表情にも声色にも、感情というものがまるでない。それがまた、軽くあしらわれているような気がして悔しかった。握り締めた拳の中の爪が、自らの柔い手のひらに刺さる。しかし、それを痛いと構っていられるほどの余裕もなかった。
「この期に及んでしらばっくれる気ですか。それで納得するとお思いですか」
『それに私は、試験に関しては一切贔屓したつもりはない』
「そんなことをしてまで、まだ――」
『それならタツヤ、お前はどうして未だに彼女を殺さないのだ』
「それは……」
どう答えよう、と考える間もなく、彼は続きを発する。
『確かに試験期間は一週間設けている。しかし、必ず最終日に答えを出せというわけではない。答えが決まった時点で実行すれば良いのだ。それが正しいかどうかはこちらが判断することだ』
「分かっていますよ、そのルールは」
『分かっているなら、何故だ?』
「何故って、それは……」
言葉に詰まった俺を見てか、彼は小さく息を吐いた。
『タツヤ、お前は殺すべきか否か迷っているのではないか』
「ッ……!」
そして、思わぬ反撃の矢が勢いよく刺さってきた。やはり、様子を全て見られているから、自分の心境でさえも容易く見抜かれてしまうというのか。「殺すための理由を探しているだけだ」と言い返したかった。しかし、それすら口にできないほど、動揺していた。
何が正解か、とは思っていた。だが、実際に他人から言い当てられてしまったことで、俺は自分自身が迷っていることを自覚せざるを得なくなってしまった。
『今日の会話で、彼女を殺すための理由の材料は揃ったはずだ。それなのにどうして迷う。これが贔屓されたハンデ試合だと主張するのであれば、お前ならすぐ答えを出せたはずだ』
「そう、です……けど……」
『あとはお前自身の問題だ。あと二日で答えを出し、私に示しなさい。健闘を祈る』
「あっ、ちょっと待っ――」
俺の最後の言葉も虚しく、通信は一方的に切られてしまった。横にいたオハラはフッと息を吹きかけ、スクリーンの存在を一瞬で消してしまった。
「……なぁ、オハラ」
「何でしょう、タツヤ様」
「オハラは……このこと、最初から知っていたのか」
ようやく刺さった爪が痛いと思えても、拳を解けずにいた。俯いた目線は河原の石を映していたため、彼の姿は見えていなかった。
「いえ、私も今、タツヤ様からのお言葉で初めて知りました。恐らく、知っていても、旦那様の最側近の秘書までかと。私はただ、『タツヤに何かあった際は動いてくれ』というお言葉をいただいたのみでして」
「……そうか」
その言葉を聞き、もう何をどうしようもないと悟った俺は、やっとのことで固まってしまった足を動かす。足元の砂利が乾いた音を立てる。
「……俺、帰るよ。悪かったな、わざわざこんなことで呼び出して」
そして元来た道を辿ろうとした時、「タツヤ様」と、落ち着いているが確かな声で呼び止められた。振り向けなかったが、足は止めた。
「これはタツヤ様の試験なので、答えを出すのはタツヤ様ご自身です。ただ、もし私の言葉が届くのであれば……。
ご自身で納得いく答えが出せるなら、それで良いのだと思います。どうか、ベストを尽くされますよう」
そんな彼の言葉に何も反応できないまま、俺は再び静かに歩き出した。